
【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!
司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF
※閉じるとこの案内は7日間再表示されません
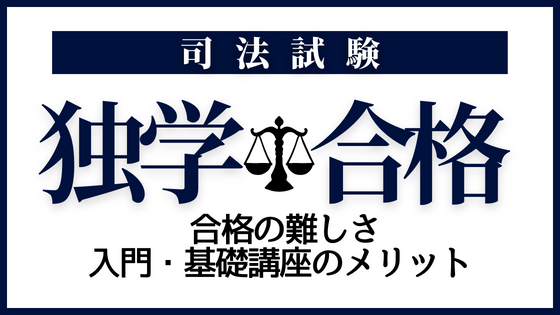
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?


司法試験に挑戦することを決意したけど、やはり「独学」で合格は難しいのだろうか?
司法試験で「独学」をしている友人がいるけど、自分は「入門講座」を受講しようと思っているけど、この判断は正しいのだろうか?
「独学」を決意しているけど、「独学」の難しさを事前に理解しておきたい
以上のような悩みを持たれている方は、多いかと思います。
法曹を志望する方であれば、誰もが「独学と予備校のどちらで司法試験合格を目指すか?」について検討をしたことがあるかと思います。
「独学」VS「予備校」
本記事では「独学」で司法試験合格を目指すことが難しい理由と、「予備校の入門講座・基礎講座がお勧め」の理由について紹介させて頂きます。



では、見ていくぞ!



やあ、法律を学ぶみんな!
今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!



そうなのそうなの〜!
受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨



特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!



あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱
お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!
📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】
司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!
現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。
\ このタイミングを逃す手はありません /
合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。
まずは、「独学」で司法試験に合格することが難しい理由について解説をさせて頂きます。主に、以下のような要因で難しく感じることが多いのではないでしょうか?
司法試験 「独学」合格を阻む要因
①「難解」な法律知識の壁
②「広範すぎる学習範囲」と「時間・労力」の限界
③知識だけでは乗り越えられない「試験特有のノウハウ」
④「長期間のモチベーション」維持
法律知識はとても難解です。
以下の項目により、通常の知識の獲得より難しくなっています。そのため、知識の習得に、時間がかかったり、悩んでも理解がとてもしにくかったりします。
法律知識 「難解さ」の要因
1. 専門用語の難しさ
2. 法律の曖昧性
3. 異なる解釈の存在
1. 専門用語の難しさ
法律用語は一般的な言葉と異なることから、理解するのが困難であることがしばしばあります。
これは、法律の分野に特有の独自の言葉が多く存在し、それらの用語が特定の法的な意味を持っているためです。その結果、法律に関する知識が乏しい場合、そもそも文章の意味を把握するのが難しくなります。



確かに、一見どのような意味なのか、分かりづらい時ってあるよね…
2. 法律の曖昧性
法律書籍や判例は「行間が読むことが難しい」と言われることがあります。
法律文書には曖昧な表現が多く用いられていることが要因となります。これは、法律はさまざまな事情や状況に適用されることを考慮して、柔軟性を持たせるために曖昧な表現が採用されることが多いためです。
そのため、法律文書の正確な意味を把握することは、初学者にとって困難な課題となります。



判例などを読んでみると、曖昧な表現が使用されていて、結局どのような意味かが分からない…なんてことあるよね!
3. 異なる解釈の存在
法律を難しくしている要因の一つとして、法律の解釈について見解が分かれることが非常に多い点です。一つの解釈に決まっていれば良いのですが、法律の解釈は、判例の見解と学者の見解が異なったりすることは多々あります。
一つのことについて、異なる見解が存在することを、理解しておく必要があるため、その内容を整理したり、違いを把握したりすることは時間がかかることがあります。
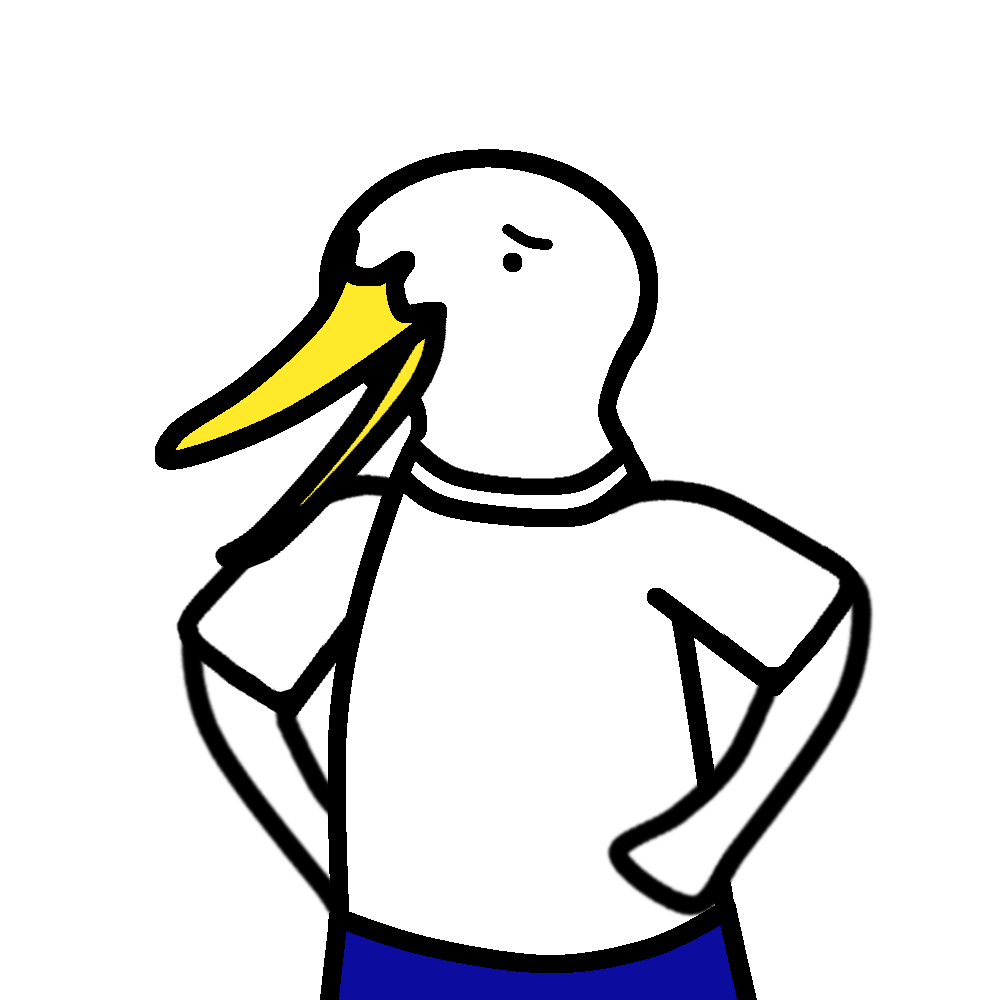
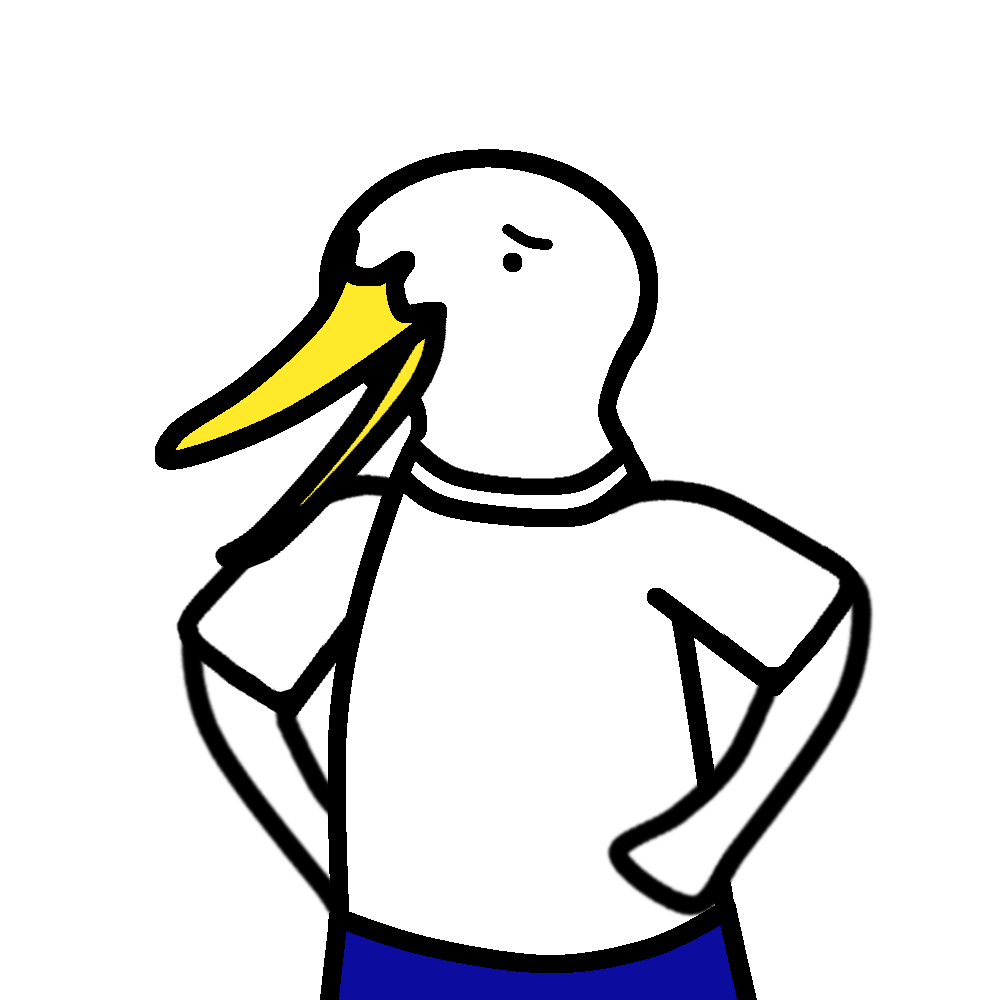
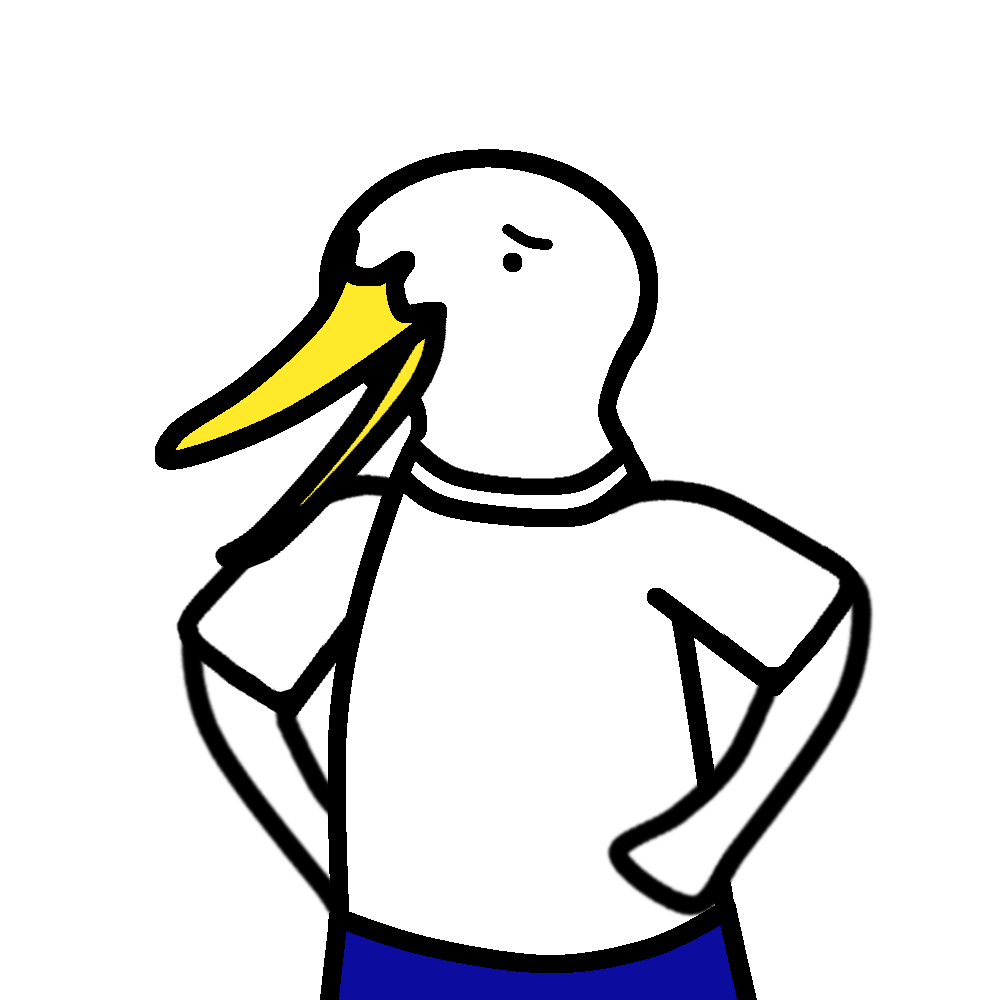
そうだよ~解釈が色々分かれていて、覚えないといけないことが多いんだ!
学習範囲が広く「時間と労力」が必要ですが、一例ですが、具体的に以下のようなことで困ることが多いです。
学習範囲が広く「時間と労力」が必要
1. 情報収集、学習計画
2. 学習の優先順位
1. 情報収集、学習計画
司法試験の範囲は非常に広く、すべてを網羅した教科書が存在しません。そのため、この一冊さえ読み切れば良いという本は存在しません。
「独学」では、様々な教材を組み合わせ、又は「法学部やロースクールの講義を活用」する必要があります。このように「独学」の場合、「情報収集」や「学習計画の立案」が難しいことがあります。
具体的には、試験範囲に含まれる膨大な法律や判例、そして法律用語を学ぶために、独学者は多くの時間と労力を投資する必要があります。しかし、情報が散逸しているため、どの情報が試験に関連するかを判断するのは初学者にとって困難です。入門者は適切な情報収集や学習計画の立案に苦労することがあります。



司法試験で合格するために「情報収集」がとても大切だ。
情報次第では、合格までの道のりに差ができることがあるよ!
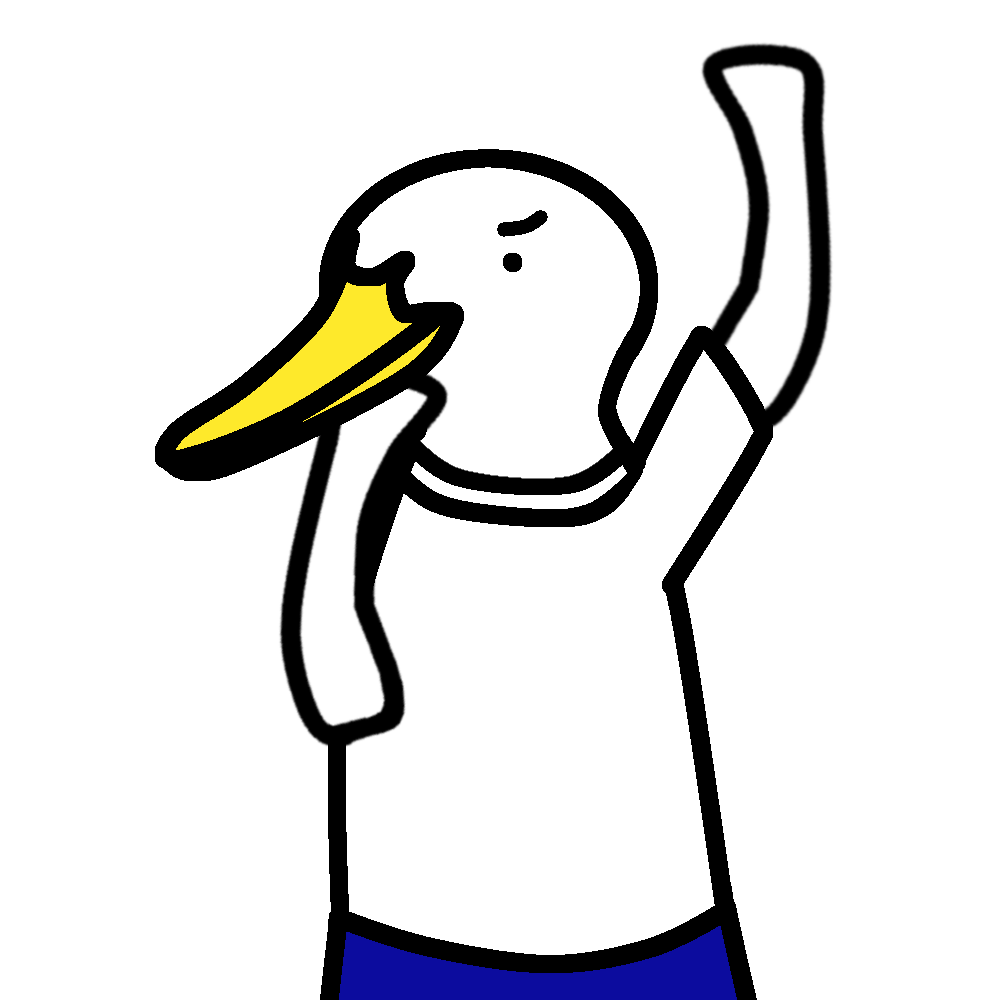
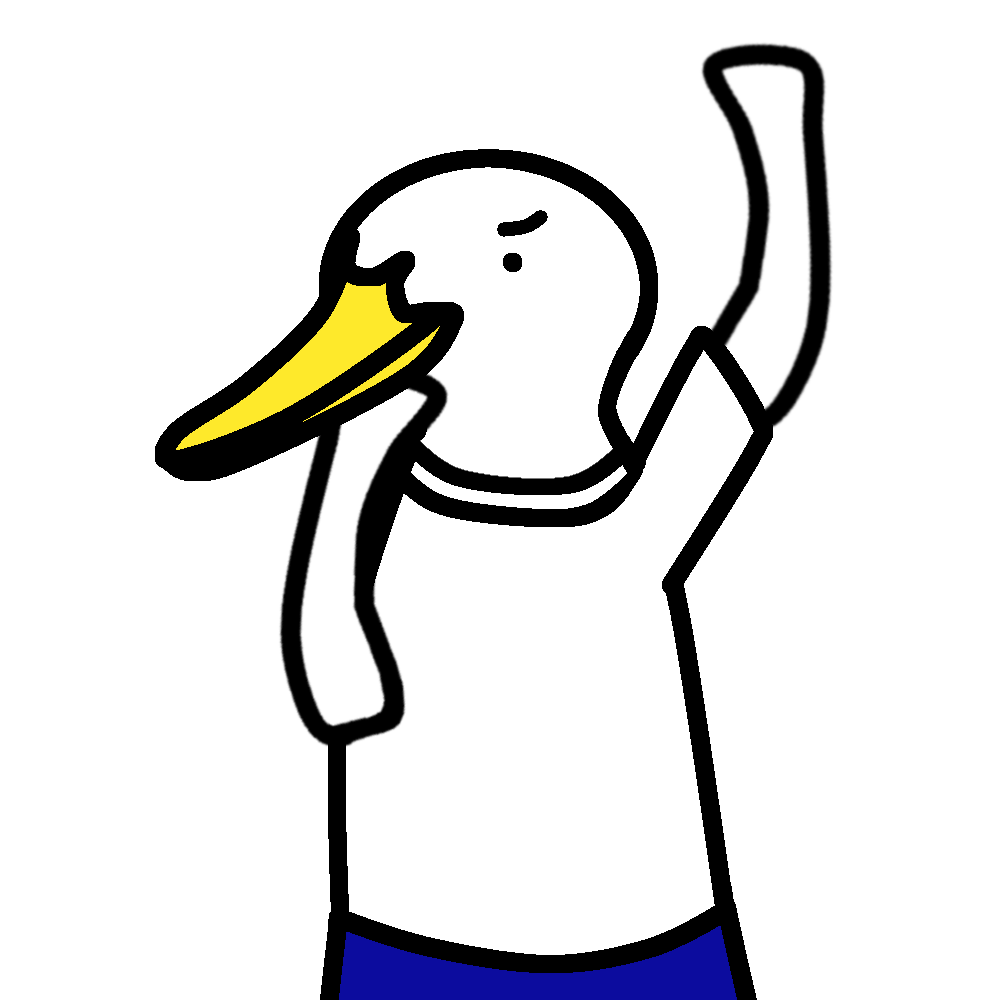
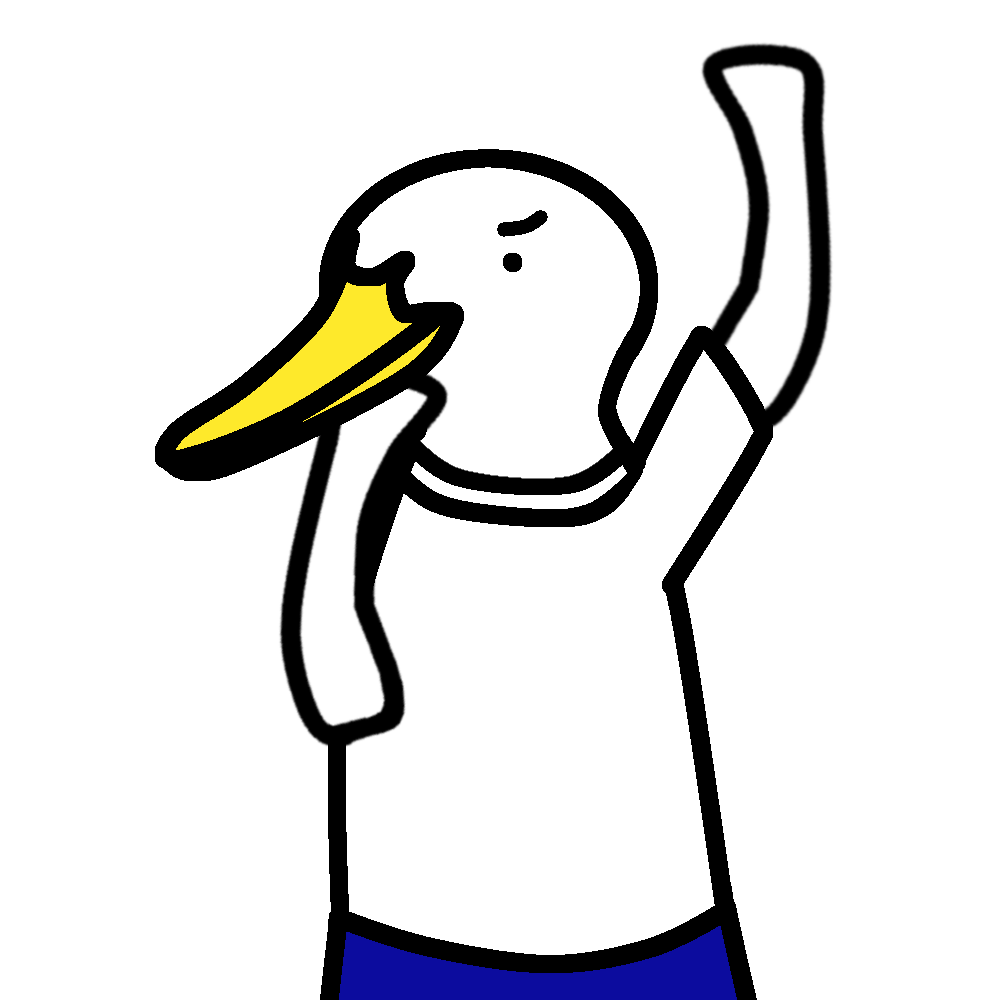
計画を今から立てるのは大変だよね…しかも、その内容で合格するかも、ちょっと不安に感じることもあるよ…
≪情報収集は法書ログで≫
法書ログではこのような課題に対して法律書籍の口コミサイトを運営しています。法律書籍の選び方を悩まれている方は是非、ご利用ください。
司法試験受験生向けのブログ記事やロースクールの口コミサイトも運営しています。
2. 学習の優先順位
「独学者」は試験対策において、学習の優先順位を決定することも難しいです。
試験範囲が広いため、どのトピックに重点を置くべきか、どの法律や判例を最初に学ぶべきかといった判断が求められます。適切な指導やフィードバックがない場合、どのテーマを優先的に勉強するべきかの判断が難しく、必要以上に時間をかけてしまったり、重要なテーマをさらっと流してしまったりしている可能性があります。
「独学者(特に初学者)」にとっては、適切な指導やサポートを受けることが、効果的な学習と試験対策につながると思います。
なお、現在は、優れた基本書、演習書が多いことから、昔に比べれれば初学者であっても勉強はしやすくなっているかと思いますが、それでも戸惑いは多いかと思います。



どの分野や、どの教材から手を付ければよいかは、実際に過去問等を通じて得られる感覚だ。
本などにも出題されやすい分野は書かれていることがあるけれど、実際見てみると、広い分野の中で本当にそこに注力してよいか迷うことがあるよね。
独学の勉強をする中で、適切な優先順位を決めることは、結構難しいことなんだ!
司法試験では「知識以外のノウハウ」が合格するために重要です。以下のような以下のような点で「知識以外のノウハウ」が必要になります。
「知識以外のノウハウ」が必要になる理由
1. 解答のバリエーションが存在する
2. 広範な法律知識が求められる
3. 論理的な思考力や問題解決力が必要
4. 時間制限が厳しい
1. 解答のバリエーションが存在する
「司法試験」は実務家登用試験で、異なる結論を示す答案を書いた人がいても、いずれも正解であることもあり得ます。
「論文式試験」で基本的に、立論する解釈は「判例通説」です。「判例通説」を批判した上で、その他の有力説で論証することも問題ありません。特定の見解を必ず取らなければならないというわけではないのです。
法律の解釈や適用は、事例や状況に応じて異なるため、「論文式試験」では複数の解答が正当性を持つことがあります。受験生の立場からすると、自分の解答が正しいかどうかを明確に判断することが難しいということがいえます。
判例通説とは?
ある法律問題について、裁判所の判例の中でも特に多くの支持を得ており、かつ、学説においても有力に支持されている見解のこと
過去に、「司法試験」で出題される問題の漏洩の事件があったことがあります。法科大学院の教員が、担当する学生に対して、実施前の「司法試験の論文式試験」の問題を漏洩したのです。教員が、作成に関わった試験問題の内容を、特定の学生に事前に教えていました。
その時に、満点の答案が登場し、問題が発覚したようです。満点を獲得できる解答はあるようですが、どのような解答も必ずしも間違えではないのです。(目的は「司法試験」に合格することなので、満点を目指す必要は必ずしもないです)



「判例通説」を批判して、他の説で論じてもいいなんて、何が正解か混乱してしまう…



「短答式試験」みたいに、明確な答えがあるわけじゃないのが、「論文式試験」の難しいところ。
自分の書いたことが本当に評価されるのか、最後までドキドキするんだよ。色々な考え方がある中で、どれを選んでどう論じるかっていうのは、本当に慣れが必要なんだよね。
2. 広範な法律知識が求められる
「司法試験」では、さまざまな法律分野に関する知識が求められ、受験生は多くの法律の「条文や判例」に精通している必要があります。広範な法律知識を習得し、問題に適切に適用することは、容易ではなく、試験が難しいとされています。
適切な解答を選択しようとする中で、「広範な法律知識」が必要なため、非常に難易度の高い試験です。
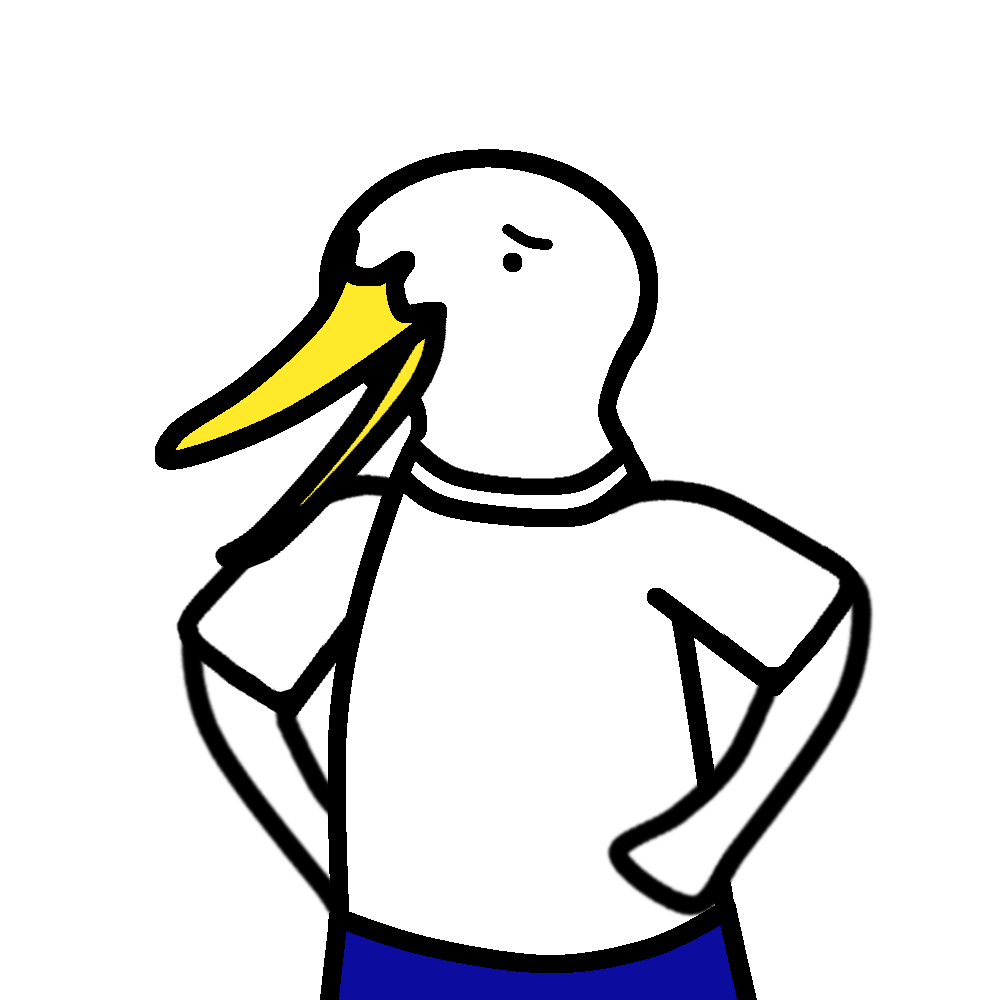
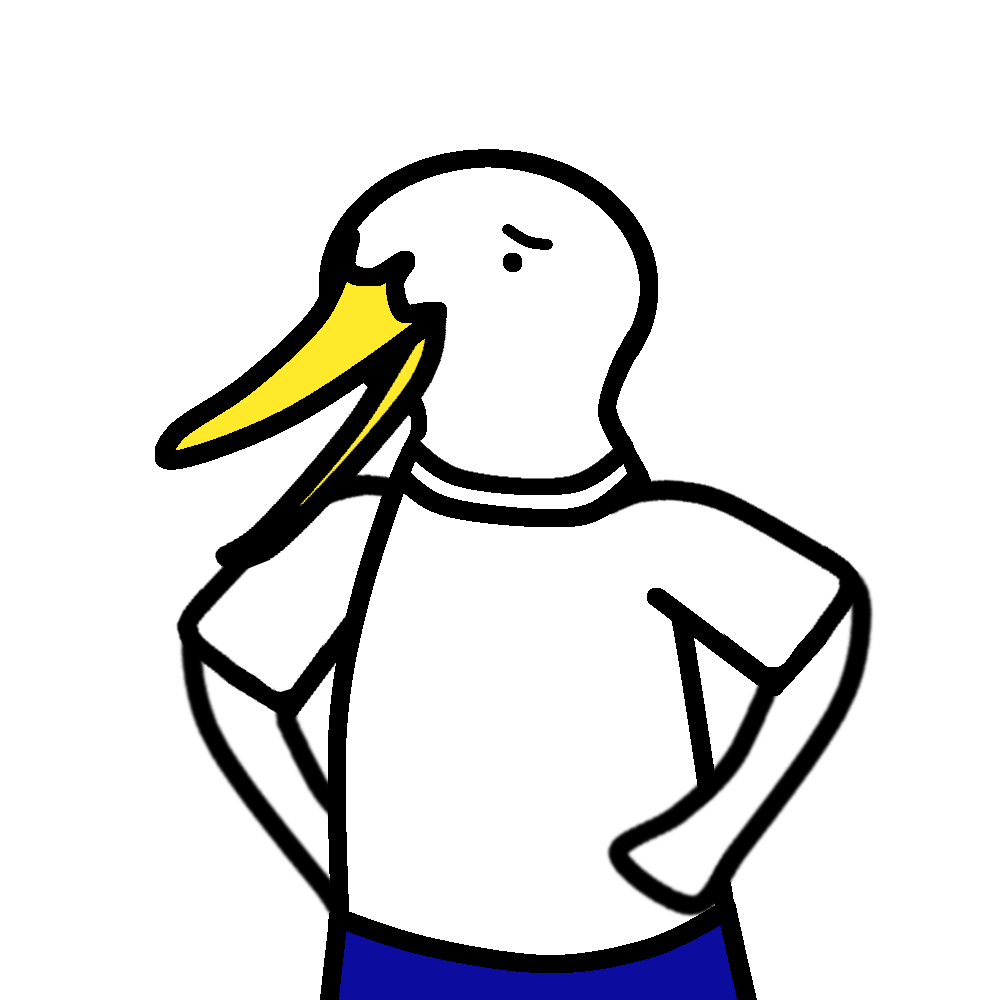
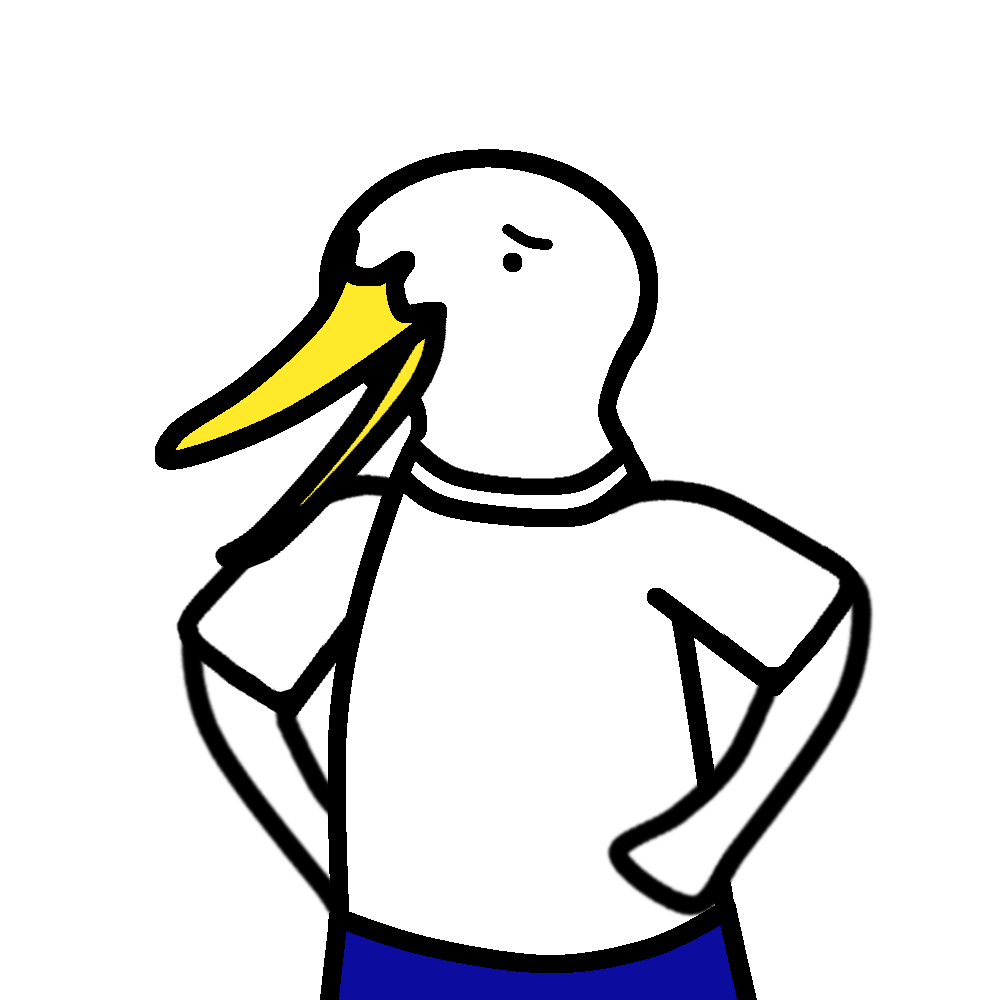
民法、刑法、憲法…テキストを眺めただけでも、出題分野が多いよね。覚えるだけでも気が遠くなるのに、それが色々な分野にまたがって出題されるなんて…!
終わりが見えなくて押しつぶされそうです。こんなにたくさんの知識を、どうやって使いこなせるようになるんだろう…



ああ、その気持ち、すごくよく分かるよ。
僕も最初は、こんなに広い範囲を全部覚えられるのかって絶望的な気持ちになっていたね。
3. 論理的な思考力や問題解決力が必要
試験の山場の「論文式試験」では、「広範な法律知識」だけでなく「論理的な思考力」や「問題解決力」も求められます。
受験生は、与えられた問題や事例に対して、法律を適切に解釈し、その根拠を明確に示す論証が必要で「短答式試験」とは異なり、独自の訓練が必要となり、難しく感じることがあります。これがこれまで受けてきた試験との大きな違いかと思います。
その力を鍛える勉強として「答案練習」があります。思考回路を鍛えるために大事な訓練で、最初は全然書けなくても、続けていくうちに少しずつ見えてくるものがあります。「論理的な思考力」や「問題解決力」を獲得するために、諦めずに練習する必要があります。
試験の山場が「論文式試験」等の情報については、試験の戦略などは下の記事に記載あるので、こちらをご覧ください。
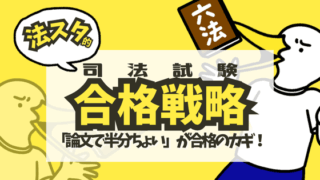
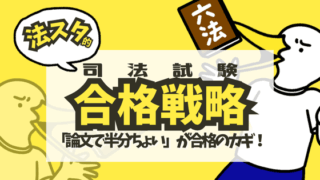
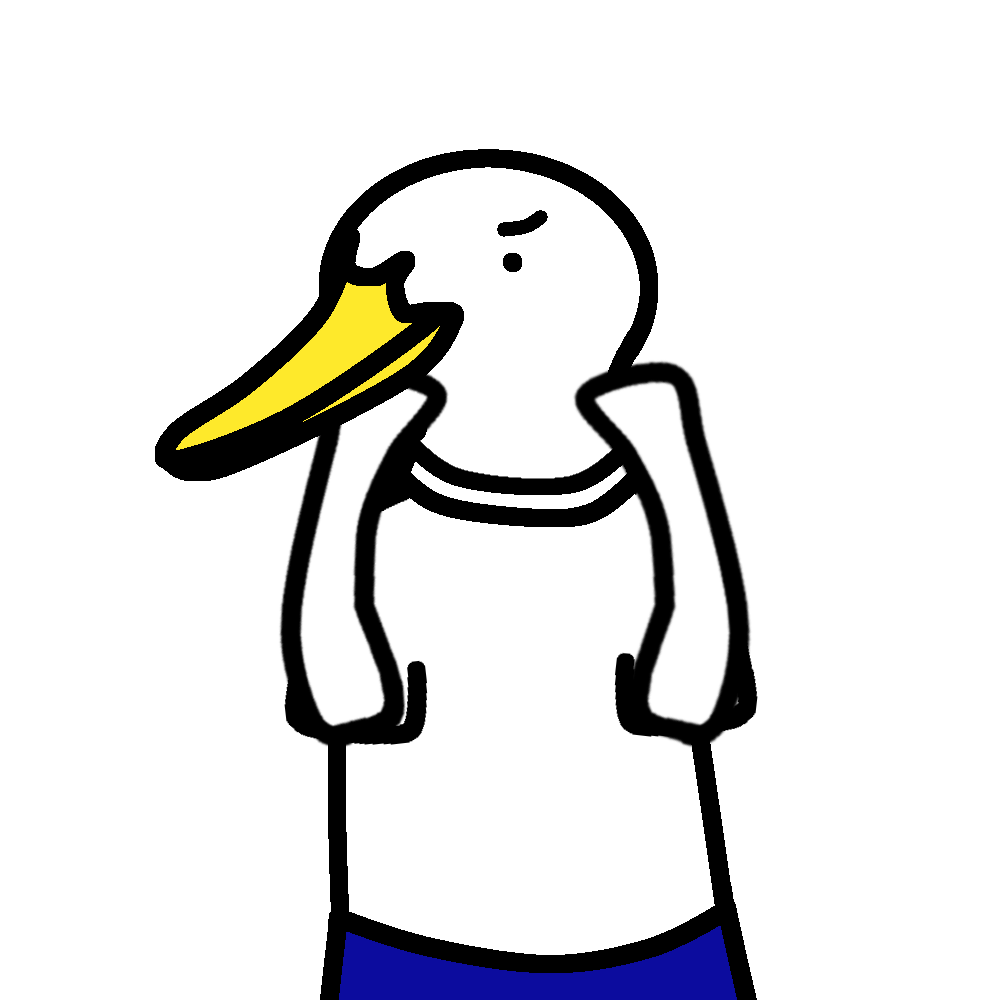
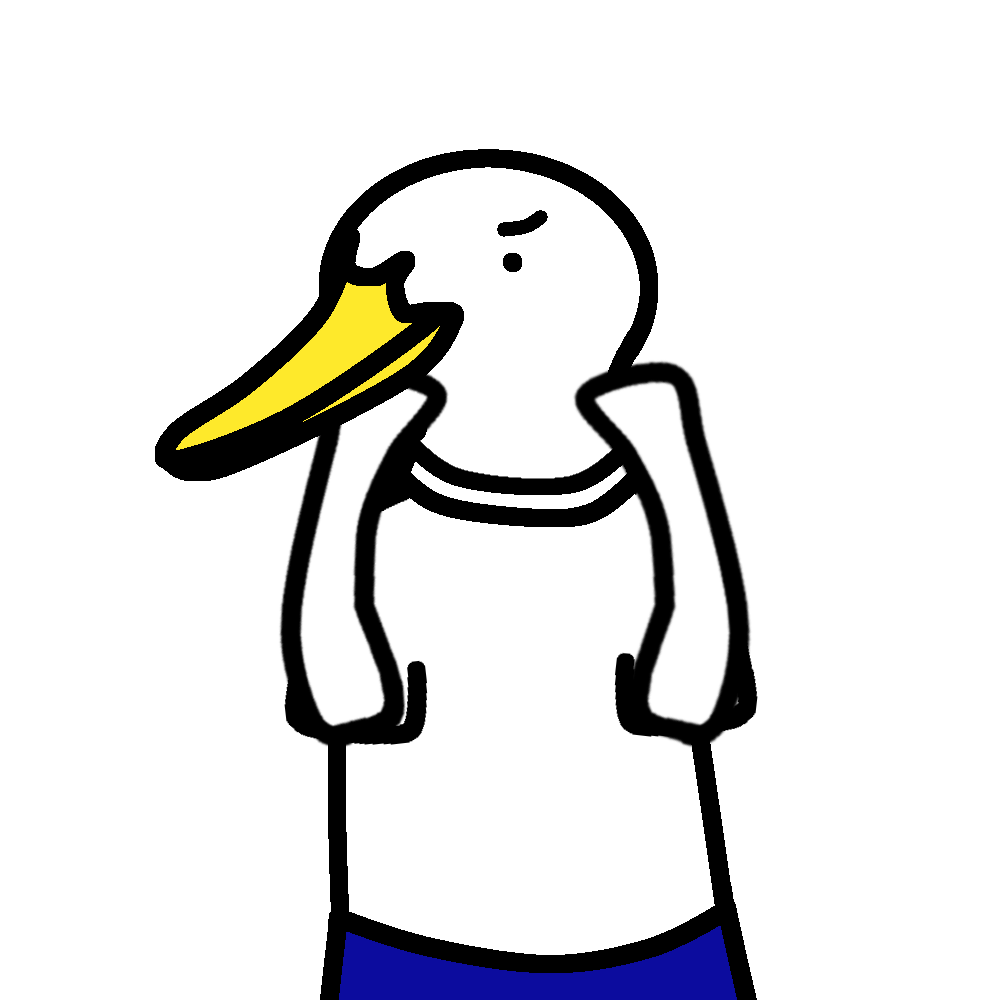
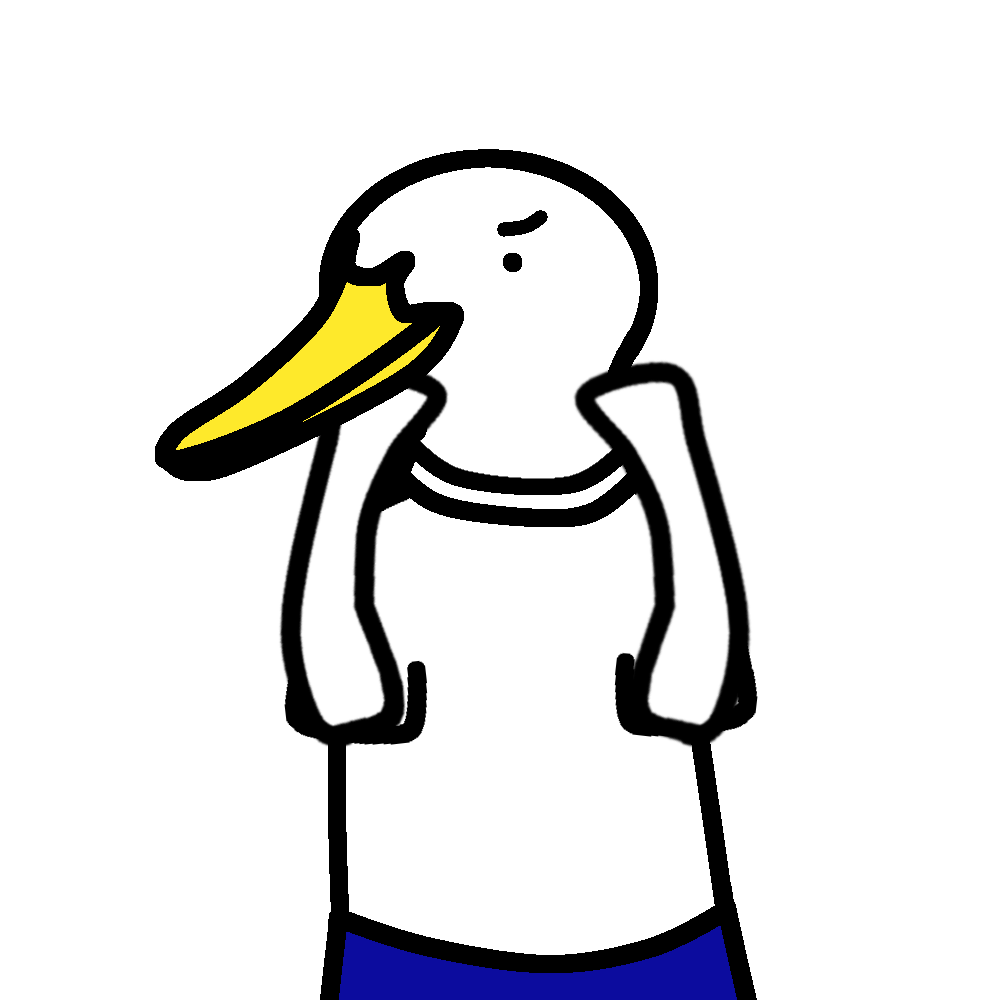
膨大な法律の知識を覚えるだけでも大変なのに、さらに論理的に考えたり、問題解決したりする力まで必要なんですか…?
「思考力」や「問題解決力」って本当に身につくんだろうか…?



知識だけじゃ太刀打ちできないのが司法試験なんだよね。
問題文を読んで、どの法律を使って、どんな流れで論じればいいのかを組み立てる力は、一朝一夕には身につかないんだ!
4. 時間制限が厳しい
「司法試験の論文式試験」は、限られた時間内で複数の問題に解答しなければならないため、時間管理が重要です。
受験生は、効率的に問題を解決し、適切な論証を行う能力が求められます。時間制限の中で事例分析、答案構成、答案作成をすることは容易でないため、難易度が高いと感じられることがあるようです。



答えを考えるだけでも時間がかかるのに、時間制限まであるなんて…!
時間内に事例分析、答案構成、答案作成をするには、どれだけの練習が必要なんだろう…



本当に、時間との戦いだ。
事例を分析して、構成を考えて、文章を書くっていう一連の流れを、限られた時間の中でやらなきゃいけないんだから。
「広範な法律知識」だけでなく「論理的な思考力」や「問題解決力」を獲得するために、長期間の学習を続ける「モチベーション」が必要です。
「独学」では、自分に合った学習ペースや環境を維持するのが困難で、モチベーションが低下しやすいです。自分で学習計画や目標設定を立てなければならず、自己管理能力が非常に重要となります。また、学習の進捗や成果を客観的に評価する方法が限られており、自分の成長や達成感を感じにくいことがあります。
多くの人にとって、自己管理が難しく、学習意欲が続かないことがしばしばあります。モチベーションの低下や学習意欲の喪失につながることがあります。
学習のモチベーションが下がる よくある理由
1. 出口の見えない学習への倦怠感と焦燥感
2. 社会との隔絶感と自己肯定感の低下
3. ルーティン化による刺激の喪失と目標の曖昧化
1. 出口の見えない学習への倦怠感と焦燥感
学習範囲が広く、終わりのない迷路を歩いているように感じてしまいます。
参考書や判例集は積み上がり、模試の結果に一喜一憂する日々に、先が見えない不安と、なかなか成果が出ない焦りが、じわじわとモチベーションを蝕んでいきます。
「一体いつまでこの生活が続くのだろうか…」という倦怠感が、特に長期間にわたると押し寄せてきます。
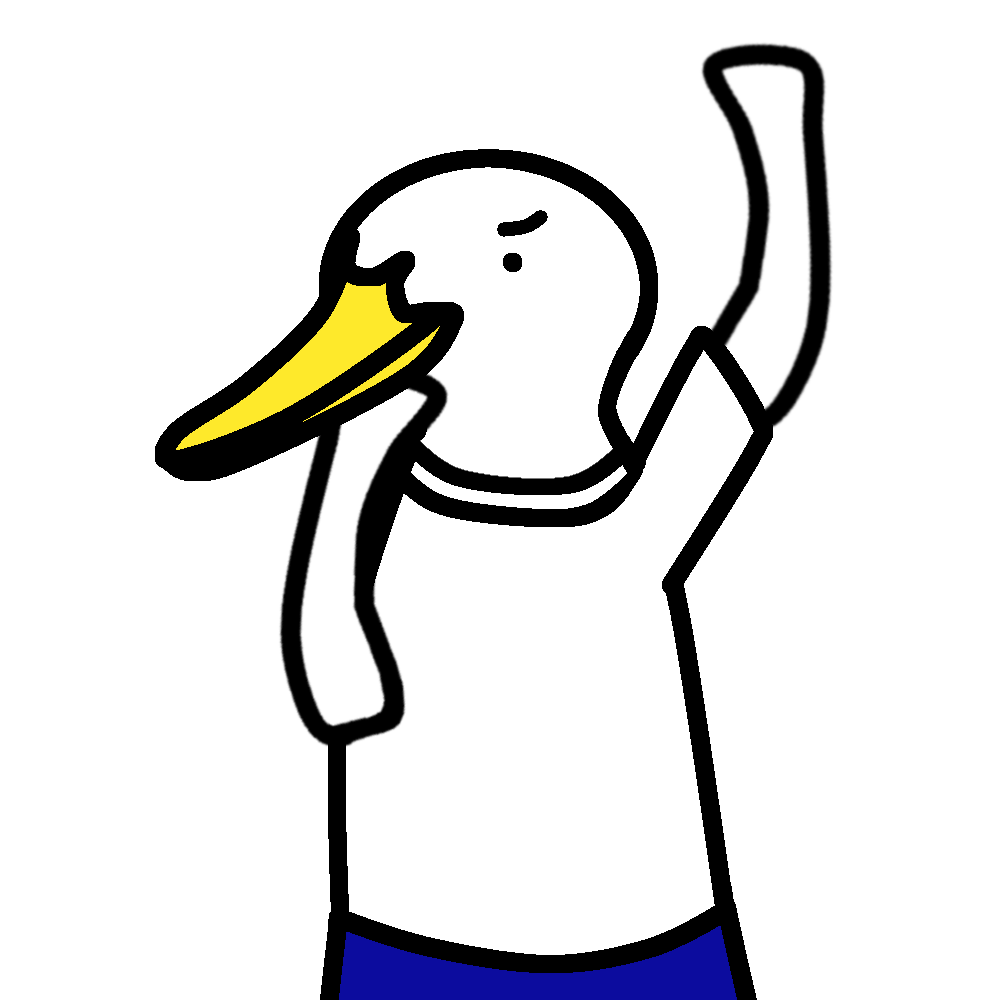
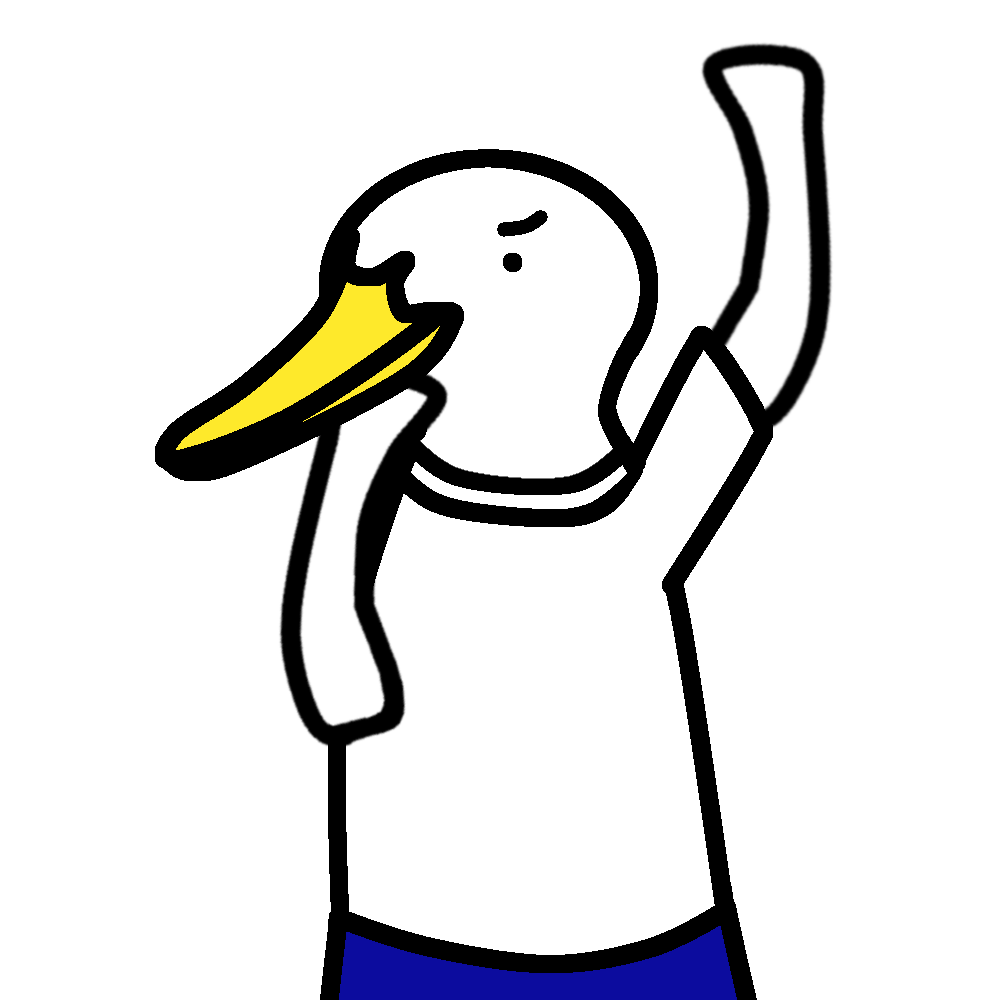
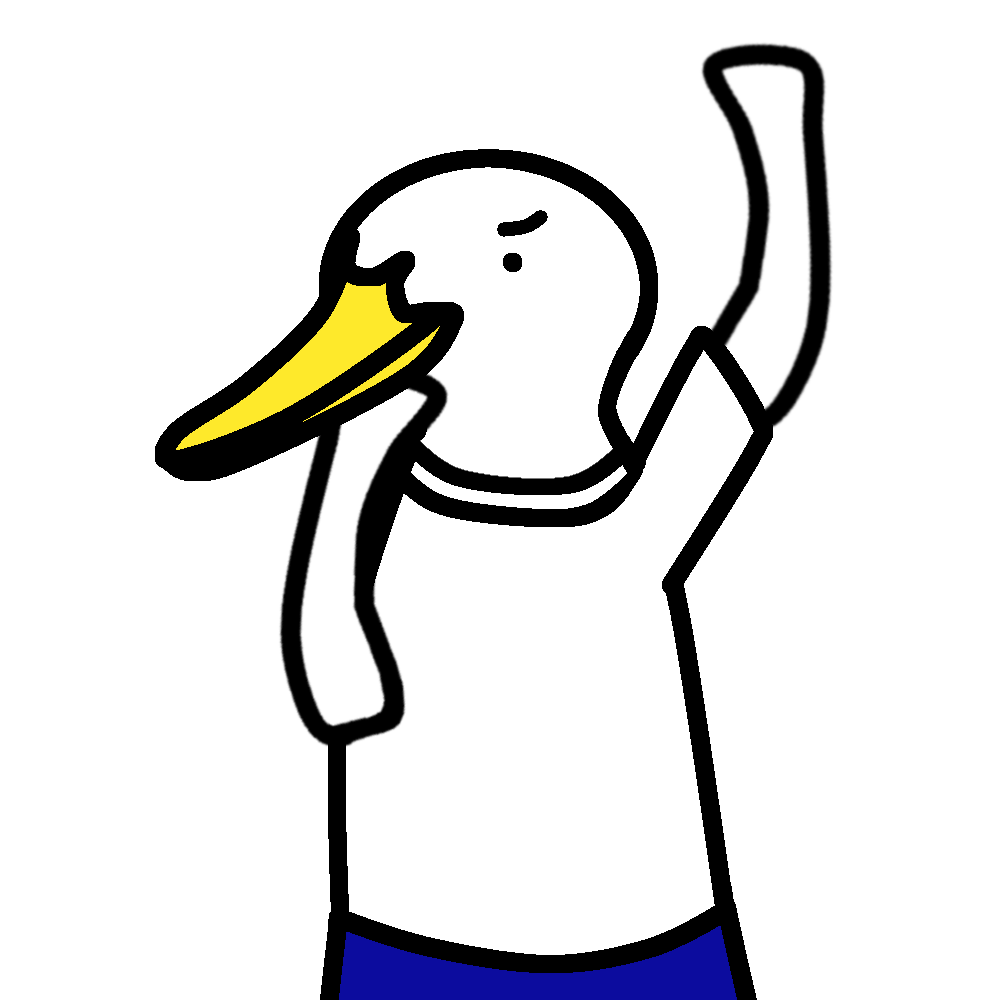
教科書を開いても、どこまで進めば終わりが見えるのか全然わからなくて、気が遠くなります。
模試の結果が返ってくるたびに、一喜一憂して、また次の模試まで同じことの繰り返し…「一体いつになったらこの苦しみから解放されるんだろう」って、何度も考えてしまいます。



ああ、その気持ち、痛いほどわかるよ。
「独学」だと、誰かに進捗を確認してもらうわけでもないから、余計に終わりが見えづらいんだよね。積み上がった教材を見ると、うんざりする気持ちになるのも当然だよ。
2. 社会との隔絶感と自己肯定感の低下
友人たちが社会で活躍していくのをSNSなどで見聞きするうちに「自分だけが取り残されているのではないか」という孤独感に襲われることがあります。
日々の努力が目に見える形で評価される機会も少なく、自己肯定感が低下しがちになります。「本当に自分は合格できるのだろうか…」という疑念が頭から離れなることがあるようです。



SNSを開くと、友達はみんな仕事で成果を出したり、楽しそうな毎日を送っていたりするんですよね…。
それを見るたびに「自分だけがこんなに時間を使って、一体何をやっているんだろう」って、すごく孤独を感じてしまいます。
誰にも褒められないし、自分の成長もなかなか実感できなくて、自信を失いかけています…。



うんうん、僕も独学で引きこもって勉強していた時期は、すごく孤独を感じたよ。
社会との繋がりが薄れていくような気がして、焦りや不安が募るんだ。それに、独学だと自分の頑張りを客観的に評価してくれる人がいないから、どうしても自己肯定感が下がりがちだよね。
3. ルーティン化による刺激の喪失と目標の曖昧化
毎日同じような学習を繰り返すうちに、新鮮な刺激がなくなり、単調な作業のように感じてしまいます。
最初の頃の「絶対に合格する!」という強い気持ちも、日々の忙殺の中で徐々に薄れていくことがあります。「何のためにこんなに頑張っているんだっけ…?」と、ふと目標を見失いそうになる瞬間が訪れてしまうことがあるようです。



毎日同じ時間に起きて、同じように勉強して…もう何が楽しくてやっているのかわからなくなることがあります。
「絶対に合格する!」って最初はあんなに燃えていたのに、今はただただ作業をこなしているような感覚で…。
たまに「何のためにこんなに苦しい思いをしているんだろう」って、目標を見失いそうになるんです。



ああ、ルーティン化は独学の落とし穴の一つだよね。
どうしてもマンネリ化して、モチベーションが維持しにくくなる。最初の頃の熱意が冷めてしまうのも、無理はないよ。
独学の場合、学習環境やリソースに制限があることが一般的です。これにより、学習に適した場所や時間を見つけることが困難になり、学習習慣が定着しづらくなることがあります。
学習リソースが限られていることは必ずしもデメリットではなく、限られたリソースを効率よく利用することで短期合格を目指せることがあります。しかし、これは試験エリートで、効率的な勉強法をすでに習得している方向けの勉強方法のように思います。
そんな中でも、もちろん「独学」には大きなメリットはあります。
すでに、読者の皆様は「独学」に魅力を感じられているため、この記事を読んでいるかと思います。詳細なことは記載しませんが、以下のようなことが考えられるのではないでしょうか?
・自分のペースで勉強を進めることができる
・費用が安く済む
・学習方法を自由に選択できる
しかし、理想ばかりを見ていては、司法試験という険しい道のりを乗り越えることは難しいと言わざるを得ません。
もちろん、デメリットもあります。先ほど挙げた難しさと重複しますが、ざっとまとめます。
・指導者の不在
・効率的な学習計画の難しさ
・学習環境の整備
・モチベーションの維持が難しい
・フィードバックの欠如
独学では、専門的な指導者がいないため、理解が不十分なまま進めてしまったり、誤った解釈を持続させる可能性があります。また、自分の弱点や誤解に気づかず、効果的な学習ができないことがあります。司法試験の勉強を開始し、挫折をしてしまう人も多いのが事実です。
独学では、自分で学習計画を立てる必要がありますが、どのように進めていくべきか分かりにくいことがあります。その結果、効率的な学習ができず、時間を無駄にしてしまう可能性があります。
独学では、自分で学習環境を整える必要がありますが、自宅では集中力が続かなかったり、環境が整わないことがあります。また、必要な教材やリソースを自分で揃える必要があり、コストや手間がかかることがあります。
独学では、自分自身でモチベーションを維持するのが難しいことがあります。学習が進まなかったり、成果が出ないときに、自分を奮い立たせることが困難になることがあります。
独学では、他人からのフィードバックや評価が得られないため、自分の学習状況や成果を客観的に把握することが難しいです。また、過去の試験問題や模擬試験で自己評価を行っても、自分の解答が正しいかどうか確信が持てないことがあります。
以上のとおり、独学のデメリットをご紹介させて頂きました。逆に、上記をデメリットとは思わないのであれば、独学でチャレンジをするのもありだと思います。また、今回の記事のテーマからは外れますが、スポット的に予備校を利用するというのもおすすめです。
司法試験では、学習で「つまづきやすいポイント」があります。
もし「独学を進める中で」や「進めた後」に、壁にぶつかり、学習の進め方に迷いや不安を感じているのであれば、一度、基礎講座・入門講座という「導き手」を迎えることを真剣に検討してみてはいかがでしょうか?
単発の講座もありますし、無料体験もありますので、一度試してみても良いのではないでしょうか?>>>「講座」の詳細はこちら
どれだけ熱意があっても、最初に躓いてしまうと再起が難しかったりします。逆に、入門段階をクリアできれば、法律の勉強の楽しさが分かってくるため、勉強の継続がしやすくなります。
「学習のつまづきやすいポイント」と「乗り越えるコツ」は法律の勉強は最初が肝心であることは法律の勉強法の記事で解説をしています。
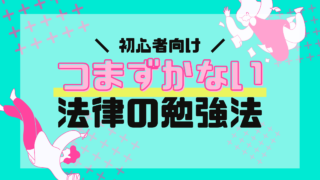
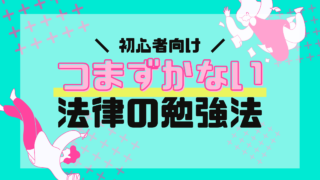
「講座」を受講するメリットは、大きく分けて、以下の4つではないでしょうか?
やはり、先ほど挙げた「独学」を難しくさせる原因を解決するようなものが多いです。
「入門講座・基礎講座」を受講する 圧倒的なメリット
①難解な法律用語と概念を「分かりやすく」解説
②「司法試験合格に特化」した講義
③「効果的な学習」が可能になる
④「学習継続」を力強くサポートする環境
講師は、専門的で難解な法律用語を平易な言葉に置き換えて説明し、受講者に分かりやすく伝えることを心掛けています。このようなアプローチにより、初心者や専門外の人でも、法律の概念や理論を理解しやすくなります。また、具体的な事例や現実的な状況を用いることで、抽象的な概念が具体的にイメージできるようになり、より深い理解が可能となります。また、講師は、受験指導のプロです。過去の受験生がどのような点で躓きやすいのかも理解しています。しかし、講師の能力や個性や指導方針もそれぞれかと思います。
実際に講師を選ぶ際には、体験講義を受けるようにしましょう。
入門講座や基礎講座では、司法試験試験対策を重視し、出題される知識に特化したカリキュラムが提供されます。これにより、受講者は重要なポイントに集中して学習ができ、無駄な時間を削減できます。また、講師は過去の試験問題や出題傾向を分析し、試験に対応した効果的な学習法を教えてくれます。これにより、受講者は短期間で必要な知識を習得し、論文式試験に臨む自信をつけることができます。
基本書で勉強をしていると、およそ司法試験対策としては不要な論点や判例の解説もされています。ある程度、勉強が進んでくると自分で判断ができるかと思いますが、初学者の場合には、試験対策上、重要な知識なのかどうかも判断できません。この意味で、司法試験対策に必要な知識の講義を受けられるというのは大きなメリットかと思います。
予備校にたまったノウハウを生かした内容でカリキュラムなどは組まれています。そのため、司法試験合格のための効果的な学習が可能になります。
具体的には、以下のようなことにより、効果的な学習を実現しています。
効果的な学習を実現する要素
・プロの指導
・明確な学習カリキュラム
・充実した学習環境
予備校では、法律の専門家や経験豊富な講師から指導を受けることができます。彼らの知識と経験を活用することで、法律の理解を深め、試験対策を効率的に行うことができます。
予備校では、司法試験に必要な知識とスキルを網羅したカリキュラムが提供されます。独学の場合、どのように学習を進めていくべきかが分かりにくい場合がありますが、予備校では学習計画が明確に示されるため、効果的に学習を進めることができます。
予備校では、集中して学習できる環境が提供されます。自宅での学習では、集中力が途切れやすいことがありますが、予備校では他の受験生と一緒に学習することで、モチベーションを維持しやすくなります。
「独学」合格するのが難しい理由でも述べたように、計画の立案や、モチベーションの維持などで難しさを感じることがあります。
入門講座・基礎講座では、事前に組まれた順番に従い講座を受講することで、受講者は自分で学習計画を立てる手間が省けます。
また、モチベーションの維持の観点からも、進捗が分かりやすかったり、学習するためのサポート面などにも配慮された作りのため、学習を続けやすくなります。
法律の学習は、 土台 が最も重要です。最初の段階でしっかりと 基礎 を築くことが、その後の学習の 質 と 速度 を大きく左右します。入門講座・基礎講座は、まさにその 土台 を築き上げるための 投資 なのです。
近年、オンライン講座の普及により、 質の高い 入門講座・基礎講座が、以前よりも 手頃な 価格で受講できるようになりました。独学で 遠くまで行く ことを考えれば、初期 投資 が、合格への 最も短く確実な道 と言えるでしょう。
近年、オンライン講義が主流になったこともあり、入門講座、基礎講座の受講料は低価格化しています。
それでも、膨大な試験範囲をカバーする講座のため数十万円することが多いです。しかし、10万円以内の基礎講座も登場しています。昔と異なり、選択肢が多いため、事前によく検討してみましょう。
今回は、独学での司法試験合格が難しい理由と入門講座・基礎講座を受講することで、その難しさを克服することができることを解説させて頂きました。
司法試験合格は決して 簡単な 道ではありません。しかし、 正しい選択 をすることで、その 困難さ は大きく軽減されます。独学という険しい道を選ぶ前に、確かな道標 となる入門講座・基礎講座を検討してみませんか?
基礎講座・入門講座を通じて、法律の基礎知識を身につけ、論文式試験に対応できる力を養い、継続的な学習を続けることができるでしょう。
おすすめの基礎講座・入門講座のご紹介
①アガルート:令和の王道予備校
令和4年司法試験合格者専有率が極めて高く、さらに、人気予備校調査において第一位を獲得している信頼出来る予備校です。
\300時間の挑戦、合格への全力疾走/


\全7科目、100時間。スピードインプット講座での確実な知識再構築/
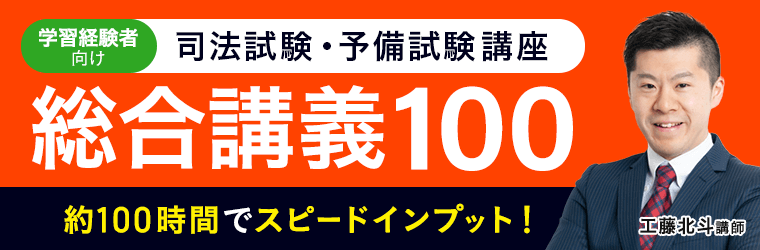
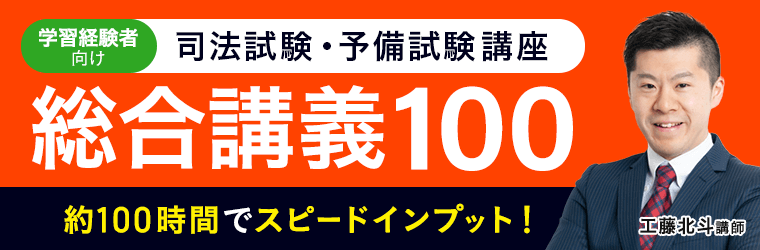
賢く資格予備校を利用して、司法試験合格を目指してみませんか?。
本記事は、アガルートアカデミーのインプット講義のうち「総合講義100」について徹底的にレビューをしています。関心のある方は是非、ご確認ください。
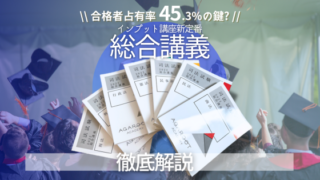
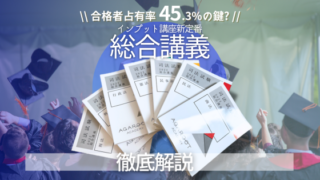
②スタディング:低価格かつスマホ特化講義
スマホ学習をするならスタディングがおすすめです。
スタディングのオンライン講座は、忙しい人向けに開発され、短期合格者の勉強法を基にしています。テレビ番組のようなわかりやすい動画講義をスマートフォンでいつでもどこでも視聴でき、WEBテキスト、自動採点機能付きの問題演習、学習レポート機能などの効率的な学習システムを提供しています。
運営コストの削減により、受講料も低価格に抑えられています。


③BEXA:ベテラン講師の講義を低価格で実現
資格講座プラットフォームのベクサもおすすめです。プラットフォーム型のため一般的な予備校の講座よりも低価格で受講することが出来ます。ベテラン講師の授業を低価格で受講することができます。また、細かなニーズに対応した講座が販売されています。他の予備校にはないメリットかと思います。
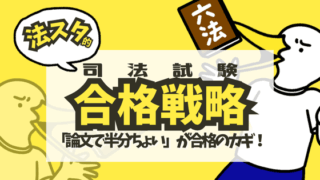
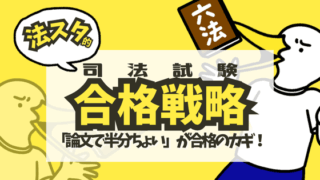
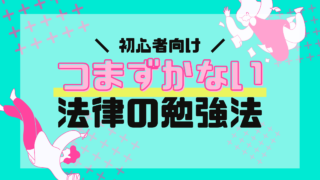
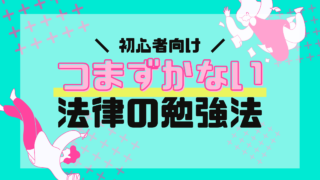
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
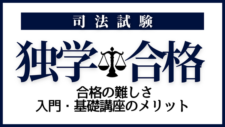
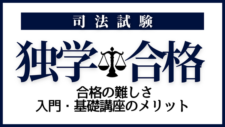
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

