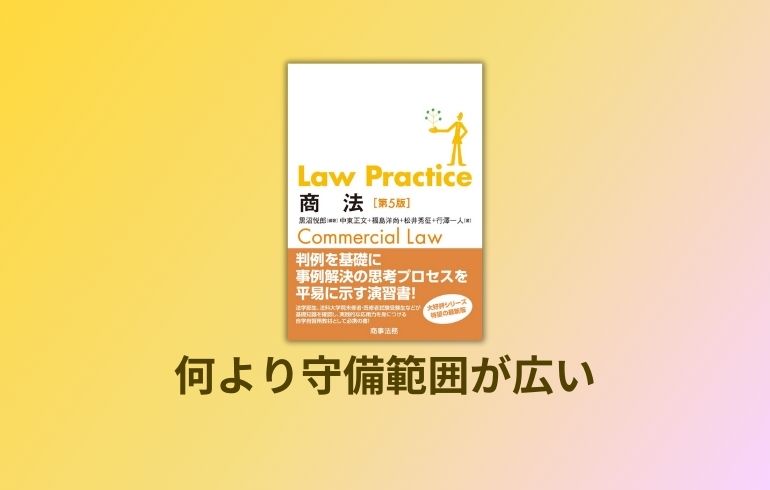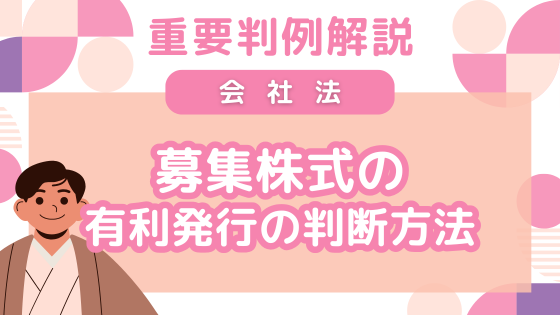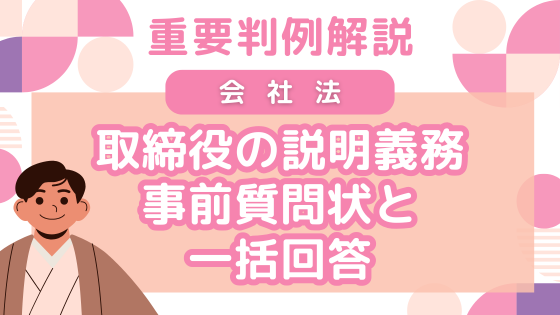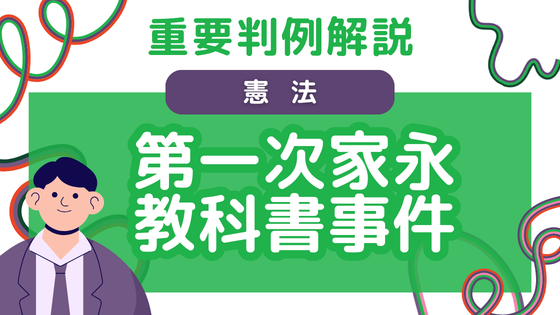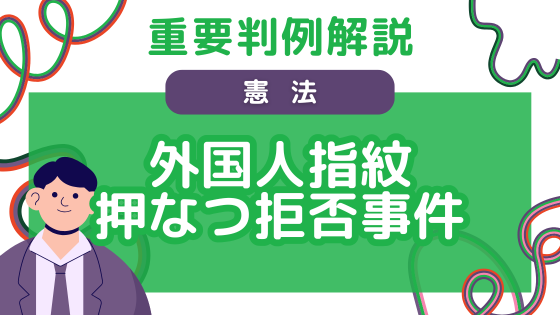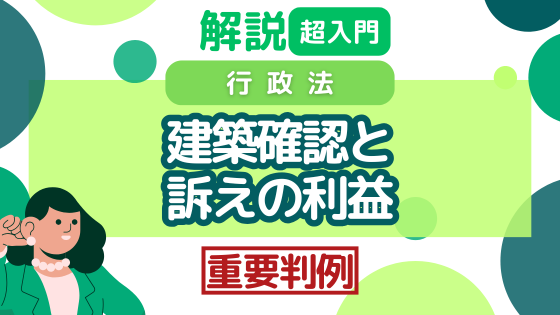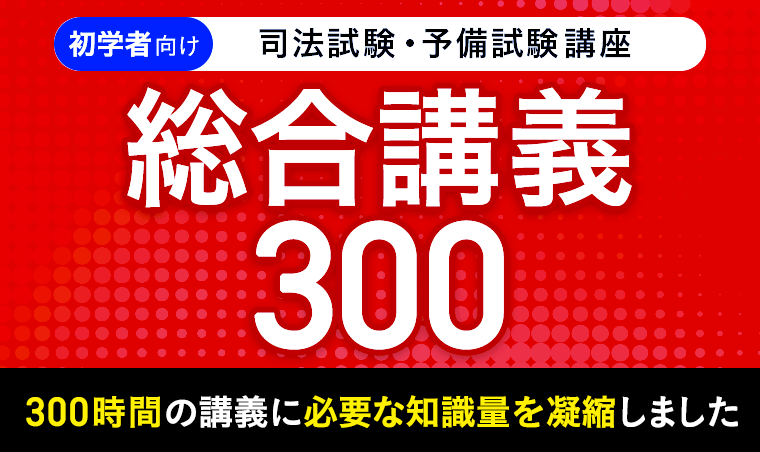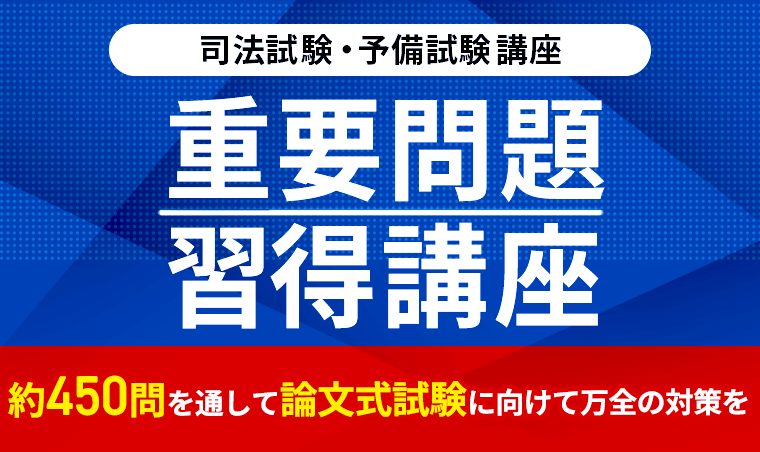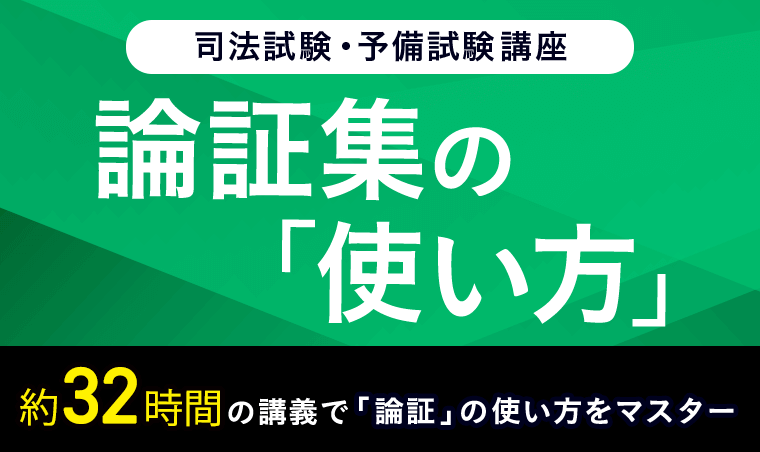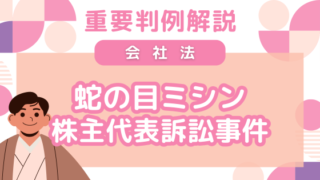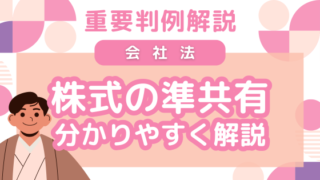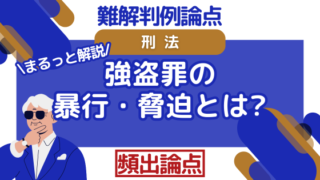【初学者向け】蛇の目ミシン事件の分かりやすい解説と論述のポイント【司法試験・予備試験】
当ページのリンクにはPRが含まれています。
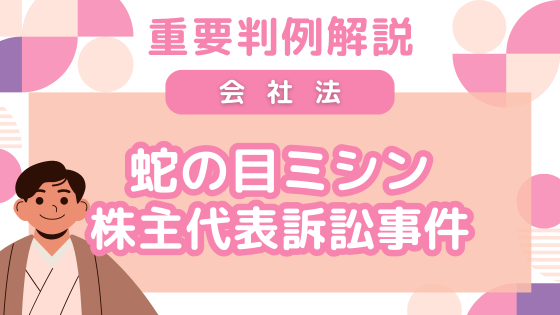
法書ログライター様執筆記事です。
前回までの会社法の判例論点解説記事
・【会社法】株式の準共有をわかりやく解説【初学者向け】
・蛇の目ミシン株主代表訴訟事件の分かりやすい解説と論述のポイント←イマココ
この記事では、蛇の目ミシン事件判決(最判平18年4月10日、会社法判例百選12事件)について、株式譲渡の対価の交付が「株主の権利の行使に関」する利益供与(会社法120条1項)に該当するかという点を中心に解説します。



ミシンメーカーでは、蛇の目ミシン(現:ジャノメ)って有名らしい!どんな事件だったのか見ていこう!
目次
蛇の目ミシン事件の事案
事案を簡略化しご紹介すると、以下のようになります。
蛇の目ミシン事件の事案
上場会社であるA社の株式を、大量に買い占めたBは、A社に対して、①当該株式を暴力団に売却したと示唆し、売却を取り消すためには300億円が必要であるとして、300億円の交付を要求しました。さらにBは、②BからCに株式を売却して、A社がCの管理下に入ることを匂わせて、Bの関連会社がA社株式等の取得のために借り入れた債務を肩代わりすることを要求しました。
A社の代表取締役Yは、取締役会の承認を経て、「①暴力団からBへの株式の譲渡にかかる対価相当額としてBに300億円を交付」し「②966億円の債務の肩代わりと担保の設定(あわせて本件方策)」をしました。
A社の株主であるXは、株主代表訴訟を提起し、「①Bへの300億円の交付」と「②本件方策」は、利益供与に該当すると主張しました。
①と②について、本判決の当時、会社法は制定されていませんでしたが、会社法120条1項に対応する旧商法の規定にいう『株主ノ権利ノ行使ニ関シ』利益を供与したといえるかが問題になりました。
利益供与に該当すると、どのような法律効果が生じるのか?
会社法120条1項にいう、利益供与に該当すると、どのような法律効果が生じるでしょうか?
[会社法 120条1項]
株式会社は、何人に対しても、…株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与…をしてはならない。
120条1項は、上記のように規定しており「株主の権利の行使に関する利益供与」を禁止しています。
このような利益供与に該当すると、利益供与を受けた者はその利益を会社に返還しなければならず(同条3項本文)、利益供与に関与した取締役は供与した財産の価額に相当する額を会社に支払う義務を負います(同条4項本文)。
本判決に会社法が適用されるとして、①Bへの300億円の交付と②本件方策が「株主の権利の行使に関」する利益供与に該当すると、BはA社に対して300億円の返還を(同条3項本文)、A社の代表取締役Yは、A社に対して300億円の返還(同条3項本文)と966億円の支払い(同条4項本文)をしなければならないことになりそうです。



当時はバブル景気で、Bは他の会社の株も買い占めていたらしいぞ!
「株主の権利の行使に関し」の該当性
本判決の判旨を見ていきましょう。
本判決は「①Bに対する300億円の交付が利益供与に該当するか」についての判断において、『株主の権利の行使に関し』の判断基準を示しました。
規範部分
「株式の譲渡は株主たる地位の移転であり,それ自体は『株主ノ権利ノ行使』とはいえないから,会社が,株式を譲渡することの対価として何人かに利益を供与しても,当然には商法294条ノ2第1項が禁止する利益供与には当たらない。しかしながら,会社から見て好ましくないと判断される株主が議決権等の株主の権利を行使することを回避する目的で,当該株主から株式を譲り受けるための対価を何人かに供与する行為は,上記規定にいう『株主ノ権利ノ行使ニ関シ』利益を供与する行為というべきである。」
「会社法120条の趣旨」は株主の権利の行使を、経営陣に都合の良いように操作する目的で、会社財産が浪費されることを防止し、会社経営の公平性・健全性を確保する点にあります。
そうすると、会社の経営陣と意見が対立する株主や経営を乗っ取ろうとする株主などの、会社から見て好ましくないと判断される株主が、自身に有利な決議の成立をもくろみ議決権を行使することが予想される状況などにおいて、会社が株主権の行使を回避するため、第三者が当該株主から株式を譲り受けるための対価を第三者に供与する行為は『株主の権利の行使に関し』利益を供与する行為にあたります。
本来、株主は経営陣の意向に関わりなく自由に権利を行使することができるところ、経営陣が自らの都合で株主の自由な権利行使を妨げることは会社経営の公平性・健全性を害します。さらに、そのような目的で会社財産を用いることは、会社の利益獲得につながらず、浪費にあたるからです。
上記枠内の太字部分は、このような前提のもと、述べられています。



論述の際には、単に規範を暗記するのみではなく、
その意味や内容を理解するように努めよう!
▽あてはめ部分①▽
①のあてはめ部分を見ていきましょう。
そして、「A社は、Bが保有していた大量のA社株を暴力団の関連会社に売却したというBの言を信じ,暴力団関係者がA社の大株主としてA社の経営等に干渉する事態となることを恐れ,これを回避する目的で,上記会社から株式の買戻しを受けるため,約300億円というおよそ正当化できない巨額の金員を,…Bに供与したというのであるから,A社のした上記利益の供与は…『株主ノ権利ノ行使ニ関シ』されたものというべきである。」
あてはめ部分においては、暴力団の関連会社というA社から見て好ましくない株主が、A社の経営等に干渉することを回避する目的で、暴力団の関連会社からBが当該株式を買い戻すための300億円を、Bに供与した行為が「株主の権利の行使に関し」されたと述べています。
つまり、暴力団の関連会社であっても、A社の株主であるので、議決権を行使することにより、自由にA社の経営に関わることができます。しかし、暴力団の関連会社が、A社に好ましくない株主であるので、A社は議決権の行使による経営への干渉を回避する目的で、暴力団の関連会社の株主の地位をBに移転させるため、株式の譲渡の対価相当額300億円をBに供与しています。当該利益の供与は、暴力団の関連会社による議決権の行使等の『株主の権利の行使に関し』されています。
論述の際には、以下の点を明らかにしましょう。
論述で明らかにしておくポイント
・どの株主が会社から見て好ましくない株主なのか?
・当該株主の議決権の行使を阻止する目的で株式譲渡の対価の交付がされたのか?



論述では、この2点を明らかにしておくべきなんだね!
▽あてはめ部分②▽
②のあてはめ部分も見ていきましょう。
本件方策においては形式的にはA社の関連会社が融資の主体として関与するものの,A社自体やその100%子会社…も所有物件に担保を設定するなどしている上,関連会社が支払不能になれば,A社が最終的に関連会社の債務を引き受けざるを得ないという前提があったというのであるから,本件方策に基づく債務の肩代わり及び担保提供の実質は,A社が関連会社等を通じてした巨額の利益供与であることを否定することができない。そして,本件方策は,…将来Bから株式を取得する者〔C〕の株主としての権利行使を事前に封じ,併せてBの大株主としての影響力の行使をも封ずるために採用されたものであるから,本件方策に基づく債務の肩代わり及び担保提供が…『株主ノ権利ノ行使ニ関シ』されたものであるというべきである。
ここでは、Bから将来株式を取得する者〔C〕とBが、A社から見て好ましくない株主とされています。Cが株式を取得することで、A社がその管理下に置かれるという事実関係から、〔C〕とBの議決権の行使により、A社の経営への干渉が考えられます。A社は、このような事態を回避する目的で、本件方策を行ったといえます。
そして、Bが負う株式譲渡の対価である966億円の債務を、A社が最終的に引き受けることで、A社が当該対価相当額を、Bに交付したことと経済的に変わらないといえます。
したがって、本件方策は『株主の権利の行使に関し』てされたものといえます。
なお、本判決において、②に関するA社の代表取締役Yの、A社に対する責任(120条4項本文)として、A社に支払う額は明らかにされていません。しかし、上記の経済的な同一性に着目すると、YがA社に対して支払う額はA社から流出した財産の価格として966億円と考えられます。
以上に見てきた通り、本判決は「①A社のBへの300億円の交付」と「②本件方策」のいずれについても、『株主の権利の行使に関』する利益供与に該当すると判断しました。
蛇の目ミシン事件の論述のポイント
ここで、論述のポイントを整理していきます。
ポイント①規範を明示する
ポイント②関係者の利害関係に着目する
ポイント①規範を明示する
会社が株主に対して、株主と第三者との間の株式譲渡の対価を交付することは、当然に『株主の権利の行使に関』する利益供与にあたりません。
会社から見て、好ましくないと判断される株主が、議決権等の株主の権利を行使することを回避する目的で、当該株主から株式を譲り受けるための対価を、何人かに供与する行為は『株主の権利の行使に関』する利益供与(会社法120条1項)に該当します。
論述の際には、本判決が示した規範を明示しましょう。
ポイント②関係者の利害関係に着目する
関係者の利害関係にも着目しましょう。
問題文の事案における、会社と株主との間の利害対立などに注目して、「どのような理由から当該株主が好ましくないと判断できるのか?」や「会社は当該株主に株式譲渡の対価を交付することでどのような事態(当該株主による議決権行使により取締役が入れ替わる等)を回避する目的があったか?」という点を具体的に明示しましょう。
利害関係に関する具体的な明示例
・どのような理由から当該株主が好ましくないと判断できるのか?
・会社は当該株主に株式譲渡の対価を交付することでどのような事態(当該株主による議決権行使により取締役が入れ替わる等)を回避する目的があったか?



論述の際は、上記2つのポイントを意識してみてくれ!
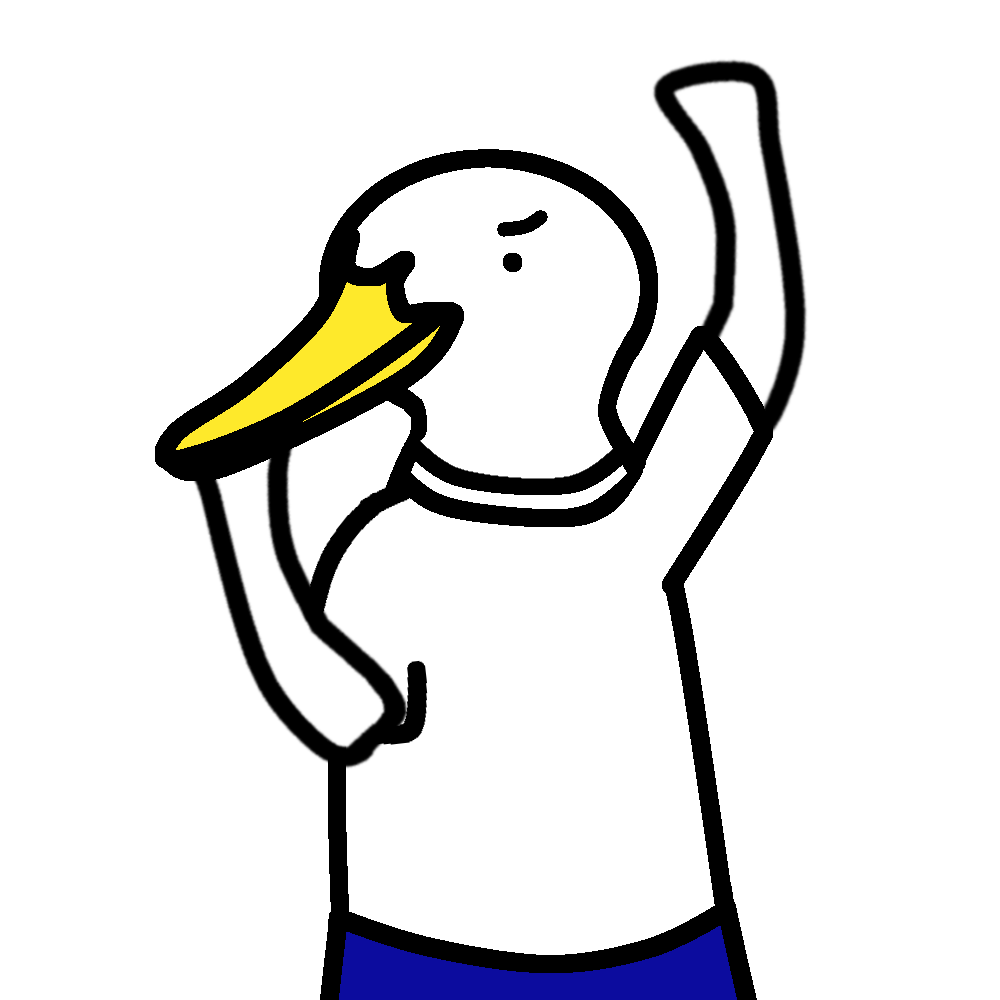
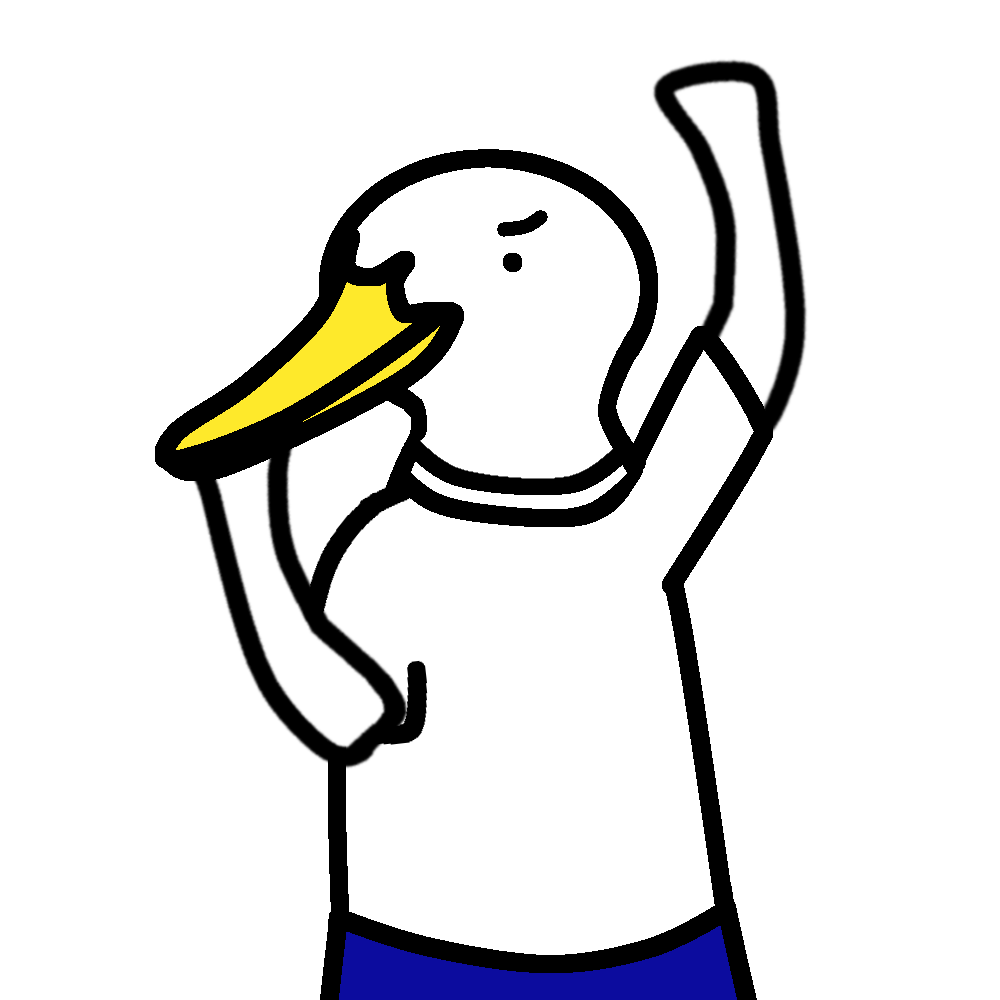
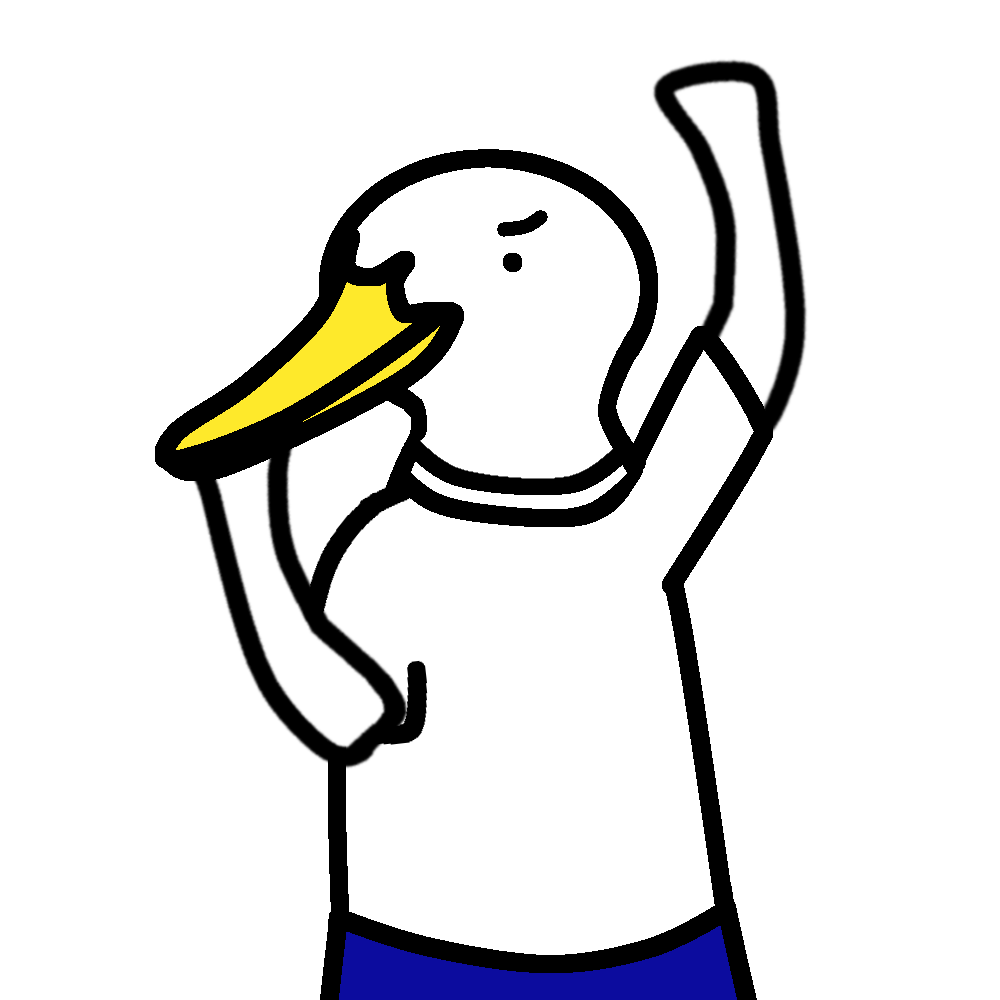
承知しました!
おわりに
この記事では、「株主の権利の行使に関」する利益供与(会社法120条1項)の判断基準について学習しました。
利益供与が問われる問題においては、120条1項の該当性を検討した上で、同条3項及び4項により、誰がどのような責任を負うのか、という点を明らかにすることが求められます。この記事では、120条1項の該当性を中心に解説しましたが、この点についても基本書などを読んで押さえておきましょう。
また、「株主の権利の行使に関」する利益供与に該当しても、「当該利益が,株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的に基づき供与される場合であって,かつ,個々の株主に供与される額が社会通念上許容される範囲のものであり,株主全体に供与される総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼすものでないとき」には、例外的に違法性が阻却されるとした裁判例(東京地判平成19年12月6日)も存在します。こちらもあわせて確認しておきましょう。
本稿が、少しでも受験者の一助になれば幸いです。
▽参考文献▽
会社法判例百選〔第4版〕別冊ジュリスト第254号(2021)
高橋ほか『会社法〔第3版〕』(弘文堂,2020)
田中亘『会社法〔第4版〕』(東京大学出版会,2023)