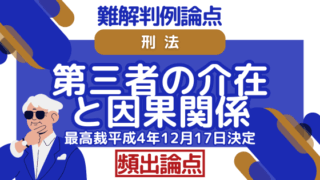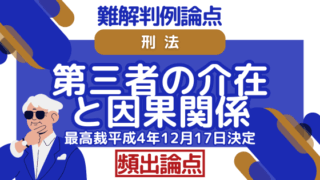【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
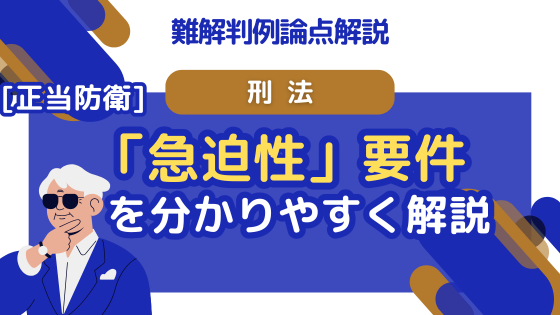
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。
動画解説の「法スタチャンネル」も大好評、運営中!
▽動画解説を順次公開中▽



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)
初めまして、宇津井です。
今回から4回にわたって、「正当防衛」についての解説をしていきます。



まずは「正当防衛」の要件を、しっかりと条文に照らしてみていきましょう!
<編集部コメント>
今回の記事は、法スタの方針変更に伴い、ライター名を明示してお届けします。刑法や刑事訴訟法の判例・論点の解説記事を担当している宇津井さんによる解説です。
「正当防衛」の要件を条文や重要判例をもとに詳しく掘り下げます。
急迫性の判断基準や、判例が示す具体的なケーススタディまで、試験対策にも役立つ内容が満載です。初学者から中上級者まで学びの多いシリーズになっていますので、ぜひ最後までご覧ください!



みなさ~ん!
この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。



「これさえやりきれば、もう怖くない!」
そんな演習書や問題集が欲しいと思ったことはありませんか?
通称「重問」と呼ばれるアガルートの重要問題がおすすめ



その人気の秘密や効果的な活用方法について、アガルートの専任講師に直接インタビューを行いました。
受験生に支持される理由が詰まった記事、ぜひチェックしてみてくださいね!
今売れてます!!
\司法試験合格者占有率37.8%/
▼重要問題だけで合格する究極の勉強法【独占インタビュー】▼


「正当防衛」は何か?を見ていきます。
「正当防衛」が成立する要件は「①急迫」「②不正」な侵害に対して、「③防衛するため」「④やむを得ずにした」行為であることです。
本来なら犯罪になることもありますが、「正当防衛」が認められれば罰せられません。
刑法(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。



今まさに危険が迫っている不正な攻撃から、自分や他の人を守るために、やむを得ず行った行為のことですね!
「正当防衛」は以下の4つの条件を満たす必要があります
①急迫:侵害が現在進行形であるか、今にも始まりそうな状態であること
②不正:侵害が法律に反していること(例:殴る、蹴る、物を盗むなど)
③防衛するため:自分の身を守るため、または他人の権利を守るために行った行為であること
④やむを得ずにした:他に侵害を防ぐ方法がなかった、またはそれに近い状況であったこと
今回は「侵害が『①急迫』であるとはどういう場合か?」について解説していきます。
「侵害の急迫性」とは「侵害が現在のものであるか、差し迫っていること」をいいます。



まずは、「自力救済」の禁止について見ていくぞ!
法律では「自力救済」が禁止されているが、その例外として、「正当防衛」があるんだ!
そもそも法律には「自力救済」の原則というものがあります。
「自力救済」は原則禁止されています。
「自力救済(じきゅうこうい)」とは?
法的な手続きや公的機関の助けを借りずに、自分の権利や利益を自分の力で回復・実現しようとする行為を指します。
過去に受けた侵害や将来受ける侵害の回復は、法に任せなければなりません。
ただ、例外的に許容される場合があります。その最も代表的なものが「正当防衛」です。
「自力救済の禁止」の例外として「正当防衛」は許容されるのは、法による保護を待っていては、間に合わない「現在の侵害」を防ぐ場合に限られるということです。
ここで重要なのが「侵害の急迫性」です。法による保護を待っていては間に合わない「現在の侵害」を防ぐ場合に限られます。
「侵害の急迫性」とは、「侵害が現在進行形であるか、今にも始まりそうな差し迫った状態であること」を意味します。「個人の生命、身体、財産」といった重要な権利が、まさに侵害されようとしている、または侵害されているという緊急の状況下では、一時的に法の原則が後退することがやむを得ないとされています。
「急迫性」は「正当防衛」の範囲から、すでに終わった過去の侵害や、まだ起こっていない将来の侵害を除外する重要な意味を持ちます。
すでに終わった過去の侵害や、まだ起こっていない将来の侵害これらの侵害に対しては、原則通り、法的な手続きによる解決が求められます。
要するに「正当防衛」の範囲から、過去と未来の侵害を除外する意味があります。
正当防衛の議論において重要な考え方の1つに「正は不正に譲歩しない」というものがあります。
これは「正当な権利を持つ者は、不正な侵害に対して、自分の権利を不当に諦めてまで回避する義務はない」という原則です。
不正な侵害を受けている状況で、自分の身を守るために反撃する際に「まず安全な場所に逃げることを考えるべきだ」という回避義務があるわけではないという意味です。



「危ないかも」と、たとえ予想ができても、その危険を避けるために、自分の行動を無理やり変える必要はないってことね!
ただ、無制限に反撃して良いという意味ではありません。
あくまで、不正な侵害に対して、自分の権利を守るための合理的な範囲内での行為が許容されるという考え方です。防衛の程度が過剰であったり、侵害がすでに終わっている状況での反撃は、正当防衛として認められない可能性があります(過剰防衛として、刑が減軽または免除される可能性はあります)。
このように、「急迫性」は、正当防衛が「自力救済の禁止」の例外として認められるための根幹となる要件であり、不当な侵害から自己や他人の権利を守るための、時間的切迫性を意味する重要な概念です。
この判例では「予期」という要素が「急迫性」の判断にどう影響するかについて、重要な線引きを示しています。単に「予期」していただけではダメで、その「予期」を利用して攻撃的な意図を持って行動したかどうか?が鍵となります。
≪昭和52年7月2日判決のポイント≫
・侵害が「予期」されていても、それだけで「急迫性」が否定されるわけではない
・しかし「予期」された侵害の機会を利用して、積極的に相手に危害を加えようとする意図があった場合は、「急迫性」を欠くと判断される
中核派に属するXらは、凶器を準備の上、集会を開いていた。
そこに対立する、革マル派のVらが攻撃をしかけてきて、一度は撃退した。再度の攻撃を予期したXらは、バリケードを強化し、待ち構えた。
VらはXらに攻撃をしかけ、反撃を受けた。
刑法36条が「侵害の急迫性」を要件としているのは、予期された侵害を避けるべき義務を課する趣旨ではない。
当然又はほとんど確実に、侵害が「予期」されたとしても、そのことからただちに「侵害の急迫性」が失われるわけではない。
しかし、同条が「侵害の急迫性」を要件としている趣旨から考えて、単に「予期」された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや「侵害の急迫性」の要件を充たさない。



相手が来るって分かってて待ち構えてたとしても、それは必ずしも悪いことじゃない。
でも、相手が攻撃してきたのをチャンスに、自分から積極的に相手を傷つけようとしたら、それは正当防衛とは言えないよ。
この判例では「急迫性」の判断において、単に侵害行為が行われている瞬間だけでなく「侵害者の攻撃意欲」や「再攻撃の可能性」を考慮することの重要性を示しています。
≪平成9年6月9日判決のポイント≫
・侵害者が体勢を崩した状況でも「急迫性」が継続すると認められる場合がある
・逃走可能性があったとしても、直ちに「急迫性」が否定されるわけではない
Vは、集合住宅の二階にして、被告人Xを鉄パイプで一回殴打し、更に追撃をしようとしてきた。
Xは、もみ合いになったり、助けを求めたり、鉄パイプを取り上げたりしていたが、最終的にVが鉄パイプを握りしめてふりかぶってきた。
そのとき、Vは、姿勢を崩して手すりの外側に身を乗り出してしまった。Vが、なおも鉄パイプを握りしめていたため、Xは、Vの足を抱えて持ち上げ、手すりの外に転落させた。Vは1階のひさしに激突し、加療3か月のけがを負った。
原審は「Xが、Vを転落させた時点で、Vは容易には元に戻りにくい姿勢となっており、Xはいつでも逃走できたため、急迫不正の侵害は終了していた」として「正当防衛」も「過剰防衛」も否定した。
Vは、被告人Xに対し、執ような攻撃に及び、その挙げ句に勢い余って手すりの外側に上半身を乗り出してしまったものであり、しかも、その姿勢でなおも鉄パイプを握り続けていたことに照らすと、
Vの、被告人Xに対する「加害の意欲」は、おう盛かつ強固であり、被告人Xがその片足を持ち上げて、同人を地上に転落させる行為に及んだ当時も存続していたと認めるのが相当である。
またVは、右の姿勢のため、直ちに手すりの内側に上半身を戻すことは困難であつたものの、被告人の右行為がなければ、間もなく態勢を立て直した上、被告人に追い付き、再度の攻撃に及ぶことが可能であったものと認められる。
そうすると、Vの被告人Xに対する急迫不正の侵害は、被告人が右行為に及んだ当時もなお継続していたといわなければならない。
VはXに対し鉄パイプで殴りつけ、さらに追いかけようとしていました。Xは抵抗を試みましたが、最終的にVが鉄パイプを振りかぶってきたため、危険が「まさに差し迫った(急迫した)状況」でした。この時点では、Xが身を守るための行動に出ることは、正当防衛として認められる可能性がありました。
しかし、その直後、Vは体勢を崩して手すりの外に身を乗り出してしまいます。



原審では、この時点で、Vからの物理的な攻撃が困難になったため、Xにとっての「急迫した侵害」は終わったと判断したんだよね!
Xは逃げることができたはずであり、「もはや身を守るための行動は必要なかった」と考えたんだね。
最高裁では、Vが体勢を崩した後もなお鉄パイプを握りしめており、Xに対する強い攻撃意欲を持ち続けていたことに注目しました。Vは、すぐに体勢を立て直して再びXに危害を加えようとする可能性が高いと判断されたのです。
つまり、Vの体勢は一時的に不利になったものの、Xにとっての危険な状況、すなわち急迫した侵害は、依然として継続していたと最高裁は捉えました。相手の攻撃の意図や、再び攻撃に出る可能性が否定できない状況下では、「急迫性」は途切れないと判断したのです。
ただし、XがVを階下へ転落させるという行為は、その急迫した侵害を防ぐための手段として、客観的に見て必要以上に強いものだったと評価されました。そのため、正当防衛としては認められず、防衛の程度を超えた過剰防衛と認定されたのです。



相手が体勢を崩してピンチに見えても、まだ攻撃する気満々で、すぐにまた襲ってくる可能性があるなら、その侵害はまだ「急迫」な状態だ。
だから、こっちが反撃しても、必ずしもアウトじゃない。ただ、やりすぎると「正当防衛」じゃなくて、「過剰防衛」になるけどね。
この判例では、侵害を予期していた状況下での被告人の「行動と意図」が「急迫性」の判断に大きく影響するということです。侵害が差し迫った状況(急迫性)があったとしても、行為者(X)側の行動や意図によっては、正当防衛が認められない場合があります。
≪平成29年4月26日判決のポイント≫
・侵害が予期されていても、それだけで直ちに「急迫性」が否定されるわけではない
・侵害を回避する容易な手段があったにもかかわらず、自ら危険な状況へ赴いた場合は「急迫性」が否定される
・防御の意図を超え、積極的に加害する意思を持って侵害に臨んだ場合も「急迫性」は否定される
被告人Xは、知人Vから身に覚えのない因縁をつけられた。
Vは、X宅の玄関扉を消火器で何度も叩いたり、電話で繰り返し怒鳴るなどしていた。Xはその態度に立腹していたところ、その翌日の夕方、Vから電話でX宅マンションの前まで出てくるよう呼び出された。
そこでXは、包丁をズボンに隠し持って出向いた。
Vは、ハンマーを片手にXに近づき、Xは殺意をもってVの腹部を包丁で突き刺した。Vは死亡した。
侵害を予期していた場合でも、侵害の急迫性については侵害を予期していたからといって直ちに満たされないわけではない。
・実際の侵害行為の内容と予期された侵害との異同
・行為者が侵害に臨んだ状況
・その際の意思内容
等を考慮し、その機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときなど、刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合には、侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきである。
Xは、
①Vの呼出しに応じて現場に赴けば,Vから凶器を用いるなどした暴行を加えられることを十分予期していながら,
②Vの呼出しに応じる必要がなく,
③自宅にとどまって警察の援助を受けることが容易であったにもかかわらず,
④包丁を準備した上,
⑤Vの待つ場所に出向き,
⑥Vがハンマーで攻撃してくるや,包丁を示すなどの威嚇的行動を取ることもしないままVに近づき,
⑦Vの左側胸部を強く刺突したものと認められる。
このような事情の状況に照らすと、侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきである。
Xは、Vから以前より嫌がらせを受けており、Vから呼び出された際、Vが凶器を使う可能性を十分に予期していました。にもかかわらず、Xは自ら包丁を準備してVのいる場所へ出向いています。
裁判所は、以下の点を重視し、この状況において「Vのハンマーによる攻撃」が始まったとしても、Xにとって「急迫不正の侵害」があったとは認められないと判断しました。
「急迫性」の判断において、単に侵害行為が行われた瞬間の状況だけでなく、行為者側のそれまでの行動、予期可能性、回避可能性、そして侵害に臨んだ際の意図を総合的に考慮することの重要性を強調しています。
たとえ客観的に侵害が差し迫っていたとしても、行為者自身が積極的にその状況を招き、攻撃的な意図を持っていた場合には、正当防衛は認められないということです。
単に「目の前で危険が迫っていた」という表面的な状況だけでは、「急迫性」は認められない場合があります。
「侵害の急迫性」の重要な判断ポイントは「侵害が現在のものであるか、差し迫っているか?」という点です。
「急迫性」の検討は、以下の流れで検討していきます。現在、侵害を受けていない場合の判断ステップも見ていきます。
もし現在、実際に攻撃を受けているのであれば「急迫の侵害」と言えます。
侵害者の主観的な意図は直接的には分からないため、離れようとしているか、攻撃的な態度を続けているかなど、客観的な事情(周りの状況)から推測します。たとえば、侵害者が離脱しようとしているのか否か、その侵害行為の態様が強いか否か、などです。
「重要判例②平成9年判決」では、「攻撃の執拗さと凶器を握っていたことから攻撃の意欲」と「すぐに体制を立て直して攻撃ができる」という点から攻撃の再開可能性を認定しています。
攻撃が再開されるまでに、警察などに助けを求める時間的な余裕があるかどうかで「すぐに再開できる」かどうか、つまり「法による救済」を得る時間的な余裕があったかどうかを判断します。
次に、侵害を『予期』していた場合の考え方を見ていきましょう。
「もしかしたら危ないかも」と侵害を「予期」していた場合であったり、なお回避しようとしなかったりしても、それだけで正当防衛の権利がなくなるわけではありません。
その機会を利用して積極的に相手に危害を加えようとした場合は「急迫性」が否定されることがあります。
しかし、判例は「侵害を予期する」のみならず、「その侵害を予期したうえで行った対抗行為」が、正当防衛の目的(刑法36条の趣旨)に照らして許容されない場合には「急迫性」を否定するとしています。
ただ、ここで重要なのは「回避義務があるわけではない」ということです。



危ないかもと予測したからといって、必ず安全な場所に逃げなければならない義務はないということだね!
言い換えれば、自身の正当な利益を犠牲にして、侵害者に対してわざわざ諦める(譲歩する)必要はないのです。
ただし、合理的な理由もなく、予測できた危険を避けずに、あえて反撃に出たような場合には「急迫性」が否定されることがあります。
「急迫性があったか?」を考える際の判断要素として、次の要素を総合的に見ます。
≪判断要素≫
重要なのは、①です。
そもそも侵害を予期していなければ、回避しないことが不合理とはとてもでなければいえません。加えて言えば、侵害を受ける可能性がほとんど確実であるといえなければ、回避しないのも合理的でしょう。
そして、その予期の内容と実際の侵害の状況が食い違っている場合には、侵害が予期できていたとはいえず、侵害を回避しない理由となるかもしれません。
次に、②です。
回避するのが容易であったり、そもそも侵害を受けそうな場所に赴く必要がない場合に、あえて侵害を受けに行くという状況であれば、急迫性を否定されることになるでしょう。
最後に、③です。
そして、侵害を予期しながら、侵害に乗じて侵害者に積極的に危害を加えようとする意思があるような場合には、急迫性が否定されます。このような意思は、客観的な事情から推認されます。
③がその代表例であり、過剰な準備や過剰な攻撃、先制攻撃があった場合には、予期したのみならずそれに乗じる意思があり、差し迫った侵害ではなかったと認められるでしょう。
今回は正当防衛第1回ということで、「急迫」について解説をしました。ところで、積極的に危害を加えようとする意思は、防衛の意思にも関わってきます。
それについてはおそらく第3回で解説することになります。
・大塚裕史『応用刑法I 総論』(日本評論社、2023)
・大塚裕史ほか『基本刑法I 総論[第3版]』(日本評論社、2019)
・佐伯仁志・橋爪隆編『刑法判例百選I[第8版]総論』(有斐閣、2020)
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼