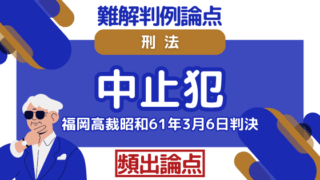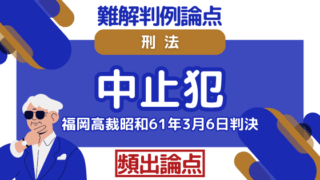【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。
動画解説の「法スタチャンネル」も大好評、運営中!
▽動画解説を順次公開中▽



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



皆さん、知ってましたか?
あのアガルートがアプリをリリースしています。



これにより講義視聴がより便利になり、学習の効率が大幅にアップしました!
是非、公式サイトで詳細を確認してください!
\講義動画のダウンロード可能/
データ通信料を気にせず受講しよう!!


今回は、司法試験予備試験の受験生、刑法を勉強されているかた向けに刑法の難解論点である「不能犯」の論点について解説してみようと思います。
なお、当サイトのおすすめの論証集は、アガルートの論証集です。おすすめの理由は過去記事をご参考にして下さい。



みなさ~ん!
この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。



「これさえやりきれば、もう怖くない!」
そんな演習書や問題集が欲しいと思ったことはありませんか?
通称「重問」と呼ばれるアガルートの重要問題がおすすめ



その人気の秘密や効果的な活用方法について、アガルートの専任講師に直接インタビューを行いました。
受験生に支持される理由が詰まった記事、ぜひチェックしてみてくださいね!
今売れてます!!
\司法試験合格者占有率37.8%/
▼重要問題だけで合格する究極の勉強法【独占インタビュー】▼


なぜ、論証から勉強するのかですが、答案で実際に書く形(論証)で勉強するのが、初学者にとって最も効果的な学習だと思うからです。
初学者が最初に目指すべき目標は、「何となくでもいいので答案を書けるようになる事」です。
何となく論証を書けるようになるには、答案の核となる規範定立部分、すなわち論証が書けるようになる必要があります。そして、論証を理解して学習すれば、問題提起と当てはめも出来るようになります。この段階となれば、何となく答案を書けるようになってきます。
答案を何となく書けるようになれば、答練を通して、基本論点の理解を深めていきます。このように答練を繰り返し行えば、最終的な目標である期末試験で上位の成績を撮ったり、資格試験に合格することが出来るようになります。
当然ですが、論証から勉強すると言っても、ただ覚えるだけでは意味がありません。なぜこのような論証になるのかを理解する必要があります。
刑法は、理解しなければならない論点が非常に多いです。大変な科目です。
不能犯の論証例は次のとおりです。
未遂犯の処罰根拠は、法益侵害の具体的危険性にある。そして、この危険性を客観的・科学的に判断すると、不能犯が広がりすぎることから、危険性判断の際の事実の抽象化は避けられない。
そこで、事実がいかなるものであったら、結果の発生があり得たかを科学的に解明し、一般人を基準にこの仮定的な事実が存在する可能性はどの程度あるかを事後的に判断し、法益侵害の具体的危険性を惹起したと言えるのか判断する。
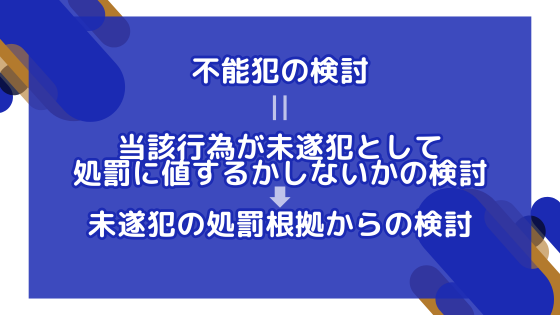
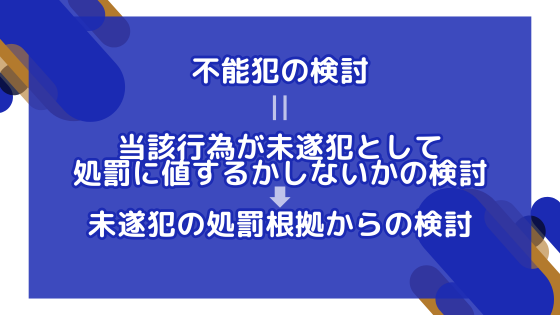
不能犯の問題は、当該行為が未遂犯として処罰に値しないかを検討するために行います。そのため、未遂犯の処罰根拠から不能犯の有無をどのように判定すべきかを論じることになります。
冒頭の論証構造は、実行の着手時期の論証と同じになります。なぜなら、不能犯も大きな分類をすれば、実行の着手の問題であるからです。この辺りから少し分からない方々がいるかもしれません。なので、まず、不能犯と実行の着手時期の関係を説明したい思います。
不能犯と実行の着手時期の論点の関係は、不能犯は行為の「質的危険性」が結果を惹起するに足りるものであるかの問題です。
また、実行の着手時期の問題は、行為の「量的危険性」がいつの段階で具体的危険性のレベルに達するかの問題であり、両者は着眼する視点が異なりますが、目的を共通(実行の着手の有無の検討)としている関係にあると説明することができます。
このような関係から、当該行為に〇〇罪の実行の着手が認められるためには、「量的」に見て当該行為に、未遂犯として処罰するに足りる危険性が認められ(実行の着手時期の問題)、かつ、「質的」に見て当該行為に、未遂犯として処罰するに足りる危険性が認められること(不能犯の問題)が必要となります。
もっとも、基本的に両問題が、同一の事案で問題になることは稀だと思います。考えられる場面として、窃取したキャッシュカードから預金を引き下ろそうと、ATMに挿入して、暗証番号を入力したところ、被害者が即時に利用停止を申し出ていたことから、引きおろせなかったという事案くらいです。
この事案の場合には、利用停止中だったことから、質的に見て占有侵害の現実的危険性があったのか(不能犯の問題)、その危険性があったとしても、暗証番号を照合した時点で窃盗の実行行為に着手したと言えるのか(実行の着手時期の問題)が問題となります。
この事案くらいを頭に入れておけばさしあたり問題ありません。
さて、論証の解説に戻ります。
この論証は、「修正的客観説」をもとに作られています。予備校本でよくみる論証とは違いますよね。予備校本では、具体的危険説をもとに論証が作成されていることが多いかと思います。
しかし、「具体的危険説」を採用してしまうと、方法の不能も場合に適切に処理することが難しくなります。当てはめをどのようにすべきなのか悩むと思います。このように、基準として不明確であることが具体的危険説への批判が認められ、受験生的にも使いづらい見解と言えます。
例えば、「毒針注射で患者を殺そうと注射したが、直前で針をすり替えられていたことから毒殺に失敗した」という事案において、「具体的危険説」を前提とすると、行為者がすり替えを認識していませんから、この限りですり替えの事実を判断の基礎に入れられないことは明らかです。
しかし、「一般人がすり替えの事実を認識し得たかどうか」という判断は難しくないですか。「行為者が認識できなかったんだから、一般人も認識できなかったんじゃないか」となりそうです。そうすると、すり替えの事実を判断の基礎に取り込めず、質的危険ありという結論になるでしょう。
結論はこれでもいいと思いますが、当てはめがしっくりこないでしょう。
一方で、修正された客観的危険説だとこの点の当てはめは容易です。すり替えが行われなったであろう可能性はどれほどあったのかを指摘し、その可能性が高かったのであれば、質的危険性ありとし、低ければ質的危険性なしとすればいいだけです。この見解では、すり替えがどれほど秘密裏に行われたのかとか、当該事案の事情をうまく使えると思います。その点で、こちらの見解が優れていると思います。
加えて、修正された客観的危険説を採用すれば、判例と同内容の結論をとることができます。(判例においては、方法の不能事例においては、結果発生の可能性を化学的な根拠を問題としつつ、かなり客観的に判断されている場合が多いが、一部の判決及び客体の不能の事例では、一般人の危険感を基準に、具体的危険説に近い方法で判断を下しています)
色々脱線しましたが、今回はここまでにさせて頂きます。不能犯の論述のポイントを解説させて頂きました。
ほかの記事でも色々解説をしておりますので、是非ご覧ください。
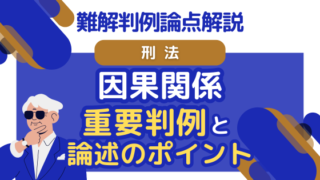
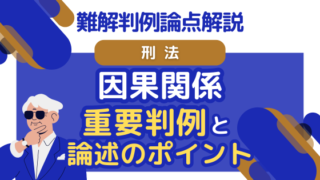
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。