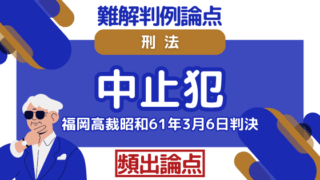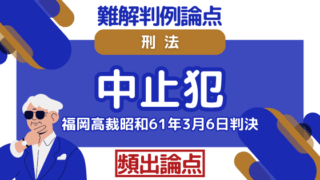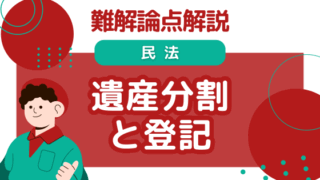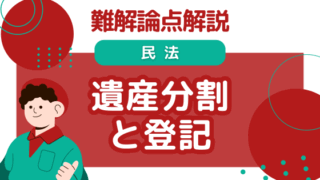【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
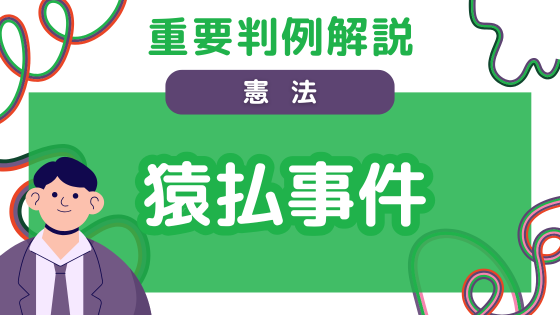
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。
動画解説の「法スタチャンネル」も大好評、運営中!
▽動画解説を順次公開中▽



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



皆さん、知ってましたか?
あのアガルートがアプリをリリースしています。



これにより講義視聴がより便利になり、学習の効率が大幅にアップしました!
是非、公式サイトで詳細を確認してください!
\講義動画のダウンロード可能/
データ通信料を気にせず受講しよう!!
猿払事件上告審は、「公務員の政治的行為が国家公務員法等によって制限されていることが合憲なのか?」「合憲だとしてその根拠は何か?」が問題となった事件です。
「猿払事件」で挙がった問題
・公務員の政治的行為が国家公務員法等によって制限されていることが合憲なのか?
・合憲だとしてその根拠は何か?
最高裁大法廷は、公務員の政治的行為が制限される理由として、全体の奉仕者論を展開し、国家公務員法第102条1項の規定も合理的関連性の基準に基づいて合憲としました。



詳しく見ていきましょう!



みなさ~ん!
この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。



「これさえやりきれば、もう怖くない!」
そんな演習書や問題集が欲しいと思ったことはありませんか?
通称「重問」と呼ばれるアガルートの重要問題がおすすめ



その人気の秘密や効果的な活用方法について、アガルートの専任講師に直接インタビューを行いました。
受験生に支持される理由が詰まった記事、ぜひチェックしてみてくださいね!
今売れてます!!
\司法試験合格者占有率37.8%/
▼重要問題だけで合格する究極の勉強法【独占インタビュー】▼


憲法21条1項では「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と定められており、この規定から、何人にも政治的活動の自由が認められているとの考えを導き出すことができます。
憲法 21条1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
一方で、国家公務員法第102条1項では、公務員の政治的行為を制約しています。さらにこの規定に違反した場合は、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります(同法110条1項18号)。
国家公務員法 第102条(政治的行為の制限)
職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
では「公務員の政治的行為が、制約されていることの根拠は何か?」という議論があります。
この点について、次の3つの説が知られています。
「公務員の政治的行為」が制限されている根拠に関する3つの説
①全体の奉仕者論
②職務性質説
③憲法秩序構成要素説
憲法15条2項には「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とあることから、この規定に根拠を求めるものです。
憲法 15条2項
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
公務員の職務の性質からして政治的行為が制限されてしかるべきだとの考えです。
憲法15条を初めとして、憲法には公務員に対する規制がいくつも盛り込まれています。そのことから、公務員の特別な法律関係と自律性を憲法的秩序の構成要素として、憲法が認めているとする説です。



では、事件を基に考えてみるぞ!
「猿払事件」の概要
Xは、北海道猿払村の郵便局に勤務する事務官でした。当時の郵便局員は国家公務員だったのです。
猿払地区労働組合協議会の事務局長を務めていましたが、昭和42年の衆議院議員選挙に際して、協議会の決定に従って、日本社会党を支持する目的で同党の公認候補のポスターを自ら公営掲示場に掲示したほか、ポスターの配布などを行いました。
これらの行為が、国家公務員法第102条1項に規定されている公務員の政治的行為に当たるとして、起訴されました。
なお、禁止される政治的行為は、人事院規則に細かく決められており、Xの行為はその一つに抵触していました。
第一審は「刑罰規定が被告人Xの行為に対する制裁としては、合理的にして必要最小限の域を超えるものであり、憲法21条等に反する」として、被告人Xを無罪とする判決を出しました。
控訴審も、第一審の判決を支持したために、検察側が「憲法解釈の誤り」を主張して上告した事件です。
最高裁は、原判決及び第一審判決を破棄し、「被告人Xに罰金刑を科する」判決を下しました。
では、どのように考えて、第一審と控訴審を覆したのかを見ていきましょう。



どのように考えたんだろう?
最高裁は、憲法15条2項の規定を示したうえで、「国民の信託による国政が、国民全体への奉仕を旨として行われなければならないことは、当然の理である」と述べています。
憲法 15条2項
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
三権分立の構造からしても、行政は「もつぱら国民全体に対する奉仕を旨とし、政治的偏向を排して運営されなければならない」としており、そのためには「『公務員の政治的中立性』が必要だ」としています。
つまり、最高裁は、公務員の政治的行為が制限されることの根拠として、「全体の奉仕者論」を持ち出していることが分かります。
「公務員の政治的中立性」のために「公務員の政治的行為」の制限が必要とされても、その制限は、どの程度まで認められるのでしょうか?
この点について最高裁は「それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである」と述べています。
では「合理的で必要やむをえない限度」と言えるかどうかの判断基準はどのように考えるべきでしょうか?
この点について最高裁は、以下の3点から検討すべきとして「合理的関連性の基準」によるとの見解を示しました。
検討すべき3点
①禁止の目的
②この目的と禁止される政治的行為との関連性
③政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡



では、先ほどの「猿払事件」へあてはめていこう!
「合理的関連性の基準」に基づき「猿払事件」ではどのように判断したのか?を確認しましょう。
公務員の政治的行為を自由に認めると行政機関の公務の運営に党派的偏向を招くおそれがあり、公務員の政治的中立性が損われます。
よって、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保する目的で、公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは、正当な理由があると判断しました。
公務員の政治的中立性を損うおそれがあると認められる政治的行為を禁止することは、禁止目的との間に合理的な関連性があるとしています。
さらに、公務員の職種・職務権限、勤務時間の内外、国の施設の利用の有無等を区別することなく、あるいは行政の中立的運営を直接、具体的に損う行為のみに限定されていないとしても、合理的な関連性は失われないと述べています。
公務員が「禁止されている政治的行為」は、人事院規則で定められた行動類型に属する政治的行為だけです。それ以外の政治的行為によって、意見表明することは公務員にも禁止されていません。
最高裁は、その点を指摘したうえで、以下2点を挙げました。
両者を比較すると「得られる利益の方が重要である」として、「公務員の政治的行為の禁止は、利益の均衡を失するものではない」と判断しました。
最高裁は「国家公務員法第102条1項は、憲法21条に違反しない」との結論を下しました。
また、刑事罰を設けていることについても、「公務員が政治的行為の禁止に違反することは、違法性を帯びることが認められ、その違反行為を構成要件として罰則を法定しても、そのことが憲法21条に違反することはない」と判断しています。
国家公務員法第102条1項には「人事院規則で定める政治的行為」とあり、政治的行為の具体的な内容を定めることについて、人事院規則に委任している点が「憲法が許容している委任の限度を超えるのではないか?」との問題があります。
憲法41条では「国会が唯一の立法機関」と定められていますが、「委任命令(委任立法)も認められる」との解釈が一般的です。
ただ「委任命令にも限界はある」と解されています。例えば「包括的白紙委任は許されず、個別具体的な授権が必要」とされています。
では、「人事院規則で定める政治的行為」という一文は白紙委任に当たるのでしょうか?
この論点については、様々な判例がありますが、猿払事件では、「『公務員の政治的中立性を損うおそれのある行動類型に属する政治的行為』を、具体的に定めることを委任した規定であることは、合理的な解釈により理解できる」としています。
そのため「白紙委任には当たらず、人事院規則への委任は合憲である」との解釈を示しました。
猿払事件上告審は、全体の奉仕者論に基づいて、合理的で必要やむをえない限度であれば、公務員の政治的行為の制限が認められるとしました。
その判断基準として「合理的関連性の基準」を持ち出しています。
その上で、国家公務員法第102条1項は憲法21条に違反しないとの判決を下しています。
また、政治的行為の具体的内容を人事院規則へ委任していることも、委任の範囲について合理的な解釈が可能として、合憲だと判断しました。
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。