
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
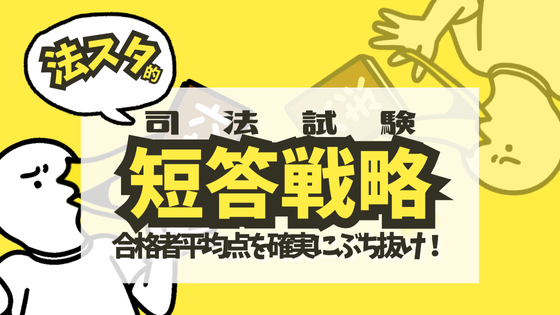
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする

司法試験合格という険しい道のりの最終日を飾るのが、短答式試験です。
マークシート形式で実施されるこの試験は、5日間にわたる長丁場の最終関門であり、受験生の集中力と知識の定着度を試す試金石となります。論文式試験対策で培った知識が活かせる部分も多い一方で、「短答プロパー知識」と呼ばれる、論文式試験では深く掘り下げられないような細かな条文や判例の知識が問われるのが特徴です。
この短答式試験の出来は、最終的な合格を左右する重要な要素となります。
なぜなら、短答式試験の得点は、論文式試験の得点と合算され、総合的な評価によって合否が決定されるからです。したがって、「できる限り高得点を狙いたい」という気持ちは当然湧き上がってくるでしょう。


しかし、ここで忘れてはならないのが、司法試験における真の主戦場はあくまで論文式試験であるという厳然たる事実です。論文式試験の配点は800点であるのに対し、短答式試験の配点は憲法50点、民法75点、刑法50点の合計175点に過ぎません。配点比率で言えば、8対1。総合評価の算出方法を見ても、短答式試験3科目の合計得点が、論文式試験1科目の合計得点とほぼ同等に扱われることが分かります。
この配点比率を考慮すると、短答式試験で満点に近い点数を追い求めるあまり、貴重な時間を短答対策に過度に費やしてしまうことは、本質的に重要な論文式試験対策を疎かにする危険性を孕んでいます。それは、合格という目標達成のために、決して効率的な戦略とは言えません。
司法試験の短答式試験において、多くの受験生が見落としがちな「足切り」の恐ろしさをご存じでしょうか。
短答式試験に合格するためには、「各科目で満点の40%以上の成績を得た上で、各実施年の合格点を獲得する」という二重の条件をクリアしなければなりません。
「短答式試験の各科目において、満点の40%点(憲法20点、民法30点、刑法20点)以上の成績を得た者のうち、各科目の合計得点が81点以上の成績を得たものは、短答式試験の合格に必要な成績を得た者とする。」
ここで特に強調したいのは、3科目の合計点が合格点を超えていても、1科目でも「満点の40%未満」であれば、その時点で不合格になるということです。
つまり、「足切り点」という絶対的な壁が存在するのです。
「さすがに足切りはクリアできるだろう」と高を括っていませんか?
実は近年の短答式試験では、この足切りに引っかかる受験生が驚くほど多いのです。
| 科目 | 最低ライン(40%)未満の者 |
|---|---|
| 憲法 | 586人 |
| 民法 | 347人 |
| 刑法 | 306人 |
令和7年司法試験の採点対象者数は3,815人。
憲法だけで見ると、実に約15%もの受験生が足切りに遭っているのです。
司法試験は、そもそも受験資格が法科大学院修了者または予備試験合格者に限られています。
つまり、すでに相当の学習を積んだ「選ばれた受験生」の中で、これだけの人数が足切りに遭っているという事実は、決して軽視できません。
足切りに遭う受験生には、いくつかの共通したパターンがあります。
「民法は得意だから大丈夫。憲法は少し手薄でも合計点でカバーできる」
このような考え方は極めて危険です。どんなに他の科目で高得点を取っても、1科目でも40%を下回れば即不合格。バランスの取れた学習が不可欠です。
短答式は基礎的な知識を問う試験だからこそ、油断が生まれます。しかし、基礎知識の正確な理解と定着がなければ、本番の緊張状態で思わぬミスを連発することになります。
難問に時間をかけすぎて、後半の解ける問題に手が回らない。これも足切りの典型的な原因です。戦略的な時間配分は、短答式攻略の生命線です。
司法試験の短答式試験は、「総合力」と「バランス」を同時に求める試験です。
合格ラインギリギリを狙うのではなく、全科目で安定して得点できる「底力」を養うことこそが、確実な合格への王道といえるでしょう。
足切りは、決して他人事ではありません。
今日から、あなたの学習戦略を見直してみませんか?


そこで法スタが提唱したいのが、「短答式試験合格者の平均点を狙う」という短答戦略です。
過去数年間の短答式試験合格者の平均点は以下の通り推移しています。
| 試験実施年 | 合格点 | 合格者の平均点 |
| 令和7(2025) | 81点 | 110.6点 |
| 令和6(2024) | 93点 | 120.3点 |
| 令和5(2023) | 99点 | 126.1点 |
| 令和4(2022) | 96点 | 123.3点 |
| 令和3(2021) | 99点 | 126.4点 |
| 令和2(2020) | 93点 | 118.1点 |
| 令和元(2019) | 108点 | 129.3点 |
| 平成30(2018) | 108点 | 128.1点 |
| 平成29(2017) | 108点 | 125.4点 |
| 平成28(2016) | 114点 | 133.2点 |
| 平成27(2015) | 114点 | 133.6点 |


これらの平均点の平均値を算出すると、およそ124.61点となります。このデータに基づき、短答式試験の現実的な目標点を「125点」と設定しましょう。明確な目標数値を定めることで、対策の方向性が定まり、モチベーションの維持にも繋がります。
重要なのは、「何度受けても125点を確実に取れる」ような対策を行うことです。これは、偶然の一致で高得点を取るのではなく、安定した実力を身につけることを意味します。
125点という目標は、満点である175点の約71%に相当します。つまり、正答率7割を目指すことが、短答式試験合格への現実的な道筋となるのです。


「正答率7割は難しくない」と考える方もいるかもしれませんが、油断は禁物です。そのためには、正しい方向でのインプットと、質の高い過去問演習が不可欠となります。
まず、インプットの段階では、論文式試験対策で培った基礎知識を土台としつつ、短答式試験特有の知識、すなわち短答プロパー知識を効率的に習得していく必要があります。市販の短答式試験対策用の教材や、予備校の短答対策講座などを活用し、論文知識だけではカバーできない細かな条文の文言や、重要な判例の結論と理由付けなどを丁寧に押さえていきましょう。この際、漫然と知識を詰め込むのではなく、体系的な理解を心がけることが重要です。関連する知識を紐付けながら学習することで、記憶の定着率を高めることができます。
次に、過去問演習は、短答式試験対策において最も重要な要素の一つです。過去問を解くことで、出題傾向や難易度、時間配分などを肌で感じることができます。単に解答を覚えるのではなく、なぜその選択肢が正しく、なぜ他の選択肢が誤っているのかを一つ一つ丁寧に検討することが重要です。間違えた問題については、必ずテキストや基本書に戻って知識を確認し、理解が曖昧な部分を解消するように努めましょう。
また、過去問演習を繰り返す中で、自分が苦手とする分野や知識が曖昧な部分が明確になってきます。そのような弱点を発見したら、集中的に復習を行い、克服していくことが合格への近道となります。
さらに、短答式試験は時間との勝負でもあります。マークシートへの記入時間も考慮し、時間配分を意識した演習も欠かせません。本番を想定し、制限時間内に全ての問題を解き終える練習を繰り返すことで、時間管理能力を高めることができます。
短答式試験対策は、ともすれば論文式試験対策の合間に行われるものと捉えられがちですが、合格のためには戦略的なアプローチが不可欠です。「主戦場は論文」という意識を持ちつつも、短答式試験の重要性を認識し、合格者の平均点を目標とした効率的な対策を講じることこそが、司法試験突破への賢明な道と言えるでしょう。焦らず、着実に、そして戦略的に学習を進めていきましょう。
短答式試験は、限られた時間で膨大な知識を繰り返し確認できる“軽さ”と“検索性”が勝負どころです。そこでおすすめなのが、加藤ゼミナールの新サービス「短答条文・判例ライブラリー」。過去問の出題実績に基づいて、条文・判例の要点と問題・解説をオンラインで一元化する“短答特化”ツールです。
主な特徴(3点)
搭載機能(抜粋)
メリット
おすすめの使い方(法スタ推奨)
こういう方に
ポイント
短答条文・判例ライブラリー
短答対策の常識を変える全く新しいオンライン教材。自分だけの学習データを蓄積し、最強の“自作短答テキスト”を育てていきましょう。
(参考)加藤ゼミナールの合格実績はここ数年で大きく伸長し、上位合格者も多数輩出。短答~論文まで一気通貫の指導力にも定評があります。法スタの詳しいレビューも併せてどうぞ。
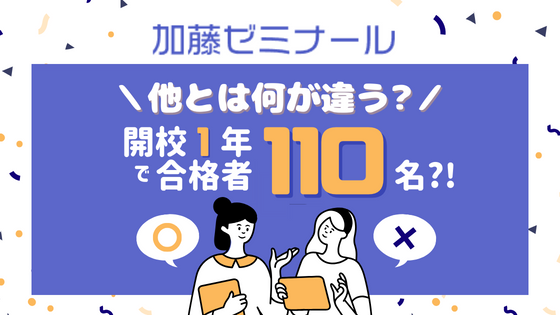
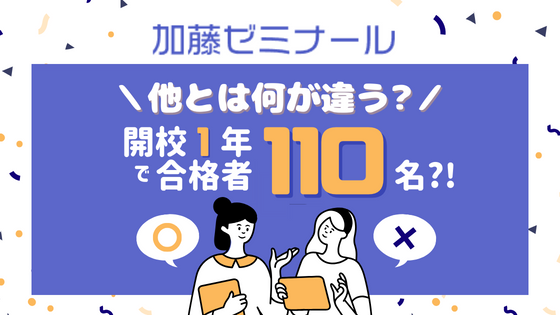
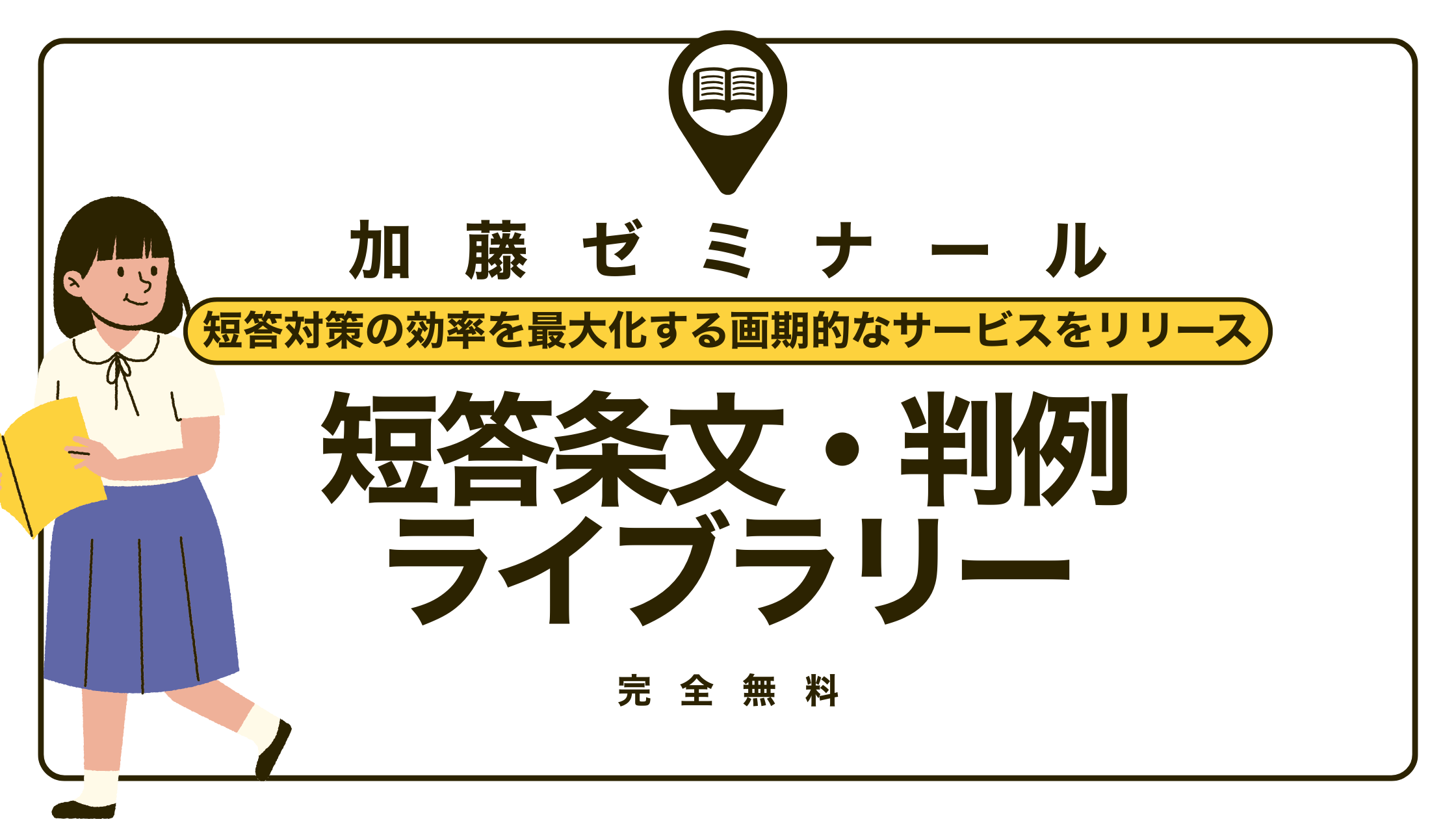
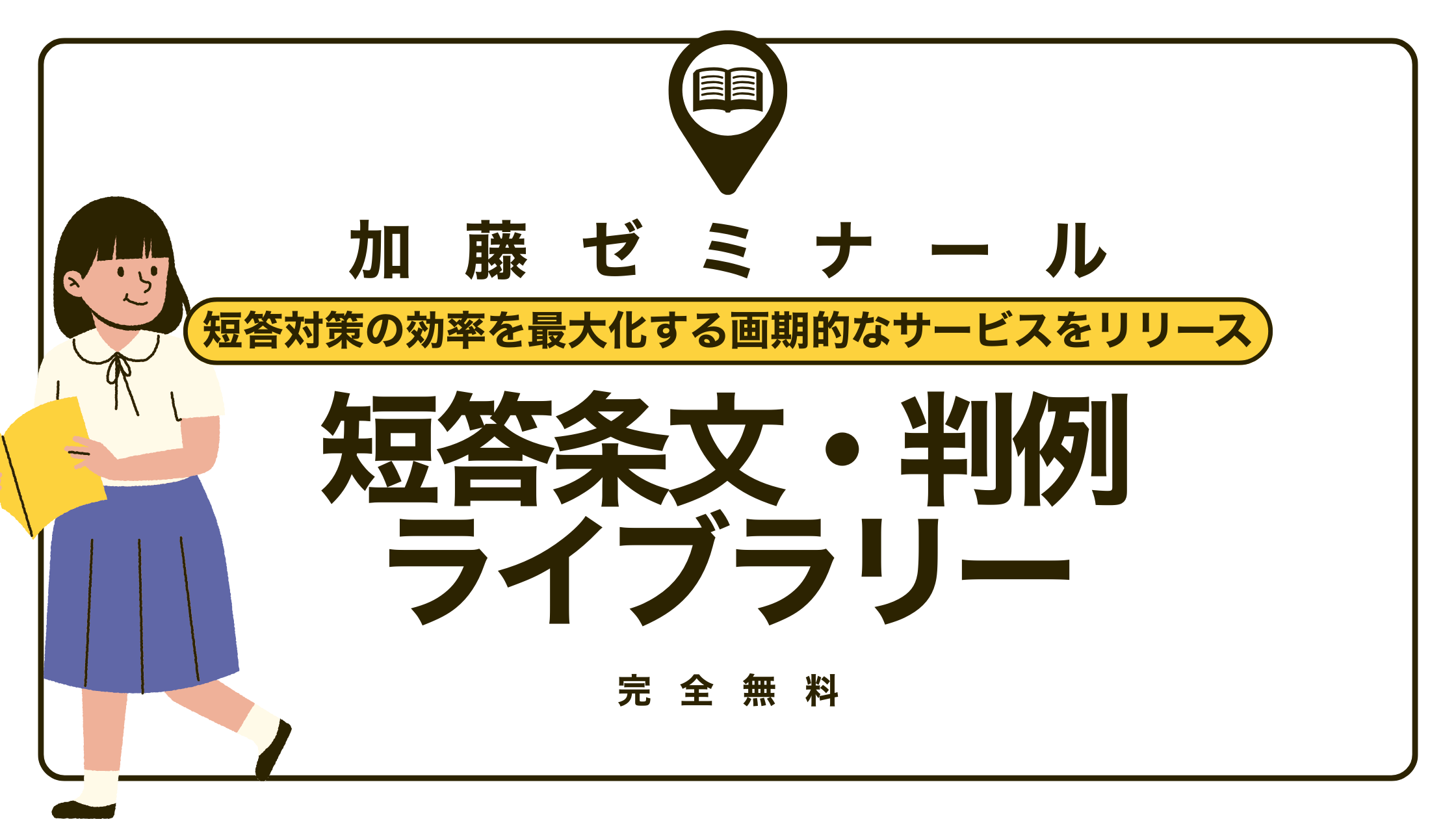
来年以降の司法試験・予備試験合格を目指す皆様に、短答式試験対策としてぜひ活用していただきたいのが、資格スクエアの短答攻略クエストです。
短答攻略クエストの最大の特長は、司法試験・予備試験の全年度の過去問をいつでもどこでも手軽に演習できる点にあります。これにより、司法試験合格に必要な短答式試験対策を、基礎から実践まで一気通貫で行うことが可能です。さらに、最新年度の問題も順次追加予定とのことで、常に最新の出題傾向に対応した学習が期待できます。
レベル到達で無料開放される豊富な問題も魅力の一つです。会員登録をするだけで令和3年度の7科目分の過去問が無料でプレゼントされ、正答問題数を積み重ねてレベルアップすることで、さらに多くの問題が無料で開放されます。「もっと解きたい!」という方には、年度・科目ごとに問題を購入することも可能です。
また、他の受験生と競い合えるミニテスト&ランキング機能も、学習のモチベーション維持に大きく貢献します。定期的に開催されるミニテストに参加することで、自分の実力を客観的に把握できるだけでなく、全国のライバルたちのレベルを知る良い機会となるでしょう。実際のテストと同じ時間制限の中で演習できるため、本番に向けた時間感覚を養うこともできます。
資格スクエアアドバイザーである東京大学薬学部 池谷裕二教授が提唱するように、脳科学理論に基づいた学習法を取り入れているのも短答攻略クエストの強みです。学習を始めたばかりの初学者こそ、ミニテストを積極的に活用することで、効率的な知識の定着が期待できます。
充実した演習機能も見逃せません。司法試験短答式試験一桁合格者が監修した詳細な解説は、まるで質の高い講義を受けているかのように学びが多く、理解度を確認できる「解説チェック」機能も搭載されています。さらに、豊富なフィルター機能で復習がしやすく、正答率や科目別分布図などで自身の学習状況を美しく可視化できるため、弱点克服に繋げやすいでしょう。
復習だけでなく予習にも活用できる点も、脳科学的に理にかなった学習法と言えます。体系目次で整理されているため、講義前に同じ体系の問題を解くことで「分からない」という記憶が残り、講義中にその知識と結びつくことで、より深い理解と記憶の定着を促します。
さあ、無料で始められる資格スクエアの短答攻略クエストを活用して、効率的に短答式試験対策を進め、司法試験合格への道を力強く歩み始めましょう。
▼詳細は以下の記事をご覧ください▼


「短答プロパー知識を効率よくマスターすることがポイント!」というアドバイスにもあるように、短答式試験特有の知識対策は合否を分ける重要な要素です。そこでおすすめしたいのが、アガルートの短答知識完成講座Ⅰ 憲法・民法・刑法です。
本講座は、既に論文式試験を中心とした総合的な知識の習得が完了した方を対象に、短答式試験のみで問われる知識(短答プロパー知識)の習得に特化した約21時間の短期集中講座です。論文式試験対策に時間を割きたい受験生にとって、効率的に短答対策を進める上で最適な講座と言えるでしょう。
アガルートのオリジナルフルカラーテキストは、予備試験・司法試験の出題実績がピンポイントで掲載されており、メリハリをつけた学習が可能。総合講義テキストとの相互参照機能も備わっているため、曖昧な知識もすぐに確認でき、学習効率を高めます。経験豊富な谷山政司講師(憲法)、渥美雅大講師(民法)、石橋侑大講師(刑法)が、論文式試験対策では手が届きにくい分野を集中的に、分かりやすく解説します。
こんな方にオススメ
着前期の方で大逆転をしたいなら、アガルートの短答知識完成講座で21時間でスピードマスターして、司法試験本番までできる限り繰り返してください。
▼司法試験の短答式試験を確実に突破したい方に▼
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
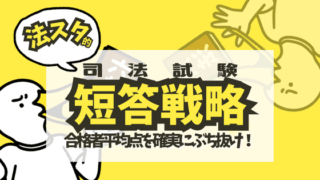
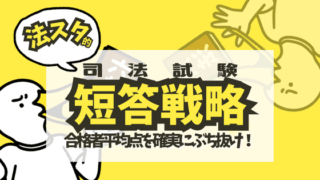
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

