
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
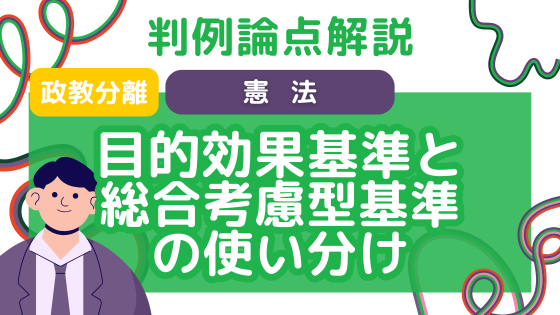
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする「政教分離原則」とは「国家と宗教」の分離を定めた憲法上の基本原則です。
日本国憲法は、特定の宗教が国家から特権を受けることや、国家が宗教的活動を行うことを禁止しています(憲法20条、89条)。しかし、実際には国家と宗教の関わりが完全に断たれているわけではありません。
例えば、地鎮祭や神社への寄付など、社会的・文化的慣習として行われる宗教的要素を含んだ行為が問題となることがあります。



では「国家と宗教」は、どの程度まで関わり合うことが許されるのでしょうか?
この問いに対して、最高裁判所は「目的効果基準」や「総合考慮型基準」といった異なる判断枠組みを用いて答えを示してきました。それぞれの意味は、記事の中で解説していきます。
本記事では、代表的な判例をもとに、以下も詳しく解説していきます。
・「政教分離原則」の意義と限界
・これらの基準がどのように使い分けられているのか
「政教分離原則」とは「国家と宗教の分離の原則」のことを言います。要は「国家と宗教は分けて考えよう」という憲法のルールです。日本国憲法には、この原則について、以下のような記載があります。
憲法に書かれている内容(ポイント)
・いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。(20条1項後段)
・国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。(20条3項)
・公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。(89条)
このように、憲法は「政治と宗教」の分離、すなわち「政教分離原則」について明文として具体的に規定しています。
現実には、国や自治体が完全に宗教と無関係ではいられないこともあります。
例えば、以下の行為は宗教的ですが、文化的な慣習として行われていることも多いです。
そのような中で、以下のようなことが問題となる可能性があります。
問題意識:「政治と宗教」は、完全に分離されていることが要求されるのか?
この点について、判例は以下のように示しています。判例は「政治と宗教が完全に分離されていないと、直ちに違憲である」という判断はしていません。
「政教分離規定は、いわゆる制度的保障であって、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。」
そして、「政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れない」「国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではない」
問題意識:「国家と宗教」との結びつきは、どの程度まで許されるか?
まずは、いわゆる「目的効果基準」を採用したリーディングケースである「津地鎮祭判決」について検討してみましょう。
この疑問に対して、裁判所は次の2つの方法(判断基準)を使って答えを出しています。詳細な意味は、重要判例の解説の中で言及していきますが、簡単には以下のような意味を示しています。
①目的効果基準:以下で判断
目的:行為の目的は、宗教的意義をもつか否か?
効果:効果として、宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為か否か?
②総合考慮型基準:以下のような事情をまとめて考えて判断
例えば…
・宗教的施設の性格
・当該土地が無償で当該施設の施設としての用に供されるに至った経緯
・当該無償提供の態様
・これらに対する一般人の評価
始めに「①目的効果基準」に関する重要判例をご紹介します。
「津地鎮祭判決」は、「政教分離原則」に違反するか否かについて、その判断の枠組みを以下に鑑みて判断することを示した(いわゆる「①目的効果基準」を用いることを示した)判例として、重要なリーディングケースとなっています。
T市は、同市体育館の建設に当たって、神式による起工式(地鎮祭)を行った。
これに対して、T市住民であるXが、本件起工式は憲法20条3項の禁止している「宗教的活動」に該当するものであり、本件起工式のために費用をT市が支出したことは憲法20条3項に違反する違法なものであったと主張した。



体育館を建てる時の、神式の地鎮祭が宗教的活動に該当し、費用の支出が違法ではないか?と争いになったぞ!
本件起工式は、宗教との関わりあいをもつものであることを否定し得ないが、
その「目的」は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、
その「効果」は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないと解するのが相当である。
「目的」と「効果」に視点を置き、判断したことが分かります。
国家は、実際上宗教とある程度の関わり合いをもたざるを得ないことを前提としたうえで、かかる関わり合いの許容性について、問題となっている行為の「目的及び効果に」鑑みて判断
宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果に鑑み、その関わり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合に「政教分離原則」違反となります。
そして「相当とされる限度を超える場合に当たるか否か?」は、以下の2本柱により判断します。
≪相当とされる限度を超える場合に当たるか否かの判断の要素≫
1.行為の目的が宗教的意義をもつか否か?
2.その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為か否か?
上記1.と2.を判断する際の「具体的な考慮要素」として、以下のように判例は示しています。
行為の外形的側面のみにとらわれることなく、「当該行為の行われる場所、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って」客観的に判断しなければならない
この「①目的効果基準」は、「愛媛玉串料訴訟(最高裁平成9年4月2日)」などそのほかの判決においても用いられています。
従来、「政教分離原則」に違反するか否かについて、裁判所は「①目的効果基準」を用いて判断をしていました。
そんな中「空知太神社事件判決」は「①目的効果基準」を採用せず、いわゆる「②総合考慮型基準」を用いて、判断をしました。
S市は、その所有する土地を、空知太連合町内会(町内会)が所有し集会場等として使用していた建物の敷地として無償使用させていたところ、本件建物の一角には神社の祠が設置され、さらには建物外壁に「神社」との表示が設けられていた。
また、土地上には鳥居及び地神宮が設置されており、S市は鳥居及び地神宮の敷地としても、町内会に無償提供をしていた。
これに対して、S市住民であるXらが、S市の本件無償提供行為は政教分離原則に違反する行為であると主張して、地方自治法242条の2の定める住民訴訟で争った事件。



神社のある土地を、無償で町内会に使わせていたが「政教分離原則」に違反するのでは?と問題になりました!
社会通念に照らして総合的に判断すると、本件利用提供行為は、市と本件神社ないし神道とのかかわり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、
信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当すると解するのが相当である。
「空知太事件判決」は、「政教分離原則」が問題となった事案であるにもかかわらず、「①目的効果基準」に言及せず、いわゆる「②総合考慮型基準」によって、「政教分離原則」に違反するかを判断しました。
いわゆる「②総合考慮型基準」は、
政治と宗教とのかかわり合いが社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超えるか否かを判断する際に、当該宗教的施設の性格等の諸要素を総合的に考慮する
具体的には、以下等を総合的に判断しています。
問題意識:現在において、「政教分離原則」違反か否かを検討する際には、「②総合考慮型基準」を採用すべきであり、「①目的効果基準」は失われたのでしょうか?
この点について、「空知太神社事件判決」は明示的に判例変更をおこなっているわけではなく、さらには、「①目的効果基準」を採用した「津地鎮祭判決」や「愛媛玉串料判決」を引用してさえいます。
また、「①目的効果基準」が採用された「白山ひめ神社事件判決」(最高裁平成22年7月22日)は、「空知太神社事件判決」より後に出されたものです。
整理すると、考察のポイントは以下のとおりです。
そのため、「②総合考慮型基準」の出現によって「①目的効果基準」は中核的・基底的な判断枠組みではなく、それを具体化した判断枠組みの一つであったといえるが、「①目的効果基準」自体が失われたというわけではないとも考えられそうです。
それでは、「①目的効果基準」と「②総合考慮型基準」はどのようにして使い分けられているのでしょうか。
この点については「空知太神社事件判決」の補足意見と調査官解説などから考えていきます。
目的効果基準が機能せしめられてきたのは、問題となる行為等においていわば『宗教性』と『世俗性』とが同居しておりその優劣が微妙であるときに、そのどちらを重視するかの決定に際してであって(例えば、津地鎮祭訴訟、箕面忠魂碑訴訟等は、少なくとも多数意見によれば、正にこのようなケースであった。)、明確に宗教性のみをもって行われたかが問われる場面においてではなかったということができる。
すなわち、以下の理解がなされています。
「宗教性」と「世俗性」が同居している事案→①目的効果基準
「宗教性」であることが明らかな事案→②総合考慮型基準
調査官は、以下のように述べています。
従来の政教分離訴訟において憲法適合性が問題とされた対象がいずれも、ある一時点における公金の支出や公務員の儀式参列行為等といった1回限りの作為行為であったのに対し、本件利用提供行為は、半世紀以上もの歴史を有する継続的行為であって、
かつ、その行為には本件使用貸借契約という作為的側面もあるものの、単に現状を放置しているという不作為の側面も併せ有するものである
すなわち、以下のような整理になります。
1回限りの作為行為→①目的効果基準
継続的行為→②総合考慮型基準
このように、近年までは、藤田裁判官の補足意見や調査官解説に挙げられている理解がなされていました。
しかし、「孔子廟事件判決(令和3年2月24日)」が出されたことにより、かかる理解に疑問が呈されています。
「政教分離」の最新判例もご紹介します。
「孔子廟事件判決」は、「宗教性」と「世俗性」が同居している事案でしたが、政治と宗教の関わり合いの相当性判断において、「②総合考慮型基準」を採用しました。
N市市長の、孔子廟などを祀る至聖廟や関連施設の設置をXに許可した上、市有地にある公園の敷地の一部の使用料を全額免除した行為について、政教分離原則に反しているかが争われた事案。
社会通念に照らして総合的に判断すると、本件免除は、市と宗教の関わり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、
信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。
藤田裁判官の補足意見でなされていた理解に基づいて、「①目的効果基準」と「②総合考慮型基準」を使い分けることは、現代においては妥当ではないと理解することも可能です。
また、調査官解説においてなされていた理解についても、1回限りの作為的行為に「①目的効果基準」を適用しなかった「冨平神社訴訟判決(最高裁平成22年1月20日判決)」があることから、疑問が呈されています。
このような理解に基づけば、「①目的効果基準」は失われたと評価することも可能ですが、明示的に判例変更をおこなったわけではなさそうであるという点には注意しなければなりません。
これまでに述べたように、「①目的効果基準」は失われていないと評価することもできるし、失われたと評価することもできそうです。この点については、今後の判決や学者の意見を待たざるを得ません。
しかし、自身が、「目的効果基準は失われた」との見解に立ったとしても、試験において、なんでも「②総合考慮型基準」を用いることは危険でしょう。
司法試験や司法試験予備試験では、既存の判例をモチーフにした事案が出題されることが少なくありません。そのため、「津地鎮祭判決」や「愛媛玉串料訴訟判決」に類似の事案が出題された場合には、やはり「①目的効果基準」を採用するのが得策でしょう。また、その際には、事案がいかなる点で「①目的効果基準」が用いられた判例と類似しているのかを述べた上、判断基準を定立することが好ましいと考えられます。
試験の際にもっとも注意しなければならないことは、「②総合考慮型基準」を定立したにもかかわらず、「①目的効果基準」を定立したかのような当てはめをしてしまうこと(その逆も然り)です。自分の立てた判断枠組みに沿った当てはめを意識しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
・横大道聡『憲法判例の射程[第2版]』(弘文堂、2020)
・長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ[第7版]』(有斐閣、2019)
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
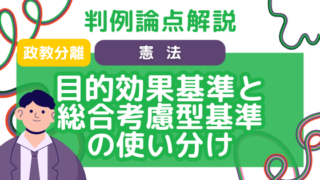
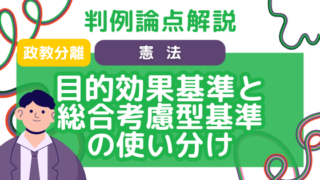
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
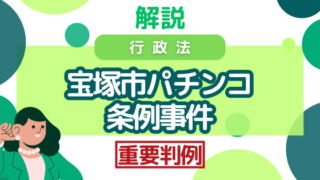
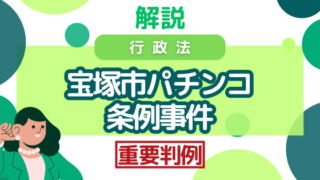














勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

