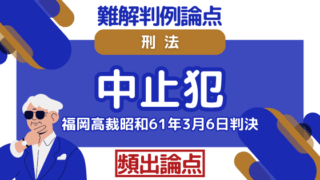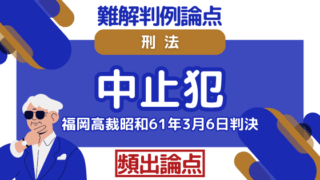【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。
動画解説の「法スタチャンネル」も大好評、運営中!
▽動画解説を順次公開中▽



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



皆さん、知ってましたか?
あのアガルートがアプリをリリースしています。



これにより講義視聴がより便利になり、学習の効率が大幅にアップしました!
是非、公式サイトで詳細を確認してください!
\講義動画のダウンロード可能/
データ通信料を気にせず受講しよう!!

「堀木訴訟の理解のポイントは?」
「生存権を具体化する法律の合憲性の判断枠組みは?」
「併給禁止規定を合憲としたロジックは?」
堀木訴訟(最大判昭57.7.7)は、生存権の社会権的側面の法的性格について最高裁が判断基準を示した判例です。法的権利説を否定し、プログラム規定説に則った見解を示しましたが、裁判規範性は認めています。
堀木訴訟における最高裁の考え方を解説していきます。
法書ログでは、憲法の重要判例の解説や刑事訴訟法の論点解説記事を多数公開しています。ぜひ、合わせてご確認ください。



みなさ~ん!
この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。



「これさえやりきれば、もう怖くない!」
そんな演習書や問題集が欲しいと思ったことはありませんか?
通称「重問」と呼ばれるアガルートの重要問題がおすすめ



その人気の秘密や効果的な活用方法について、アガルートの専任講師に直接インタビューを行いました。
受験生に支持される理由が詰まった記事、ぜひチェックしてみてくださいね!
今売れてます!!
\司法試験合格者占有率37.8%/
▼重要問題だけで合格する究極の勉強法【独占インタビュー】▼


憲法25条は、1項ですべての国民に生存権が保障されていることを規定し、2項で生存権実現のために国に努力義務を課する規定になっています。
では、生存権にはどのような法的性格があるのかが問題になります。つまり、憲法25条を根拠に国民はどのような権利主張ができるのかという話です。
この点、生存権には次の二つの法的性格があると解されています。
①自由権的側面
②社会権的側面
自由権的側面とは、すべての国民は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を有しており、国家は国民の権利を阻害してはならないという意味です。
自由権的側面については、法規範性、裁判規範性のどちらも認められています。(サラリーマン税金訴訟(最判平成元年2月7日)の第一審、第二審判決など。最高裁は明示せず)
つまり、国が国民の生存権を阻害している場合は、裁判によってその阻害をやめるように求めることができます。
一方、社会権的側面とは、国民が国に対して、「健康で文化的な最低限度の生活の実現」を求める権利という意味です。
つまり、国に対して、健康で文化的な最低限度の生活ができるように衣食住や生活資金を用意するように求めることができるという意味になります。
しかし、国の予算には限度があるため、社会権的側面についてはどの程度認めるべきかが問題になるわけです。
まずは、生存権に自由権的側面と社会権的側面があることを理解する。そして、生存権の判例を学習する際には、自由権側面が問題となっているのか、社会権的側面が問題となっているのかを意識する
生存権の社会権的側面が、どの程度、具体的な権利と言えるのかについては、大きく次の2つの見解に分かれています。
・法的権利説
・プログラム規定説
法的権利説は、国民は国に対して、生存のために必要な措置を講じるように要求する法的権利があるという考え方です。法規範性があるので、国がその権利を実現しない場合は裁判で争うことができます。
法的権利説は細かく分けるとさらに、具体的権利説と抽象的権利説に分かれます。
具体的権利説は、憲法25条が生存権を具体的に規定していると捉えて、個別の法律によるまでもなく、憲法25条を根拠に生存権を主張できるとする考え方です。
もしも、生存権に関する法律が制定されない場合は、立法不作為として違憲確認訴訟を提起できると考えます。
抽象的権利説は、憲法25条の生存権は、法律が制定されないと明確な権利として主張できないとする考え方です。生存権に関する法律が制定されなくても、立法不作為として違憲確認訴訟を提起することはできないと考えます。
プログラム規定説は、生存権の社会権的側面につき、法規範性も裁判規範性も認めない考え方です。
憲法25条は、国に対して政治的な義務を課したにすぎないと考えます。
なぜなら、日本国憲法が前提とする資本主義社会では、自助の原則、つまり、自分の力で生き抜くことが前提であるし、生存権の社会権的側面を実現するにしても、国家の予算には限度があるためです。
よって、プログラム規定説の考え方を採用した場合、国民は、国に対して、「健康で文化的な最低限度の生活の実現」を求めることはできないし、もちろん、憲法25条を根拠に裁判を提起することもできないと考えます。
生存権を実現するための法律が制定されたとしても、その法律が憲法25条に違反すると訴えることもできません。
堀木訴訟は、生存権の社会権的側面の法的性格について、最高裁が判断を示した裁判です。
▽事件の概要▽
Xは、全盲の視力障害者で障害福祉年金を受給していました。
Xには子どもがおり、児童扶養手当の対象と考えられたため、Xは兵庫県知事に対して、児童扶養手当受給の申請を行いました。
ところが、兵庫県知事がXの申請を却下しました。
当時の法制度では、障害福祉年金を受給している人が、児童扶養手当を併給することが認められていなかったためです。
そこで、Xは、併給を認めない規定が、憲法25条2項に違反するとして、裁判を提起した。
①生存権を具体化する法律の合憲性を争う(堀木訴訟)
②生存権を具体化する法律の不存在を争う(立法義務付け、立法不作為の違憲確認、国賠)
③生存権の自由権的側面の侵害を争う(最低限度の生活を下回らせる課税など)
④生存権を具体化する法律の適用の違憲性を争う(行政より適用の誤り)
⑤具体化された権利水準の引き下げの違法性を争う(制度後退の場面


生存権の判例を学習する際は、裁判上、どのように争われているのかを意識しよう!堀木訴訟では、生活保護の受給権を制限する併給禁止規定の合憲性が問題となっており、①の場面が問題となっている。
結論から言うと、最高裁は、明確に法的権利説とプログラム規定説のどちらかの立場に立っているわけではありません。
生存権の社会権的側面について、法的権利は認めていないため、法的権利説の立場ではありません。一方で、裁判を提起することは認めているため、完全なプログラム規定説の立場であるとも言えないわけです。
最高裁の考え方は、学説とは違う考え方として押さえる必要があります。
最高裁の考え方を見ていきましょう。
まず、最高裁は、憲法25条について、「国には、福祉国家の理念により、国政を運営する責務があることを宣言した規定に過ぎず、個々の国民に具体的、現実的な権利を付与する規定ではない」としています。
つまり、法的権利説の考え方を否定し、プログラム規定説の立場に立つと言えるわけです。
プログラム規定説の場合、生存権の社会権的側面をどの程度実現するかは、国が判断することになります。最高裁も続けて、次のように述べています。
「健康で文化的な最低限度の生活の程度は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定すべきである。」
また、その判断に際しては、「国の財政事情や様々な事情を考慮し、高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とする」としています。
国が生存権の社会権的側面を実現するに当たっての一応の道筋を示したと言えます。
プログラム規定説の考え方によれば、生存権の社会権的側面の実現に関して、国がどのような政策を取ろうと、裁判所は一切、関与できないことになりますが、最高裁は、その点については一部修正し、次のように述べています。
「具体的にどのような立法措置を講じるかは立法府の広い裁量にゆだねられており、裁判所が違憲審査するのは、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合に限る。」
裁判所が、国の政策に対して、違憲審査する余地を認めている。つまり、憲法25条の裁判規範性を認めているわけです。
堀木訴訟の最高裁判決でもう一つ押さえたいことは、生存権の違憲審査基準として、「明白性の原則」を採用している点です。
明白性の原則とは、国の生存権に関する規定が立法裁量の限界を超えて、著しく不合理であることが明白な場合に限って違憲とする考え方です。
経済的自由に関する積極目的の規制と同様の考え方を採用しています。
学説もおおむねこの考え方に賛同していますが、生活保障の内容を最低限度の生活保障と、より快適な生活保障の二つに分けて、前者の生活水準は具体的、客観的に決められるのだから、厳格な合理性の基準を採用し、後者のみ立法府の裁量を認めて明白性の原則を採用すべきとする学説もあります。
①25条1項、2項の趣旨と関係を論述する
25条1項は「福祉国家理念に基づき、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるような国政を運営すべきことを国の責務として宣言したもの」、25条2項は「福祉国家理念に基づき、社会的立法及び社会的施設の創造拡充に努力すべきことを国の責務として宣言したもの」
↓
②国の責務として立法者は「すべての国民」との関係で、国民が「健康で文化的な最低限度の生活」を営むために必要な立法措置を講じる義務を有する
↓
③ただし、「健康で文化的な最低限度の生活」という概念は相対的抽象的な概念であるから、(具体的な内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものである。また、国の財政状況も無視できない)。どのような立法措置を講ずべきかについては、立法府に広い裁量権が認められる。
↓
④したがって、生存権を具体化する立法措置が著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱、濫用と見ざるを得ないような場合を除き、合憲と解するべきである。


簡略的な論述例だけど、生存権を具体化する法律の合憲性が争われた際は、堀木訴訟のロジックになぞって、判断枠組みを定立するのが良いと思うぞ!
判断枠組みの定立が苦手な受験生は、「躓かない司法試験予備試験の論文対策の方法」の記事における「問題の解決基準(規範)を定立できるか」が苦手というこです。


憲法は特に規範定立が苦手です。
どうしたらいいの?


▽参考記事▽
・躓かない司法試験予備試験の論文対策の方法
・憲法のおすすめの書籍
・アガルートの論証集の使い方講座のレビュー記事
上記の判断基準を示したうえで、最高裁は、堀木訴訟で問題となった障害福祉年金と児童扶養手当の併給を認めていない点について次のように判示しました。
▽堀木訴訟の判決結果▽
障害福祉年金と児童扶養手当はいずれも憲法25条の趣旨実現のための制度である。また、いずれも受給者に対する所得保障の制度で同一の性格を有する。
障害福祉年金と児童扶養手当の併給が必須とは限らず、社会保障給付の全般的公平を図るため公的年金相互間における併給調整を行うかどうかは、立法府の裁量の範囲に属する事柄であり、給付額が低額だとしても当然に憲法25条違反になるわけではない。
よって、Xの主張は認められない。


結論としては、併給禁止規定は、著しく不合理ではないとしているね!


そのロジックとして①2つの給付の性格の同一性、②一般的な事故数と稼働能力低下との比例関係の不存在を指摘しているぞ!
堀木訴訟では、Xは、憲法25条の他、憲法14条、13条違反も理由として上告しています。
併給調整条項により、児童扶養手当を受給できる者とできない者との間で、差別を生ずることが、法の下の平等に反するという主張です。
この点、最高裁は、このような差別が生じても、「なんら合理的理由のない不当なものであるとは言えない」とし、また、併給調整条項は、「児童の個人としての尊厳を害し、憲法13条に違反する恣意的かつ不合理な立法とは言えない」と判示して、いずれの主張も退けています。
最高裁は、生存権の社会権的側面について基本的に「プログラム規定説」の立場に立ち、法的権利性を認めていませんが、裁判規範性は認めています。
そして、生存権の違憲審査基準は、「明白性の原則」を採用しているということです。
学説と完全に一致するわけではなく、ややこしいですが、頑張って覚えてください。
①堀木訴訟では、生存権を具体化する法律の合憲性が争われた(まずは場面を理解する。裁判所における争われ方も理解する)
②生存権の社会権的側面について基本的にプログラム規定説に立ちつつも、当該立法措置が著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱、濫用とみられる場合には違憲となることを示した。
③結論としては、併給禁止規定は合憲としたが、そのロジックとして、二つの給付の性格の同一性、一般的な事故数と稼働能力低下との比例関係の不存在を指摘した。
理解をしても答案で表現できなければ意味がありません。
論文対策は、事例問題に挑戦するのが最も効果的です。
合格実績に優れたアガルートの「重要問題習得講座」はご存知でしょうか。
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。