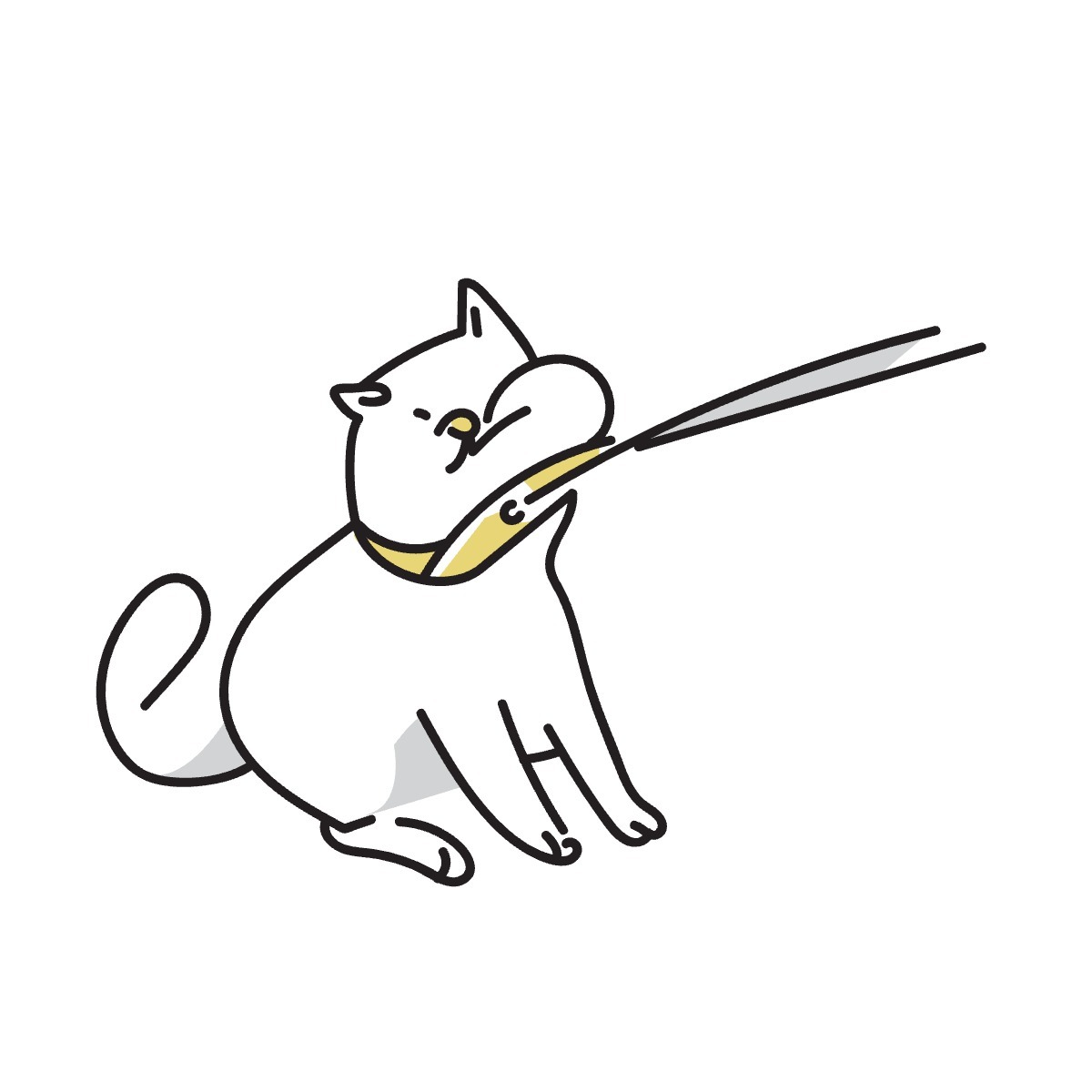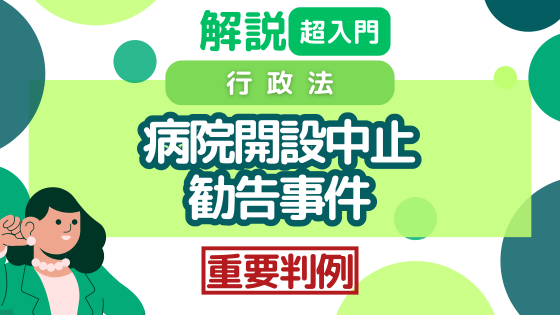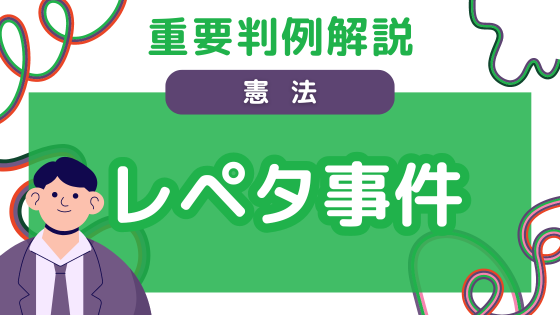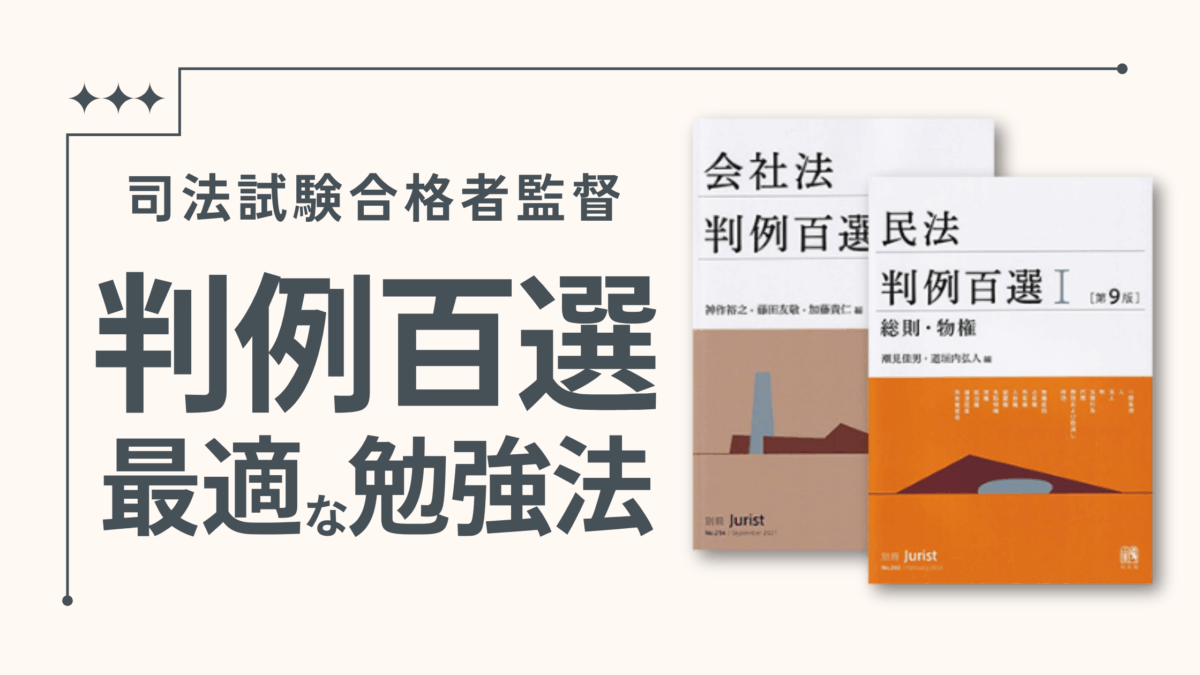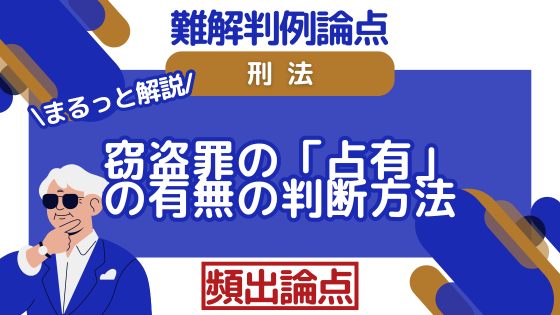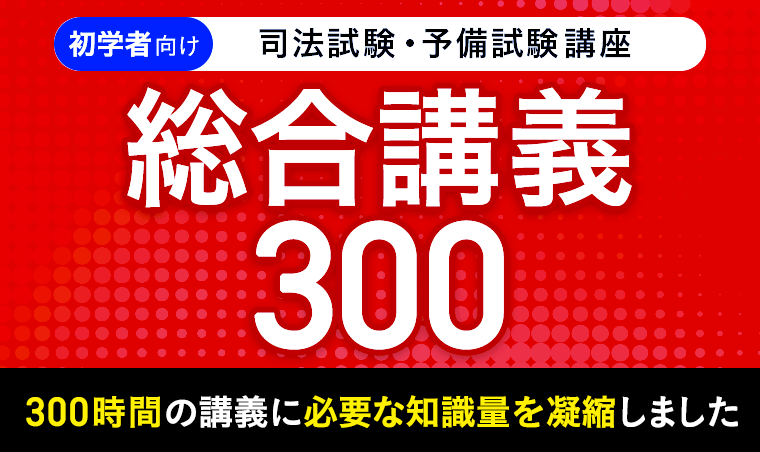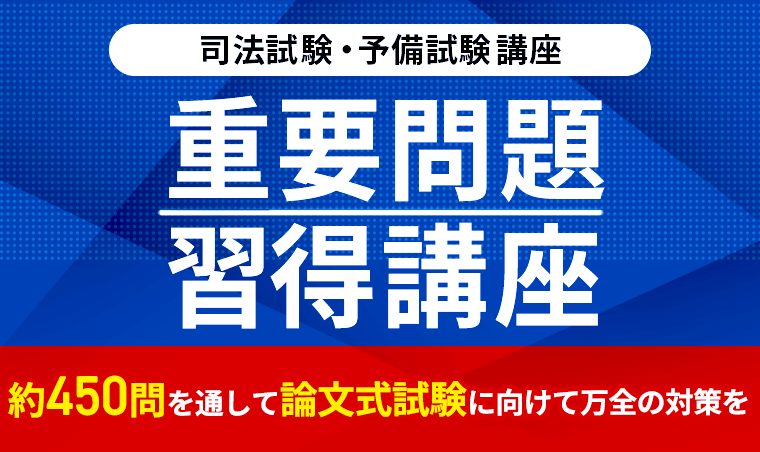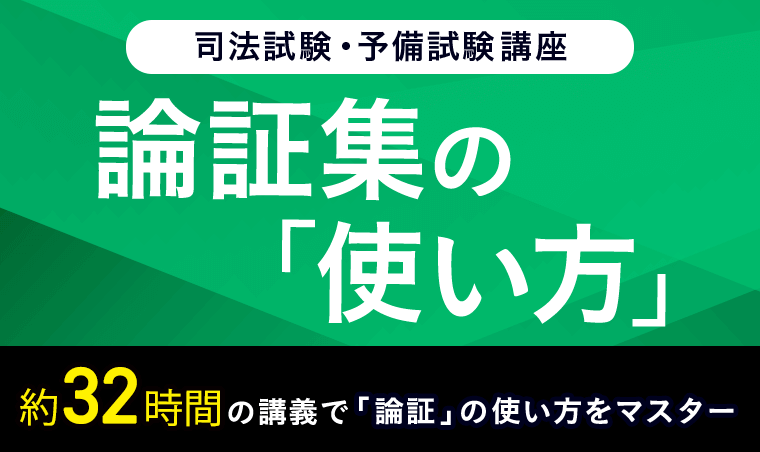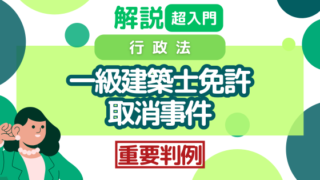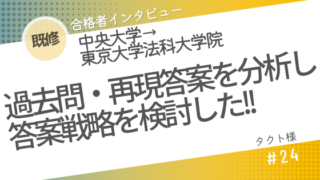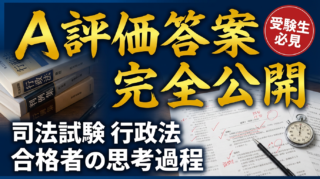一級建築士免許取消事件のどこよりも丁寧な解説【初学者から司法試験受験生まで】
当ページのリンクにはPRが含まれています。
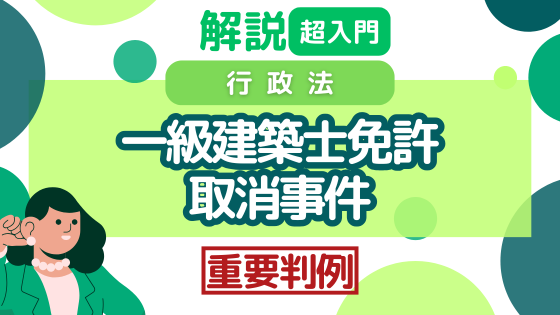
この記事では「一級建築士免許取消し(最判平成23年6月7日)」について、初学者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説していきます。
まず初めに、「一級建築士免許取消事件」の判決を理解するための3つのポイントと、簡単な結論を以下に示しておきます。
「一級建築士免許取消事件」を理解するためのポイント 3つ
1. 本判決はどのような事案か
原告が「一級建築士の免許を取消す処分」に対して、「当該処分は理由の提示という手続きを欠いた違法なものである」とし、取消しを求めた事案です。
2. 本判決の論点と規範
不利益処分をする場合、理由の提示が要求されますが(行政手続法14条1項)、「どの程度具体的に理由を示せばよいのか?」が問題となりました。
3. 本判決の判断
結論としては「処分基準の適用関係が示されていない、本件処分の理由の提示は不十分であり、本件処分は違法である」と判断しました



では、始めて行くぞ!
目次
「一級建築士免許取消事件」の事案
「一級建築士免許取消事件」の事案
- X(原告)は、「一級建築士」として建築物の設計を行ってきましたが、国土交通大臣から「建築士法10条1項2号及び3号に基づき一級建築士免許取消処分(以下本件処分という)」を受けました
- 当時、このような懲戒処分については「処分基準」が定められ、公にされていました
- このような「不利益処分」をする際には「理由の提示(行政手続法14条1項)が要求」されています
- Xへの本件処分の「通知書に記載された理由」には「処分基準の適用関係」が記載されていませんでした
- そこでXは「本件処分は、公にされている処分基準の適用関係が理由として示されておらず、行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法な処分である」として本件処分の取り消し訴訟を提起しました



参考情報だけど、もともと、Xは、複数の建築物の設計者として、建築基準法令の構造基準に適合しない設計を行い「耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させ」て、「構造計算書に偽装が見られる不適切な設計を行った」ということで、免許取消処分を受けたみたいだよ!



さて、今回は「免許取消処分」の中で、「理由の提示」で「処分基準の適用関係」が示されておらず、「どの程度具体的に理由を示せばよいのか?」が問題となったんだ!
詳しく見ていくぞ!
今回の「一級建築士免許取消事件」では、行政手続について、そのなかでも特に「理由の提示」について見ていくことになります。
Xの主張の概要
Xの主張は、要するに以下のような内容です。
Xの主張
・本件処分には「理由の提示」が必要なはずである。
・しかし、私は「処分基準がどう適用されて、本件処分がなされたのか?」を説明してもらっていない。
・それでは「理由の提示」として不十分であり、「理由の提示」があったとは言えない。
・なので、本件処分は「違法」である。
「処分基準」とは?
前提として「処分基準」という単語が分からない方のためにその意味を説明しておきます。
「処分基準」とは、ざっくり言うと「行政が作る不利益処分に関する内部基準」の事です。「処分基準」があると裁量権行使に関する予測可能性や透明性が向上します。
「処分基準」とは?
行政が作る不利益処分に関する内部基準
「裁量」とは?
「???」と思う方もいるかと思うので、まず「裁量」について簡単に説明しましょう。
「処分」の中には行政に判断の幅が認められているものが存在します(これを「裁量がある処分」と言います)。
「裁量がある処分」をする場合、行政としては「ある処分をするのかしないのか?」という判断や「Aという処分をするのかBという処分をするのか?」という判断を、ある程度自由に行うことができます。
「裁量」が認められると、「行政による柔軟な法適用」が可能になりますが、「処分」を受ける国民の側からすると、「行政の判断の予測可能性が立ちにくく、行政の判断が不透明」な状態になります。
もう少し、詳しく説明しましょう。
「裁量がない処分」なら、行政に判断の余地がなく「Xという行動をしたら、法律に書いてある通りにAという処分がなされるはずだ」との予測が立ちます。しかし、「裁量がある」場合、行政にある程度の判断の余地が認められているので、「Xという行動をしたら、AかBという処分がされるかもしれない。されないかもしれない。」といった具合に予測は立ちません。(予測可能性がない)
また「裁量がない処分」の場合、「なぜAという処分がされたのかは法律を見れば分かる」ことも多いです。しかし、「裁量がある処分」の場合、法律を見ても「AかBかCをすることができる」などと書いてあるので、「なぜBでもCでもなくAという処分が選択されたのか?」や、「なぜしてもしなくてもよいAという処分がされたのか?」を知ることができません。(不透明)
このように「裁量」には「行政の予測可能性や透明性を損なう」という弊害があるわけです。
そしてここで出てくるのが「処分基準などの裁量基準」です。たとえ「裁量のある処分」でも、裁量行使に関する「行政の内部基準」が定められ、それが公表されていれば、国民はその基準を見ることで処分に関する予測を立てやすくなりますし、「処分の透明性」も向上します。
ちなみに行政手続法も「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」(12条1項)として、「処分基準の設定、公表」を努力義務化しています。
まとめると「『処分基準』とは、『行政が作る不利益処分に関する内部基準』であり、これによって『国民の裁量権行使に関する予測可能性や透明性が確保』される」ということになるかと思います。
行政の処分における「裁量の有無」の違いと、「処分基準」の関係
裁量がない処分:行政に判断の余地はなく、法律等に「処分の根拠」が示されている
裁量がある処分:法律を見ても「AかBかCをすることができる」などと書いてあり、「処分の理由」が分かりにくく(不透明)、行政にある程度の判断の余地が認められているので、具合的な予測が立ちにくい(予測可能性がない)
→「行政に裁量がある処分」でも、「行政庁は、不利益処分等に関する内部基準である『処分基準』を定め、公にする」ことに努め、「国民の裁量権行使に関する『予測可能性』や『透明性』の確保をしてね」とされている
上記のことから、Xは「『処分基準がどう適用されて、本件処分がなされたのか?』の説明がなく、『理由の提示』として不十分であり、『理由の提示』があったとは言えない」と主張しています。
「一級建築士免許取消事件」の判決の論点と規範
まず、行政が不利益処分をする場合「理由の提示」が要求されます。根拠は以下です。
行政手続法 14条1項
行政庁は「不利益処分」をする場合には、その名あて人に対し、同時に、「当該不利益処分の理由」を示さなければならない。
では、「どの程度具体的に」理由を示せばよいのでしょうか?この点について本判決は、以下のように述べました。
「一級建築士免許取消事件」の判決
行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。
そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、①当該処分の根拠法令の規定内容、②当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、③当該処分の性質及び内容、④当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。
これは長いですが、重要な規範です。
判決後半に記載がある「どの程度の理由を提示すべきか?」の考慮要素について、簡単に説明すると、以下になります。これらを総合的に考慮して「どの程度提示すべきか?」を判断します。
「どの程度の理由を提示すべきか?」は、以下を総合考慮して決定される
①処分の根拠法令の規定内容:「どういう条文に基づく処分なのか?」
②処分に係る処分基準の在否及び内容並びに公表の有無:「その処分に関する基準はあるのか?あるならどのような基準か?公表されているか?」
③処分の性質及び内容:「その処分はどのような処分か?」
④処分の原因となる事実関係の内容等:「どういう原因で処分がされたのか?」



少しでもわかりやすくするために図式化したので、参考にしてみてくれ!


「一級建築士免許取消事件」の判決の判断
では本判決では①から④を用いて、処分基準の適用関係が理由として示されていない本件の理由の提示は不十分であると判断しました。(以下太線は判例の言い回し)
①「どういう条文に基づく処分なのか?」
①について本件処分は建築士法10条2号、3号によるものでした。
当時2号は「この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。」3号は「業務に関して不誠実な行為をしたとき。」となっており、処分要件は抽象的な規定ぶりでした。また違反したときにも戒告、業務の停止、免許取消しのいずれの処分を選択するかも処分行政庁の裁量に委ねられていました。すると、法律だけ見ても具体的なことはわからないわけですから処分基準を示す必要性は高まりそうですね。
②「その処分に関する基準はあるのか?あるならどのような基準か?公表されているか?」
②について基準は手厚い手続を経た上で定められて公にされており、内容はかなり複雑なものでした。このような経緯がありさらに公表までされている処分基準は重く見るべきですし、内容が複雑なのだから行政が説明してくれないと国民は理解できません。すると処分基準を示す必要性は高まりそうです。
③「その処分はどのような処分か?」
③については、本件処分は一級建築士としての資格を直接にはく奪する重大な不利益処分であり、丁寧な理由の提示が求められそうです。
④「どういう原因で処分がされたのか?」
④については,上告人 X1が,札幌市内の複数の土地を敷地とする建築物の設計者として,建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い,それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させ,又は構造計算書に偽装が見られる不適切な設計を行ったということですが、このような事実関係だけからなぜ当該処分が行われたのかを知ることはむずかしいです。
以上より、処分基準の適用関係が理由として示されていない本件の理由の提示は不十分であると判断がされました。
おわりに
今回の記事もお読みくださりありがとうございました。
▽参考文献▽
行政判例百選II〔第8版〕 別冊ジュリスト 第261号.
櫻井敬子,橋本博之(2019)『行政法[第6版]』弘文堂.
下山憲治,友岡史仁,筑紫圭一(2017)『行政法』日本評論社.
海道俊明,須田守,巽智彦,土井翼,西上治,堀澤明生(2023)『精読行政法判例』弘文堂