
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
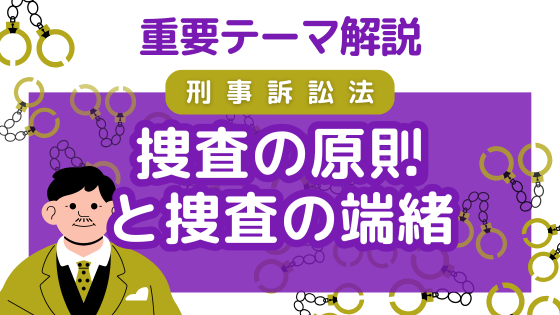
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする刑事訴訟法は「犯罪捜査や刑事裁判の流れを定めたルール」であり、法律を学ぶ上で欠かせない科目です。
特に「捜査の原則」と「捜査の端緒」は、刑事事件がどのように始まり、どんなルールのもとで進められるのかを理解するうえで重要なテーマです。
これらは、少し難しく感じるかもしれませんが、一つずつ整理して学んでいけばしっかりと身につけることができます。本記事では、具体例も交えながら初学者でもわかりやすいように解説していきますので、一緒に基本を押さえていきましょう。



それでは始めるぞ!
「捜査の原則」と「捜査の端緒」は、刑事事件がどのように始まり、どんなルールのもとで進められるのかを理解するうえで重要なテーマです。まずは「捜査の原則」から確認していきましょう。
捜査においては「令状主義」や「強制処分法定主義」といった基本的なルールが存在します。これらは、捜査機関による権力の濫用を防ぎ、被疑者や被告人の基本的人権を守るために設けられているものです。
このように「令状主義」と「強制処分法定主義」は一部重なる部分があるものの、それぞれ独立した原則として理解しておく必要があります。


次に「捜査の端緒」について解説していきます。
このテーマは、「刑事訴訟法の中で捜査がどのように始まるのか?」を示す重要な部分です。「捜査の端緒」は簡単に言えば「捜査が開始されるきっかけ」を指します。
犯罪捜査は「捜査機関が、犯罪の発生を何らかの形で知ったとき」にスタートします。その「知る契機」を刑事訴訟法は明確に整理していますので、これを一つずつ確認していきましょう。
刑事訴訟法では、「捜査の端緒」として、主に以下6つが挙げられます。これらが端緒となって、捜査が開始していくイメージが持てれば良いでしょう。



条文を引用しているが、自分の六法でも実際に確認してくれ!
「捜査の端緒」の種類6つ
捜査の主体としては、大きく以下の3種類の捜査主体(捜査機関)が存在します。
捜査主体(捜査機関)の3種類
そして「司法警察職員」は、さらに「司法警察員」と「司法巡査」に分かれます。
それぞれ役割が異なり「司法警察員」と「司法巡査」は警察官としての立場から捜査に当たります。一方「検察官」と「検察事務官」は検察庁に所属し、事件の訴追や処理を主導する役割を担います。
重要なことは「各主体に認められた権限が異なるため、それぞれが行える捜査内容に違いがある」という点です。この規律に基づいて、捜査が適切に運用される必要があります。
刑事訴訟法において、これらの捜査機関に関する用語は、明確に使い分けられているので条文を読む際は注意をしましょう。
今回取り上げた「捜査の原則」と「捜査の端緒」は、刑事訴訟法を学ぶうえで欠かせない基盤となるテーマです。これらの原則は、犯罪捜査がどのように始まり、どのようなルールのもとで進められるのかを体系的に理解するための土台となります。
「令状主義」や「強制処分法定主義」が人権保障の観点でどれほど重要か、また「捜査の端緒」がどのようにして犯罪捜査のスタートとなるのかを学ぶことで、刑事訴訟法全体の構造がより明確に見えてくるはずです。
こちらの法スタの解説記事は、超基礎です。
深く勉強をしたい方は、刑事訴訟法の基本書や予備校の講義を受講しましょう。法律は勉強が進めば進むほど楽しくなります。


次のステップは、【強制処分と任意処分の違い】です。
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
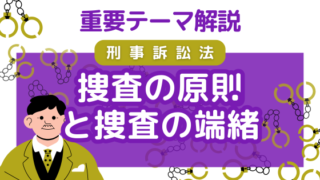
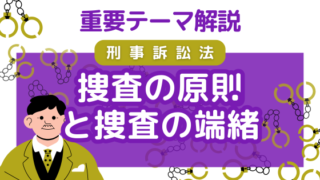
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

