
【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!
司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF
※閉じるとこの案内は7日間再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)
「もう少しで期末試験だけど、法律試験の対策の仕方がわからない」
「とにかく時間がない。何から始めればいいのだろうか」
「期末試験は論文式試験らしい。論文の書き方が分からない」
今回は、法学部の期末試験の勉強法について解説させて頂きます。
法学部は、出席不要で、評価は試験のみというところが多いです。普段は楽だが、期末試験の時期には大変になるのが法学部です。筆者も法学部生の時に、試験直前になり焦っていたことをよく覚えています。
法学部の成績評価は「ほぼ100%試験の結果」=成績は試験の結果次第
また、法学部の成績評価は、ほぼ100%試験の結果ですよね。授業にきちんと出席した方も、全く出席してこなかった方も、成績は、試験の結果次第です。フェアと言えばフェアですが、一回勝負のため不安にもなりますよね。



今回は、法学部の期末試験の乗り切る方法や勉強法について解説させて頂きます!
本記事を読めば、以下が分かります。
≪こちらの記事で分かること≫
①法学部の期末試験の対策
②法学部の勉強法
③暗記で乗り切れるのか



やあ、法律を学ぶみんな!
今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!



そうなのそうなの〜!
受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨



特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!



あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱
お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!
📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】
司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!
現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。
\ このタイミングを逃す手はありません /
合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。
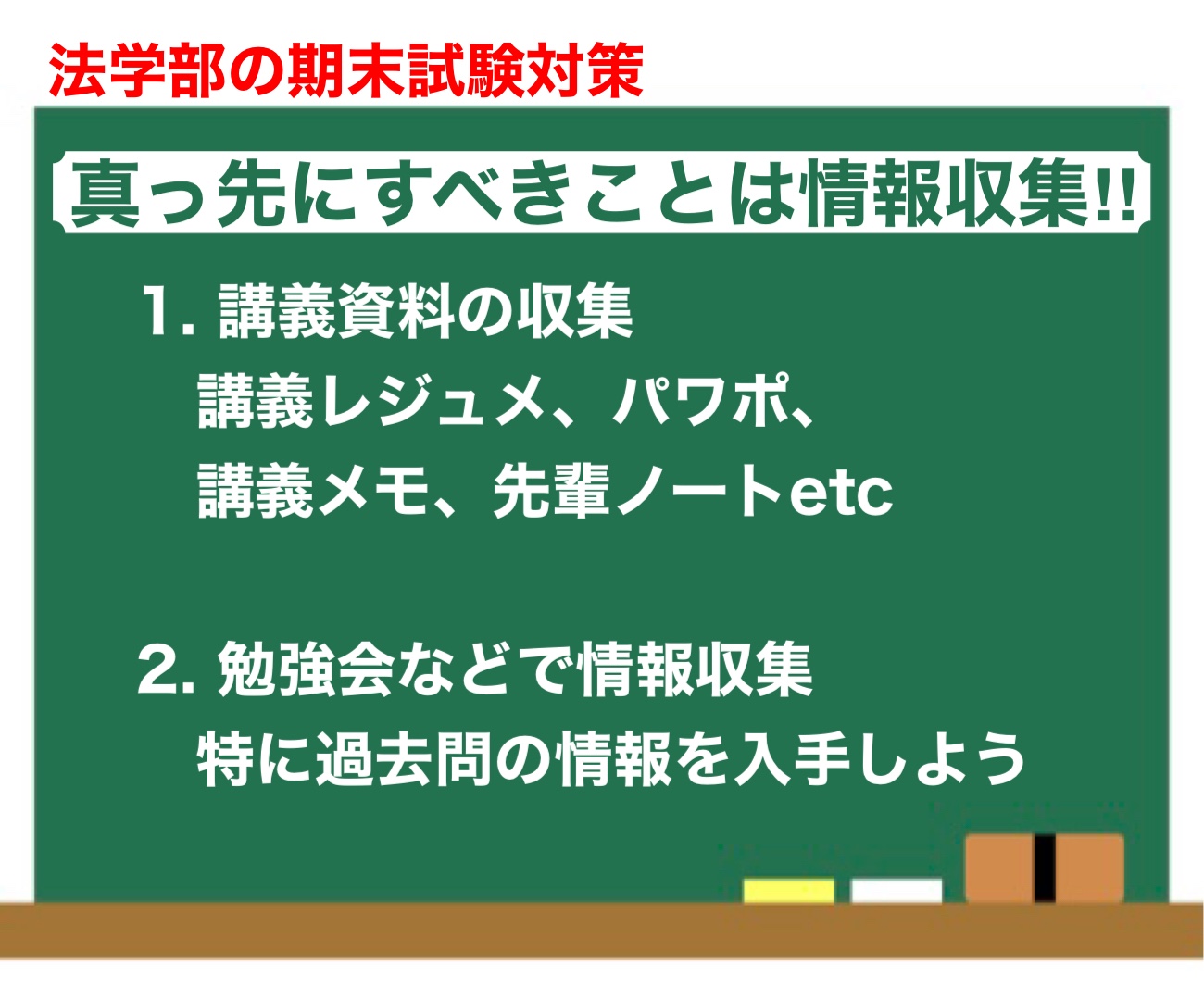
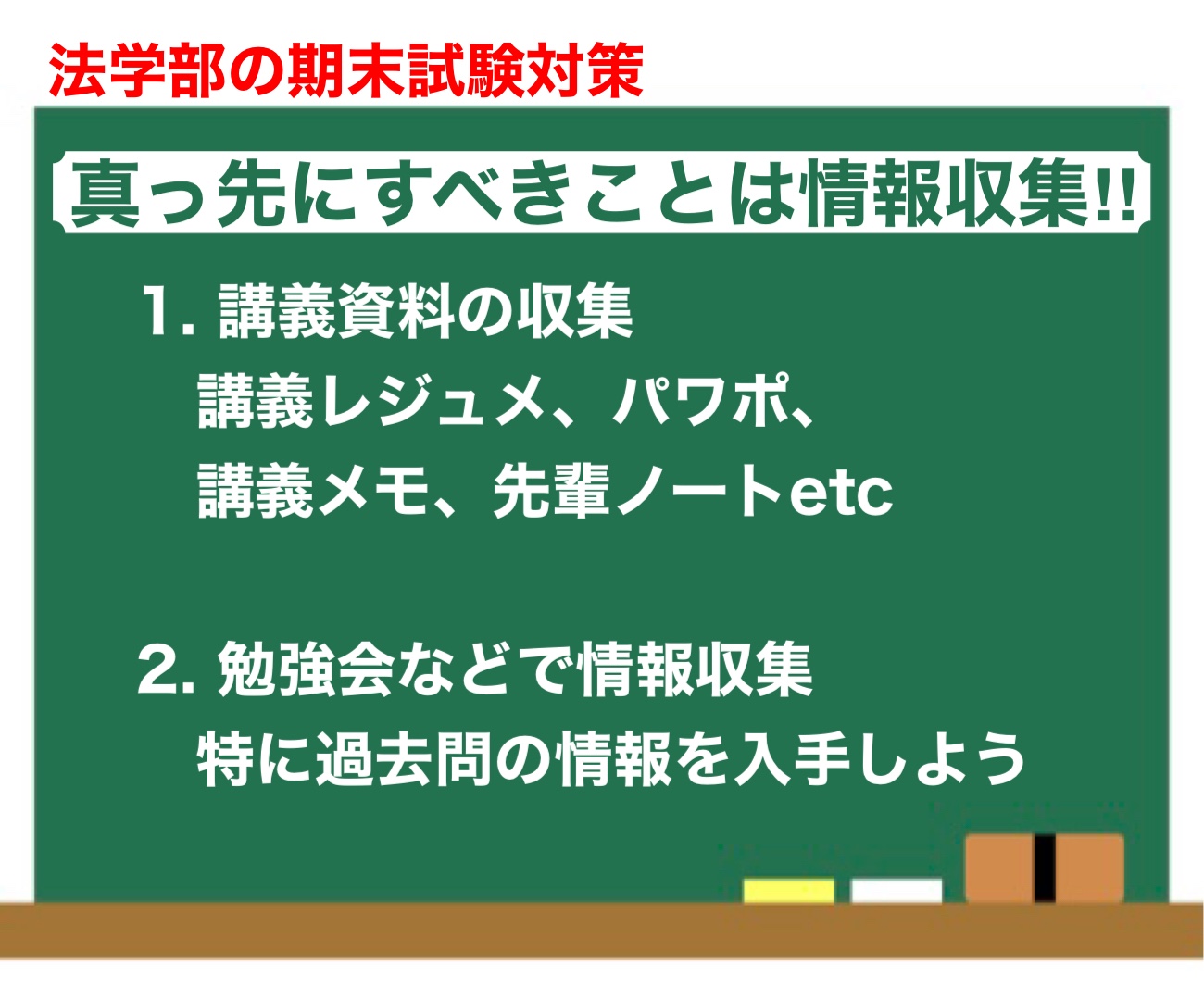
法学部の期末試験は、論文式試験が基本ですが、出題傾向などは問題を作成する教授によって大きく異なります。勉強に自信がある方も情報収集をするようにしましょう!!
期末試験対策で最も重要な事は、情報の収集です。情報収集をどれだけ適切に出来るかで、単位が取れるか、上位の成績が取れるかが変わると言っても過言ではありません。
「講義レジュメ」や「過去問」の情報を収集することが大切です。
試験は「講義内容」を踏まえて出題されますので、まずは、「講義レジュメ」を収集して講義の内容を把握しましょう。ここで遺漏なく資料を収集しているか否かで単位を取れるかどうかも決まると言っても過言ではありません。
試験対策で、最も大切な情報収集は「講義レジュメ」の収集です。
「過去問」に関する情報もかき集めましょう。出題の形式などは、教授によって癖があったり、特定のテーマを毎年出題している教授も珍しくありません。先輩にお願いするなどして、過去問に関する情報も出来るだけ集めましょう。
講義レジュメの収集の方法としては、まずは友人に声をかけて資料の収集に協力してもらいましょう。お互いに持っている資料を交換し合うと良いでしょう。
大学によっては、過去問集が存在するようです。そのような情報を入手したら、周りの友人に聞いてみても良いでしょう。
期末試験対策は情報戦です。どれだけ迅速に情報を収集出来るかがポイントとなります。普段から情報収集に努めましょう。
講義の中で、教授が「試験」について話していることがあります。
勉強会などで情報収集をしましょう。
たとえば、出題形式や配点や「この判例については必ず出題する」等を講義の中で話していることがあります。
授業に出ていないと入手できない情報です。すべての講義に出席できていない人は、出席していた友人に声をかけて、確認しておきましょう。筆者も学部時代に、あまり関わりのない人にも頭を下げて、講義レジュメや過去問の情報を教えてもらったりしていました。


まずは、とにかく情報収集だね!
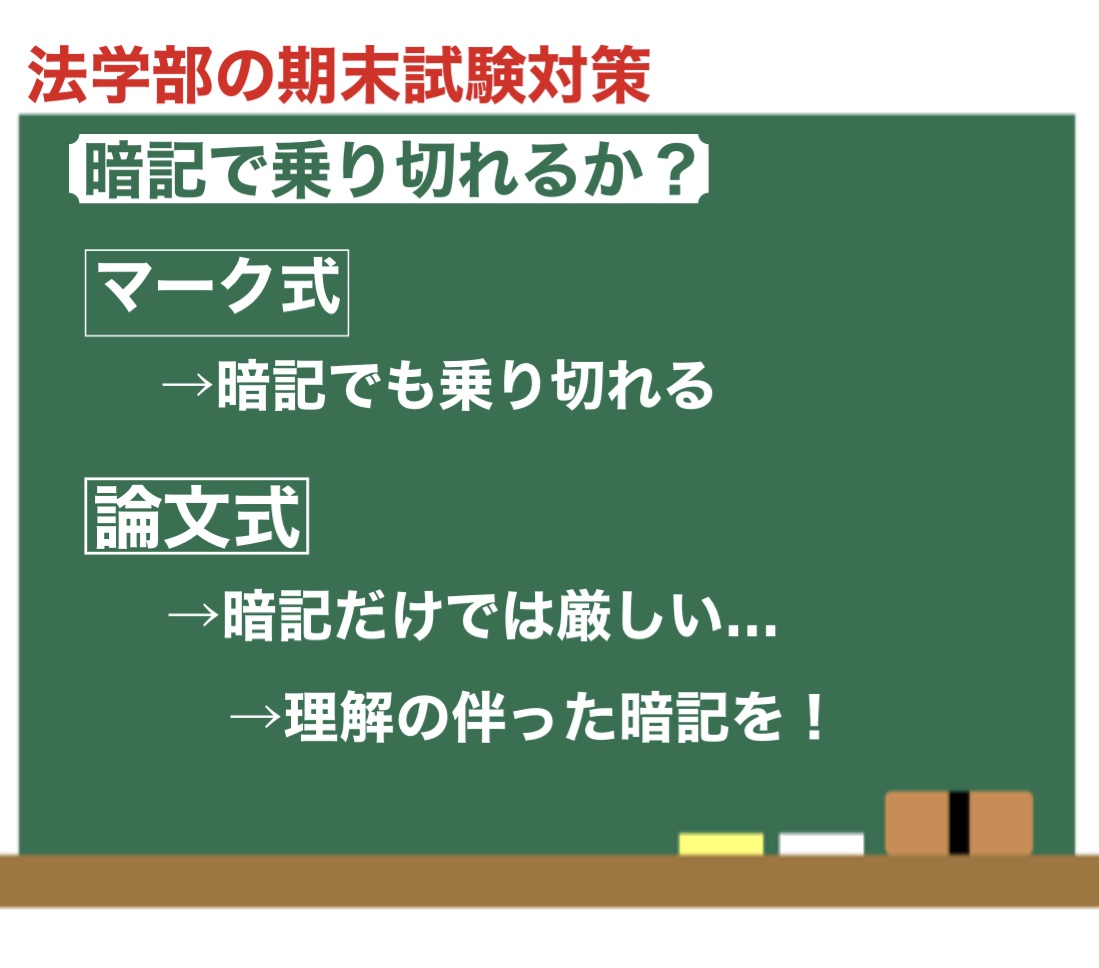
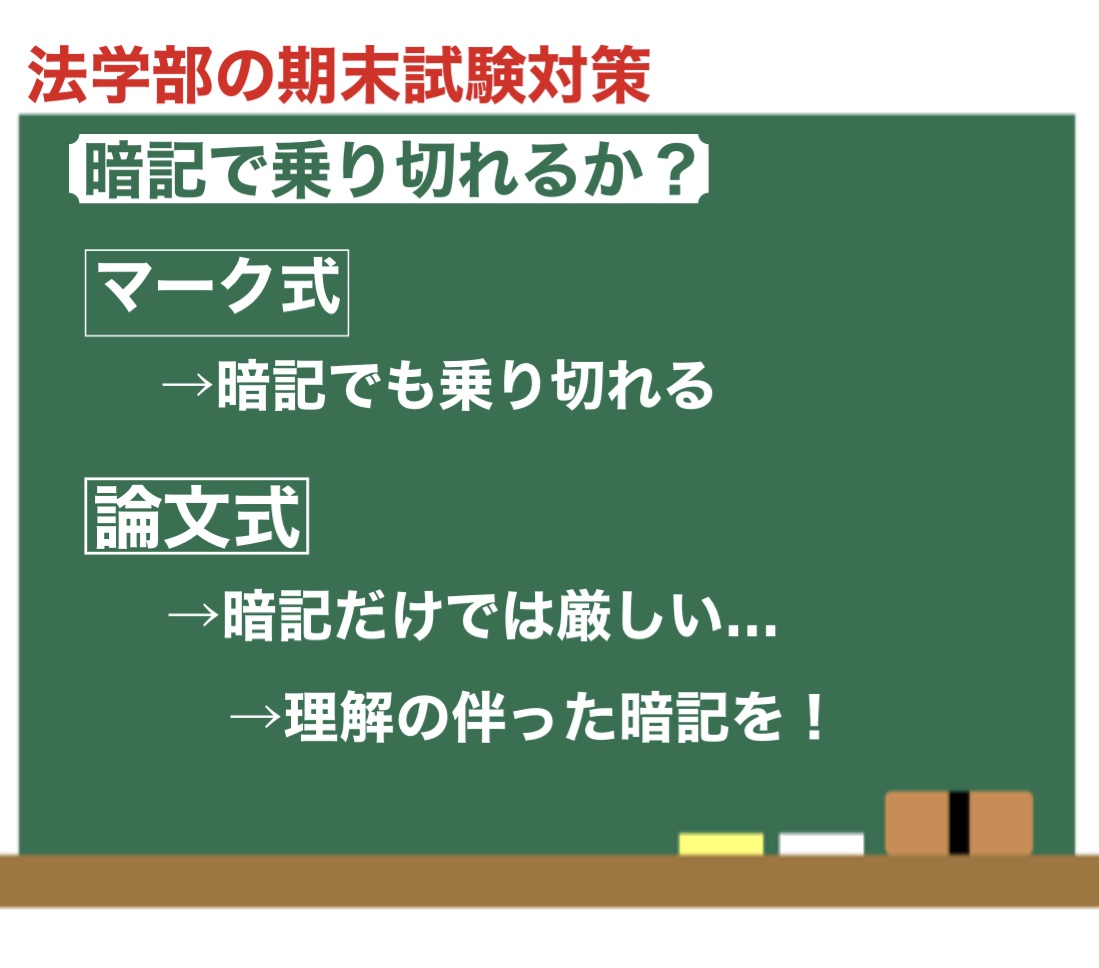
よくある質問として、「法学部の期末試験は暗記で乗り切れるのか?」という質問があります。試験の形式にもよるかと思います。例えば、マーク式試験の場合は、有る程度暗記するだけでも乗り切ることが出来るでしょう。
ただ、多くの大学では、法学部の期末試験は、論文式試験だと思います。
論文式試験の場合、「暗記で乗り切れるか?」に対する答えは「NO」だと思います。暗記をしなければならないこともありますが、いくら暗記したとしても理解が出来ていないので有れば、単位取得することは難しいでしょう。
筆者も暗記で詰め込んで、徹夜で民法の試験に挑んだことがありますが、全く頭が回らず、かつ、理解もしていないので、単位を落としてしまったことがあります。
法学部の期末試験は、基本的に論文式試験のため、暗記がそのまま得点に直結するものではありません。
遠回りと思われるかもしれませんが、理解を優先して勉強をしていきましょう。
法律の試験は暗記で乗り切れないことを認識し、出来るだけ早く試験対策に着手する必要があることを理解しておきましょう。他の学部の友人と合わせていると、時間が足りないという事態になります。
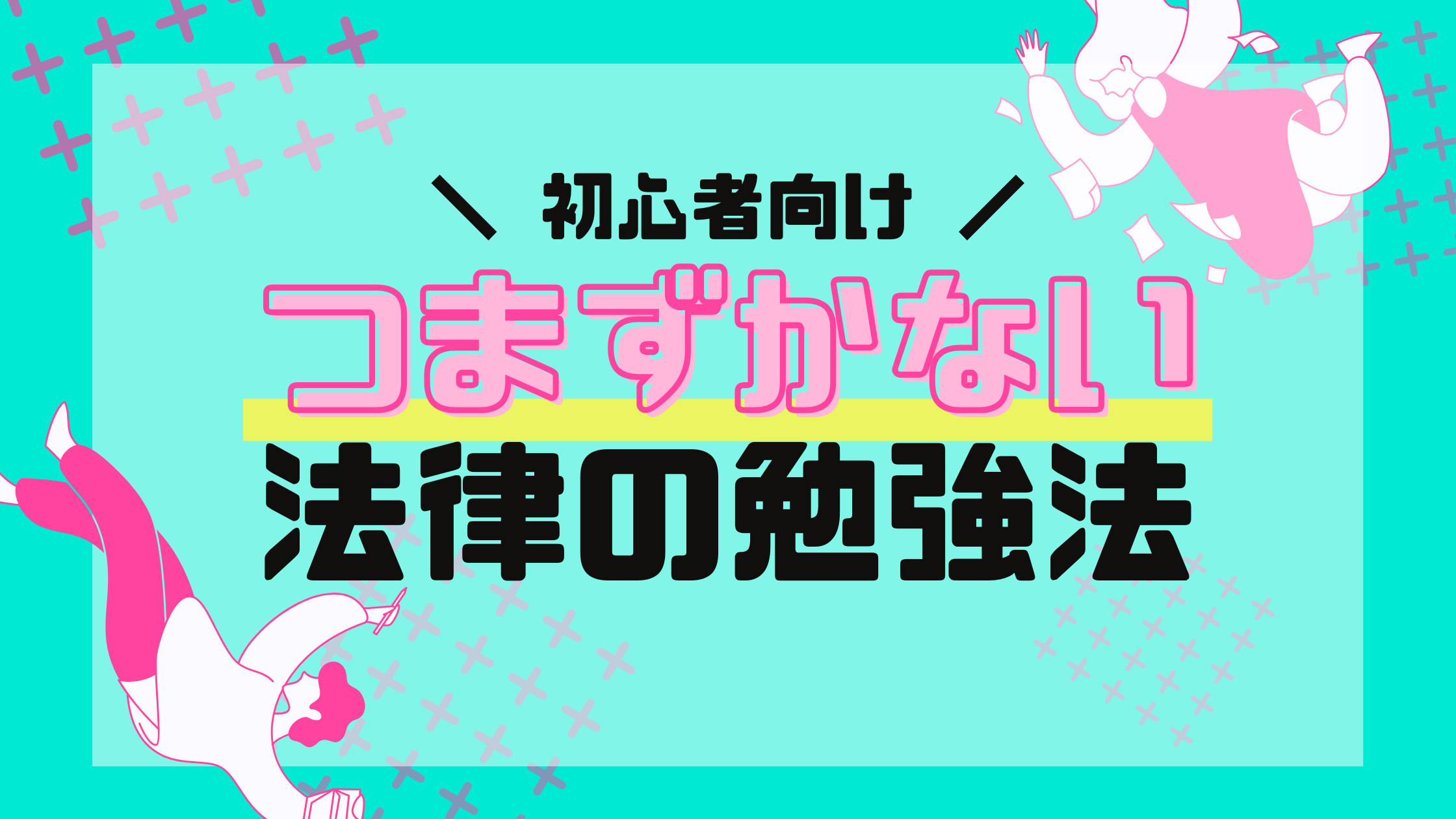
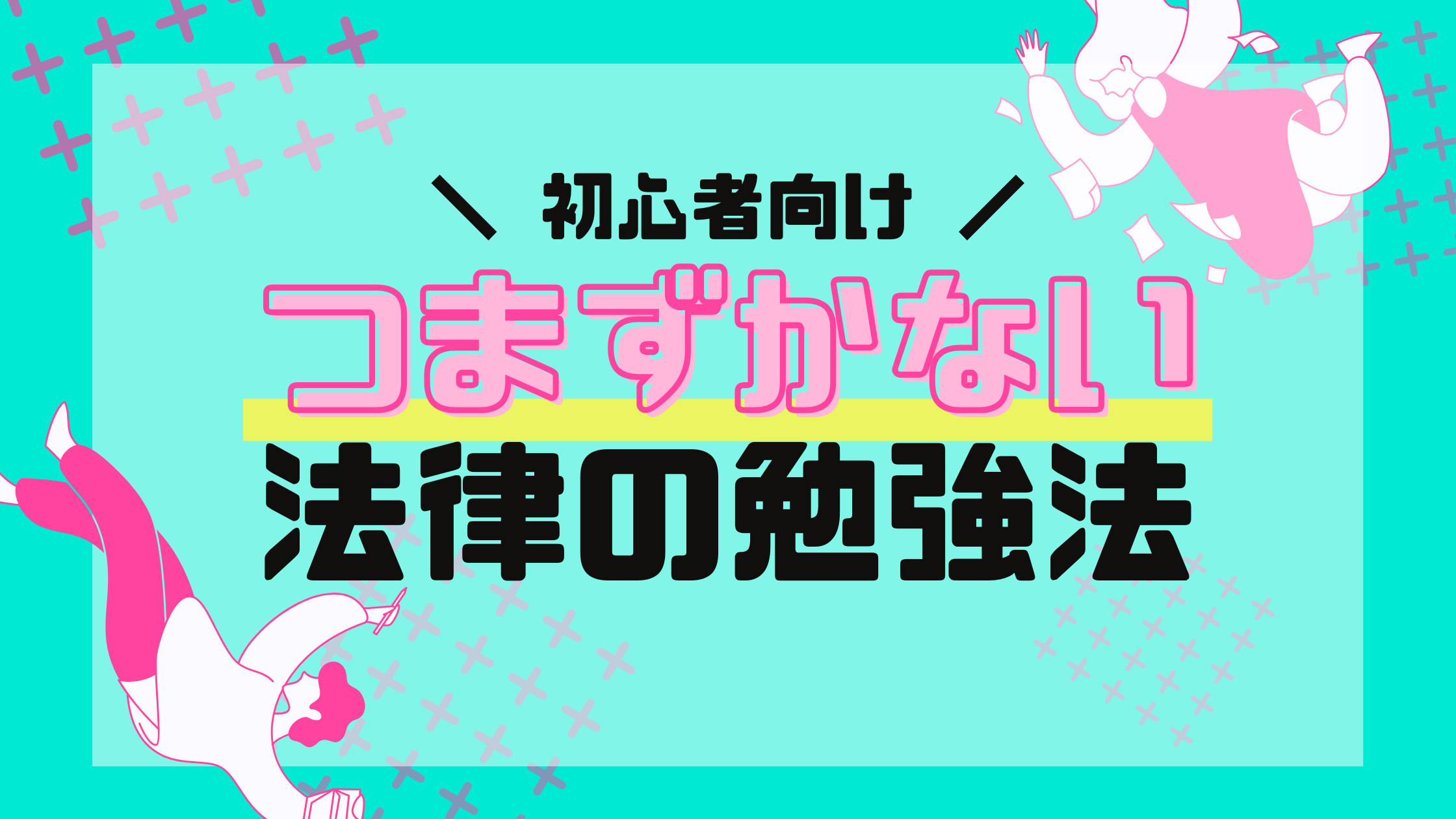
続いて法学部の期末試験の対策について具体的に話して行きたいと思います。
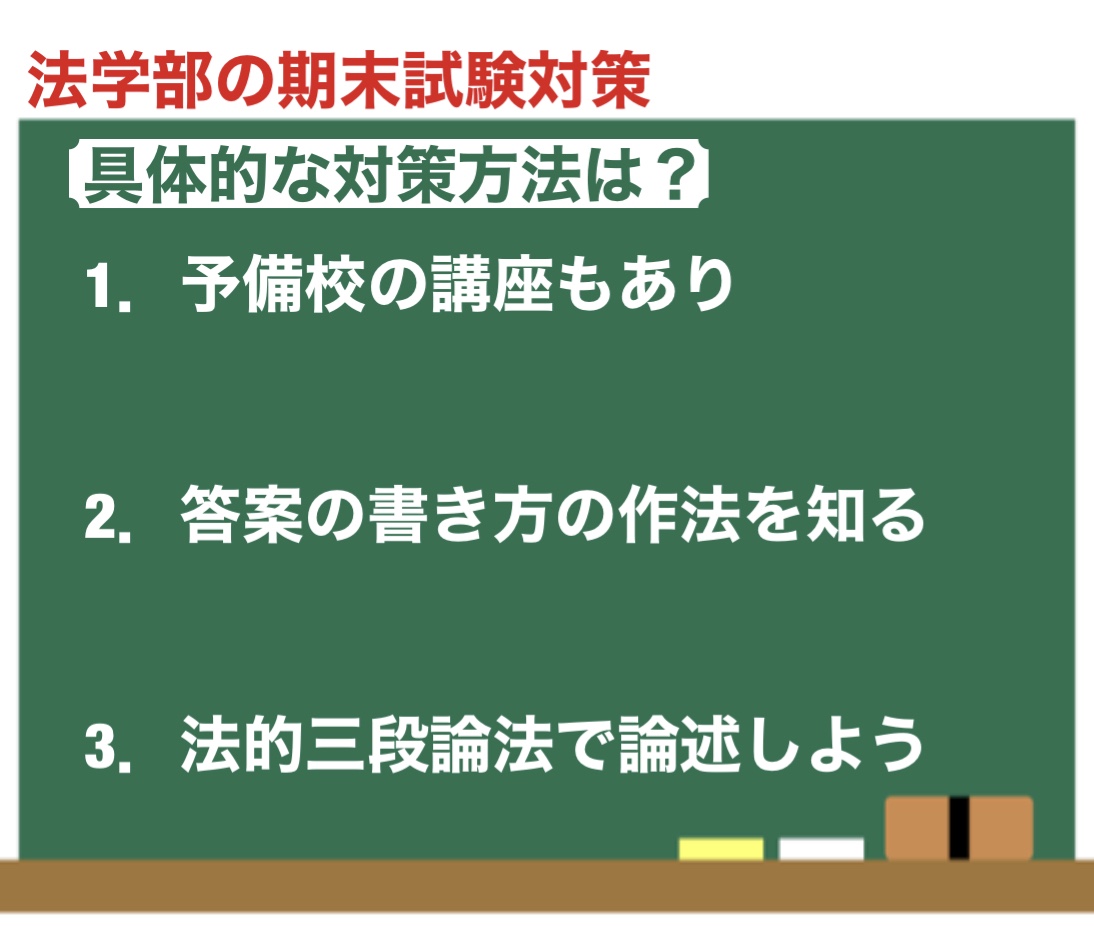
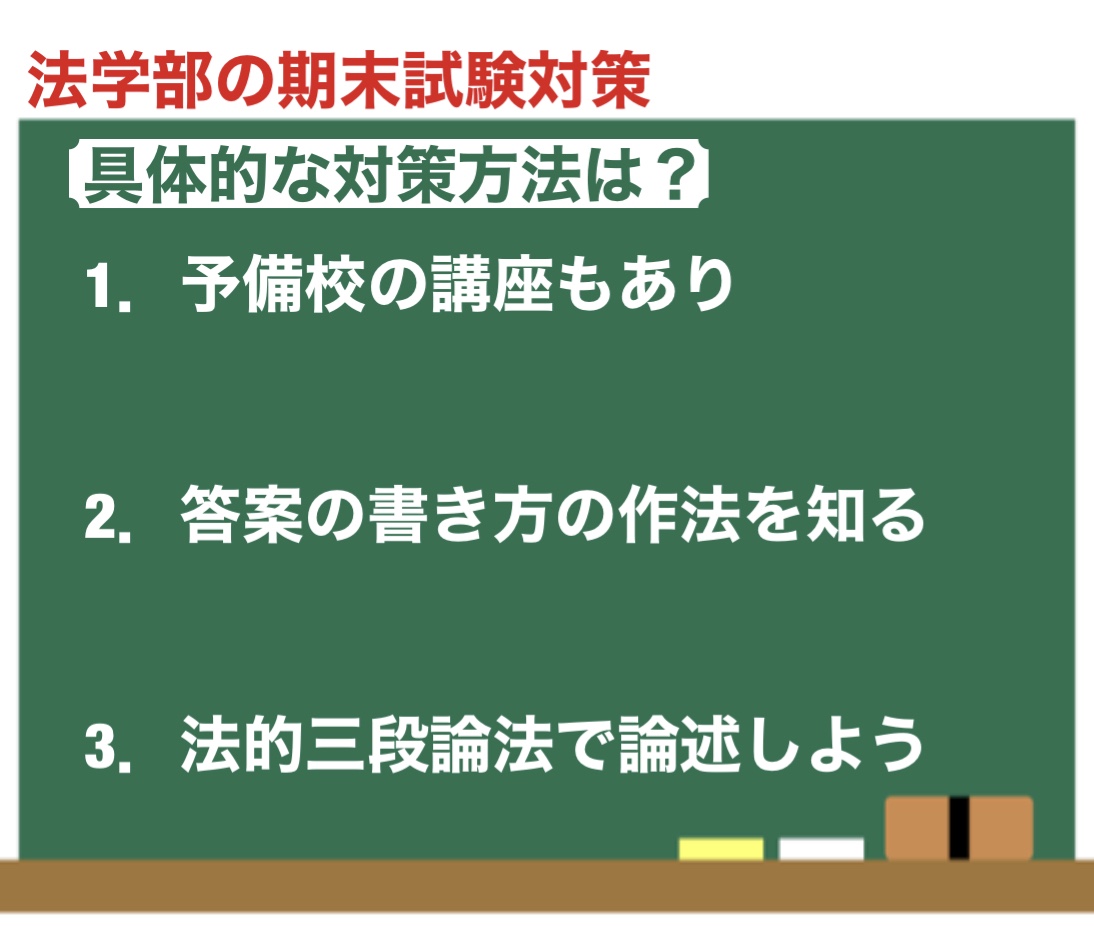
予備校の無料講座を利用するのも一つの手です。特に、オンライン予備校は無料講義を揃えているので、一回試してみると良いと思います。
無料講義を配信している予備校はいくつかありますが、おすすめはアガルートアカデミーです。
アガルートアカデミーは、「受けちゃえ、難関試験」のキャッチコピーで最近、大人気の資格予備校です。現在は、法律系資格のみならず、幅広く講座を提供していますが、元々は、司法試験予備校として非常に人気の予備校でした。
↓司法試験の合格者の多くが利用している予備校です↓


また、会員登録することなく、無料で受講することができるので、個人情報を提供する必要はありません。また、サンプルテキストも公開されているので気軽に受講を始めることができます。また、各科目、無料講義が用意されています。
司法試験の合格者数も多く、急成長している予備校です。
余裕がある人はお試し受講も検討してみましょう。
\無料講座で効率よく試験対策を/
法律科目の論文試験には「書き方」の作法があります。「法的三段論法」と呼ばれるものです。
「法的三段論法」を踏まえた論述を出来ているかどうか?で答案の出来栄えはもちろん、評価にも関わってきます。
また、どの試験にも共通することですが、設問をきちんと読みましょう。そして、問われていることに答えるようにしましょう。
「答案の書き方」の作法を知らないと、知識はあるのに得点が取れないということになりかねません。せっかくの知識を得点に繋げるためにも、「法律答案の書き方」を心得ておきましょう。
以下は、司法試験予備試験受験生向けの記事ですが、法学部生にも参考になるはずです!
論文式試験の対策については以下の記事で解説しています。
>>>【初学者向け】躓かない司法試験予備試験の論文対策の方法
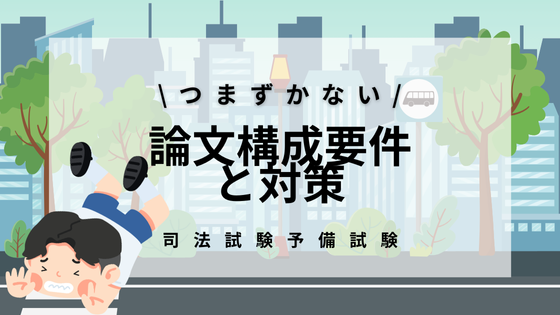
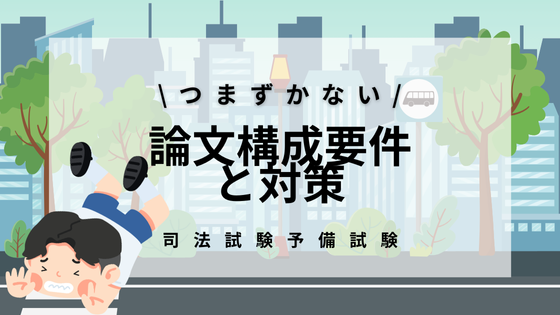
司法試験予備校の講座でしっかり学びたい方はこちら!
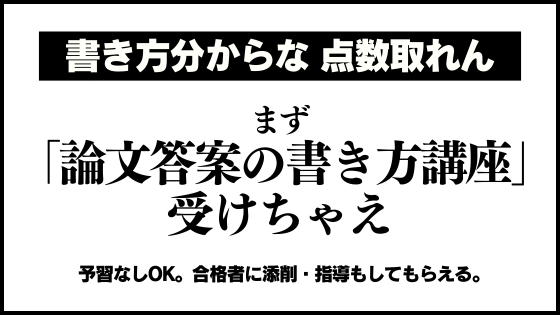
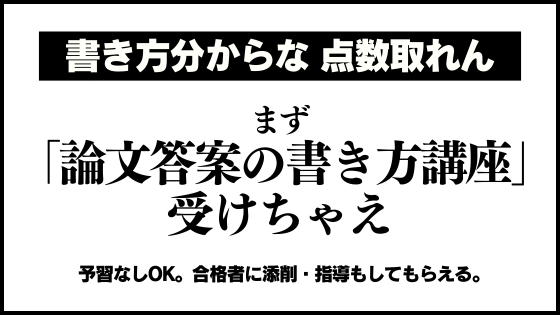
「法的三段論法」とは、一般的に「大前提(=法解釈)」に「小前提(=事実認定)」を当てはめて結論を導くというものと言われいます。
法律の答案で考えると、ここで、大前提とは、いわゆる規範のことです。そして、小前提とは、問題文で与えられている事実のことです。
「法的三段論法」は、法学部の試験では、当然の前提となっている論述の方法です。「法的三段論法」に沿わない答案は高評価を獲得するのは難しいでしょう。



答案では、「法的三段論法」をどれだけ意識するかが非常に大切だ!
法的三段論法を無視した答案では、どれだけ論述しても、単位を取得するのは厳しいと思うぞ!
「法的三段論法」を踏まえた答案の型をご紹介しておきます。
この「法的三段論法」に従い、答案を作成することが法律答案の大切な作法の一つとなります。「法的三段論法」を意識して答案を作成することができるようにしておきましょう。
条文解釈上の問題、文理解釈などの問題意識を示す。
問題の解決基準(規範)を示す。理由付けも行う。
定立した規範を事案にあてはめる。
あてはめの結果。問題提起に対する結論を示す。
法律の答案のうち「規範定立」は型がある程度決まっているため、事前に対策をすることで対応することができます。
司法試験受験生の中では、当たり前の事実ですが、この「規範定立」のみを一冊に纏めた教材があります。
それは「論証集」です。その名の通り、法律の答案の「論証」例を集めたものになります。「論証集」を使って対策をすれば、ある程度の論述が可能となります。
「規範定立」と言われてもピンときていない方は、「論証集」をまずは確認してみても良いかもしれません。
また、「論証集」は、法律試験の対策のための教材です。従って、「論証集」を出版しているのは、司法試験対策のプロである司法試験予備校です。司法試験対策のプロが作った論証のため、安心して使用することができます。
\論証集は、法学部の強い味方です/
【2024年】アガルートの論証集の使い方講座の評判|ロジックとコアキーワードをマスター【口コミ】
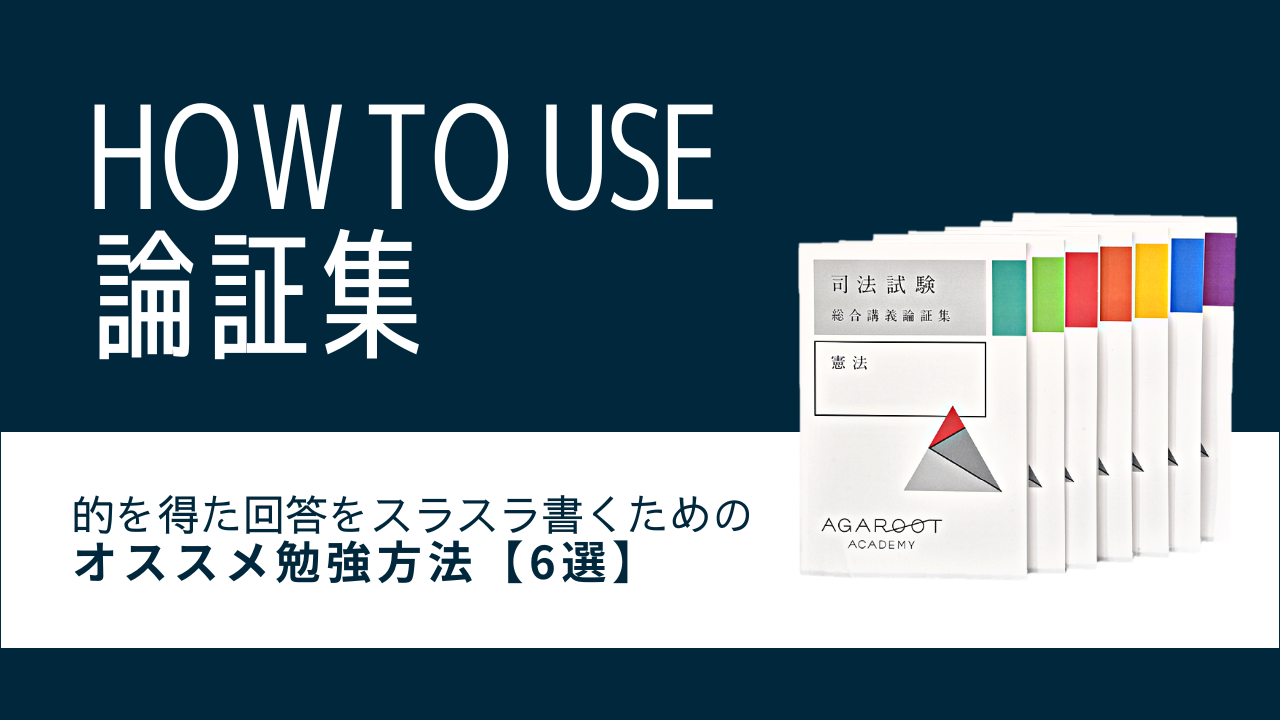
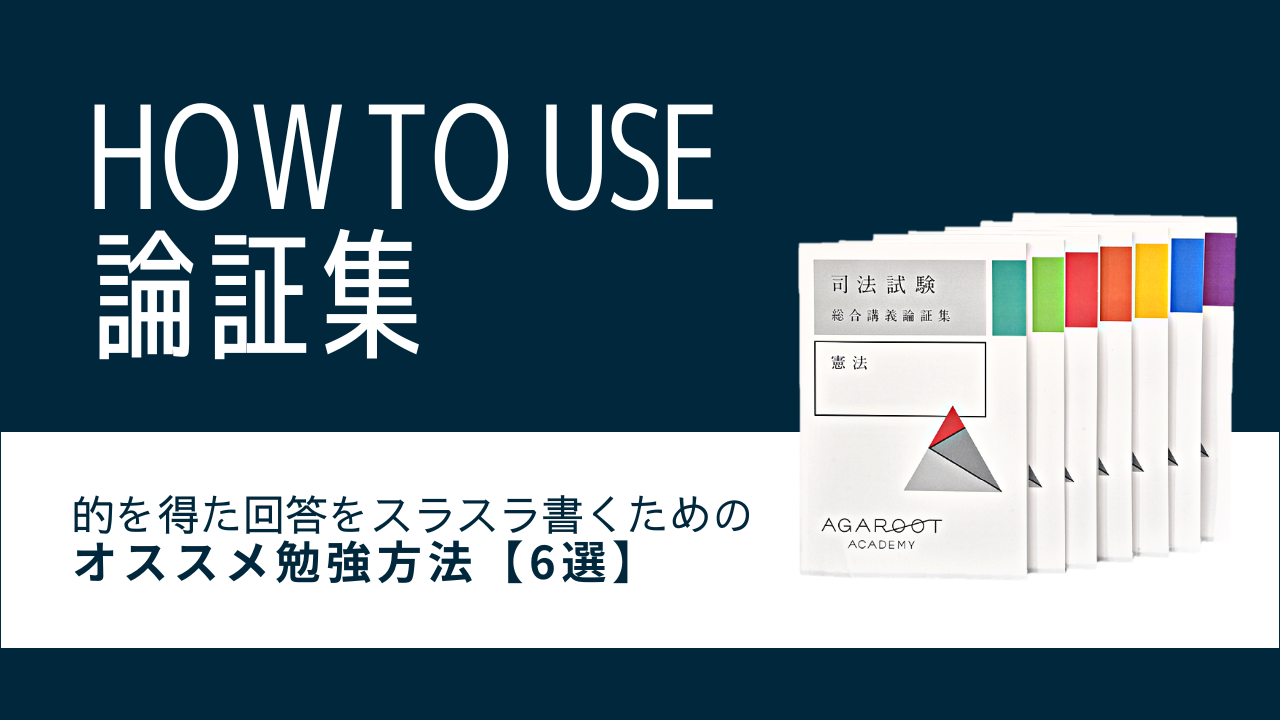
「法律の勉強法をもっと詳しく知りたい」という方は、「躓かない法律の勉強法」をご覧ください。
多くの大学では、持ち込める教材は、六法のみだと思いますが、授業によっては、指定された資料を持ち込めることがあります。
事前に持ち込めるものは何なのか確認するようにしましょう。
「六法」も、書き込みのない六法と指定されていることが多いかと思います。うっかり、書き込みのある六法を持ち込んでしまった場合、失格となってしまいますので、注意をしましょう。普段から勉強用の六法と、試験に持ち込む用の六法を分けて使っておくと良いかもしれません。
試験時間に気をつけてください。普段から、答案を作成していない方にとって、答案を作成することはかなり難しいことだと思います。
起案する時間に相当時間がかかるものと考えて、答案構成の時間に長くかけすぎないように気をつけましょう。
期末試験当日、試験が始まったら、配点と設問を必ず確認するようにしましょう。
配点の表示があるかどうかは、作問者にもよるかと重いますが、表示されていればラッキーです。配点を考慮して、検討時間や起案の時間の配分を考えましょう。
いかがでしたでしょうか。今回は、法学部の期末試験の勉強法についてご紹介させて頂きました。
法学部の場合、成績が期末試験一本で決まることも多く、期末試験の重要性は他の学部よりも高いといえます。また、論文式で問われることが多く、対策の仕方も難しく、直前に焦っている法学部生も多いかと思います。
期末試験の対策は、早く手を打つことがなによりも大切です。
本記事でご紹介した方法を実行して、期末試験を乗り換えてください。
・法学部の期末試験は、他の学部よりも長くかかる。
・真っ先に情報収集を。
・とにかく早く対策に着手する。
「期末試験対策をきっかけに本格的に法律の勉強を始めてみませんか?」
法律の勉強は、司法試験予備校を利用すると安心して勉強を始めることができます。
「司法試験予備校って高額じゃないの?」
こういうイメージを持たれている方も多いかと思いますが、最近はそんなことないですよ!
10万円未満で司法試験予備試験の本格的な講座を受講することができます。
詳細は、以下の司法試験予備校ランキングで詳しく解説していますので良かったらご覧ください。
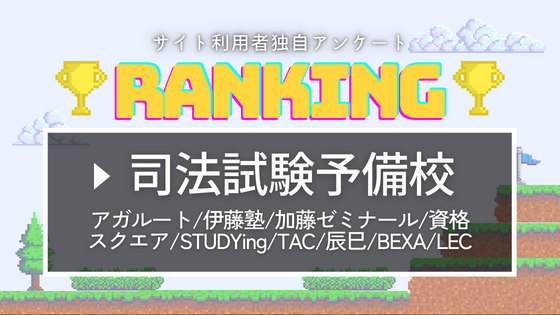
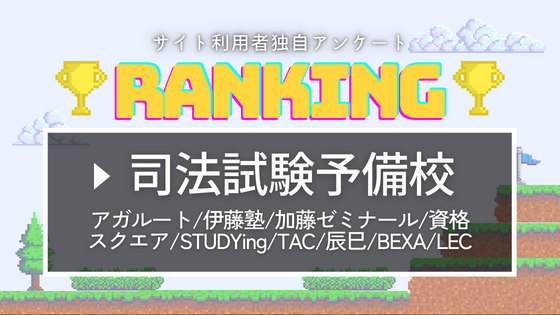
【165名が回答】司法試験予備校人気ランキング【全9校】1位はcmでお馴染みのあの予備校
【法科大学院に関心がありますか?
#ロースクールはいいぞでは、法科大学院の実体をこれから法科大学院に進学することを検討している方に向けて情報を提供するために、全国34の法科大学院の口コミを掲載しています。
法科大学院に少しでも興味・関心がある方は、ぜひ、一度、サイトに訪れくてださい!
\法科大学院の口コミ検索サイト/


最後に法学性の皆様は、大学生の間に「リーガルマインド」を身に着けてください。
リーガルマインドは、非常に希少性の高いスキルです。
法律家を目指さない方であっても、法学部に在学中にこのスキルを身に着けて、ビジネスの世界で羽ばたいてください。
リーガルマインドって?という方は、こちらの記事を一読してください。
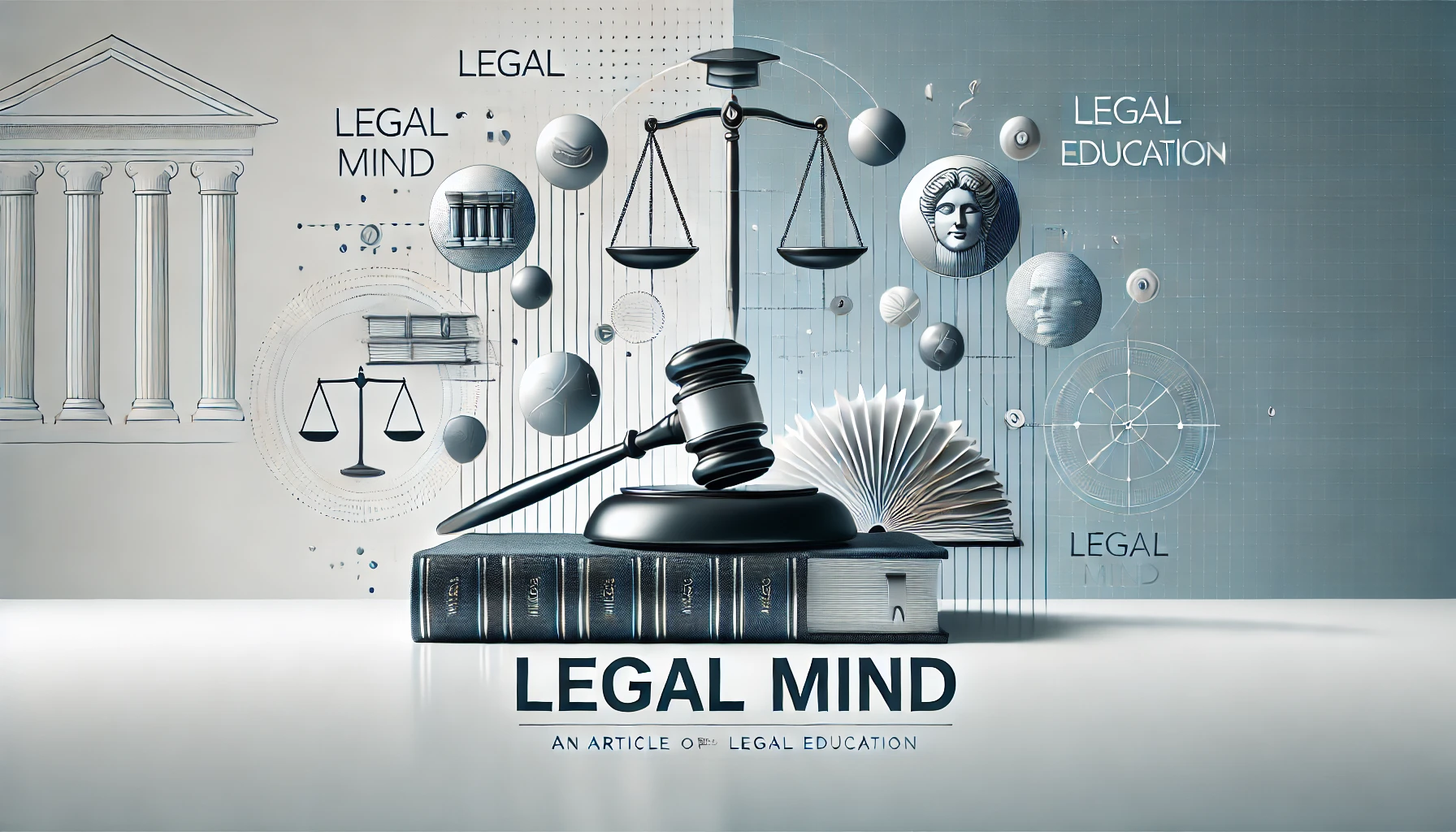
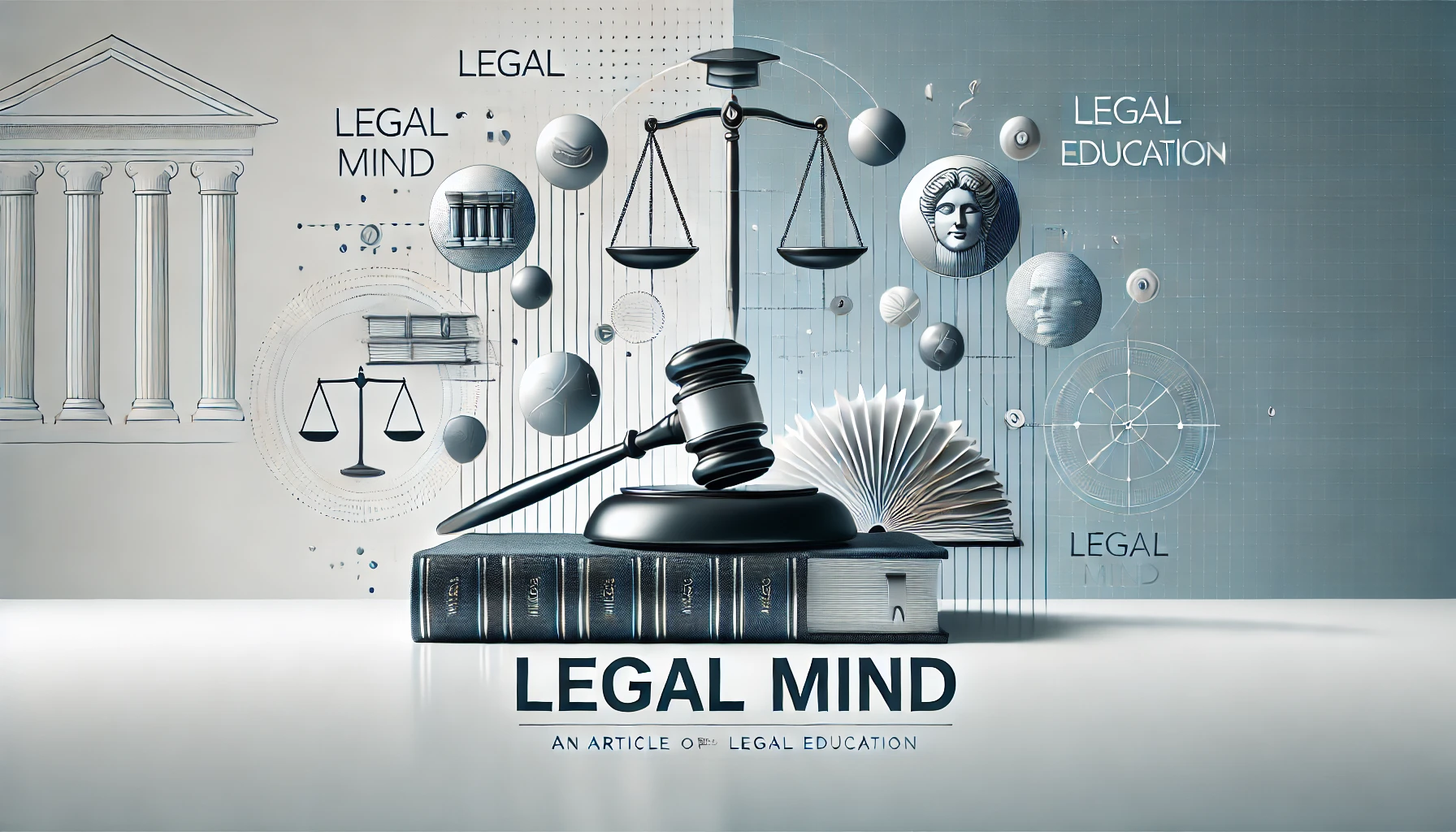
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
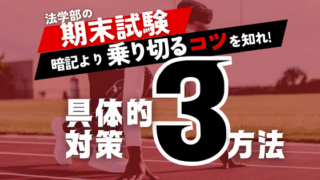
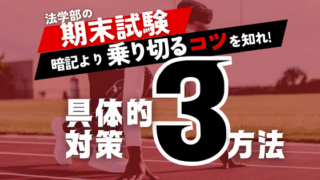
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

