
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
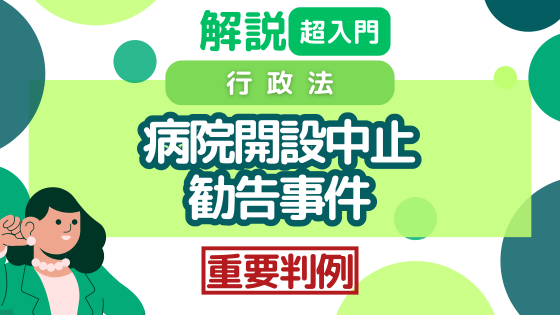
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックするこの記事では、病院開設中止勧告事件(最判平成17年7月15日)について、初学者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説していきます。
まず初めに本判決を理解するための3つのポイントと簡単な結論を以下に示しておきます。
1. 本判決はどのような事案か
原告が病院開設中止「勧告」等の取り消しを求めて訴訟を提起した事案です。
2. 本判決の論点
行政指導である「勧告」に取消訴訟の訴訟要件である処分性が認められるかが論点となります。
3. 本判決の判断
結論としては行政指導である「勧告」に処分性を認めました。



早速解説していくぞ!
では事案の説明に入りましょう。
事案説明の段階では、事案や下の図をざっと把握する程度で結構です(わからない所があっても大丈夫です)。1-3「病院開設中止勧告事件(最判平成17年7月15日)の事案の説明再び」までいったときに、「事案の全体」を理解できることができるようになると思います。
この事案を理解するためには、事案に出てくる「行政の行為の意味と性質」をしっかりと押さえておく必要があります。事案を説明しますので「行政の行為の意味と性質」について少し考えながら、読んでいただくと良いかと思います。



「行政の行為の意味と性質」だね!ここは押さえていくぞ!
病院開設中止勧告事件(最判平成17年7月15日)の事案説明
・平成9年3月6日X(原告)は、富山県高岡市内に病院を開設するために、富山県知事Y(被告)に対して、病院開設許可申請を行いました。
・これに対し、Yは高岡医療圏における病院の病床数が、富山県地域医療計画に定める必要病床数に達していることを理由に、医療法30条の7の規定に基づき、病院の開設を中止するように勧告をしました。
・Xは本権勧告を拒否して、すみやかに本件申請に対する許可をするように、Yに求ました。
・するとYは、平成9年12月16日付で、本件申請に対する開設許可処分をしました。しかしそれと同時に「中止勧告にも関わらず病院を開設した場合、保健医療機関指定申請をしても拒否処分をすることとされている」旨の通告をしました。
・これに対し、Xは本権勧告(及び本件通告)の取消訴訟を提起しました。





図を付けたので、適宜参照してくれ!
「病院開設中止勧告事件」では勧告、開設許可、保険医療機関の指定拒否、という行政の活動が出てきます。
これらの意味は、かみ砕いて言うと、次のようになります。
「病院開設中止勧告事件」で出てくる行政の活動
1.勧告→「病院の開設を辞めてもらえませんか?」というお願い
2.開設許可処分→病院を開設するために必要な「都道府県知事の許可」
3.保険医療機関指定拒否→「この病院を保険医療機関に指定してください」という申請を拒否すること
2.開設許可処分ですが、法律の要件を満たしている場合には、必ず許可をしなければならないです。ちなみに「病院開設中止勧告事件」でXは、その要件を充足していました。
3.保険医療機関指定拒否は、保険医療機関への指定がないと、保険証を利用して診察をすることができないようになっています(そんな病院には誰も行かないので、許可を受けないと事実上病院の開設不能)。ちなみに「病院開設中止勧告事件」では、保険医療機関指定の申請もその拒否処分も、実際には行われていません。あくまでも「もしこのまま手続きが進行していくとどうなるか?」という仮の話です。
次に、これらの行為の性質についてです。



いきなりですがクイズです!
いきなり!クイズ!
1.勧告
2.開設許可処分
3.保険医療機関指定拒否
上の3つの「行政の行為」のうち、「行政指導」はどれで、「行政行為」はどれでしょうか?
答えは↓↓↓↓↓
答え
1.勧告が行政指導で、2.開設許可処分と3.保険医療機関の指定拒否が行政行為です。
行政指導:1.勧告
行政行為:2.開設許可処分、3.保険医療機関の指定拒否



「そんなの当たり前だよね!」ってなる人は、1-2「行政指導と行政行為の区別」を飛ばして1-3「病院開設中止勧告事件(最判平成17年7月15日)事案の説明再び」に進んでも大丈夫だ!
以下1-2「行政指導と行政行為の区別」の章では「行政行為と行政指導」について、そして上のクイズの答えがそうなる理由について、説明します。
行政行為とは「行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接・具体的に国民の権利義務を規律する行為」などと定義されます。対して、行政指導とは「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」(行政手続法2条6号)と定義されています。
行政行為
行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接・具体的に国民の権利義務を規律する行為
行政指導
行政機関が、その任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める「指導、勧告、助言その他の行為」であって、処分に該当しないものをいう(行政手続法2条6号)
流石にこれだけだと何が何やらさっぱりわからないと思いますので、もう少しかみ砕いて両者の区別を説明しましょう。



ん~、ちょっと難しいです…
両者の区別を一言で表現すると「法効果の有無」です。
「行政行為」には、国民の権利や義務を決定する法効果があります。一方、「行政指導」にはそのような法効果はありません(このように国民の権利義務に影響を及ぼさない行為を事実行為と言います)。
行政指導と行政行為の区別のつけ方「法効果の有無」
行政行為:国民の権利や義務を決定する「法効果」がある
行政指導:上記ような「法効果」はない(国民の権利義務に影響を及ぼさない行為を事実行為と言う)
行政行為の定義の「国民の権利義務を規律する」という部分から法効果を読み取ることができます。



行政指導と行政行為って「法効果の有無」で違いがあるんだね!
では、この事案に出てくる行政の各行為は行政行為でしょうか?行政指導でしょうか?



「1.勧告、2.開設許可処分、3.保険医療機関指定拒否」はそれぞれ「行政指導と行政行為」のどちらになると思いますか?
開設許可処分と保険医療機関の指定拒否は行政行為です。申請に対する許可や拒否は国民の法的な権利を認めたり、制限したりするものなので法効果があり、典型的な行政行為と言えます。
そして勧告が、行政指導でした。勧告は法効果がなく、行政手続法2条6号でも行政指導の典型例とされていました。
「病院開設中止勧告事件」の行政の行為
1.勧告:行政指導
2.開設許可処分:行政行為
3.保険医療機関指定拒否:行政行為


ここまでで「勧告は行政指導であり、病院開設許可処分と保険医療機関指定拒否処分は行政行為である」ということが理解できたと思います。その上で再度事案を確認していきましょう。



さ、事案を再度確認して行くぞ!
今まで学んだ行為の意味や性質を踏まえると本件の事案は次のようになります。
「行為の意味や性質」を踏まえた、本件の事案の捉え方
・まずXが「病院を開設しよう」と、富山県知事Yに対して、病院開設許可の申請をしました。
・富山県知事Yは「その地域内の病床数が過剰になる」と考え、勧告(行政指導)により、病院の開設をやめるようお願いをしました。
・しかし、Xはこのお願いを突っぱねて、早く許可処分をするように求めてきました。
・富山県知事Yは、Xが許可の要件を満たしている以上、病院開設許可(行政行為)をせざるを得ません。
・そこで富山県知事Yは、許可するとともに「もし勧告に従わないまま保険医療機関の指定申請をしてきても、拒否(行政行為)されますからね(仮定の話)」という通告をしました。
・これに対し、Xは本権勧告(及び本件通告)の取消訴訟を提起しました。
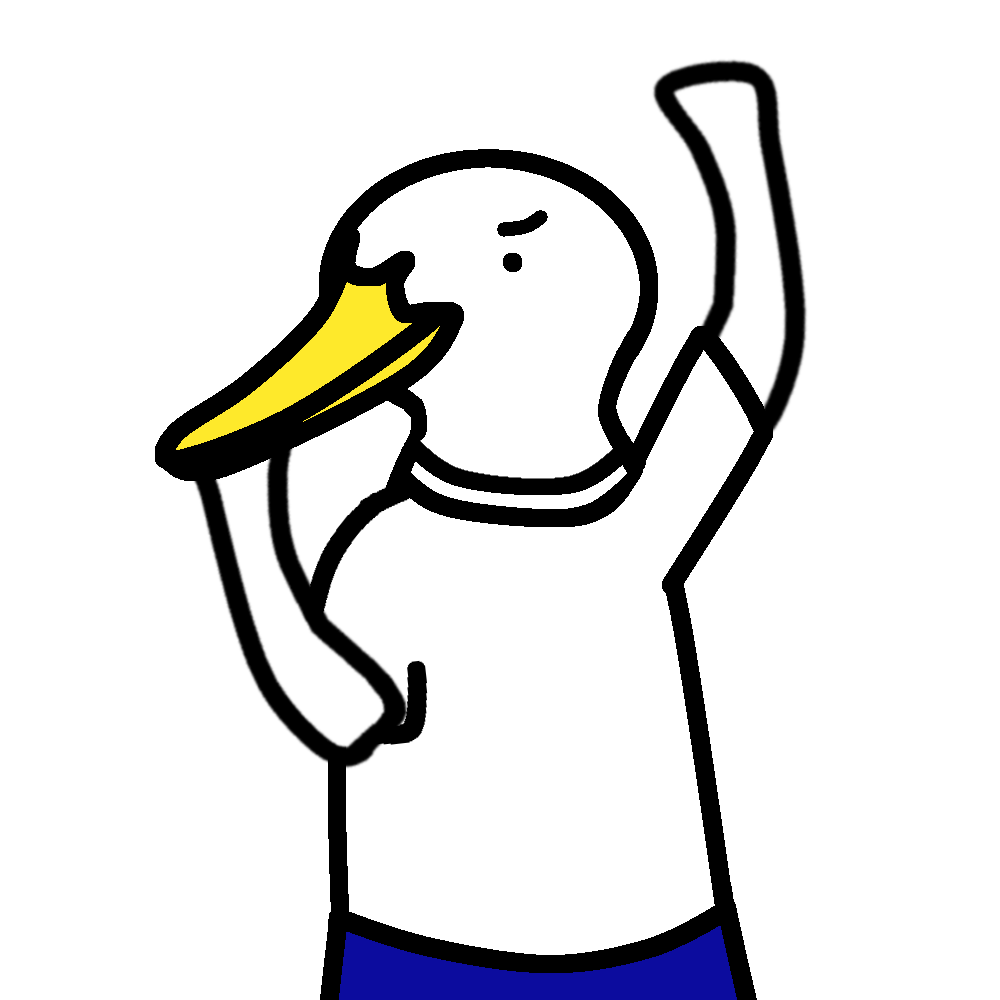
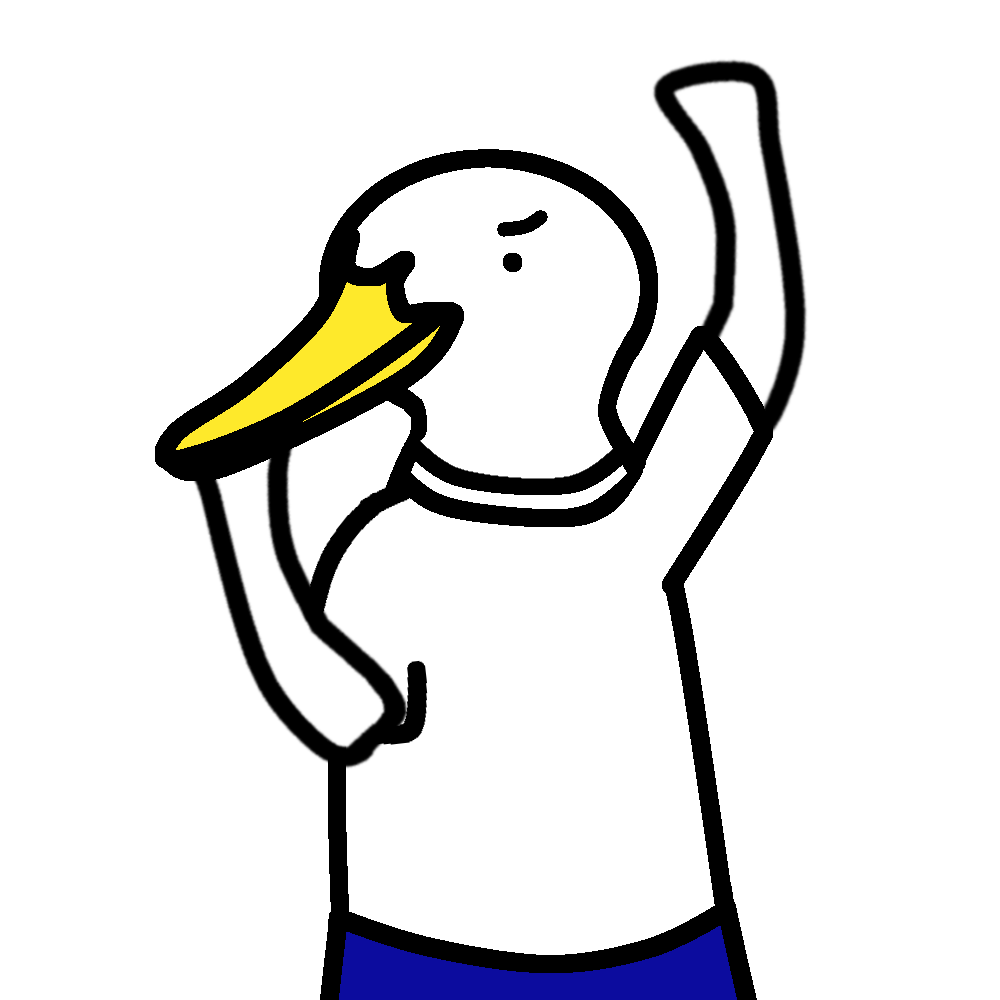
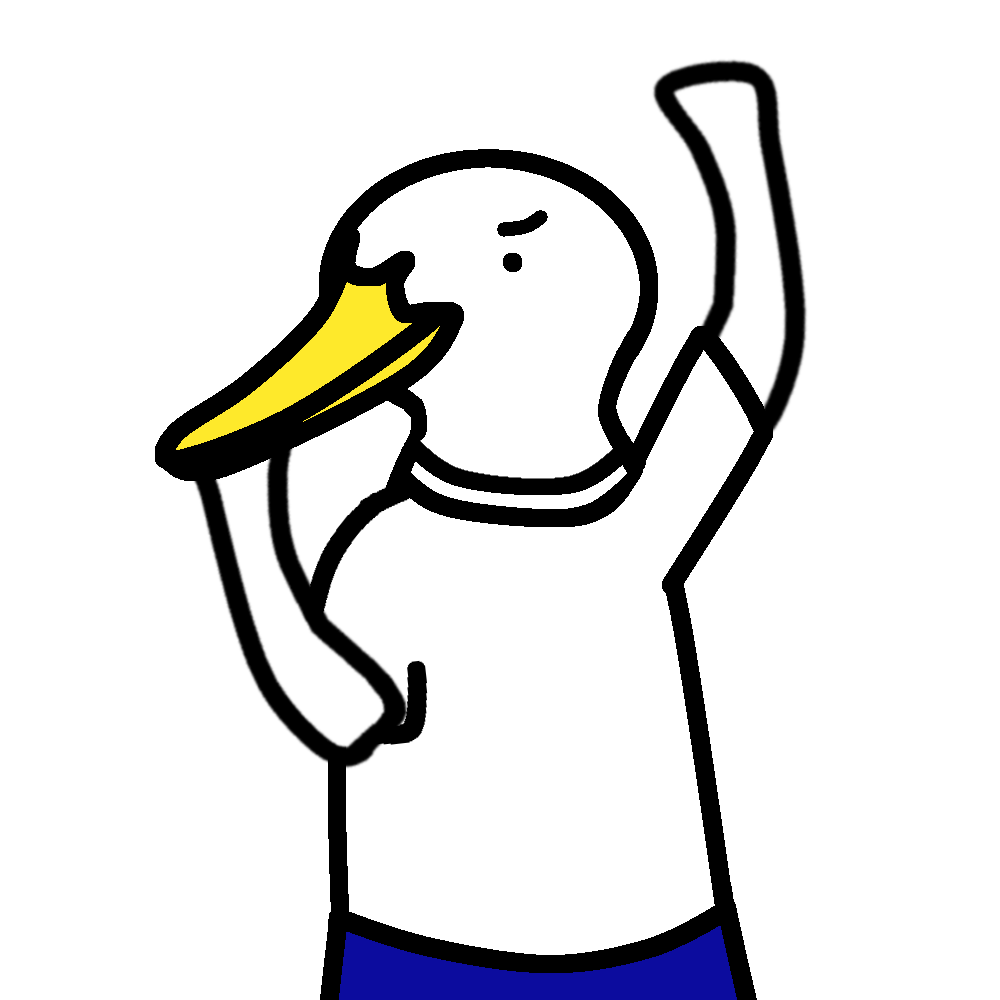
なるほど、そういうことだったんだね!
Xは「勧告」についての取消訴訟を提起しています。「取消訴訟を提起」するには、「取り消しを求める行政の活動に処分性がある」と言えなければなりません。(よくわからないという方は「土地区画整理事業」についての記事を参照してください)。
本件で、Xは勧告の取り消しを求めていますから「勧告に処分性があるか?」が論点となります。
おさらい:処分性ってなに?
処分性は「取消訴訟を適法に提起するために必要な訴訟要件」です。
処分性は「①公権力性+②直接具体的法効果性」で判断されます。





この記事の最後にも同じリンクを貼るので、「処分性」がいまいち分からない…となったらこの記事の次に読んでみてくれ!
「勧告」に処分性はあるのでしょうか?一般には「勧告のような行政指導には、処分性はない」とされています。
行政指導(勧告)には処分性はない



なぜ「行政指導(勧告)には処分性はない」と言えるんだろう?
「処分性がある」と言えるためには「①公権力性」と「②直接具体的法効果性」がともにあることが必要でしたね。
しかし、上述のように行政指導は「法効果がない事実行為」です。すると②「直接具体的法効果性」が認められず、行政指導に処分性は認められません。
普通に考えるとこうなりますね。納得した方も多いでしょう。
しかし、本判決は「勧告という行政指導に処分性を認めました」。



え!処分性を認めたんだ!
ではなぜ、本判決は「勧告という行政指導に処分性を認めた」のでしょうか?
「保険医療機関指定(以下、指定といいます)申請の拒否処分」との関係が大きいです。以下で詳しく見ていきます。
「勧告という行政指導に処分性を認めた」理由は、大きく分けて2つあります。
「勧告という行政指導に処分性を認めた」理由
①勧告が指定拒否処分と連動していたこと
②指定拒否処分の不利益が甚大であること
まず①について見ていきましょう。
指定拒否処分の要件は健康保険法43条の3第2項で「保険医療機関等トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキ」と定められていました。
そして、同項の運用として「上記の勧告に従わずに指定の申請をしてきたらこの要件に該当するとして拒否処分がなされること」となっていました。つまり、勧告に従わないと「相当程度の確実さをもって」(判例の言い回し)指定を受けられないという、両者の連動があったわけです。
つぎに②についてです。
これは、事案の説明の所でほぼ書いてしまったのですが「国民皆保険制度」が採用されている日本では、保険証を利用せずに病院を受診する人なんてほぼいません。すると、保険医療機関の指定を受けることができないと「開設自体を断念しなくてはならない」という重大な不利益が生じることになります。
ここで①も②も書いてあること自体は理解できたという人が多いと思います。しかしこう思った方もいるでしょう。
「で、勧告の法効果は?」
少し前に「勧告には法効果性がないから、原則として処分性は否定される」と書きました。
にもかかわらず、「判決は処分性を肯定したのだから、判決は何らかの理由で『勧告にも法効果があるのだ』と言ったのかな?」と考えるのは何もおかしくありません。処分性を認めるための要件としても、上述の通り「直接具体的法効果性」が要求されているのだからなおさらです。
しかし、本判決は勧告の法効果には言及していません。
この点で「従来の処分性の判断の定式」からは少し外れた判断になっているのです。
このように、従来の判断の定式から外れてまで本判決が勧告の処分性を認めたのは「実効的権利救済の観点」を考慮したからだと考えられています。



どういうこと?
ここでまた例の図をご覧ください。
今まで確認してきた通り、判例は「『②勧告』(番号は図の中のもの)が『⑦保険医療機関指定拒否処分』と連動していること」と「『⑦保険医療機関指定拒否処分』が重大な不利益をもたらすこと」を理由に②に処分性を認めました。
ここで「『⑦保険医療機関指定拒否処分』が問題なら、⑦自体を争えば済む話なのでは?」と思わないでしょうか?


しかし、現実にはそれが難しいのです。
なぜかと言うと、省令上病院開設者は『⑥保険医療機関指定申請』の前に、「施設や人員を確保しなければならない仕組み」になっています。『⑦保険医療機関指定拒否処分』が出て、はじめて争えるとすると、病院開設者としては「もう施設も人員も確保したのに、事実上開業できない」という状態になるリスクを、抱えなければならないことになります。
言い換えると「『⑦保険医療機関指定拒否処分』ではじめて争うのは、Xにとって、あまりにリスクが大きすぎて、難しい状態」でした。
このように『⑦保険医療機関指定拒否処分』の不利益が大きいのに、⑦で争うのでは、Xにとって現実的に難しい状態だったので、Xの実効的権利救済を図るために『②勧告』の段階で「処分性」を認めて、争うことを可能にしたわけです。
今回の記事では、判決の前提となる「事実関係の説明、前提知識の確認、判決の裏側にある考慮」などにフォーカスを当てて説明をしました。是非、これらを踏まえて判決文を読んでみてください。
少しでも、判決が分かりやすくなっていれば嬉しいです。
行政判例百選II〔第8版〕 別冊ジュリスト 第261号.
櫻井敬子,橋本博之(2019)『行政法[第6版]』弘文堂.
下山憲治,友岡史仁,筑紫圭一(2017)『行政法』日本評論社.
海道俊明,須田守,巽智彦,土井翼,西上治,堀澤明生(2023)『精読行政法判例』弘文堂


司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
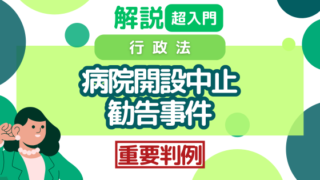
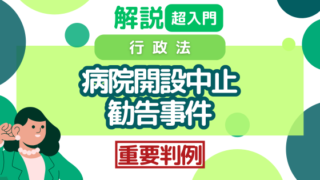
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法律記事を書いております犬橋です。現在は国立大学法科大学院に在籍しながら、行政法の判例の解説記事を主に執筆しています。令和7年司法試験合格者。
初学者の方にもわかりやすく、興味を持ってもらえるような記事を書くことを目指しています。
















勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

