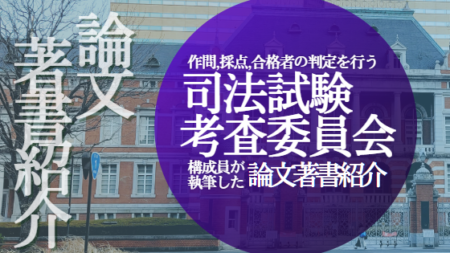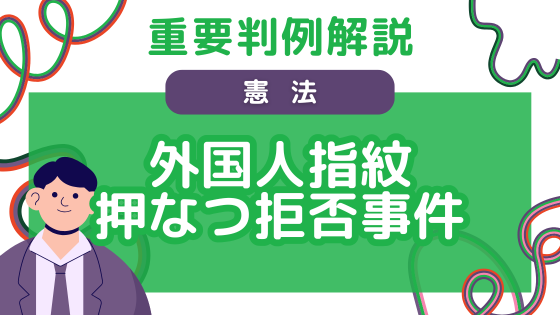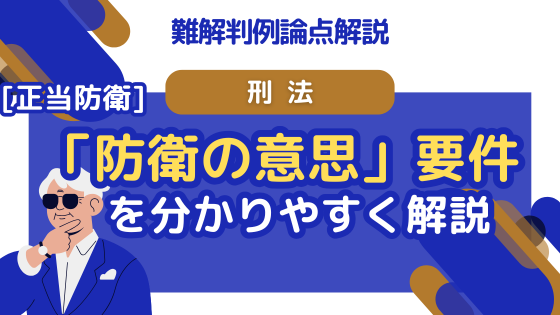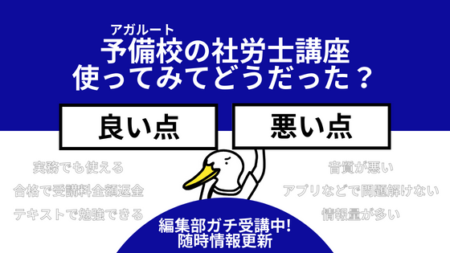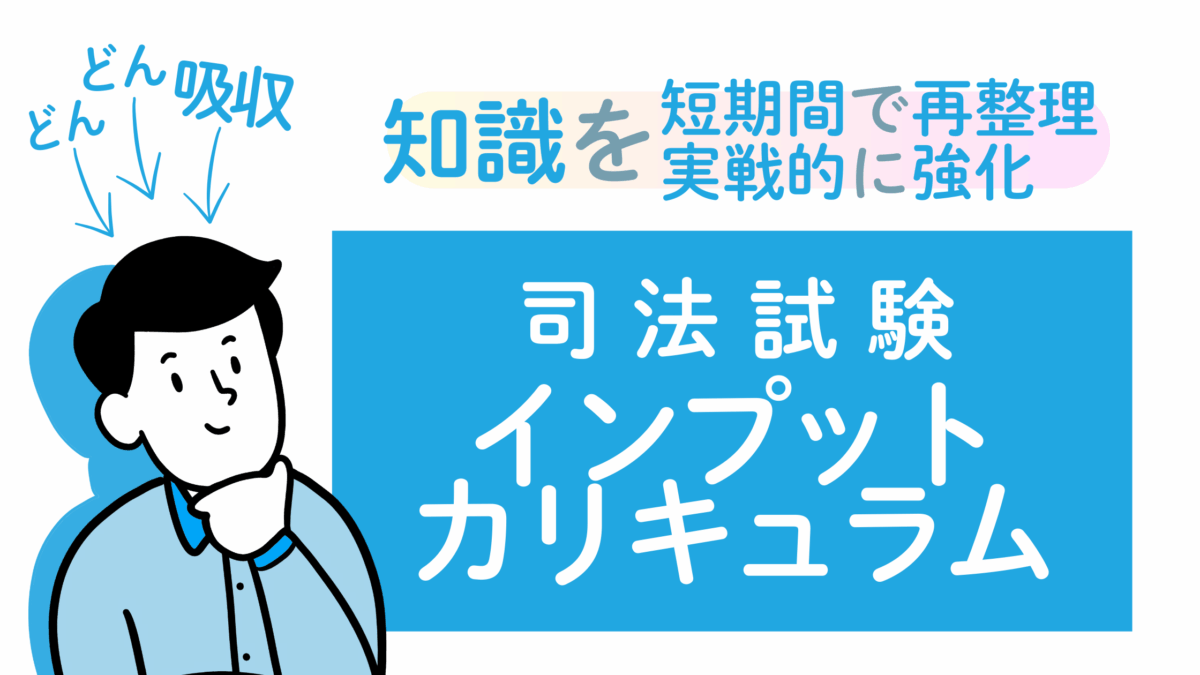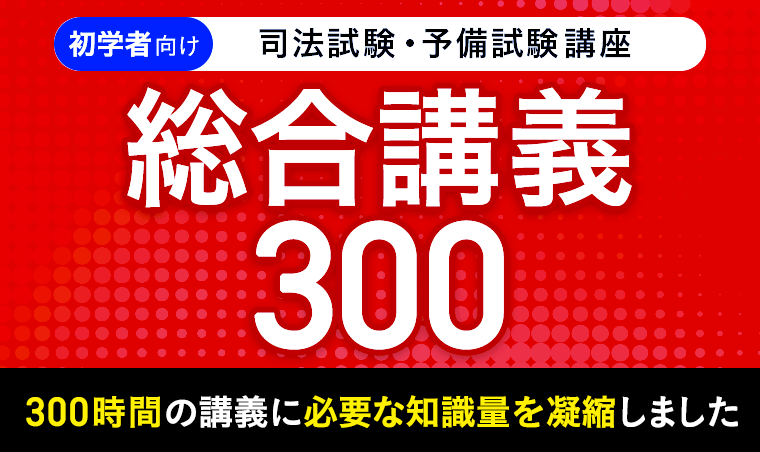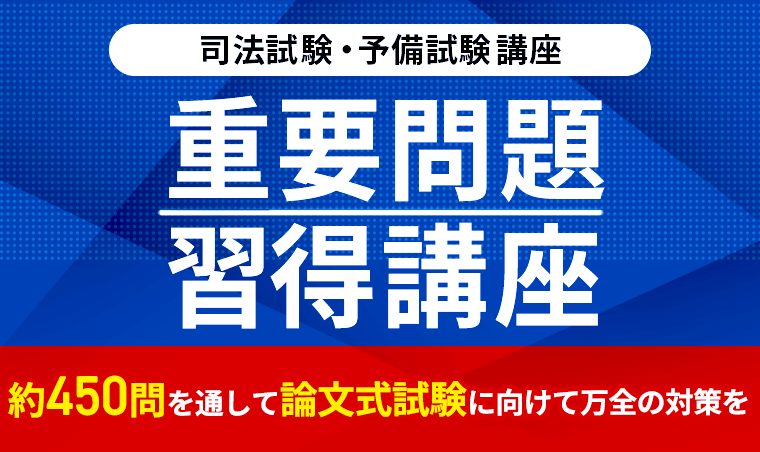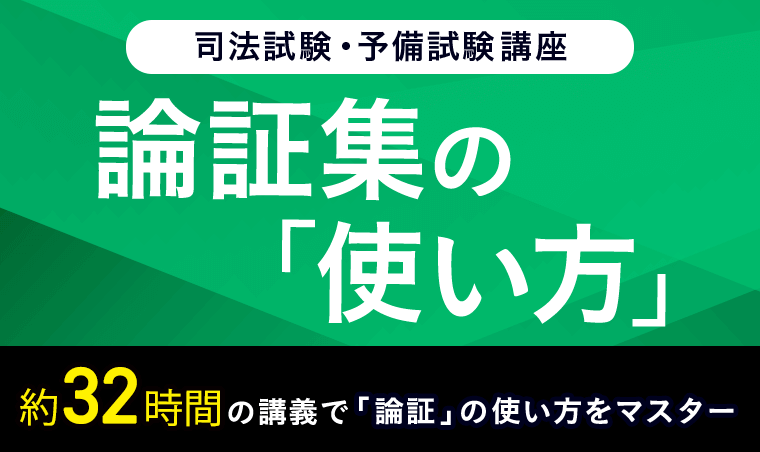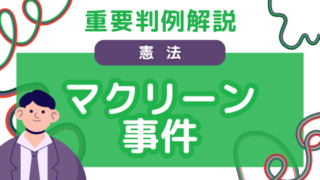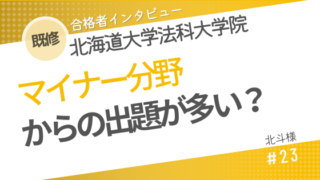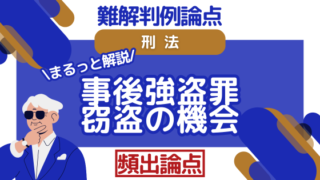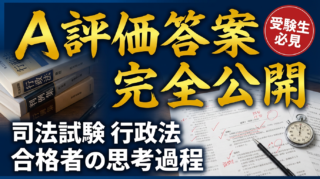マクリーン事件をどこよりも分かりやすく解説
当ページのリンクにはPRが含まれています。
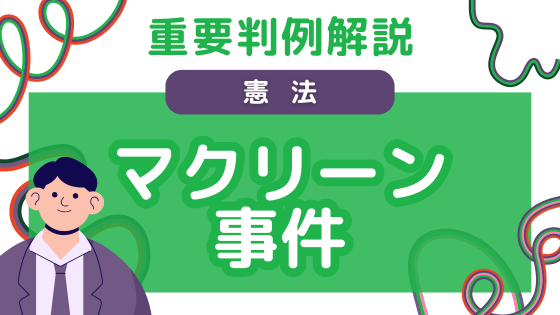
「外国人の人権ってどこまで認められるの?」
「在留資格の更新が政治活動のせいでダメになるって、不公平じゃない?」
「マクリーン事件のポイントは?どこが試験に出る?」
マクリーン事件(最大判昭53.10.4)は、外国人の「人権享有主体性、入国の自由、政治活動の自由」が問題になった判例です。
特に、外国人の人権についての、基本的な考え方を示した判例として知られているため、しっかり押さえましょう。
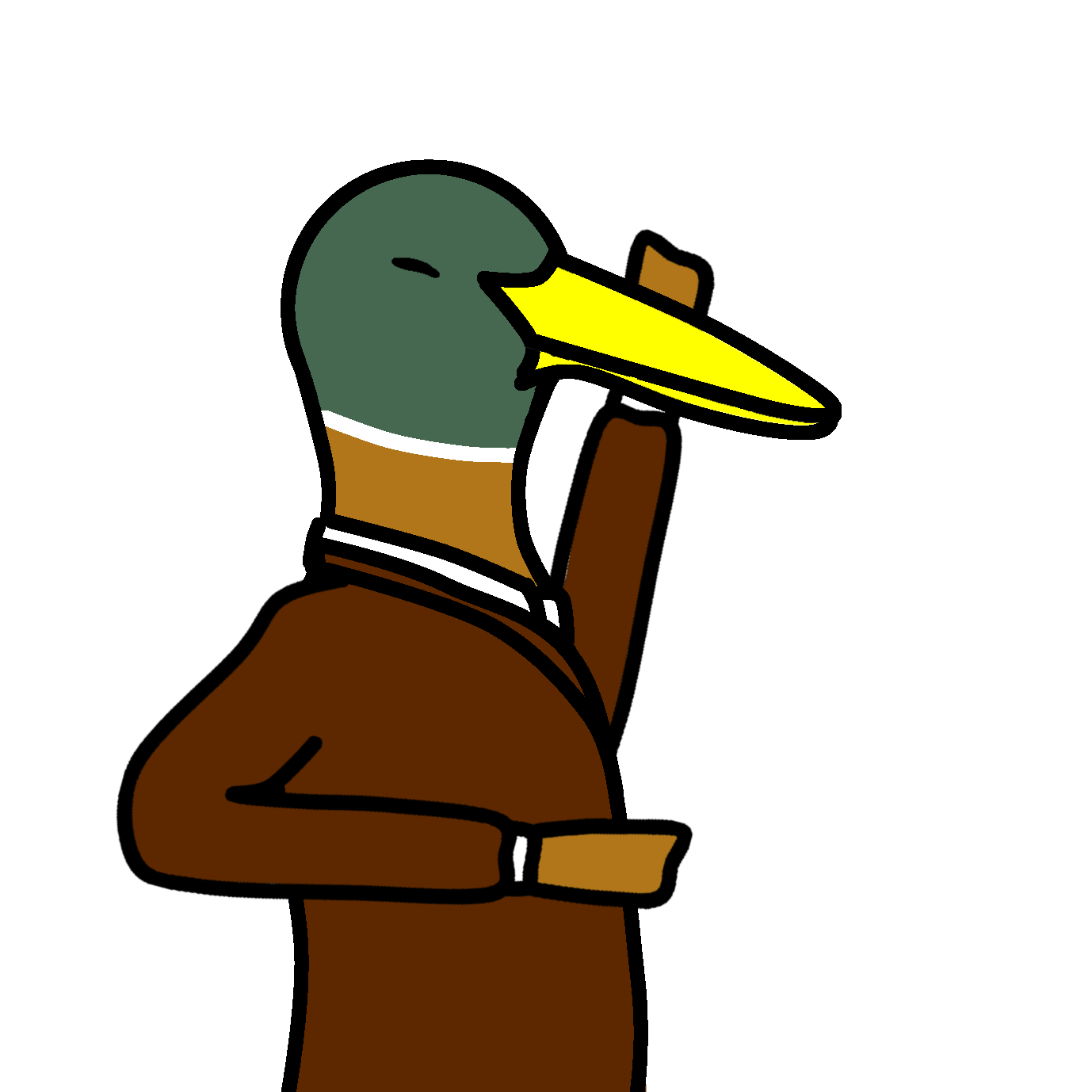
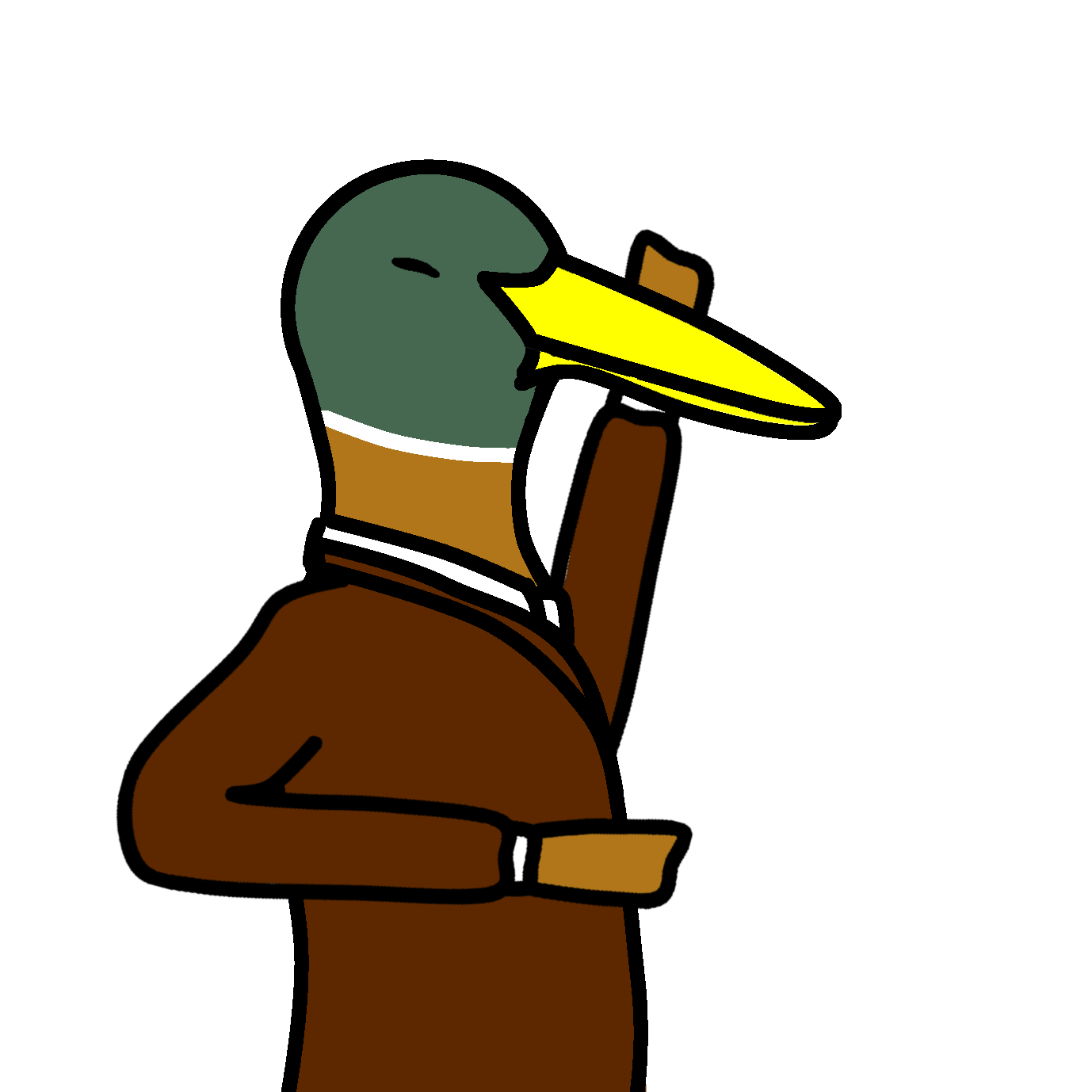
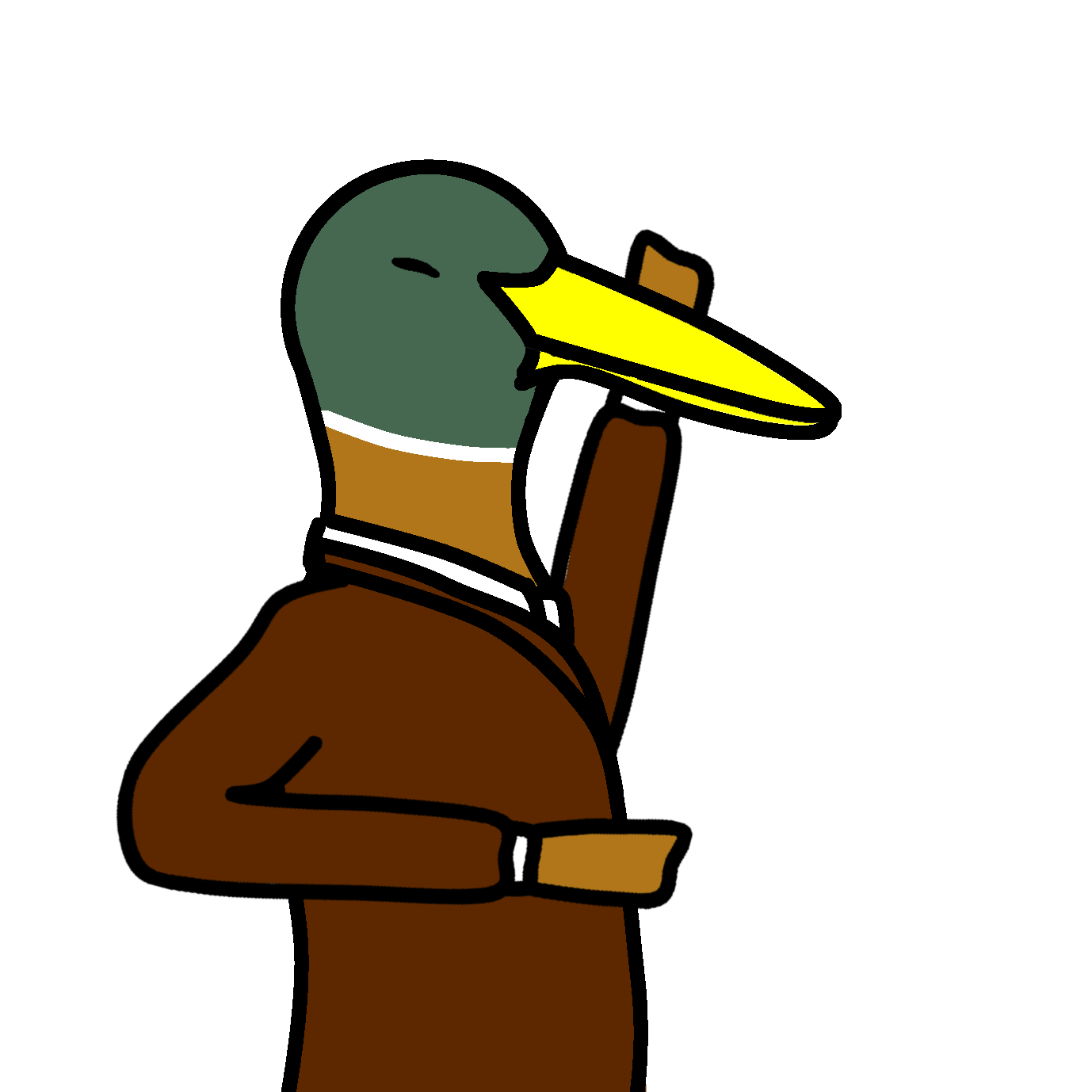
解説を始めるぞ!
目次
マクリーン事件の概要
マクリーン事件の概要は以下です。
概要:マクリーン事件
アメリカ国籍を持つXは、語学学校の英語教師として1年間の在留許可を得て、来日しました。
Xは、英語教師としての仕事を続けるために、法務大臣に対して、在留許可の更新を申請したところ、法務大臣は更新を許可しない処分を下しました。
法務大臣が「Xの在留許可の更新を不許可」としたのは、次の理由によります。
Xの在留許可の更新を不許可とした理由
・Xが在留期間中に無届転職していた
(当初の語学学校を17日間で退職して、別の語学学校で働いていた)
・外国人ベ平連に所属して、アメリカによるベトナム戦争介入反対、日米安保条約反対、出入国管理法案反対等を呼びかける政治活動に参加していた
(ベ平連=ベトナムに平和を!市民文化団体連合)
これに対して、Xは、不許可処分の取り消しを求めて、訴えを提起しました。
第一審
第一審は、在留許可について法務大臣が「相当広汎な裁量権を有している」と認めつつも、「この裁量権も憲法その他の法令上、一定の制限に服するのは当然」としました。
その上で、上記の理由で不許可処分をすることは、「社会観念上著しく妥当性を欠く」として、不許可処分を取り消しました。
第二審
第二審では、当時の条文について、法務大臣は更新申請があった場合、更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合のみ許可するものであると解釈しました。
そして、その判断は、法務大臣の自由な裁量に任せられており、法務大臣が高度の政治的配慮から、在留期間中に行った適法な政治的活動を消極の事由として判断したとしても違法ではない。として、第一審判決を取り消しました。
これに対して、Xが上告したのが本件です。
マクリーン事件の憲法上の論点
マクリーン事件の憲法上の論点は大きく3つに分けられます。
憲法上の論点
論点① 外国人の人権享有主体性
論点② 外国人の入国の自由
論点③ 外国人の政治活動の自由



それぞれの論点について、最高裁はどのように考えたのかを、確認していきましょう!
論点① 外国人の人権享有主体性
初めに「外国人の人権享有主体性」とは何か?について整理していきます。
「外国人の人権享有主体性」とは?
日本国憲法第11条では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」と定めています。
憲法第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
国民であれば、誰しも基本的人権を有するという当然の規定ですが、この条文は「国民」が主語になっています。そのため、外国人には基本的人権が認められないのかという問題が生じます。
この点については、次の2つの学説があります。
外国人には基本的人権が認められないのかという問題についての学説
・文言説
・性質説
「文言説」は「憲法の条文を忠実に読もうとする説」です。
主語が「国民」となっている条文は、国民のみに認められる。一方「何人も」という文言が使われている条文は、外国人にも保障されると解する説です。この説に対しては、憲法は「国民」と「何人も」を厳格に区別して規定されているわけではないという批判があります。また、憲法22条2項では、「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」とあるため、外国人に国籍離脱の自由を認めてしまうという背理が生じるという批判があります。
そこで登場したのが「性質説」という考え方です。
権利の性質上、日本国民のみに認められている基本的人権を除き、日本に在留する外国人にも等しく及ぶとする説です。
マクリーン事件では、「文言説」と「性質説」のどちらを採るのかについての最高裁の考え方が示されました。
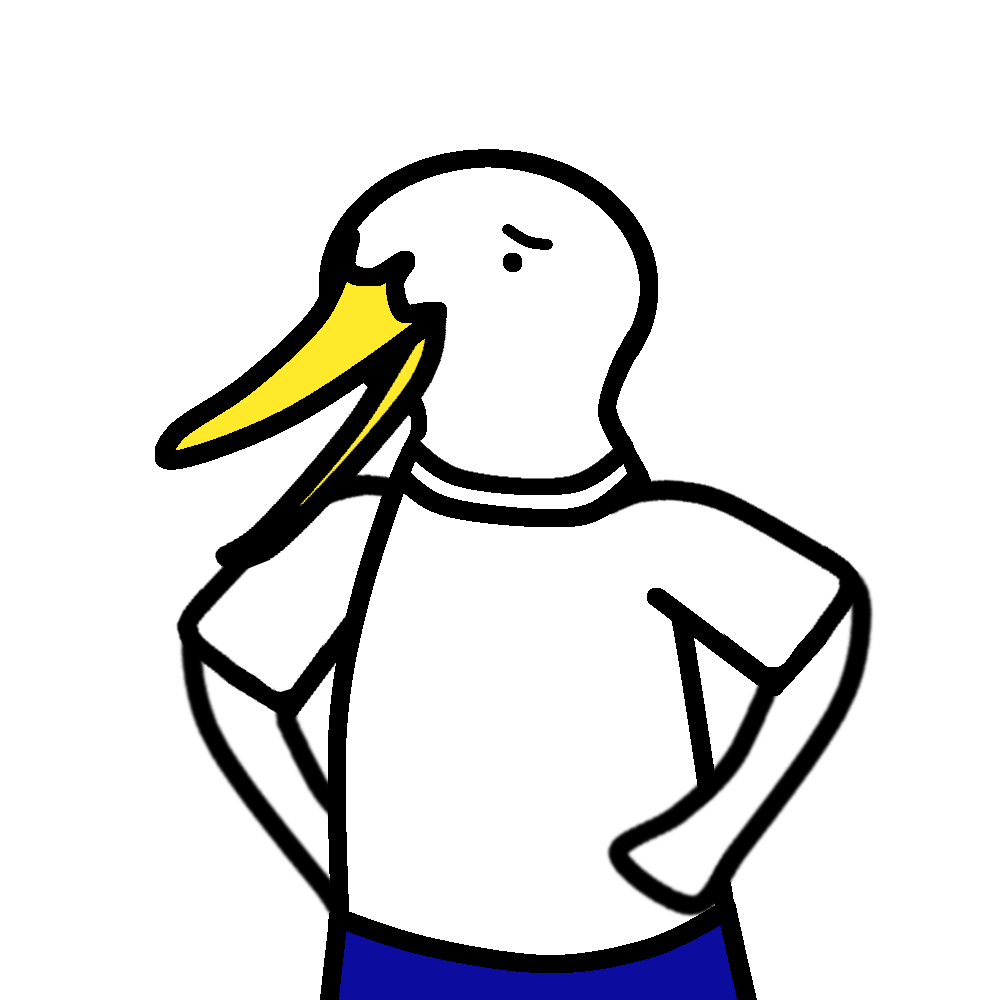
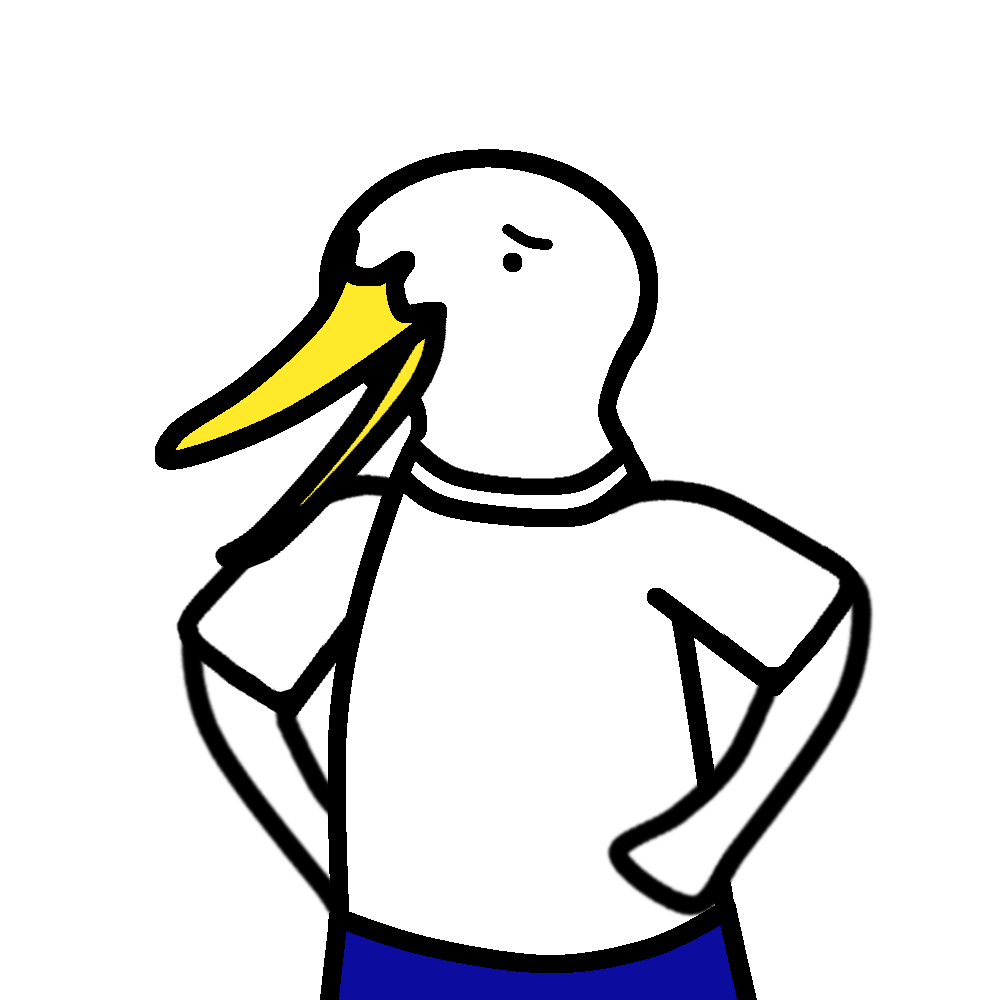
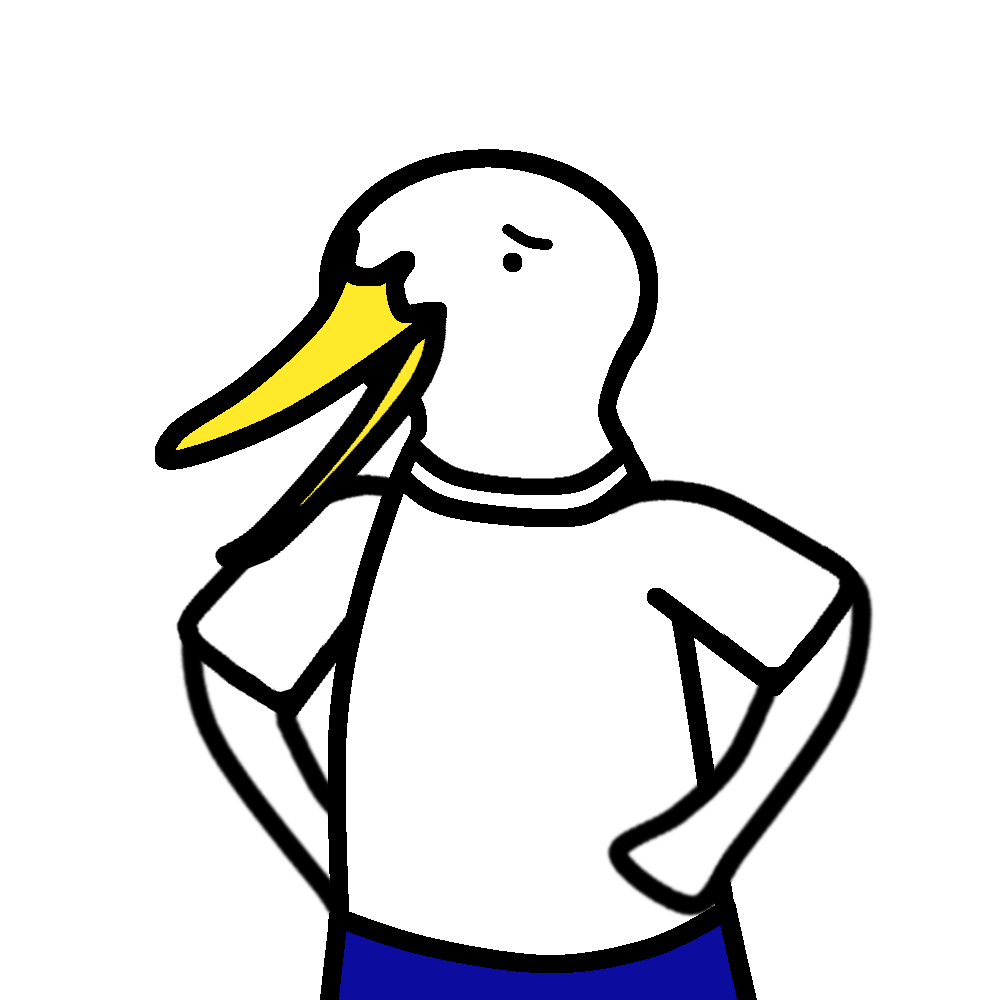
「文言説」と「性質説」のどっちを採ったんだろう?
「外国人の人権享有主体性」についての最高裁の考え方


マクリーン事件の最高裁判決では「外国人の人権享有主体性」について、次のように述べています。
最高裁の考え方:「外国人の人権享有主体性」について
「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」である。
つまり、最高裁は、「性質説」の立場を採ることを明言しました。



「性質説」は権利の性質上、日本国民のみに認められている基本的人権を除き、日本に在留する外国人にも等しく及ぶとする説だね!
論点② 外国人の入国の自由
憲法22条1項には、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と定められています。
憲法22条1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
この規定による「居住、移転の自由」は外国人にも保障されると解することができるわけですが、言い換えれば、外国人が日本に入国する自由も、この規定により保障されていると解することもできるわけです。
では、そのように解釈できるのでしょうか?



外国人が日本に入国する自由も、保障されるのかな?
「外国人の入国の自由」についての最高裁の考え方
最高裁は、次のように述べています。最高裁の考え方は、試験に出る重要ポイントです。
最高裁の考え方:「外国人の入国の自由」について
・憲法22条1項は、日本国内における、居住・移転の自由を保障するだけの規定である。
・外国人が日本に入国することについては、なんら規定していない。
・国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負っておらず、特別の条約がない限り、外国人の入国を認めるか否かは、国家が自由に決定することができる。
よって、憲法上「外国人は、日本に入国する自由を保障されていない」となり、憲法22条1項を根拠に、「外国人が入国の自由を主張することはできないし、在留の権利や、引き続き在留できる権利を主張する根拠にもならない」ということです。



外国人が入国の自由を主張することはできないし、在留の権利や、引き続き在留できる権利を主張する根拠にならないんだ!
論点③ 外国人の政治活動の自由
「政治活動を行う自由」は基本的人権の一つとして、日本国民には認められていますが、外国人が日本国内で政治活動を行う自由は保障されているのでしょうか?



政治活動の自由は保障されるのかな?
「外国人の政治活動の自由」についての最高裁の考え方
最高裁は「外国人の人権享有主体性」について、「性質説」を採用したうえで、「政治活動の自由」についても、次のように述べています。
最高裁の考え方:「外国人の政治活動の自由」について
「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」
つまり、外国人にも「政治活動の自由」が認められるということです。



政治活動の自由が認められるんだね!
在留資格更新時に政治活動を斟酌してよいのか?
外国人にも「政治活動の自由」が認められるならば、「在留資格更新時に、在留期間中に政治活動を行っていた点について、斟酌すべきではない」と考えられそうです。
在留期間中の政治活動が、在留資格更新時に斟酌されるとすれば、萎縮的効果をもたらし、実質的に外国人に政治活動の自由を保障していないのと同じになるからです。
その点、最高裁は次のように判断しています。
最高裁の考え方:在留資格更新時に政治活動を斟酌してよいのか?
・外国人に対する憲法の基本的人権の保障は「外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない」としています。
・「在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為(政治活動)を在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことの保障は与えられていない」と判断しました。
この判断に対しては「学説上は、萎縮的効果をもたらす」として強い批判があります。
法務大臣の裁量権について(行政法の論点)


マクリーン事件では「法務大臣は行政裁量を行った結果、Xの在留資格更新を不許可」としています。では、法務大臣の裁量権はどの程度認められているのでしょうか?
最高裁は、次のように述べています。
最高裁の考え方:法務大臣の裁量権はどの程度認められているのか?
法務大臣が在留期間の更新の許否を決める際は、「外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立つて、申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしやくし、時宜に応じた的確な判断をしなければならない」としています。
最高裁は、「政治的裁量」が認められるとの判断を示しました。
そのためには、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せ、「その裁量権の範囲を広汎なもの」とする必要があるとしています。このように法務大臣に「政治的裁量」が認められるにしても、裁判所の審査が及ばないわけではありません。
裁判所が「法務大臣の判断が違法かどうか?」の判断は以下のように行われています。
「その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により、その判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等によりその判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうか」について審理し、それが認められる場合に限り、法務大臣の判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法とする
最高裁の結論
最高裁は、以下の結論を出しています。
Xが、日本の国益に反する内容の政治活動に加わっていた点を鑑みて、法務大臣がXを将来日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者と判断し、Xの在留資格更新申請を不許可としたことは、違法とは言えない
そのため「Xの上告を棄却する」との判決を下しました。
判決文を読んでみよう!
「一 本件の経過
(一) 本件につき原審が確定した事実関係の要旨は、次のとおりである。
(1) 上告人は、アメリカ合衆国国籍を有する外国人であるが、昭和四四年四月二一日その所持する旅券に在韓国日本大使館発行の査証を受けたうえで本邦に入国し、同年五月一〇日下関入国管理事務所入国審査官から出入国管理令四条一項一六号、特定の在留資格及びその在留期間を定める省令一項三号に該当する者としての在留資格をもつて在留期間を一年とする上陸許可の証印を受けて本邦に上陸した。
(2) 上告人は、昭和四五年五月一日一年間の在留期間の更新を申請したところ、被上告人は、同年八月一〇日「出国準備期間として同年五月一〇日から同年九月七日まで一二〇日間の在留期間更新を許可する。」との処分をした。そこで、上告人は、更に、同年八月二七日被上告人に対し、同年九月八日から一年間の在留期間の更新を申請したところ、被上告人は、同年九月五日付で、上告人に対し、右更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるものとはいえないとして右更新を許可しないとの処分(以下「本件処分」という。)をした。
(3) 被上告人が在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるものとはいえないとしたのは、次のような上告人の在留期間中の無届転職と政治活動のゆえであつた。
(ア) 上告人は、ベルリツツ語学学校に英語教師として雇用されるため在留資格を認められたのに、入国後わずか一七日間で同校を退職し、財団法人英語教育協議会に英語教師として就職し、入国を認められた学校における英語教育に従事しなかつた。
(イ) 上告人は、外国人ベ平連(昭和四四年六月在日外国人数人によつてアメリカのベトナム戦争介入反対、日米安保条約によるアメリカの極東政策への加担反対、在日外国人の政治活動を抑圧する出入国管理法案反対の三つの目的のために結成された団体であるが、いわゆるべ平連からは独立しており、また、会員制度をとつていない。)に所属し、昭和四四年六月から一二月までの間九回にわたりその定例集会に参加し、七月一〇日左派華僑青年等が同月二日より一三日まで国鉄新宿駅西口付近において行つた出入国管理法案粉砕ハンガーストライキを支援するため、その目的等を印刷したビラを通行人に配布し、九月六日と一〇月四日ベ平連定例集会に参加し、同月一五、一六日ベトナム反戦モラトリアムデー運動に参加して米国大使館にベトナム戦争に反対する目的で抗議に赴き、一二月七日横浜入国者収容所に対する抗議を目的とする示威行進に参加し、翌四五年二月一五日朝霞市における反戦放送集会に参加し、三月一日同市の米軍基地キヤンプドレイク付近における反戦示威行進に参加し、同月一五日ベ平連とともに同市における「大泉市民の集い」という集会に参加して反戦ビラを配布し、五月一五日米軍のカンボジア侵入に反対する目的で米国大使館に抗議のため赴き、同月一六日五・一六ベトナムモラトリアムデー連帯日米人民集会に参加してカンボジア介入反対米国反戦示威行進に参加し、六月一四日代々木公園で行われた安保粉砕労学市民大統一行動集会に参加し、七月四日清水谷公園で行われた東京動員委員会主催の米日人民連帯、米日反戦兵士支援のための集会に参加し、同月七日には羽田空港においてロジヤース国務長官来日反対運動を行うなどの政治的活動を行つた。なお、上告人が参加した集会、集団示威行進等は、いずれも、平和的かつ合法的行動の域を出ていないものであり、上告人の参加の態様は、指導的又は積極的なものではなかつた。
(二) 原審は、自国内に外国人を受け入れるかどうかは基本的にはその国の自由であり、在留期間の更新の申請に対し更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかは、法務大臣の自由な裁量による判断に任されているものであるとし、前記の上告人の一連の政治活動は、在留期間内は外国人にも許される表現の自由の範囲内にあるものとして格別不利益を強制されるものではないが、法務大臣が、在留期間の更新の許否を決するについてこれを日本国及び日本国民にとつて望ましいものではないとし、更新を適当と認めるに足りる相当な理由がないと判断したとしても、それが何ぴとの目からみても妥当でないことが明らかであるとすべき事情のない本件にあつては、法務大臣に任された裁量の範囲内におけるものというべきであり、これをもつて本件処分を違法であるとすることはできない、と判断した。
(三) 論旨は、要するに、(1) 自国内に外国人を受け入れるかどうかはその国の自由であり、在留期間の更新の申請に対し更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるかどうかは法務大臣の自由な裁量による判断に任されているものであるとした原判決は、憲法二二条一項、出入国管理令二一条の解釈適用を誤り、理由不備の違法がある、(2) 本件処分のような裁量処分に対する原審の審査の態度、方法には、判例違反、審理不尽、理由不備の違法があり、行政事件訴訟法三〇条の解釈の誤りがある、(3) 被上告人の本件処分は、裁量権の範囲を逸脱したものであり、憲法の保障を受ける上告人のいわゆる政治活動を理由として外国人に不利益を課するものであつて、本件処分を違法でないとした原判決は、経験則に違背する認定をし、理由不備の違法を犯し、出入国管理令二一条の解釈適用を誤り、憲法一四条、一六条、一九条、二一条に違反するものである、と主張することに帰するものと解される。
二 当裁判所の判断
(一) 憲法二二条一項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくするものと解される(最高裁昭和二九年(あ)第三五九四号同三二年六月一九日大法廷判決・刑集一一巻六号一六六三頁参照)。したがつて、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。
そして、上述の憲法の趣旨を前提として、法律としての効力を有する出入国管理令は、外国人に対し、一定の期間を限り(四条一項一号、二号、一四号の場合を除く。)特定の資格によりわが国への上陸を許すこととしているものであるから、上陸を許された外国人は、その在留期間が経過した場合には当然わが国から退去しなければならない。もつとも、出入国管理令は、当該外国人が在留期間の延長を希望するときには在留期間の更新を申請することができることとしているが(二一条一項、二項)、その申請に対しては法務大臣が「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができるものと定めている(同条三項)のであるから、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは、明らかである。
右のように出入国管理令が原則として一定の期間を限つて外国人のわが国への上陸及び在留を許しその期間の更新は法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可することとしているのは、法務大臣に一定の期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させようとする趣旨に出たものであり、そして、在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨からであると解される。すなわち、法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたつては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立つて、申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしやくし、時宜に応じた的確な判断をしなければならないのであるが、このような判断は、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければとうてい適切な結果を期待することができないものと考えられる。このような点にかんがみると、出入国管理令二一条三項所定の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかの判断における法務大臣の裁量権の範囲が広汎なものとされているのは当然のことであつて、所論のように上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることは許されないと解すべきものではない。
(二) ところで、行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めることがあつても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなのであるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない。処分が違法となるのは、それが法の認める裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限られるのであり、また、その場合に限り裁判所は当該処分を取り消すことができるものであつて、行政事件訴訟法三〇条の規定はこの理を明らかにしたものにほかならない。もつとも、法が処分を行政庁の裁量に任せる趣旨、目的、範囲は各種の処分によつて一様ではなく、これに応じて裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法とされる場合もそれぞれ異なるものであり、各種の処分ごとにこれを検討しなければならないが、これを出入国管理令二一条三項に基づく法務大臣の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかの判断の場合についてみれば、右判断に関する前述の法務大臣の裁量権の性質にかんがみ、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法となるものというべきである。したがつて、
裁判所は、法務大臣の右判断についてそれが違法となるかどうかを審理、判断するにあたつては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法であるとすることができるものと解するのが、相当である。
なお、所論引用の当裁判所昭和三七年(オ)第七五二号同四四年七月一一日第二小法廷判決(民集二三巻八号一四七〇頁)は、事案を異にし本件に適切なものではなく、その余の判例は、右判示するところとその趣旨を異にするものではない。
(三) 以上の見地に立つて被上告人の本件処分の適否について検討する。
前記の事実によれば、上告人の在留期間更新申請に対し被上告人が更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるものとはいえないとしてこれを許可しなかつたのは、上告人の在留期間中の無届転職と政治活動のゆえであつたというのであり、原判決の趣旨に徴すると、なかでも政治活動が重視されたものと解される。
思うに、憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。
しかしながら、前述のように、外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねられ、わが国に在留する外国人は、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求することができる権利を保障されているものではなく、ただ、出入国管理令上法務大臣がその裁量により更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断する場合に限り在留期間の更新を受けることができる地位を与えられているにすぎないものであり、したがつて、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であつて、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしやくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。
在留中の外国人の行為が合憲合法な場合でも、法務大臣がその行為を当不当の面から日本国にとつて好ましいものとはいえないと評価し、また、右行為から将来当該外国人が日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者であると推認することは、右行為が上記のような意味において憲法の保障を受けるものであるからといつてなんら妨げられるものではない。
前述の上告人の在留期間中のいわゆる政治活動は、その行動の態様などからみて直ちに憲法の保障が及ばない政治活動であるとはいえない。しかしながら、上告人の右活動のなかには、わが国の出入国管理政策に対する非難行動、あるいはアメリカ合衆国の極東政策ひいては日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に対する抗議行動のようにわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものも含まれており、被上告人が、当時の内外の情勢にかんがみ、上告人の右活動を日本国にとつて好ましいものではないと評価し、また、上告人の右活動から同人を将来日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者と認めて、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、その事実の評価が明白に合理性を欠き、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず、他に被上告人の判断につき裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたことをうかがわせるに足りる事情の存在が確定されていない本件においては、被上告人の本件処分を違法であると判断することはできないものといわなければならない。
また、被上告人が前述の上告人の政治活動をしんしやくして在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないとし本件処分をしたことによつて、なんら所論の違憲の問題は生じないというべきである。
(四) 以上述べたところと同旨に帰する原審の判断は、正当であつて、所論引用の各判例にもなんら違反するものではなく、原判決に所論の違憲、違法はない。論旨は、上述したところと異なる見解に基づいて原判決を非難するものであつて、採用することができない。」
まとめ
マクリーン事件の憲法上の論点は次のとおりです。
・外国人の人権享有主体性…性質説の立場を採用。
・外国人の入国の自由…認めていない。
・外国人の政治活動の自由…認められる。ただし、在留期間の更新時に斟酌されない保障はない。
外国人の人権に関する大変重要な判例なのでしっかり押さえましょう。