
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする

本記事は、法書ログライター様の執筆記事となります。
共犯論の連載記事第2弾です。
第一弾の記事をまだお読みでない方は、第一弾の記事からお読み頂けますと幸いです。
前回までの連載
・【刑法】共犯論の理解に必要な前提知識-共犯論#1
・【刑法】共謀共同正犯を分かりやすく解説-共犯論#2←今ココ
・共同正犯の錯誤をどこよりも分かりやすく解説 共犯#3
・【論証例】承継的共同正犯論をどこよりも分かりやすく解説 共犯#4
前回書いた通り、「教唆や幇助」は実務上ほとんど適用されません。
特に、教唆犯に関しては「絶滅危惧種」とまで言われるほどです。
したがって、「共同正犯」そして「共謀共同正犯」が共犯論のメインとなります。
「共謀共同正犯」は、司法試験においては頻出論点となっています。共謀共同正犯を中心とした問題も多いです。しかし、他の論点が中心の問題を出しておいて、被告人を共謀共同正犯っぽくするというパターンも多いです。
こうまでして共謀共同正犯を出したいのは、やはり難しい論点なクセに実務で頻出するためでしょう。
「共謀共同正犯は難しいけど、これができない人間を実務家にはできません」
と、こういうことなのでしょう。そのくらい重要な内容です。
・正犯性
・狭義の共犯の希少性
今回は共同正犯・共謀共同正犯の成立要件について説明していきます。
共同正犯とは、二人以上が共同して犯罪を実行することを言います。
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
共同正犯とされた場合、実行行為の一部のみを行ったに過ぎなくても、その全部の責任を負います。これを「一部実行全部責任の原則」といいます。
次の【例1】と【例2】は、共に共同正犯が成立する事例です。
【例1】
XとYは二人協力してVに暴行を加えることを計画した。XとYは一斉にVに襲い掛かったが、Vは強く、辛うじてYの爪の一撃がVの頬を掠めて出血を引き起こしたものの、それ以上の傷を負わせることはできなかった。
【例1】では、人類最強と名高いVに手傷を負わせたのはYだけですが、Xも暴行罪でなく、傷害罪の共同正犯となります。


【例2】
XとYは二人協力して、W宅に押し入り金目の物を奪おうと企てた。W宅にて、Xが、猛犬の如く激しく抵抗するWを殴る蹴るして抑圧している間に、Yがタンスから現金を抜き取った。その後、二人は逃走した。
【例2】では、XはWに暴行したものの物の占有を奪取しておらず、逆にYは暴行せずに物を奪取しています。
ここだけ見ると、Xは暴行罪、Yは窃盗罪で処罰されそうです。しかし、共同正犯が成立するので、X、Yは両方とも、強盗罪の共同正犯として処罰されるのです。


このように、実行行為を一部しか分担していなくとも、その全部の責任を負うのが共同正犯ということになります。
とはいえ、犯罪の成立に少し加担したために、その結果のすべての責任を負うというのは、「教唆・幇助」の場合でも同じです。
つまり、たとえ従犯として少し手を貸しただけだったとしても、正犯が引き起こした結果に応じて責任を負うことになります。共同して犯罪を行った他の者が引き起こした結果を自分も負うことになることと同じということです。
では、「共同正犯」と「教唆・幇助」の違いは、実行行為を分担したことにあるのでしょうか?
結論から言えば、違います。
判例・学説は異なる解釈を採っています。
練馬区所在の甲工場の従業員で構成される労働組合U1は、同じく甲工場の従業員で構成される労働組合U2と対立しており、U1の構成員が暴行を行い検挙されるなどしていた。
そこで、U1の構成員A・Bは、U2の委員長Vと練馬警察署の警察官Wに対して暴行を加えることを、構成員C~Jと協議し、C~JはWに暴行を加えて死亡させた。
A・Bは協議はしたが、現場には赴いていない。


「共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互に他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認められなければならない。
したがって右のような関係において共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味において、その間刑責の成立に差異を生ずると解すべき理由はない。
さればこの関係において実行行為に直接関与したかどうか、…は右共犯の刑責じたいの成立を左右するものではないと解するを相当とする。」
上記判例は、共謀共同正犯の要件を示しつつ、直接実行行為に関与していない者が実行行為を分担した者と同じ罪責を負う理由を、こう説明しています。
「他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味で…差異を生ずると解すべき理由はない」
つまり、共同正犯が正犯となるのは、実行行為の一部または全部は他人が行ったものでも、相互利用補充関係の下、「自己の犯罪」の手段に利用したからと言えます。
そして、「自己の犯罪であると評価できること」、これが「正犯性」であり、狭義の共犯との違いです。
共同正犯の正犯性の具体的な中身は以下であると、教科書では説明されています。
【共同正犯の正犯性】
・他の関与者と協力して自分たちの犯罪を犯す意思(正犯意思)
・重大な寄与
共同正犯が成立するために必要な要素は、纏めずに言えば、①関与者との意思連絡、②正犯意思、③重大な寄与、④共謀に基づく実行行為を関与者の誰かが行ったことです。
【共同正犯が成立するために必要な要素】
①関与者との意思連絡
②正犯意思
③重大な寄与
④共謀に基づく実行行為を関与者の誰かが行ったこと
この要件をどう纏めるかについては、諸説ありますが、ここでは、『基本刑法I』に則って、次の三つに区分します。これらについて解説を進めていきます。
【共同正犯の要件 3つに分けた場合】
①共謀
②重大な寄与
③共謀に基づく実行
共謀とは、犯罪を共同して実行する旨の合意です。
この要件に、①意思連絡、②正犯意思を含みます。次の項目でそれらについて解説していきます。
犯行の本質的部分に関する意思の連絡が必要です。
ただ、この要件はあまりキツくはなく、互いに協力していることを知らせていれば足ります。犯行の前に意思の連絡をしている(事前共謀)場合だけでなく、現場で協力することを謀議しても(事後共謀)構いません。
また、先に挙げた判例(昭和33年5月28日)では、AとBはC~Jに対して一人一人順次に意思を伝えていました。いわゆる、順次共謀ですが、それでも足ります。
場合によっては、黙示の意思でも足りるというのが判例です。
Xは暴力団A組の組長である。A組にはXを警護するためのボディーガード隊通称「スワット」がおり、拳銃等で武装しXに帰宅するまで終始帯同していた。
Xは「スワット」を伴って東京に遊びに行ったところ、警察官らがXとボディーガードが乗る車列に対して捜索差押許可状に基づき捜索し、拳銃3丁などを押収した。東京地裁・高裁は銃砲刀剣類取締法違反の共謀共同正犯として、Xに懲役7年を言い渡した。Xは上告した。


「Xは、『スワット』に対してけん銃等を 携行して警護するように直接指示を下さなくても、『スワット』が自発的に被告人を警護するために本件けん銃等を所持していることを確定的に認識しながら,それを当然の こととして受け入れて認容していたものであり,そのことを『スワット』も承知していた」
「前記の事実関係によれば,Xと『スワット』との間にけん銃等の所持につき黙示的に意思の連絡があったといえる。…指揮命令する権限を有するXの地位と彼らによって警護を受けるというXの立場を併せ考えれば,実質的には,正に被告人がCらに本件けん銃等を所持させていたと評し得るのである。」
共同して「自己の犯罪」を犯す意思です。この要件が一番あてはめし甲斐があります。
自己の犯罪を犯す意思があったかどうかは、他の周辺事情から推認されるものです。
具体的には以下などに即して判断します。
【自己の犯罪を犯す意思があったかどうかを判断する要素】
・被告人と他の関与者との関係
・犯行の動機
・当該犯罪の利益の享受
・積極性
・共謀の内容・客観的な犯行への寄与
もっとも、次の「共謀の内容」や「客観的な寄与」は、次の要件である重大な寄与と重なります。
この要件のあてはめで重要なのは、犯行の動機や利益です。
実行行為を分担してれば、それだけで重大な寄与といえます。
共謀共同正犯の場合には、実行行為を担当した者と同等の寄与をしたかどうかを検討します。
具体的には以下を考えることになります。
【実行行為を担当した者と同等の寄与をしたかどうか検討するための要素】
・被告人の地位(他の関与者との関係)
・謀議への積極性
・分担箇所の寄与度(犯行に不可欠な道具や情報を提供したか)
共謀共同正犯では、被告人が実行行為をする必要はありません。
しかし、共謀した者の誰かが実行行為をする必要があります。
【重要ポイントまとめ】
・共同正犯は相互利用関係の下、各自が自分の犯罪を犯す意思を実現したから、正犯としての処罰に値するのである。
・したがって実行行為に直接関与せずとも、謀議に参加し、重大な寄与を及ぼした者であれば、この処罰根拠が妥当する。
・そこで、ある者が共同正犯として処罰されるためには、①共謀の上、②犯行の遂行に重大な寄与を及ぼし、③共謀の結果として犯罪の実行が行われたことを必要とする。
・共謀とは、自己の犯罪を犯す意思をもって相互に意思連絡をなすことである。
・自らの犯罪を犯す意思は、特に、犯行の動機・利益の帰属等から推認する。
・重大な寄与をなしたかどうかは、被告人の地位や人間関係、謀議への積極性、犯行全体への寄与などを考慮する。
今回は共同正犯の成立要件について説明していきました。
しかし、共同正犯・共謀共同正犯に関連する論点は、もっとあります。
たとえば、「共謀」と異なる犯罪を実行担当が行ったら、謀議担当はどうなるのか。これは共犯の錯誤という論点です。
次回以降も、よろしければお読みください。
・大塚裕史『応用刑法I 総論』(日本評論社、2023)
・大塚裕史ほか『基本刑法I 総論[第3版]』(日本評論社、2019)
・『アガルートの司法試験・予備試験合格論証集 刑法・刑事訴訟法』アガルートアカデミー編著(サンクチュアリ出版、2020)
・佐伯仁志・橋爪隆編『刑法判例百選I[第8版]総論』(有斐閣、2020)
・佐伯仁志「絶滅危惧種としての教唆犯」山口厚外編『西田典之先生謹呈論文集』(有斐閣、2017)171頁以下


司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
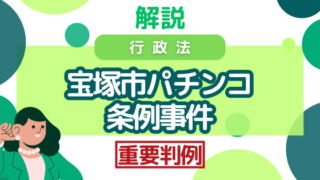
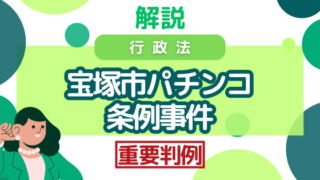














勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

