
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)
法書ログライター様執筆記事です。
前回は、土地区画整理事業事件で登場する用語などを解説させていただきました。今回は判例の中身を見ていきます。
▽前回までの行政法の判例論点解説記事▽
・【難解判例】土地区画整理事業と処分性をわかりやすく解説(前編)
・土地区画整理事業事件(最高裁平成20年9月10日大法廷判決)を分かりやすく解説(後編)←イマココ
・初学者でも分かる!小田急線高架化判決の丁寧な解説
・初学者でも分かる!長沼ナイキ基地訴訟の丁寧な解説
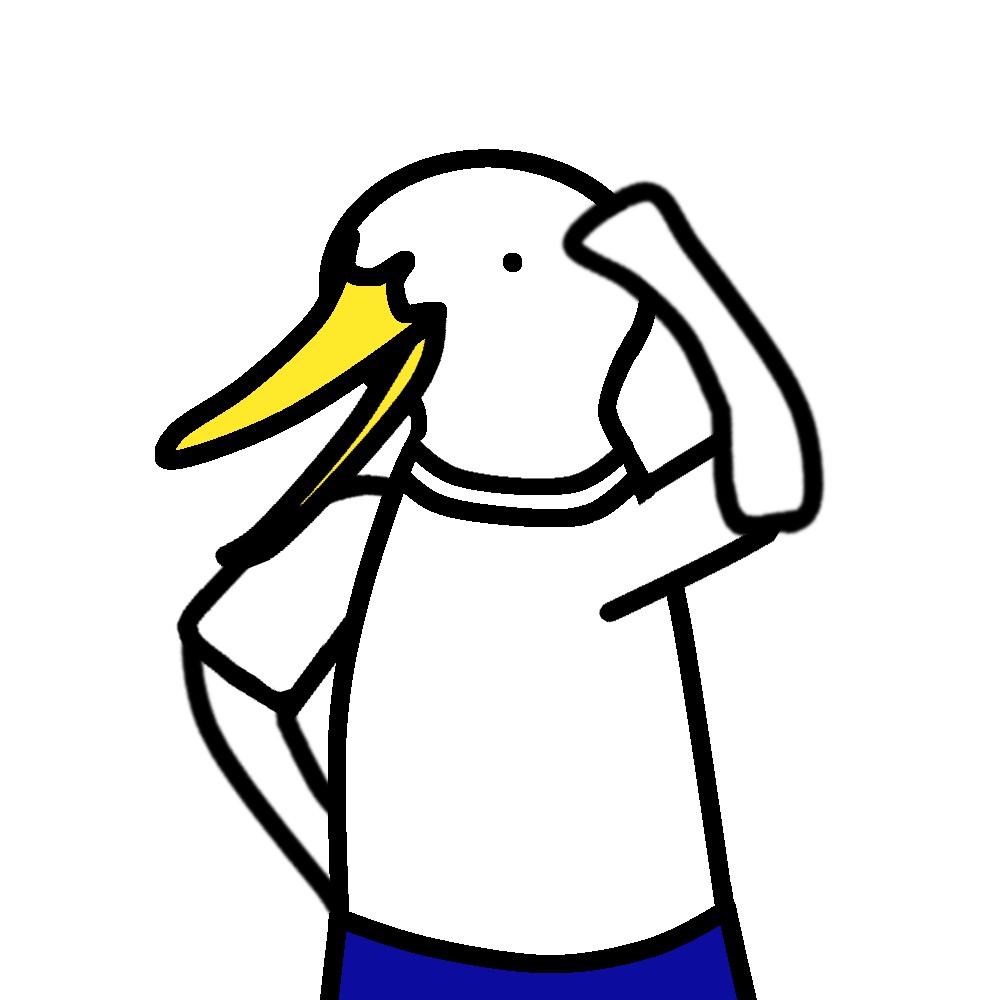
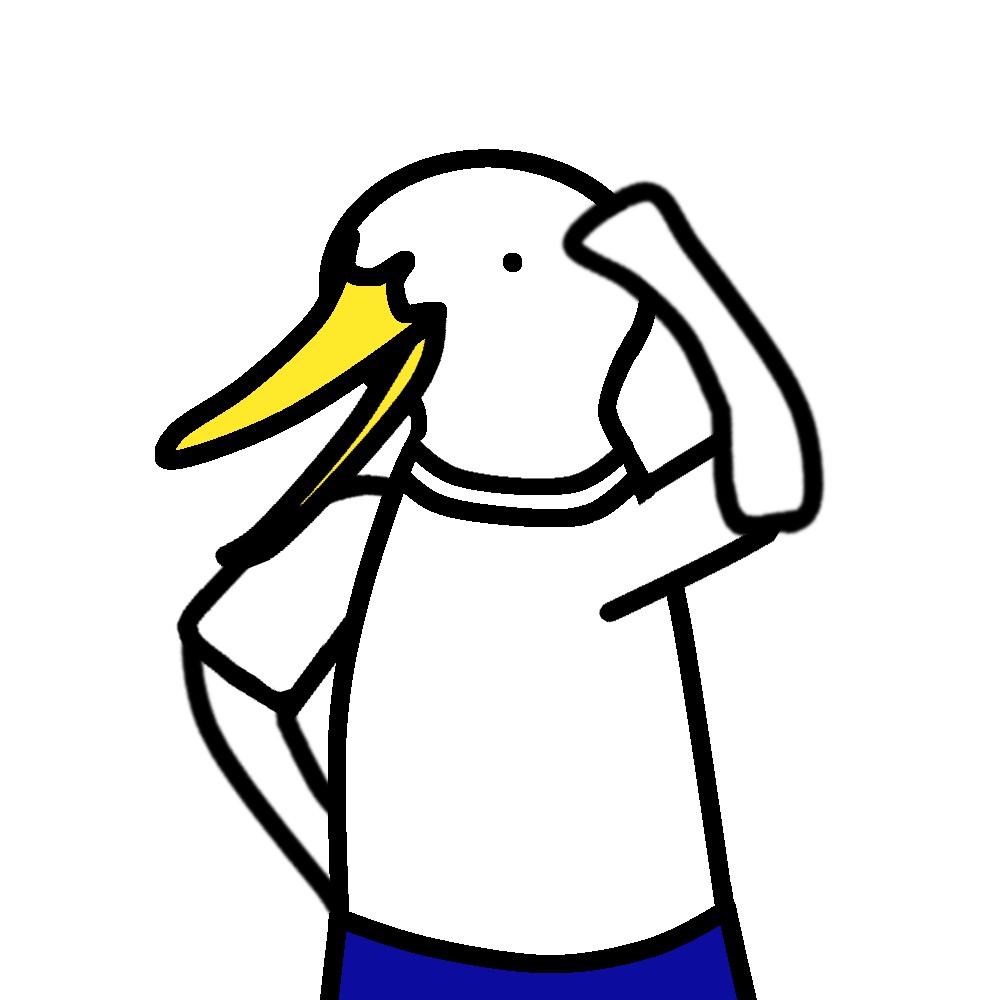
前の記事で出てきた、「土地区画整理事業の4ステップ」全部覚えてるかな…?記事にたくさん出てくるらしいから、もう一回読んでおこっと!


前回は用語などを解説した!
読んだ人は、おさらいを読み飛ばしてくれ!



やあ、法律を学ぶみんな!
今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!



そうなのそうなの〜!
受験生応援セール(5%OFF)と、会員数20万人突破記念キャンペーン(5%OFF)が一緒に使えるんだよ〜✨



つまり、併用で最大10%OFF!
対象講座を選んで、クーポンコード【AGAROOT20】を入力するだけ!



あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱
お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!
📣 【今だけ!アガルートW割キャンペーン実施中】
司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!
現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)と会員数20万人突破記念キャンペーン(5%OFF)のWキャンペーンを開催中です。
💡 両方併用で、なんと最大10%OFF!
\ このタイミングを逃す手はありません /
合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。
前編では①土地区画整理事業とは何か、②処分性とは何かについて説明しました。それを踏まえて後編では③浜松市土地区画整理事業事件(最高裁平成20年9月10日大法廷判決)の判断について説明していきます。
そのため、まずは前回のおさらいを行っていきます。
【判例理解の重要ポイント】
①土地区画整理事業とは?
要するに「ぐちゃぐちゃだった街を整理しよう!」ということです。
②「処分性」とは?その判断基準は?
「処分性」は取消訴訟を適法に提起するために必要な訴訟要件です。
「処分性」は公権力性+直接具体的法効果性(+αの実効的権利救済の観点)で判断されます。
③本判決の意義と理由は?
最高裁は青写真判決を変更し、土地区画整理事業計画の決定に処分性を認めた点に意義があります。
理由は、①同決定が法効果を有すること(直接具体的法効果性)②実効的な権利救済を図る必要があること(実効的権利救済の観点)です。
前編では土地区画整理事業の手続きについて、「ステップ1」から「ステップ4」に分けて解説しました。後編でもこの分類を頻繁に使用しますので引用しておきます。すでに前編をお読みの方は読み飛ばしてください。(以下引用)
ステップ1:土地区画整理事業計画の決定
街をきれいに整備したいわけですから、まずはしっかりと計画を練らなければいけません。この計画が『土地区画整理事業計画』です。
浜松市はこの計画について、静岡県知事から認可を受けたうえで、土地区画整理事業計画の決定を行いました。さらに、事業計画の決定の後、浜松市長はその公告(正式な通知)を行いました。「土地区画整理事業やるよー」ということをお知らせするわけです。
そして、公告がなされると施行地区内では勝手に建築工事などをすることができないという規制がかかります。(土地区画整理法76条1項)
▼
ステップ2:仮換地の指定
その後、仮換地の指定などが行われます。紙面の都合上、仮換地の詳しい説明は割愛します。
▼
ステップ3:工事
そしていよいよ工事が行われます。建物を移転したり、道路を築造したり、公園を整備したりします。
▼
ステップ4:換地処分
最後に換地処分が行われます。換地処分により整理前の土地上の権利が整理後の土地(換地)上に移行します。
重要なポイントは、「基本的には換地処分は工事の後に行われる」ということです。
(引用終わり)


なんで「土地区画整理事業事件」って、重要なんだっけ?
この判決の要旨を確認します。この判決は「土地区画整理事業計画の決定に処分性を認めた判例」でした。
では、この判例は何が画期的だったのでしょうか?そしてどのような理屈で処分性を認めたのでしょうか?


従来は、土地区画整理事業計画の決定について『処分性』が認められていなかったんだ!
従来の判例では土地区画整理事業計画の決定について、『処分性』が認められていませんでした。そのような判断を下した判決が「青写真判決」(最大判昭和41年2月23日)です。この判決は単純化すると次のようなことを言っている判例です。
青写真判決(最大判昭和41年2月23日)
土地区画整理事業の手続きがまだ「ステップ1:土地区画整理事業計画の決定」の段階なのに訴訟を提起するのは早すぎる。
→土地区画整理事業計画の決定について処分性が認められてなかった
上述の通り土地区画整理事業は複数の手続きが連なって進行していきます。土地区画整理事業の具体的な4ステップの整理だと「ステップ1~4」まで手続きが続いていきます。
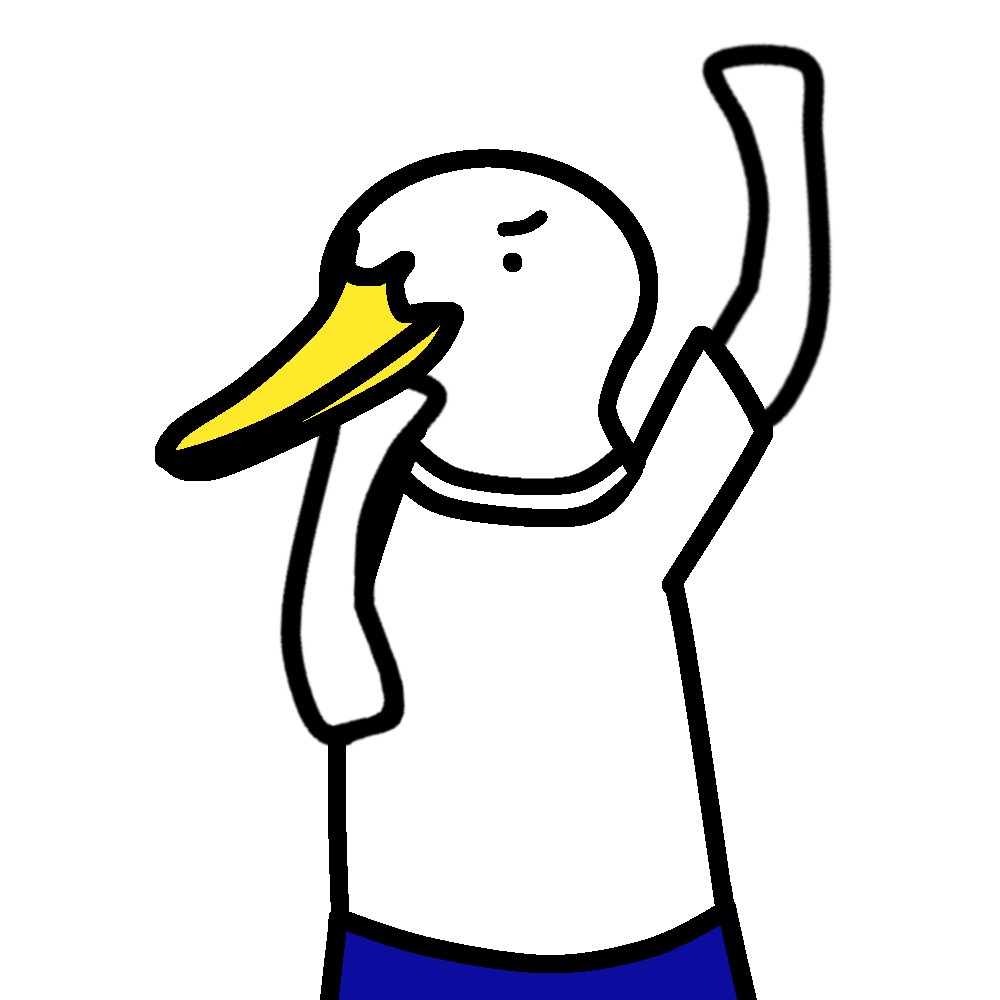
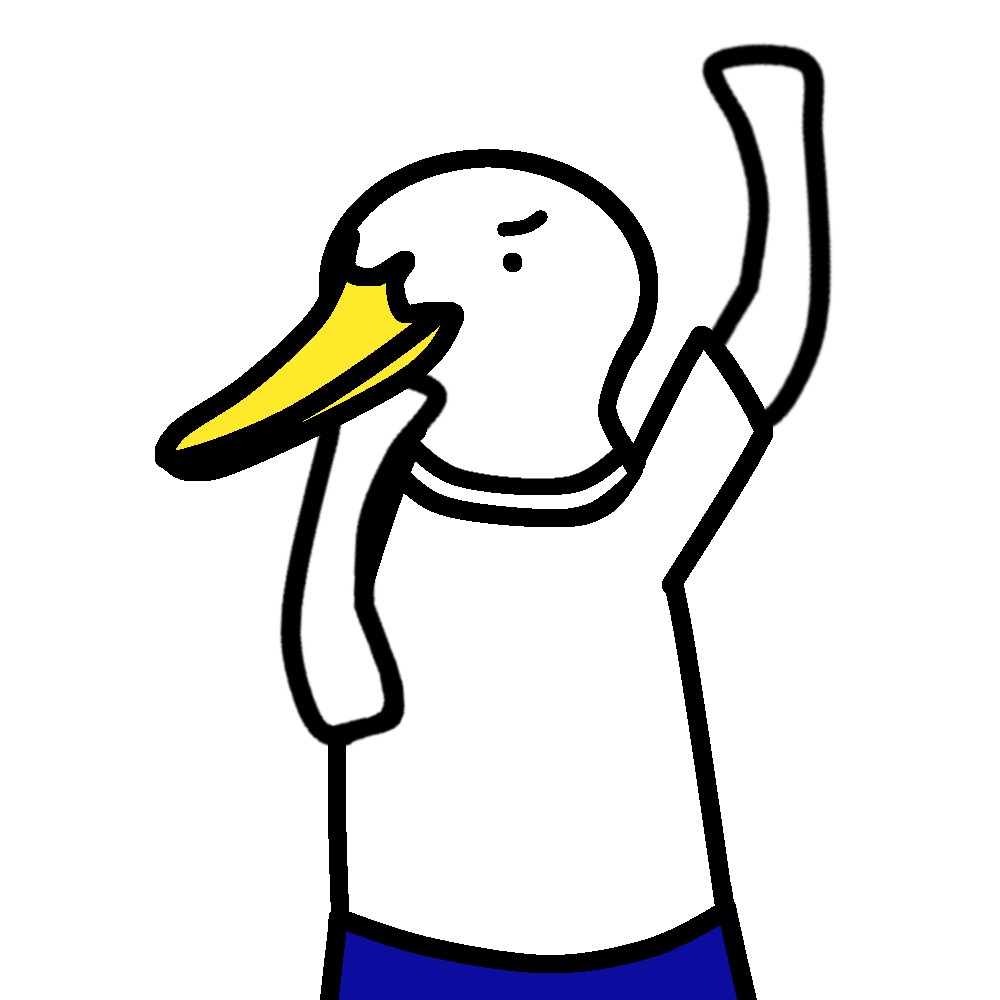
土地区画整理事業の4ステップは以下だったよね!
ステップ1:土地区画整理事業計画の決定
ステップ2:仮換地の指定
ステップ3:工事
ステップ4:換地処分
青写真判決は「ステップ1:土地区画整理事業計画の決定」の段階で訴訟を提起するのではなく、「それよりも後の段階で訴訟を認める方がよい」としたわけです。
【処分性を否定した理由】
①「ステップ1計画の決定」ではまだ直接具体的法効果性が認められない
②「ステップ1計画の決定」ではまだ実効的権利救済の観点からも取消訴訟を提起する必要はない
青写真判決ではそのように判断し、具体的には1つ目に「ステップ1:土地区画整理事業計画の決定」の段階ではまだ直接具体的法効果性が認められないとされました。
2つ目に「ステップ1:土地区画整理事業計画の決定」の段階では、まだ実効的権利救済の観点からも同決定について取消訴訟を提起する必要はない、として同決定の『処分性』を否定しました。
しかし、これに対して土地区画整理事業事件の判決では同決定の『処分性』を認めました。
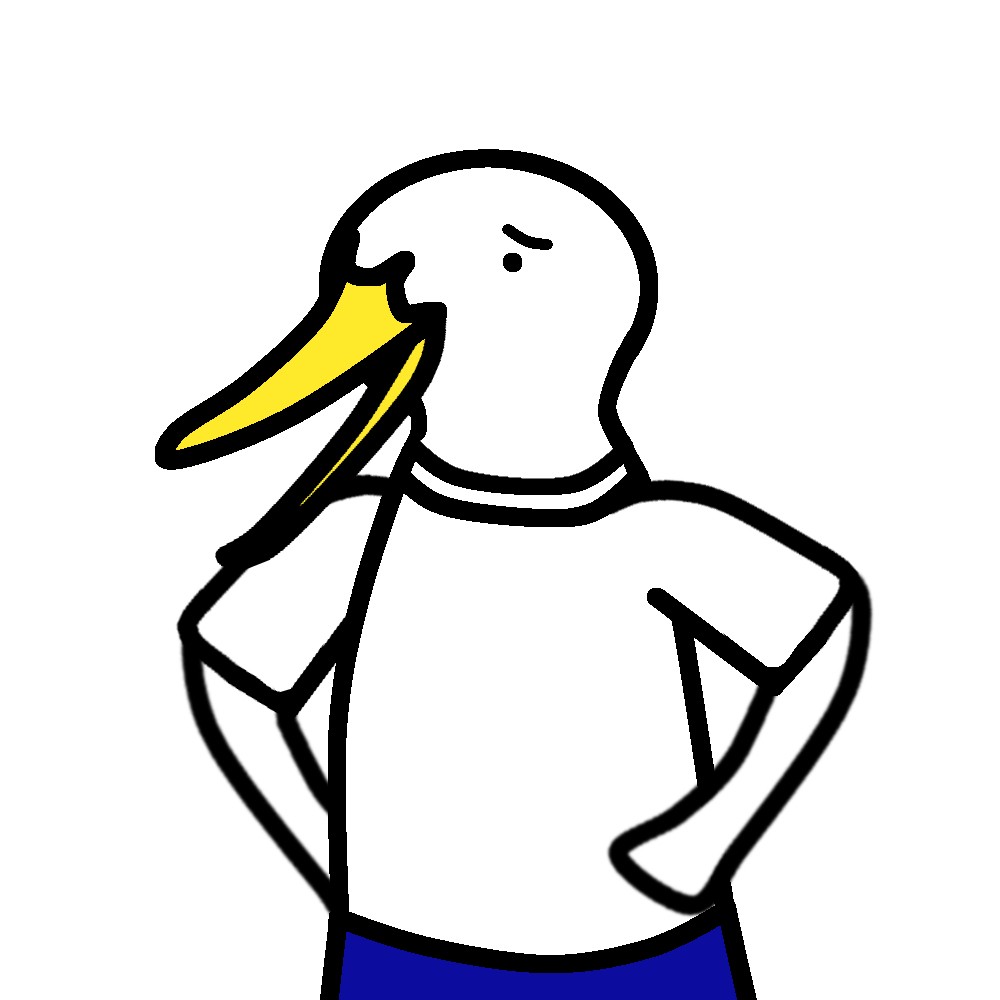
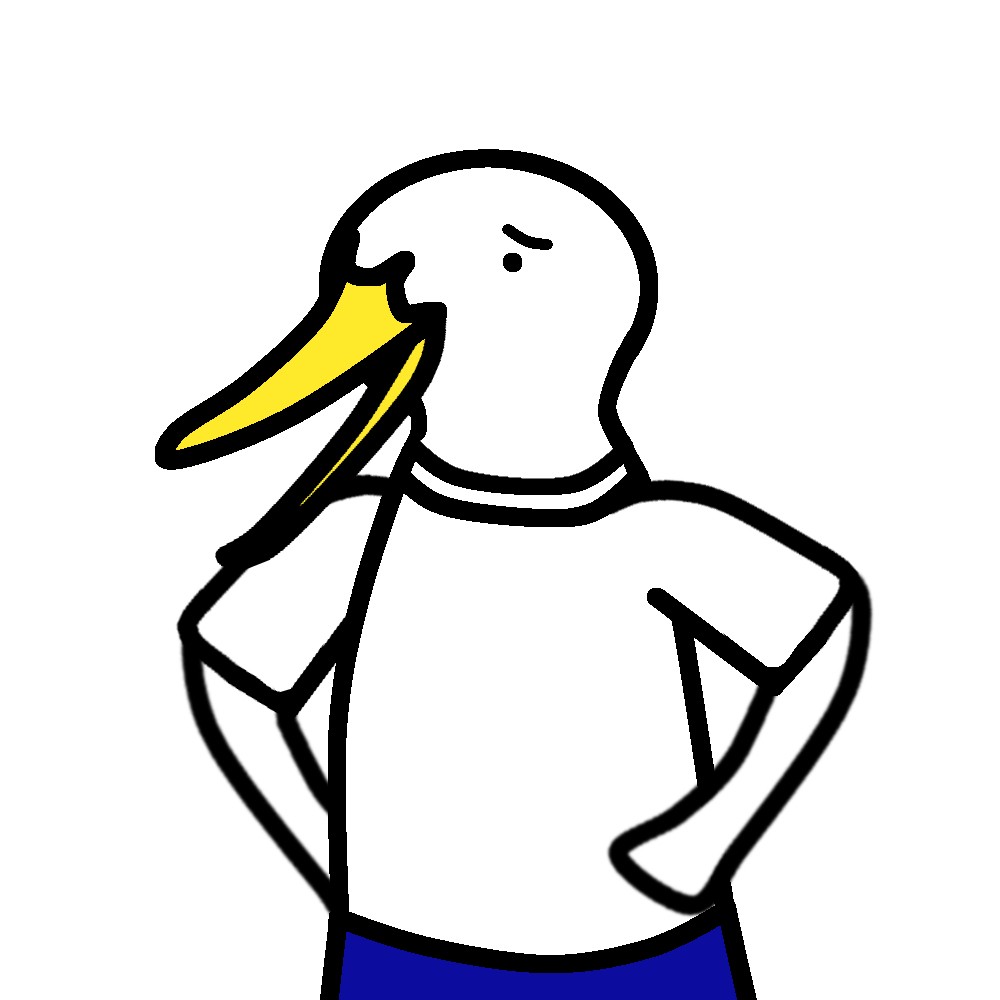
でも、なんで認めたんだろう?


まず、土地区画整理事業事件は以下のような状況でしたよね


では土地区画整理事業事件の判決は、どのような理由で土地区画整理事業の『処分性』を認めたのでしょうか?
【土地区画整理事業の処分性が認められた理由】
以下が合理的であるとされたからです
①「ステップ1:土地区画整理事業計画の決定」に直接具体的法効果性が認められること
②実効的な権利救済を図るためには「ステップ1:土地区画整理事業計画の決定」の取消訴訟を認めること
1つ目に、同決定に直接具体的法効果性が認められること、2つ目に、実効的な権利救済を図るためには同決定について取消訴訟を認めることが合理的であることにあります。
(ちなみに、前述の通り同決定に公権力性があることについては争いがありません)


これらの理由を、それぞれ、分かりやすく説明していくぞ!
まず①について説明します。
【法効果性が認められる理由】
①-1. 「ステップ1:土地区画整理事業計画の決定」の公告により規制を伴うため
①-2. 「ステップ1:土地区画整理事業計画の決定」がされたということは、後に施行地区内の宅地所有者ら(Xさん達)が換地処分を受けるべき地位に立たされる可能性が高いため
法効果性が認められる理由は、「①-1同決定の公告が規制を伴うため」、また「①-2同決定により施行地区内の宅地所有者ら(Xさん達)が換地処分を受けるべき地位に立たされるため」です。
土地区画整理事業の手続き「ステップ1」で、同決定の公告(正式な通知)がなされると一定の法的規制がかかるということを説明しましたね。
①-1はこれを、公告(正式な通知)に直接具体的法効果性が、認められる理由の一つとしています。
法的規制によって、私人の権利が制限されるという「法効果」があるわけです。


ステップ1で、公告がなされると「施行地区内では勝手に建築工事などをすることができない」という規制がかかるっていう話だったよね!
土地区画整理事業の計画はいったんその決定がされると、特段の事情のない限りその事業計画に従って具体的な事業がそのまま進められます。
「ステップ1:土地区画整理事業計画の決定」の時点で、区域内の土地所有者は、後の換地処分(新しい土地の割り当てなど)により権利が侵害される、蓋然性がある(ある事柄が実際に起こる可能性が高い)という風に考えることができるでしょう。
このような蓋然性をもって、判例は「換地処分を受けるべき地位に立たされるものということができ、その意味で、その法的地位に直接的な影響が生ずるもの」と表現して、直接具体的法効果性が認められるとしています。
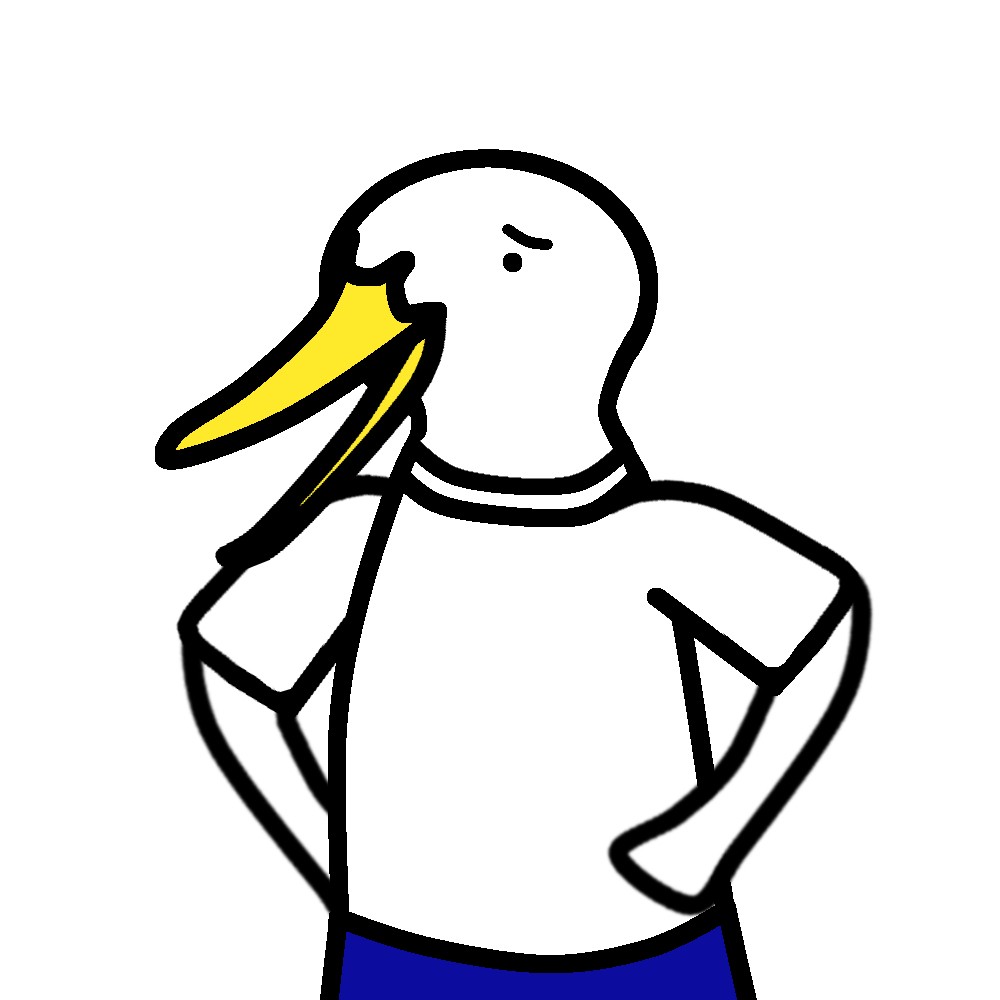
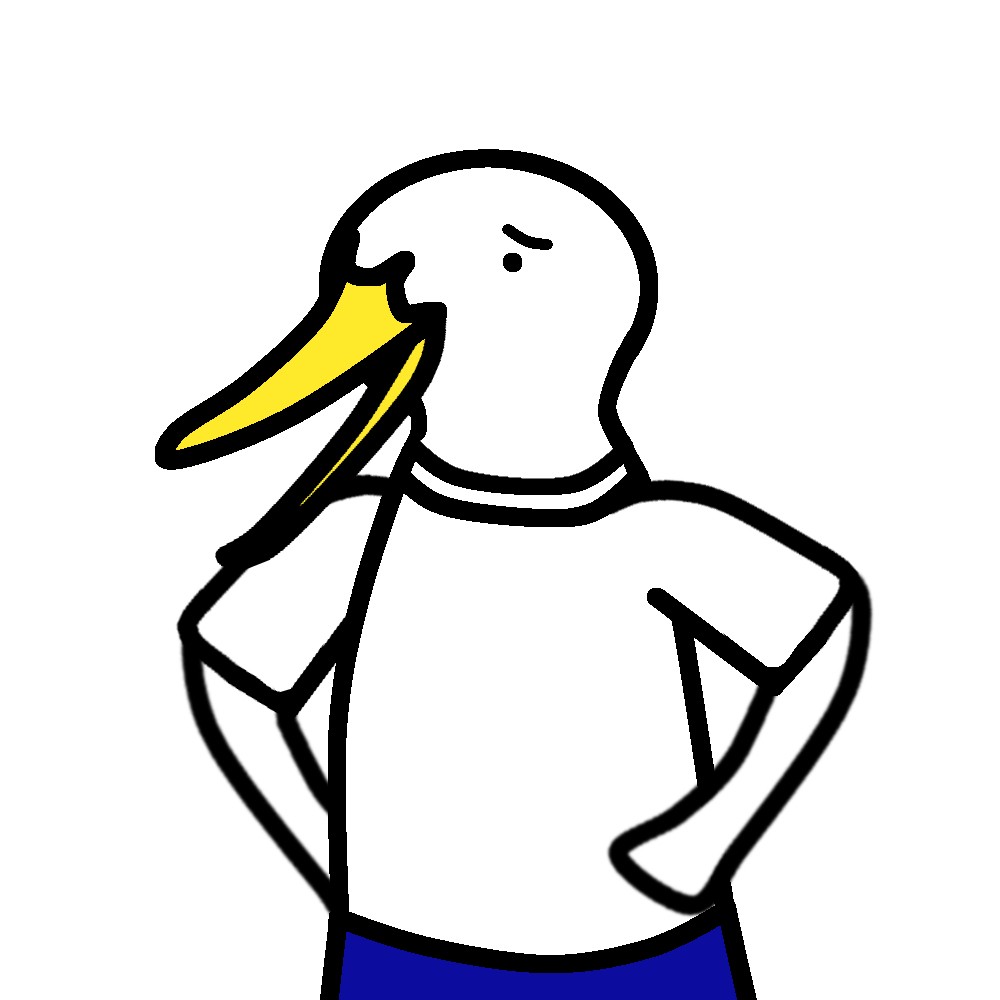
確かに、土地所有者は計画が進んでいくと、「換地処分」受けることがほぼ確実であると考えられる状態だと言えるかもしれないね!
次は、理由②についてです。
青写真判決は、「ステップ1:土地区画整理事業計画の決定」より後の段階で訴訟を提起するとしても原告の権利救済は十分に達成できると判断しました。
しかし、土地区画整理事業事件の判決は「事業計画の適否が争われる場合、実効的な権利救済を図るためには、事業計画の決定がされた段階で、これを対象とした取消訴訟の提起を認めることに合理性があるというべきである。」として、「ステップ1:土地区画整理事業計画の決定」の段階での訴訟提起が原告の権利救済のために合理的だといいます。
ではなぜそのように言えるのでしょうか?
例えば「ステップ4:換地処分」の換地処分の時点で訴えを提起するのではいけないのでしょうか?


確かになんで後のステップで訴えを提起するのはいけないんだろう?
この点について判例は次のように説明しています。
「もとより,換地処分を受けた宅地所有者等やその前に仮換地の指定を受けた 宅地所有者等は,当該換地処分等を対象として取消訴訟を提起することができるが,換地処分等がされた段階では,実際上,既に工事等も進ちょくし,換地計画も具体的に定められるなどしており, その時点で事業計画の違法を理由として当該換地処分等を取り消した場合には,事業全体に著しい混乱をもたらすことになりかねない。
それゆえ,換地処分等の取消訴訟において,宅地所有者等が事業計画の違法を主張し,その主張が認められたとしても,当該換地処分等を取り消すことは公共の福祉に適合しないとして事情判決(行政事件訴訟法31条1項)がされる可能性が相当程度あるのであり,換地処分等がされた段階でこれを対象として取消訴訟を提起することができるとしても,宅地所有者等の被る権利侵害に対する救済が十分に果たされるとはいい難い。」
まず、「ステップ4:換地処分」の段階でも取消訴訟を提起することは可能です。しかし「ステップ4:換地処分」で学びましたが、換地処分は基本的に工事の後に行われます。すると「ステップ4:換地処分」の段階では既に街を整理する工事がかなり進んでしまっていることが予測されます。
そのような後戻りできない段階になってから訴訟を提起しても「違法ではあるけれど、いまさら処分を取り消すと混乱が大きすぎて公共の福祉に反するから処分は取り消せません」という事情判決が出されてしまう可能性があります(行政事件訴訟法31条1項)。すると原告の請求は棄却され、原告の権利救済は十分には果たされません。
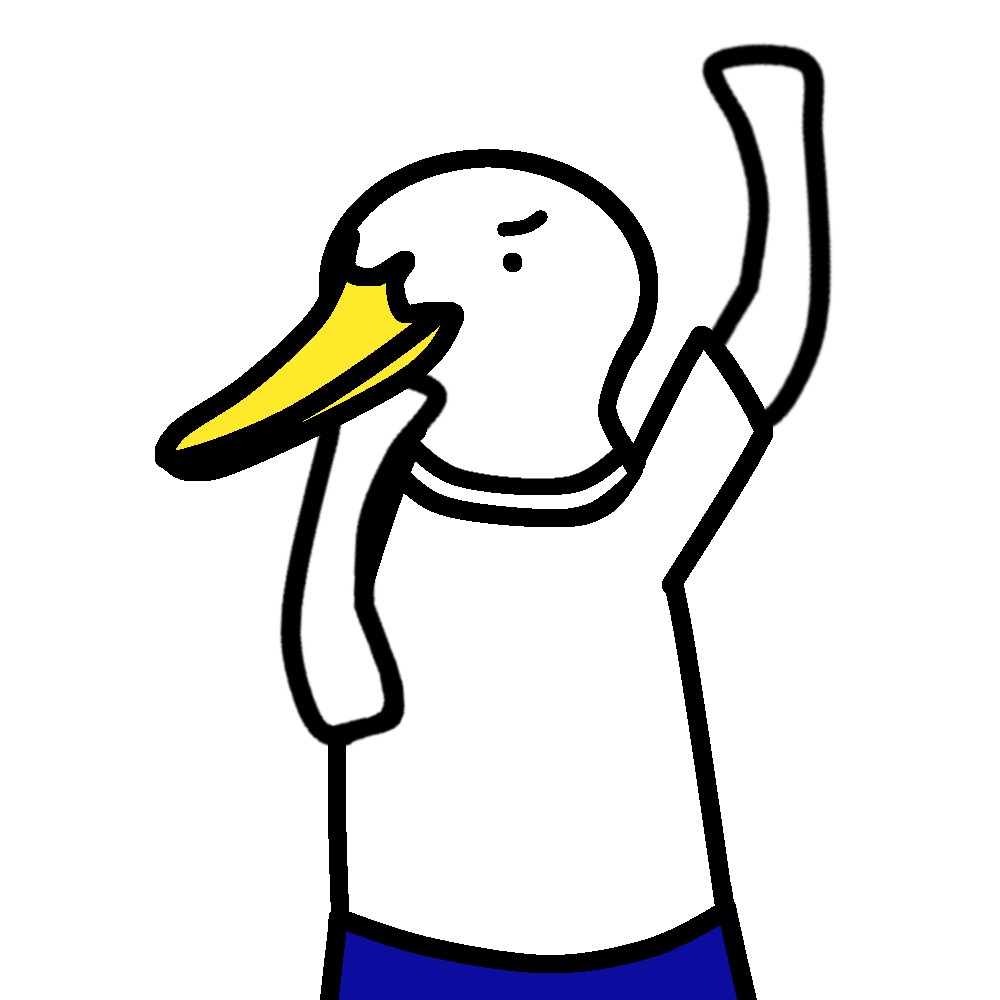
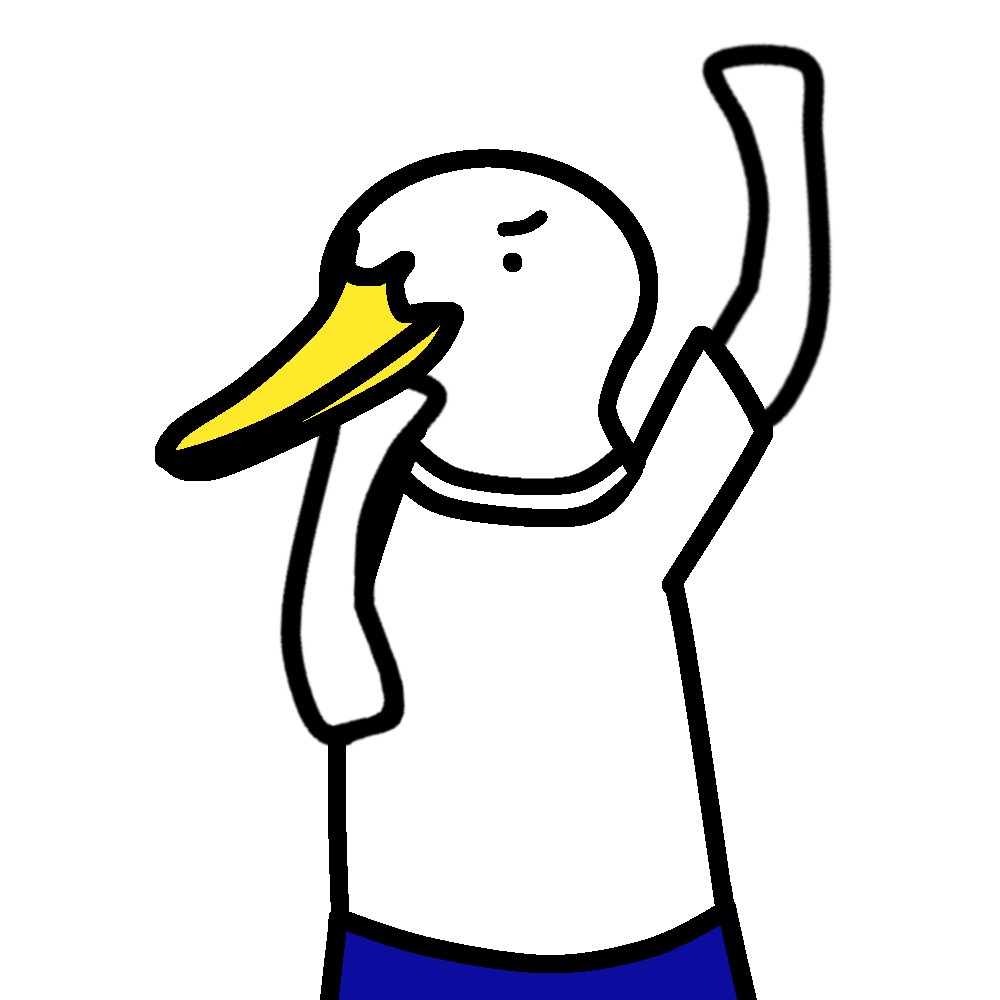
確かに、ステップ4で提起すれば「もう工事後だから取り消せない」と言われ、ステップ1だと「早すぎる」って言われるのは、違和感があるね!
このように、本判例は後(例えば「ステップ4:換地処分」の段階)で取消訴訟を提起しても原告が十分に救済されないのだから、「ステップ1:土地区画整理事業計画の決定」の段階で原告による訴訟の提起を認めるべきだと判断したわけです。
【土地区画整理事業の処分性が認められた理由 まとめ】
①「ステップ1計画の決定」は、直接具体的法効果性が認められる
なぜなら、決定の公告により規制を伴うため
また、施行地区内の宅地所有者らが換地処分を受けるべき地位に立たされる可能性が高いため
②実効的な権利救済を図るためには「ステップ1計画の決定」の取消訴訟を認める
なぜなら、取消訴訟を提起が遅いと権利救済が十分にされない可能性があるため
この記事では浜松市土地区画整理事業事件において土地区画整理事業計画の決定に処分性が認められたことについて解説しました。だいたいわかったよ(なにごとも完璧に理解するというのは難しいものです)という方は判例百選などの判例集や各自の持っているテキストを改めて読んでみてください。
(個人的には行政判例百選Ⅱ第8版147番の山下先生の解説が非常に分かりやすいと思います。この記事の執筆の際にも参考にさせていただきました。)
そのときに今までよりも少しでも本判決について理解がしやすくなっていれば嬉しく思います。
下山憲治,友岡史仁,筑紫圭一(2017)『行政法』日本評論社.
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?
詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法律記事を書いております犬橋です。現在は国立大学法科大学院に在籍しながら、行政法の判例の解説記事を主に執筆しています。
初学者の方にもわかりやすく、興味を持ってもらえるような記事を書くことを目指しています。


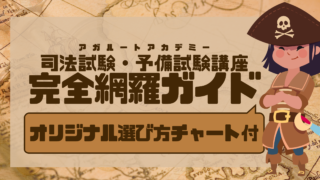
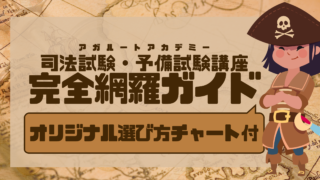
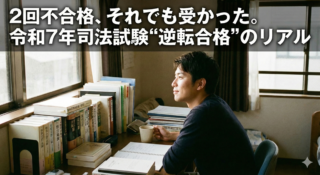
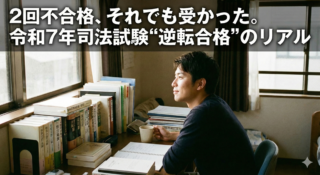
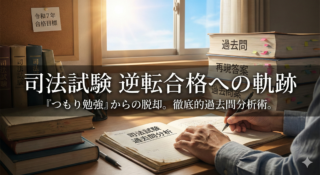
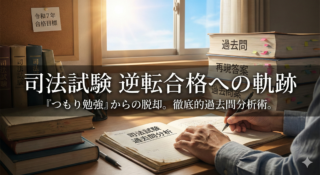






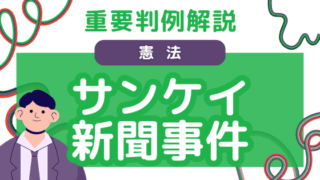
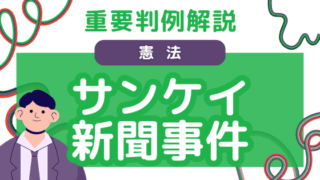
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

