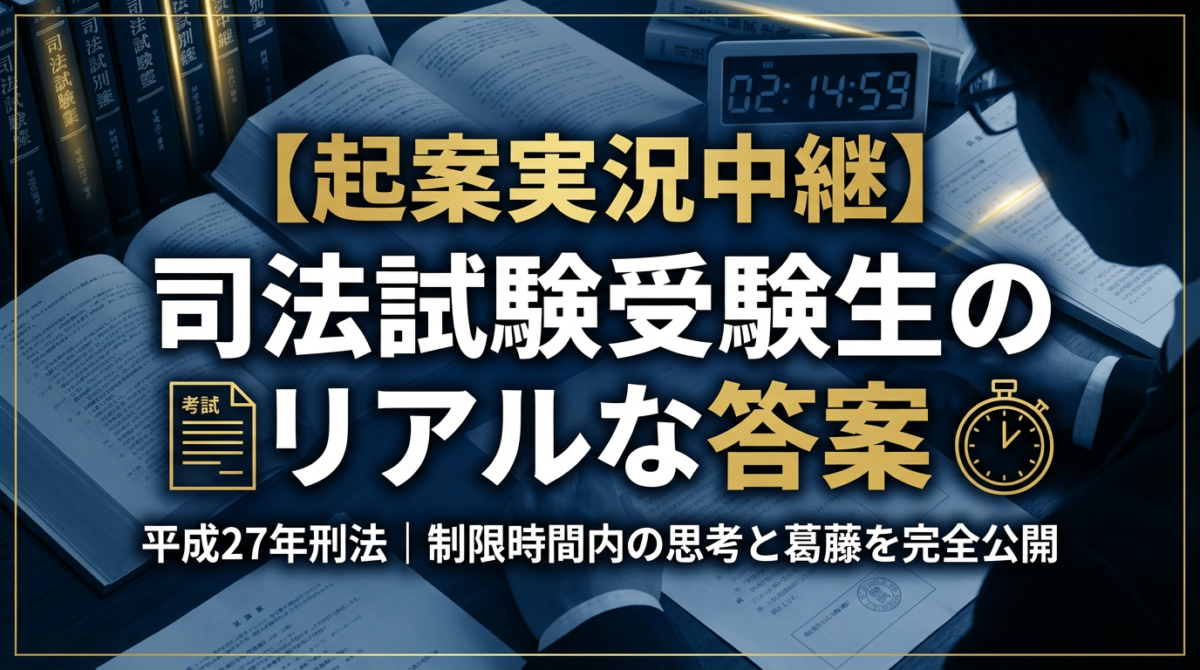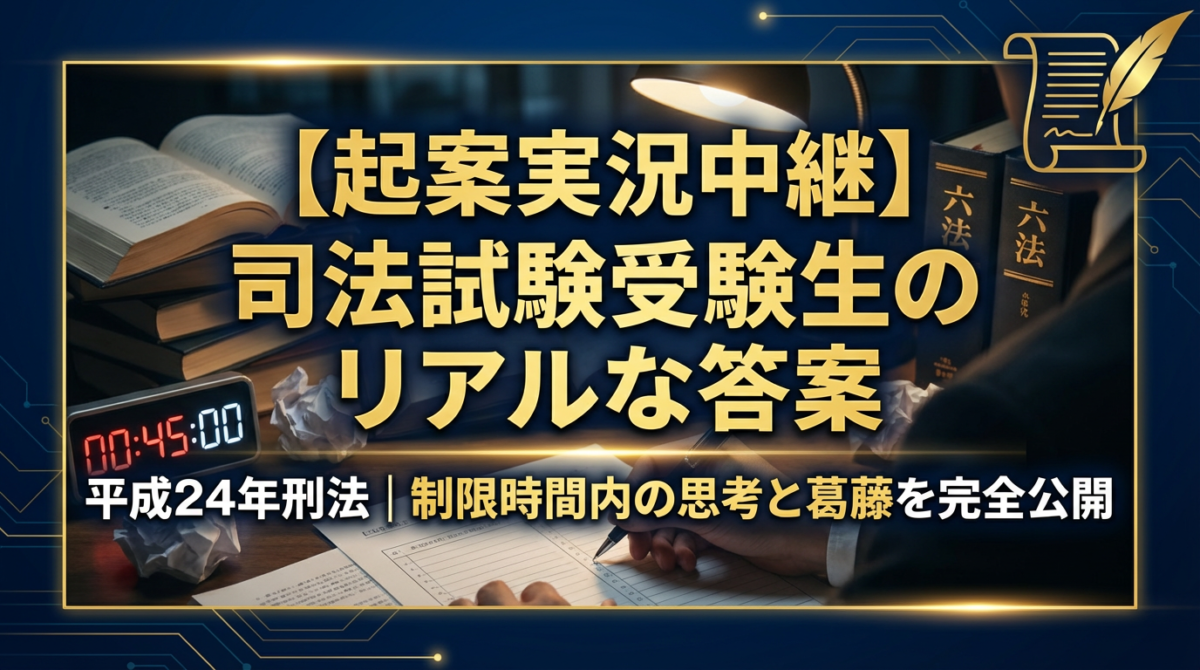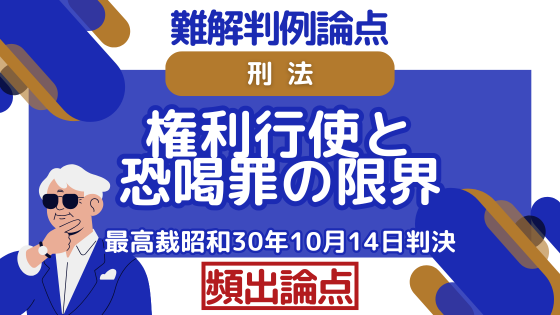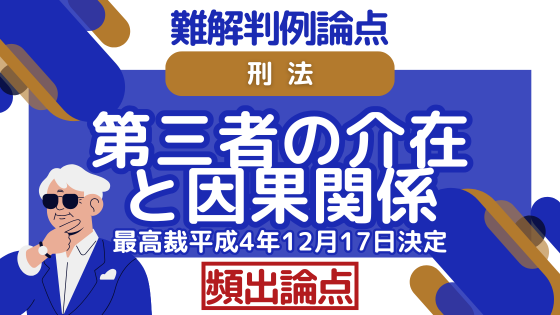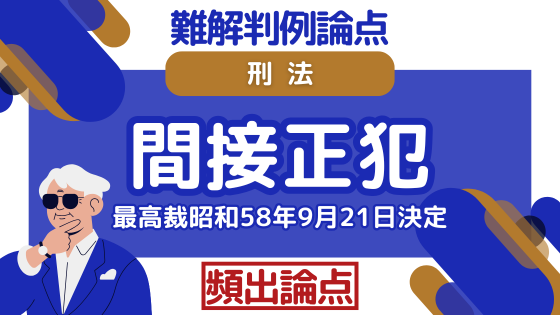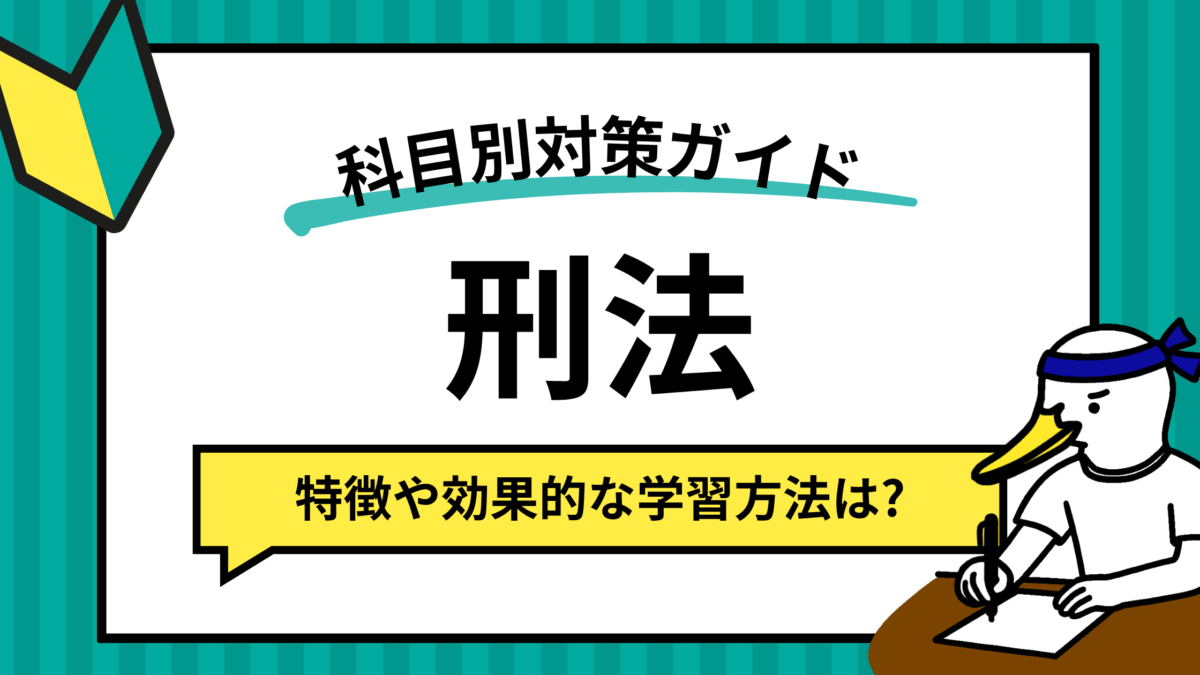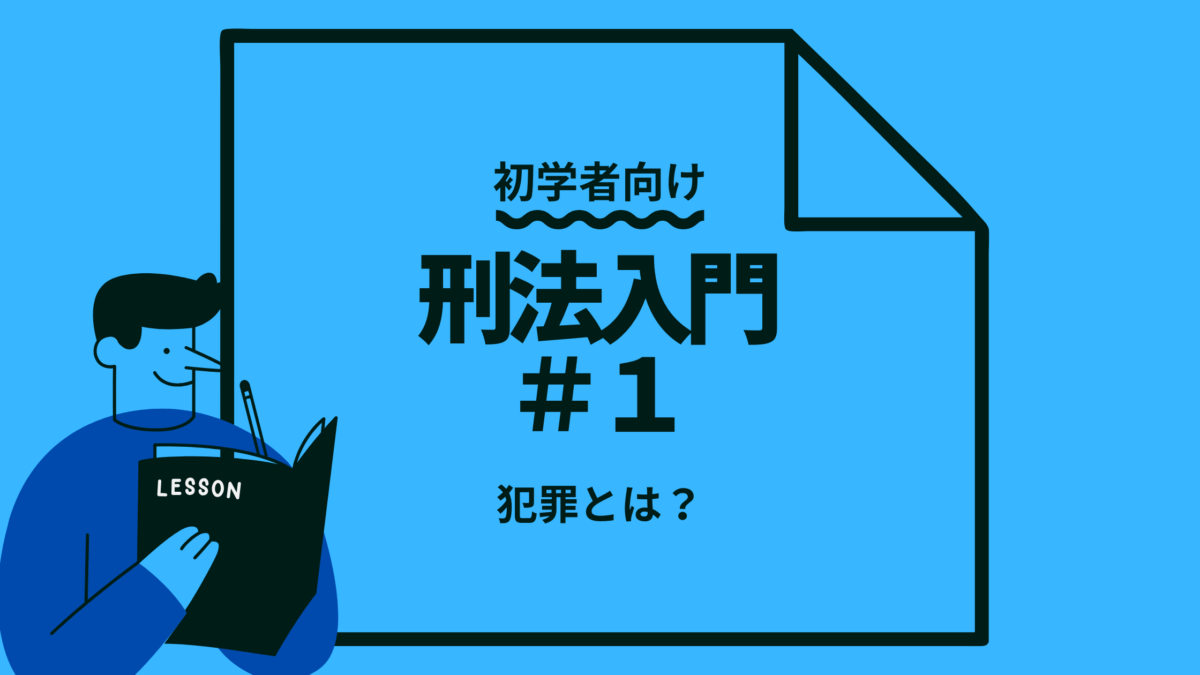刑法– tag –
-

【起案実況中継②】司法試験受験生のリアルな答案と起案後雑感【平成27年刑法】
司法試験・予備試験の学習において、最も参考になるのは、「模範解答」ではなく、実は「合格に向けて日々研鑽を積み、真剣に課題と向き合う受験生の生の軌跡」ではないでしょうか。 本企画は、令和8年司法試験合格を目指す、ある受験生の起案をシリーズで... -

司法試験合格者が教える刑法の3ステップ学習法と厳選教材7選【初学者向け】
本記事は、令和7年(2025年)司法試験に見事合格された方により、自身の受験経験を余すことなく反映して執筆されました。 司法試験の学習、とりわけ「刑法」という科目は、抽象的な理論や膨大な学説の対立に足を取られ、途中で挫折してしまう方が少なくあ... -

【起案実況中継】司法試験受験生のリアルな答案と起案後雑感【平成24年刑法】
司法試験・予備試験の学習において、最も参考になるのは、「模範解答」ではなく、実は「合格に向けて日々研鑽を積み、真剣に課題と向き合う受験生の生の軌跡」ではないでしょうか。 本企画は、令和8年司法試験合格を目指す、ある受験生の起案をシリーズで... -

最高裁昭和30年10月14日判決で学ぶ権利行使と恐喝罪の限界
恐喝罪(刑法249条)は、暴行・脅迫を用いて相手に財産的損失を与えた場合に成立しますが、債権者が正当な権利を回収するために恐喝的手段を用いた場合にも、果たして恐喝罪は成立するのでしょうか? 最高裁昭和30年10月14日判決は、この問題に正面から向... -

営業中のATMでも『侵入』?最決平19・7・2にみる建造物侵入罪と偽計業務妨害罪の実行行為
建造物侵入罪(刑法130条前段)における「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りをいうとされるのが通説・判例の立場です。また、偽計業務妨害罪(刑法233条)における「偽計」も、単なる虚偽ではなく、人を欺罔し錯誤に陥れるような行為である必要が... -

【第三者の介在と因果関係】最高裁平成4年12月17日決定に学ぶ相当因果関係の限界
刑法における「因果関係」は、実行行為と結果をつなぐ重要な要件です。 しかし、「行為者以外の第三者の介在」や「被害者自身の不適切な行動」が結果に影響した場合、それでもなお「因果関係」を肯定できるのでしょうか? 「最高裁平成4年12月17日決定」は... -

『自殺を命じた者』は殺人犯か?平成16年最高裁決定に学ぶ間接正犯の射程
被害者に自殺を強要し、その行為を利用して保険金を得ようとした――このような異常な事案に対して、刑法上どのように評価すべきでしょうか。 最高裁平成16年1月20日決定は、被害者が自ら命を絶とうとした行為について、その背景にある加害者の暴行・脅迫や... -

【間接正犯】意思の抑圧と刑事未成年者利用をめぐる重要判例を分かりやすく解説【最高裁昭和58年決定】
司法試験刑法で頻出のテーマのひとつに「間接正犯の成否」があります。 特に、「刑事未成年者」や第三者を「道具」のように利用した犯罪において、「正犯」としての処罰が可能かどうかは、刑法総論の核心的論点です。 本記事で取り上げる最高裁昭和58年9月... -

【2025年】刑法のおすすめ書籍15選【基本書、演習書、判例集、入門書、参考書】
皆さん、かもっちです。数ある記事の中から、本記事をお選び頂きありがとうございます。刑法のおすすめの基本書、演習書、判例集、入門書など刑法のおすすめ書籍をお探しですか。 刑法は、市販の書籍数も多く、どれがおすすめの書籍なのか分からないな。 ... -

正当防衛の要件④「やむを得ずにした」を分かりやすく解説
本稿では正当防衛の第4要件『やむを得ずにした』の解説をしていきます! 刑法 第三十六条(正当防衛)急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑... -

司法試験 刑法の勉強法 〜これから司法試験対策を始める方へ〜
これから司法試験の勉強を始めようとする皆さんにとって、試験科目のひとつである「刑法」の対策をどのように進めるべきか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。刑法は、法律の基本的な思考を学ぶうえで非常に重要な科目であり、正しい学習法を採る... -

司法試験受験生のための刑法入門#1 犯罪とは?
司法試験受験生の皆さん、こんにちは! 今回は、刑法総論の第一歩である「犯罪とは何か」というテーマについて、丁寧に解説していきたいと思います。刑法の学習において、この「犯罪概念の理解」は、いわば土台にあたる部分です。 この基礎がしっかりして...