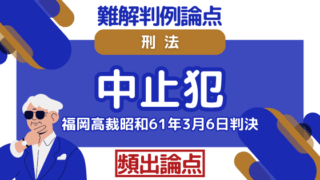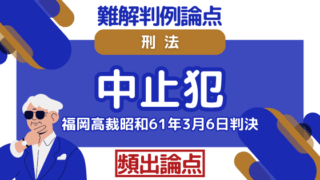【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。
動画解説の「法スタチャンネル」も大好評、運営中!
▽動画解説を順次公開中▽



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



皆さん、知ってましたか?
あのアガルートがアプリをリリースしています。



これにより講義視聴がより便利になり、学習の効率が大幅にアップしました!
是非、公式サイトで詳細を確認してください!
\講義動画のダウンロード可能/
データ通信料を気にせず受講しよう!!


「予備試験論文式試験の合格点はどうなってるんだろう?」
「予備試験の論文式試験の合格率ってどのくらいなんだろう?」
「予備試験の論文式試験の攻略法は?」


今回は、予備試験の論文式試験の合格点、合格率を解説するぞ。
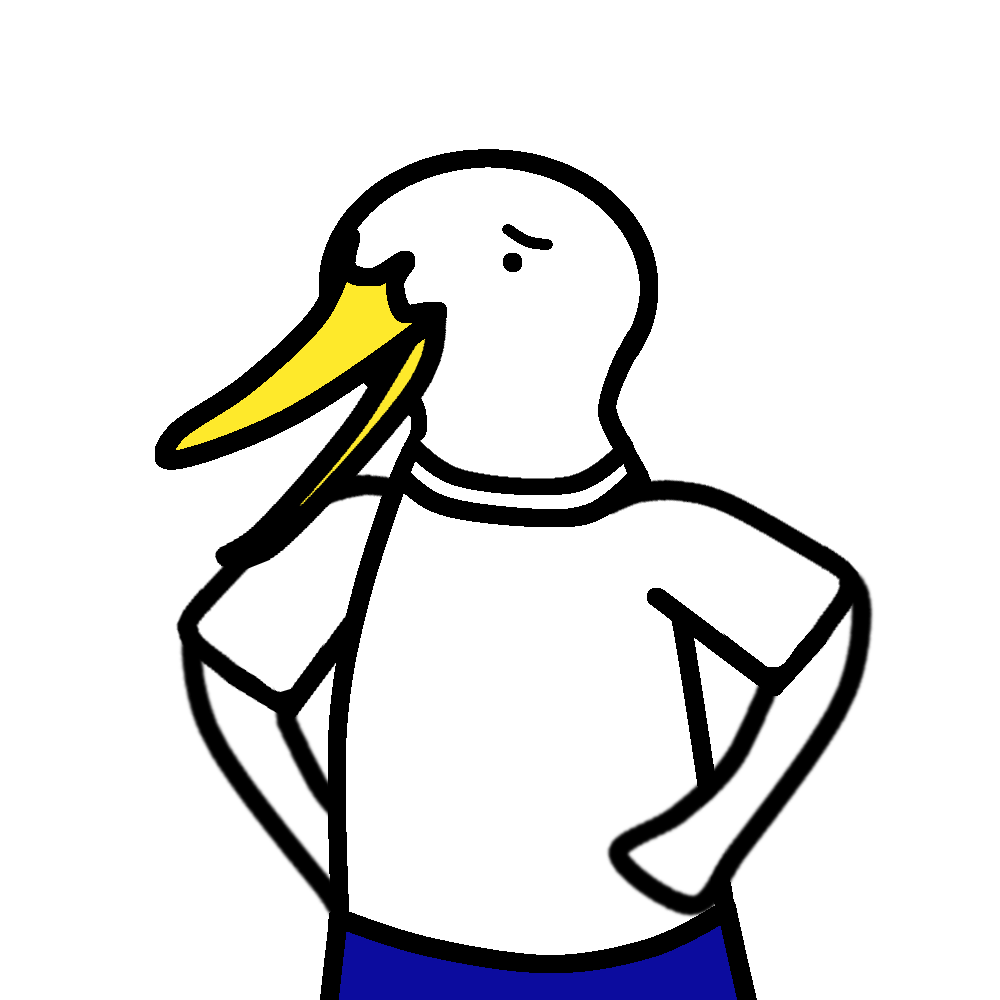
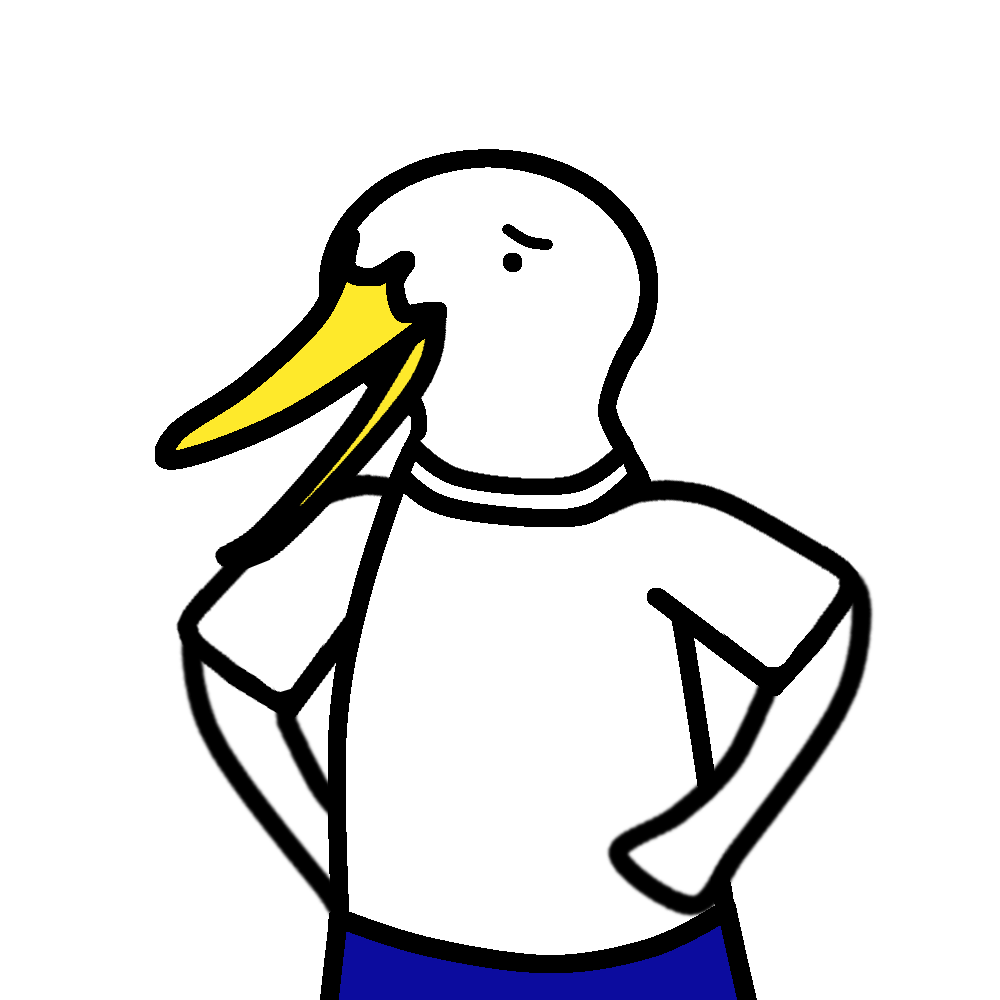
予備試験って、論文式試験が天王山なんだよね?


そうだよ、あひるっぺ!。予備試験は、短答式試験、論文式試験、口述試験の3つの試験にすべてに合格しないとだめだけど、その中でも論文式試験が最難関なんだ。
今回は、予備試験の論文式試験の合格点及び合格率について、過去12年分の予備試験の結果を基に紹介をさせて頂きます。
予備試験の短答式試験の合格点、合格率については、以下の記事をご参考にしてください。
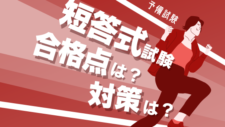
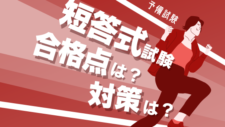



みなさ~ん!
この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。



「これさえやりきれば、もう怖くない!」
そんな演習書や問題集が欲しいと思ったことはありませんか?
通称「重問」と呼ばれるアガルートの重要問題がおすすめ



その人気の秘密や効果的な活用方法について、アガルートの専任講師に直接インタビューを行いました。
受験生に支持される理由が詰まった記事、ぜひチェックしてみてくださいね!
今売れてます!!
\司法試験合格者占有率37.8%/
▼重要問題だけで合格する究極の勉強法【独占インタビュー】▼


司法試験予備試験の論文式試験は、短答式試験を勝ち抜いた人たちのみが受けられる試験です。
一定以上の実力がある人達の間で競われる試験であるため、合格率が高そうに見えても、試験突破の難易度は高くなります。
その後に行われる口述試験は、短答式試験と論文式試験のどちらも突破した人たちの間での試験ですから、合格率は90%超と高くても油断はできません。
もっとも、口述試験は、よほど緊張して、頭が真っ白になってしまったとかでない限り、しっかり対策しておけば、まず合格できる試験とされています。
そのため、司法試験予備試験で、一番難易度の高い試験は、論文式試験ということになります。資格予備校などでも、「論文式試験が天王山」と表現しており、司法試験予備試験合格に向けた山場ということになります。
予備試験論文式試験の各年度の合格率は次のようになっています。
| 受験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2011年(平成23年) | 1301人 | 123人 | 9.5% |
| 2012年(平成24年) | 1643人 | 233人 | 14.2% |
| 2013年(平成25年) | 1932人 | 381人 | 19.7% |
| 2014年(平成26年) | 1913人 | 392人 | 20.5% |
| 2015年(平成27年) | 2209人 | 428人 | 19.4% |
| 2016年(平成28年) | 2427人 | 429人 | 17.7% |
| 2017年(平成29年) | 2200人 | 469人 | 21.3% |
| 2018年(平成30年) | 2551人 | 459人 | 17.9% |
| 2019年(令和元年) | 2580人 | 494人 | 19.1% |
| 2020年(令和2年) | 2439人 | 464人 | 19.0% |
| 2021年(令和3年) | 2633人 | 479人 | 18.2% |
| 2022年(令和4年) | 2695人 | 481人 | 17.8% |
| 2023年(令和5年) | 2562人 | 487人 | 19.0% |
合格率だけを見れば、比較的簡単な宅建士試験とほとんど変わりません。
だからと言って、宅建士試験並みに簡単なのかと言うと、全く違いますから、勘違いしないように注意してください。
毎年約2500人の受験者がいますが、彼らは、予備試験短答式試験を突破した人たちです。レベルの高い人たちの間で行われる試験ですから、その中からさらに上位17%に食い込むことは、容易ではありません。
その意味で、予備試験論文式試験の合格率から、甘く見てしまうと痛い目に遭いますから注意が必要です。
一方で、予備試験論文式試験は、最上位の数%に食い込まなければ、合格できない試験ではないことも分かると思います。合格率が1ケタ台になったのは、最初の年だけで、その後は、2ケタ台、20%に近い合格率です。
こうしたことから、途方もない試験ではなく、やるべきことをしっかりやっておけば、合格が見えてくる試験でもあると言えるでしょう。
予備試験の論文式試験の試験科目を確認しておきましょう。カッコは試験時間です。
●法律基本科目
憲法と行政法(2時間20分)
民法、商法と民事訴訟法(3時間30分)
刑法と刑事訴訟法(2時間20分)
●選択科目
選択した科目(1時間10分)
●法律実務基礎
民事系と刑事系(3時間)
10科目出題され、各科目ごとに、50点満点となっています。合計500点満点の試験です。
このうち、法律基本科目は、「基本的な知識、理解及び基本的な法解釈・運用能力並びにそれらを適切に表現する能力を問う」問題とされています。
司法試験でも論文試験があることや法律実務基礎科目があることから、難解な問題が出されるわけではなく、基本をしっかり押さえて、手堅く論文を書くことが重要な科目と言えるでしょう。
選択科目は、一般教養科目に代わって、令和4年度から新たに導入されました。
倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)及び国際関係法(私法系)から一科目選択します。


選択科目は司法試験で出題されていたんだけど、予備試験でも出題されるようになったんだ。
司法試験本試験でも同様の科目があることから、予備試験では、「基本的な知識、理解及び基本的な法解釈・運用能力並びにそれらを適切に表現する能力」があるかどうかが問われるということです。
やはり、基本を押さえて手堅く論述することが大切と言えるでしょう。
そして、法律実務基礎科目は、民事訴訟実務、刑事訴訟実務及び法曹倫理の問題が出題されますが、「法科大学院における法律実務基礎科目の教育目的や内容を踏まえつつ、民事訴訟実務、刑事訴訟実務及び法曹倫理に関する基礎的素養が身に付いているかどうかを試す出題」とされています。
法科大学院を卒業せずに司法試験を受けられるだけの力があることを試すのが予備試験ですから、出題趣旨を踏まえると、法律実務基礎科目が最も重要な試験と言えるとも思われます。
しかし、得点配分は、法律実務基礎科目だけが特別に高いわけではなく、法律基本科目と同様に50点満点です。
したがって、法律実務基礎科目に、特別に力を入れて対策をしなければならないわけではありません。
令和5年(2023年)の予備試験論文式試験の合格点(合格ライン)は245点でした。
その他、過去13年間の合格点を確認してみまとょう。
| 2011年(平成23年) | 245点 |
| 2012年(平成24年) | 230点 |
| 2013年(平成25年) | 210点 |
| 2014年(平成26年) | 210点 |
| 2015年(平成27年) | 235点 |
| 2016年(平成28年) | 245点 |
| 2017年(平成29年) | 245点 |
| 2018年(平成30年) | 240点 |
| 2019年(令和元年) | 230点 |
| 2020年(令和2年) | 230点 |
| 2021年(令和3年) | 240点 |
| 2022年(令和4年) | 255点 |
| 2023年(令和5年) | 245点 |
13年間の合格点の平均は、235.3点となっています。試験年度にもよりますが、500点満点中50%の250点を超えていれば、合格できる試験と言えそうです。
なお、論文試験でも短答式試験と同様に、最低ライン点(足きりライン)は設けられていません。
そのため、得意科目で高得点をとって、苦手科目の失点をカバーするという戦略も成り立ちますが、予備試験合格後の司法試験最終合格を目指すなら、苦手科目は作らず、どの科目も満遍なく得点できるようにしておくべきでしょう。
論文答案の書き方に不安がある方は、アガルートの論文答案の書き型講座がおすすめです。こちらの記事で徹底的に解説をしているのでよかったら参考にしてください。
論文試験は、短答式試験と違い、得点がはっきりとわかるわけではなく、どのように採点しているのか分かりにくい面があります。
ただ、「令和4年11月29日司法試験予備試験考査委員会議申合せ事項」により、採点方法が公表されているので確認しておきましょう。
採点方針は次のようになっています。
・優秀答案は、50点から38点
・良好答案は、37点から29点
・一応の水準の答案は、28点から21点
・不良答案は、20点から0点
・白紙答案は、0点
また、各ランクの分布割合の目安が次のように公表されています。
・優秀答案は、5%程度
・良好答案は、25%程度
・一応の水準の答案は、40%程度
・不良答案は、30%程
そして、論文式試験において受験をしていない科目が1科目でもある場合は、それだけで不合格とされています。
以上を踏まえると、論文式試験全科目を受けることは言うまでもありませんが、どんなに苦手科目でも、何かすら書いておけば、得点にはなりますので、白紙で答案を提出すべきではないと言えるでしょう。
その上で、各科目とも、一応の水準の28点から21点を目指すべきだと言えるでしょう。
全科目、一応の水準の上位28点を得点できれば、合計280点になりますから、どの年度でも合格点を超えます。
もしも、1科目で0点を取ってしまったとしても、9科目で28点を得点できれば、合計252点ですから、年度によっては合格点を超えられるわけです。
予備試験論文式試験の各年度の最高得点が公表されています。次のとおりです。
予備試験論文式試験の各年度の最高得点
| 2011年(平成23年) | 302.68点 |
| 2012年(平成24年) | 308.52点 |
| 2013年(平成25年) | 312.03点 |
| 2014年(平成26年) | 318.23点 |
| 2015年(平成27年) | 325.61点 |
| 2016年(平成28年) | 331.89点 |
| 2017年(平成29年) | 335.45点 |
| 2018年(平成30年) | 332.82点 |
| 2019年(令和元年) | 333.22点 |
| 2020年(令和2年) | 358.94点 |
| 2021年(令和3年) | 351.14点 |
| 2022年(令和4年) | 360.73点 |
| 2023年(令和5年) | 363.40点 |
最高得点の一覧から言えることは、全科目優秀答案を取って合格した人はいないということです。
全科目優秀答案だとすると、最低で380点です。論文試験合格者の上位の人でさえ、それは無理だということです。
もちろん、正確な得点配分は分かりませんが、最高得点を取った人でも、全科目の平均は、良好答案の範囲でしかありせん。
全科目優秀答案を目指すことは、現状は非常に難しく、現時点で達成した人はいない。また、全科目良好答案を目指すことさえも、かなり大変であろうことが伺えます。
こうしたことを考えると、全科目平均して一応の水準の答案を目指すことが、現実的な戦略と言えるでしょう。
もちろん、優秀、良好答案を目指せる科目は、目指した方がより確実に合格点を超えられますので、得意科目は、さらに伸ばしつつも、苦手科目を作らず、苦手意識がある科目も、一応の水準を目指すべきでしょう。
論文式試験では、まず問題文を読み、論点を見つけ、構成を考えて、文章を書き出す作業を1科目1時間10分で行わなければなりません。
短答式試験は時間との戦いですが、論文式試験は短答式試験以上に、時間に余裕がありません。
過去問や資格予備校の答練を利用して、時間切れにならずに書き上げられるよう練習しておくべきでしょう。
そして、特定の科目だけに絞って優秀、良好答案を目指すのではなく、どの科目も平均して、一応の水準の答案を書けるようにしておきましょう。
どんな問題が出されても手堅く論文を書けるようにしておくことが、論文式試験突破のカギとなると言えます。
そして、予備試験に本気で合格をしたい方には、お勧めしたい講座があります。


このカリキュラムは予備試験に合格するために必要な講座が
全て揃ったカリキュラム!
この講座を使い切れば、予備試験合格レベルに到達できるように設計されています。
予備校との出会いによって、一気に合格に近づく人も少なくありません。多くの合格者を輩出しているアガルートの看板カリキュラムで予備試験に挑戦してみませんか?
少しでも気になったひとは、以下の記事を必ずチェックしてください。あなたの学習が激変します!
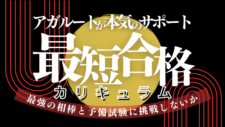
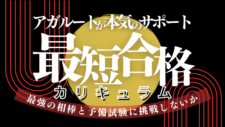
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。