
【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!
司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF
※閉じるとこの案内は7日間再表示されません
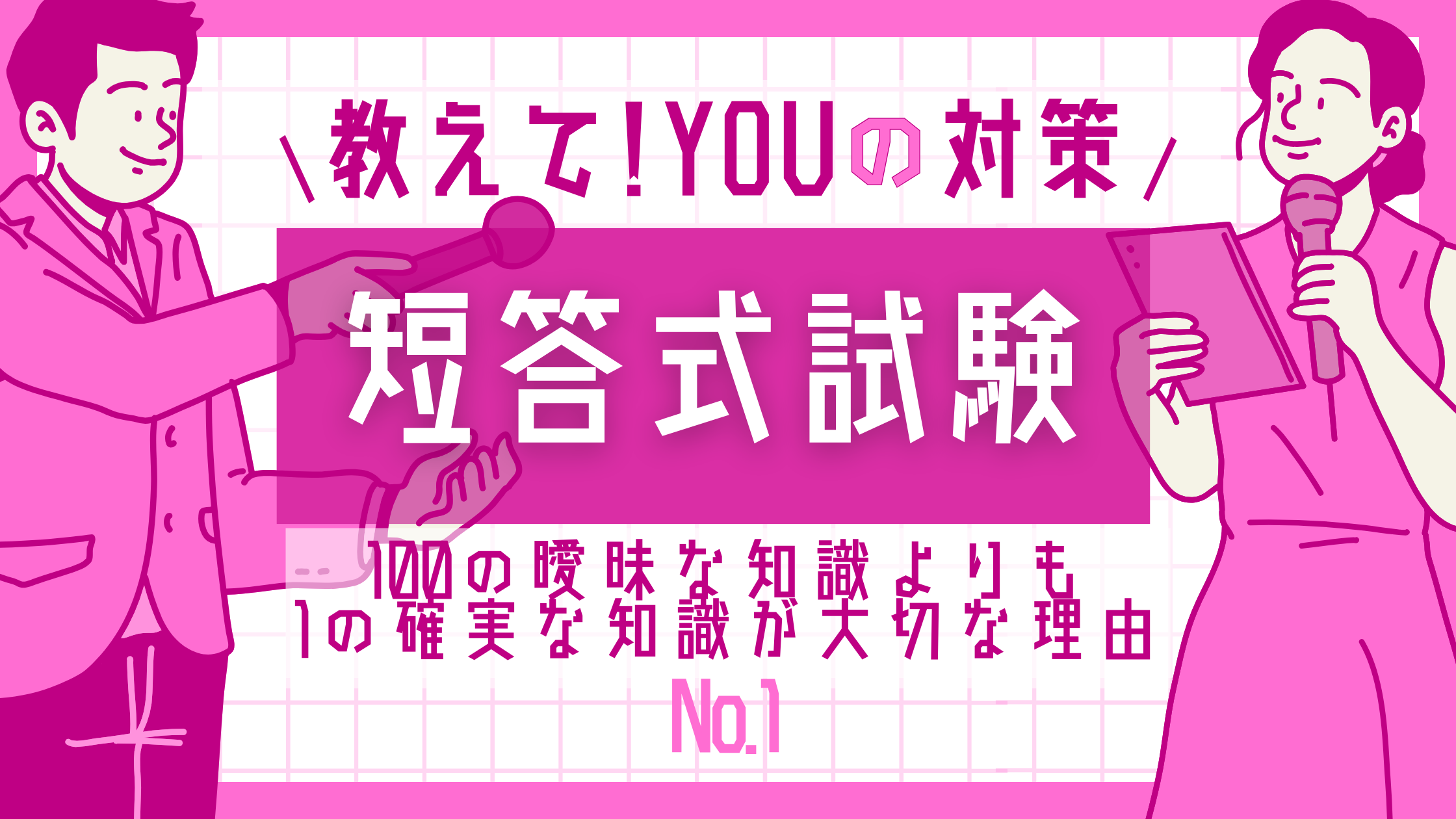
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?


短答の対策をする際に「ほかの人ってどうやってるのかな?」と思うことはありませんか?
今回は、令和7年度司法試験の短答式試験で「合格者平均点」を獲得された方へのインタビューを通じて、その具体的な対策法をまとめた記事です。
法スタでは、短答式試験の目標点を「合格者平均点」に設定することを推奨しています。まさにその基準を達成された方々にご協力いただき、実際にどのように学習を進めてきたのかを“短答対策レポート”として執筆していただきました。
質問項目はこちらで整理しましたが、回答はすべて合格者ご本人の体験に基づくリアルな声。机上の空論ではなく、合格を勝ち取った受験生の生きた勉強法が詰まっています。
短答式試験対策に悩んでいる方にとって、必ずヒントになるはずです。ぜひ本企画を参考に、ご自身の学習計画に取り入れてみてください。



まず「回答者の基本情報」を、見ていきましょう!



今回は、どんな人が解答してくれたのかな?



やあ、法律を学ぶみんな!
今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!



そうなのそうなの〜!
受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨



特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!



あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱
お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!
📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】
司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!
現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。
\ このタイミングを逃す手はありません /
合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。
経歴を教えてください
※出身ロースクール、既修or未修、修了年度、受験回数、予備試験の合否、受験歴など。匿名性確保の観点で難しい場合には、記載されておりません。



経歴を教えていただきました!
<経歴>
・2019年4月 東京大学 教養学部理科二類 入学
・2024年3月 東京大学 文学部人文学科 卒業
・2025年1月 司法試験予備試験 最終合格
・2025年7月 司法試験受験(初受験)
※予備試験短答は12位(218点)で合格
今回の短答式試験の結果を教えてください
総合得点、各科目の得点、合格者平均点との比較など
| 科目 | 点数 |
|---|---|
| 憲法 | 33点 |
| 民法 | 69点 |
| 刑法 | 43点 |
| 総得点 | 145点 |
・順位:42位
・合格者平均点:110.6点
※法スタ編集部において上記得点を獲得されたことを成績通知書で確認済みです。
短答式試験対策全体は、どのような「方針・戦略」で臨まれましたか
各科目のバランス、重点科目の設定、時期別の対策方針など
私は予備試験短答に向けてしっかり勉強した貯金があったので、司法試験短答に向けてはあまり勉強時間を割きませんでした。
そのため、以下の記述は予備試験短答のために行った勉強に関するものがメインとなりますので、ご了承ください。
ただし、司法試験短答と予備試験短答は、科目数が違うだけで、基本的に勉強方法は同じですので、ロースクール生の方にもご参考になると思われます。
さて、本題に入りますが、私は短答対策全体を通して、『短答を軽視しない。極端に言えば、論文対策よりも短答対策を重要視する。』というマインドセットで勉強しておりました。その理由は3つあります。
まず1つ目の理由は、短答に出てくる知識は、論文を解くための土台として必要であることです。
世間一般的には、短答は重箱の隅をつつくような細かな知識を問うていると思われています。しかし、その考えは誤解であり、実際に短答の過去問をみれば、論文に活きるような基礎知識を問うていることが分かるのではないかと思います。(ただし、予備試験短答に限っては、下4法(行政法・民訴法・商法・刑訴法)で細かな知識が問われることも多いですが。)。
つまり、短答の勉強は論文の勉強に“直結”するので、短答に本腰を入れて勉強できると良いのではないかと考えます。例えば、令和7年司法試験論文憲法では、珍しく、選挙権に関する出題でした。論文対策ばかりしていた受験生は表現の自由や職業選択の自由などの頻出分野ばかり勉強していたため、非常に困ったと思います。
しかし、短答の勉強にしっかり取り組んでいた受験生は、選挙権についての十分な知識があったと思うので、それほど困らなかったと思います。
次に2つ目の理由は、短答でライバルとの間でついた差を、論文で逆転するのは至難の業であることです。
世間一般的には、論文の方が短答よりも配点が大きいため、論文に重点を置いて勉強するべきだと主張する人もいます。一理はありますが、私はその言葉を鵜呑みにすべきではないと考えます。
なぜなら、短答知識が十分な人の論文と短答知識が不十分な人の論文では、当然ながら前者の人の答案の方が正確な記述がなされている可能性が高いからです。
冷静に考えれば当然のことですが、以上の理由から短答をおろそかにしない方が良いと考えます。
最後に3つ目の理由は、短答は論文と異なり、確実に点数を上げる方法が存在するので、コストパフォーマンスが良いということです。
短答は論文と異なり、過去問がそのまま再出題されたり、民法の条文がそのまま出題されたりするため、正しい勉強方法さえわかっていれば、確実に高得点を取れます。その詳しい勉強方法は後述します。
以上の理由から、私は短答対策に重点を置いて勉強していました。
憲法は、どのような勉強法を取られましたか
使用教材、勉強方法、重点分野、条文対策、判例対策など
①伊藤塾入門講座基礎マスター憲法
(予備校が出している基本書は試験に出るところだけ記述されているのでオススメです。信頼できる基本書であれば、何でもいいと思います。)
②体系別短答式過去問集憲法(早稲田経営出版)
③伊藤塾司法試験模試
④ポケット六法
第1 「伊藤塾入門講座基礎マスター憲法」の使い方
その際に、以下の2つの作業をする。
1つ目は、論点の問題提起部分を読んだ後、目を閉じて、頭の中でその論点の通説と学説のそれぞれについて、結論と理由づけと代表的判例を思い出すという作業をする。
例えば、刑法総論において(憲法対策についての説明をしていますが、説明のし易さの観点から、刑法総論を具体例として使います)、因果関係の論点の問題提起部分をみたら、頭の中で「たしか、相当因果関係説や危険の現実化説や客観的因果関係説があったよな〜。そして、それぞれの説のメリット・デメリットは〜だよね〜。そして、大阪南港事件判例や米兵ひき逃げ事件判例は危険の現実化説で判断してたな〜。一方で、被害者を突き倒して被害者の持病である脳梅毒が相まって死亡した判例は客観的因果関係説で判断してたな〜」と想起します。
想起できたところは印を外す。
私はこの方法で勉強し、最終的には、伊藤塾入門講座基礎マスター憲法を10周ほどしました。
第2 「体系別短答式過去問集憲法」の使い方
間違えた選択肢だけでなく、解答の理由が瞬時に想起できなかった選択肢にも全てに印をつける。
上記と同様に、間違えた選択肢だけでなく、解答の理由が瞬時に想起できなかった選択肢全てに印をつける。一方で解答の理由まで瞬時に想起して正解できた問題から印を外す。
私はこの方法で勉強し、最終的には、体系別短答式過去問集憲法を6周ほどしました。
第3 「伊藤塾司法試験模試」の使い方
模試を通じて、時間配分の練習をするとともに、試験の緊張感に慣れましょう。
第4 「ポケット六法」の使い方
人権分野は現場思考問題や難問が出題されることが多いです。しかし統治分野は、条文を知っていれば、安定的に得点できる分野なので、統治分野は重点的に勉強しましょう。
そのために、憲法条文の統治分野を諳んじられるくらい暗記してしまいましょう。ここの暗記はきついかもしれませんが、ここさえ乗り越えれば憲法の得点も安定してくるので、頑張って乗り越えましょう。
民法は、どのような勉強法を取られましたか
使用教材、勉強方法、重点分野、判例・条文対策など
①伊藤塾入門講座基礎マスター民法
(予備校が出している基本書は試験に出るところだけ記述されているのでオススメです。信頼できる基本書であれば、何でもいいと思います。)
②体系別短答式過去問集民法(早稲田経営出版)
③伊藤塾司法試験模試
④ポケット六法
基本的に上記憲法の勉強方法と同じです。そのため、異なるところだけお伝えします。それは、「体系別短答式過去問集民法」と「ポケット六法」の使い方についてです。
まず、「体系別短答式過去問集民法」では、問題を体系的に考えながら解くことを意識してください。
例えば、過去問で「抵当権に物上代位性があるか○か×か」という問題に出会ったら、「あれ、じゃあ同じ典型担保物権の留置権には物上代位性はあるのかな〜?」と考える癖をつけるというようなことです。
次に、「ポケット六法」では、「共同抵当と根抵当権と根保証のところ」以外は、条文番号を見れば、どんなことが書かれているかある程度思い出せるようになると良いです。
刑法は、どのような勉強法を取られましたか
使用教材、勉強方法、重点分野、判例・学説対策など
①伊藤塾入門講座基礎マスター刑法
(予備校が出している基本書は試験に出るところだけ記述されているのでオススメです。信頼できる基本書であれば、何でもいいと思います。)
②体系別短答式過去問集刑法(早稲田経営出版)
③伊藤塾司法試験模試
④基本刑法Ⅱ各論(大塚ら著、日本評論社出版)
⑤ポケット六法
基本的に上記憲法・民法の勉強方法と同じです。そのため、異なるところだけお伝えします。
「基本刑法Ⅱ各論」は、もともと予備試験口述試験対策用に頭に叩き込みましたが、本書は「伊藤塾入門講座基礎マスター刑法」に載っていない部分についても詳しく書いており、司法試験の短答式試験に役立ちました。
例えば、令和7年司法試験短答刑法では、暴力団に所属していることを隠してゴルフ場の利用申し込みをすることが詐欺罪の欺罔行為に当たるかという点が問われましたが、基本刑法Ⅱ各論にはこの論点の記載があったので、難なく解答できました。
短答対策で使用された、主要な教材を教えてください
過去問集、問題集、基本書、予備校教材、アプリなど
それぞれの教材を、どのように活用されましたか
できる限り詳しくご説明ください
短答対策で使用した教材及び教材の活用方法は上述のとおりです。
過去問対策は、どのように行われましたか
開始時期、回転数、分析方法、復習方法など
過去問の回転数、分析方法、復習方法は上述のとおりです。
また、過去問演習の開始時期については、私は予備試験短答に向けて勉強した際の知識貯金があったので、司法試験1ヶ月前から過去問演習を始めて、試験当日までに各科目10年分を2周演習するだけで足りました。
膨大な短答知識を定着させるために、どのような工夫をされましたか
暗記方法、復習スケジュール、まとめノートの作成、知識整理の方法など
暗記方法には3つコツがあると思います。
まず1つ目は、結論のみ覚えるのではなくて、制度の目的・条文の趣旨・結論を導く理由を理解することを大事にすることです。そうすることで、記憶に定着しやすいですし、応用問題にも対応しやすくなるためです。
次に2つ目は、同じ教材を使うということです。いろんな教材に浮気するよりも、1つの信頼できる教材を何回も読み込んだ方が、記憶の定着に良いと思います。
最後に、教材をできるだけ短期間に高速周回することです。エビングハウスの忘却曲線によると、1度理解した知識を完全に忘却する前に思い出す作業をすると知識が長期記憶に入るそうです。
(ただ、私は両親に衣食住を揃えてもらえるという非常に恵まれた環境にありましたので、大変ありがたいことに1日24時間勉強に充てることが可能という特殊な環境にいたため、上述のような高速周回学習が可能であったと思います。通常はそれほど時間を取れない人の方が多いと思いますので、各人の可能な範囲で高速周回を意識して勉強されれば大丈夫だと思います。)
資格予備校や通信講座は利用されていましたか
利用されていた場合は、どの講座をいつから利用され、どのように活用されましたか
利用していない場合は、独学でどのように勉強を進められたか教えてください
伊藤塾入門講座の利用を「2022年10月」から開始しました。
利用方法は、与えられたカリキュラム通りにこなしただけです。また、司法試験直前には伊藤塾の司法試験模試を受講しました。
短答対策と論文対策をどのようにバランスを取って進められましたか
時期別の配分、相互の活用方法など
私は予備試験短答に向けて勉強した際の知識貯金があったので、司法試験1ヶ月前までは「短答」と「論文」の勉強時間比率は0:10でしたが、そこから司法試験当日までの1ヶ月間は比率は6:4くらいでした。
試験直前期(試験3ヶ月前〜当日まで)はどのような対策を行われましたか
総復習方法、新しい問題への取り組み、メンタル管理など
上述のとおり、予備試験短答合格後から司法試験1ヶ月前まで、一切短答対策はしませんでした。
今年度の短答式試験について、科目別に雑感を教えてください
問題の難易度、傾向の変化、各科目の特徴、受験当時の心境、予想との相違点など
憲法
例年以上に難化した印象でした。最新判例についての出題もありましたが、私は勉強不足で間違えてしまいました。来年の受験生には最新判例についても、一通り判決文を読んでおくことをお勧めします。
また、「伊藤塾司法試験模試」の「憲法短答」は最新判例も考慮して作問されていたので、受験してみてもいいかもしれません。
民法
例年通りの難易度でした。どれだけ過去問に真剣に取り組み、条文を読み込んだかで勝負が決まるなと感じました。
刑法
試験の出題形式に若干の変更があり、穴埋め形式の問題(旧司法試験のような?)が多くなっていました。受験当時、私はその形式変更に面食らって動揺してしまい、顔に嫌な冷や汗をかいたのをよく覚えています。
しかし、その難しい穴埋め形式の問題に固執せず、簡単な問題から解いていこうという風に、現場で柔軟に対応できたので、なんとか大失敗は防ぐことができました。来年の受験生は、穴埋め問題対策をしてもいいかもしれません。
短答式試験当日に気を付けるべきことがあれば教えてください
時間配分、マークミス対策、見直し方法、休憩時間の過ごし方、持参すべきものなど
今年度の刑法短答で出題形式が変更されたように、来年もイレギュラーがあるかもしれません。もしそうなったときに、慌て過ぎず冷静に対応することが大事です。
私のような比較的短答試験に自信のある受験生でも、試験時間中は動揺してしまいましたので、全受験生が動揺していると楽観的に考えて、心を落ち着かせてください。
短答対策で失敗したこと、もっとこうすれば良かったと思うことがあれば教えてください
私は、「伊藤塾入門テキスト」をはじめとした基本書を何周も通読してから、過去問演習を始めました。
しかし、基本書を読むことと並行して、該当箇所の短答の過去問演習をするようにすれば、基本書のどの部分が試験問題になりやすいのか意識しながら通読できるようになり、より効率的にインプットできたのではないかと反省しています。
特に効果的だったと感じる勉強法や工夫があれば、具体的に教えてください。
特に効果的だった具体的な勉強方法は上述のとおりです。
それに1つ加えると、短答対策では『100の曖昧な知識よりも、1の確実な知識』というマインドセットを持ちながら勉強した方が良いと考えます。
緊張感の高まる本番において曖昧な知識では決して太刀打ちできません。
また、例えば、選択肢が5つある中で、その中の2つの選択肢の正誤判定を確実にできれば、それ以外の3つの選択肢について分からなくても、選択肢の組み合わせの関係上、即座に解答を選べる問題が多いので、確実な知識が大変重要です。
司法試験短答式試験を迎える後輩受験生の方に、アドバイスをお願いします
司法試験短答式試験を迎える後輩受験生の皆様にお伝えしたいことは以下の4つです。
①まず、この文章を読んでくれている司法試験短答受験生の皆さんは、予備試験合格者又はロースクールで2〜3年間もの間一生懸命勉強されてきた人なはずです。そのため、短答式試験を受験できること自体が凄いことです。それをぜひ誇りに思っていただきたいです。
②次に、短答試験の勉強は砂を噛むような単調な勉強になりがちで辛い時期があると思います。私もそんな時期を嫌というほど経験しました。でも、そんな時こそ、それを楽しむ自分なりの工夫と根性で乗り切って欲しいなと思います。
③次に、短答試験の本番では、その試験時間の短さから、おそらく緊張したり汗が止まらなくなったりすると思います。そんな時は、高得点を取るような人でもみんなと同じように冷や汗かいていることを忘れないでください。
④最後に、繰り返しになりますが、兎にも角にも短答式試験は、『100の曖昧な知識よりも、1の確実な知識』を大事にしてください。
お伝えしたいことは以上となりますが、この文章が少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。応援しています!
法スタでは、今回ご紹介した記事以外にも 短答対策に役立つ記事を多数ご用意しています。
試験勉強を進めるうえでのヒントや、得点力を高めるコツをわかりやすくまとめていますので、ぜひあわせてチェックしてみてください。
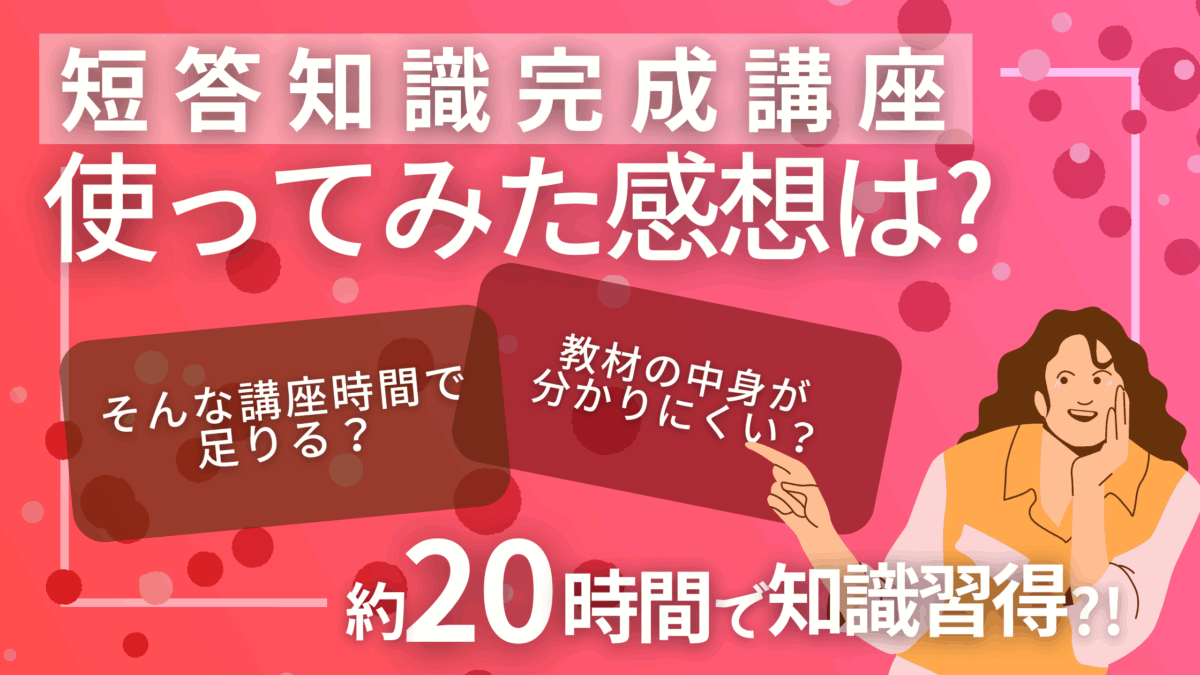
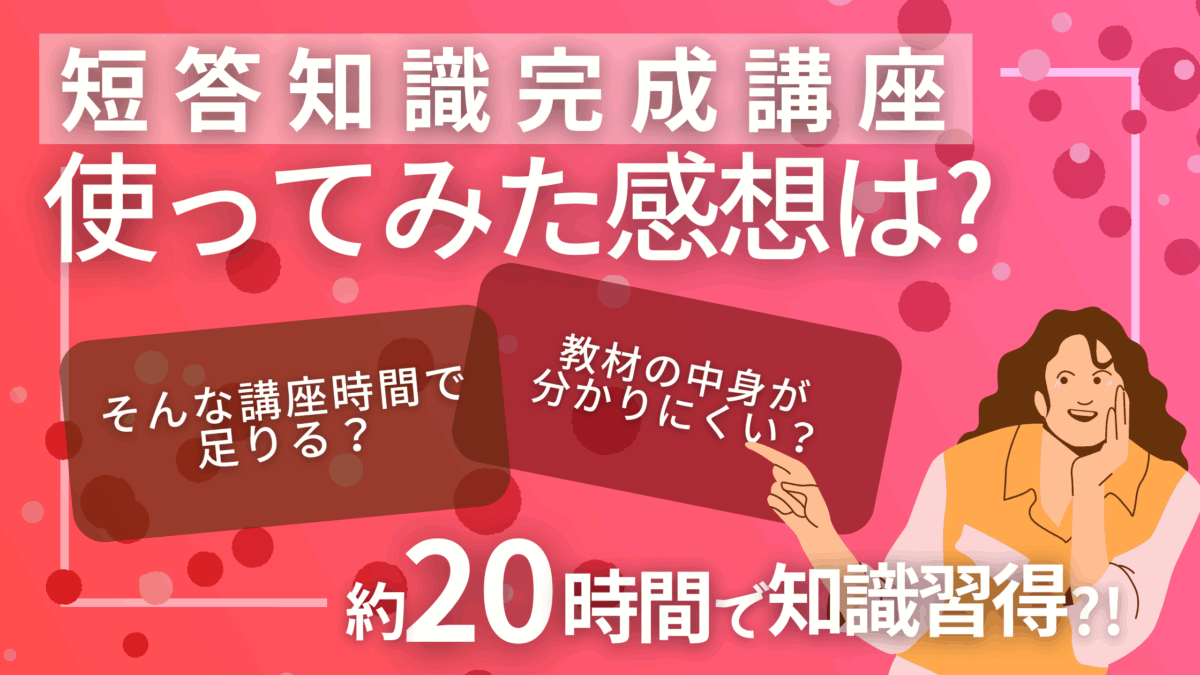
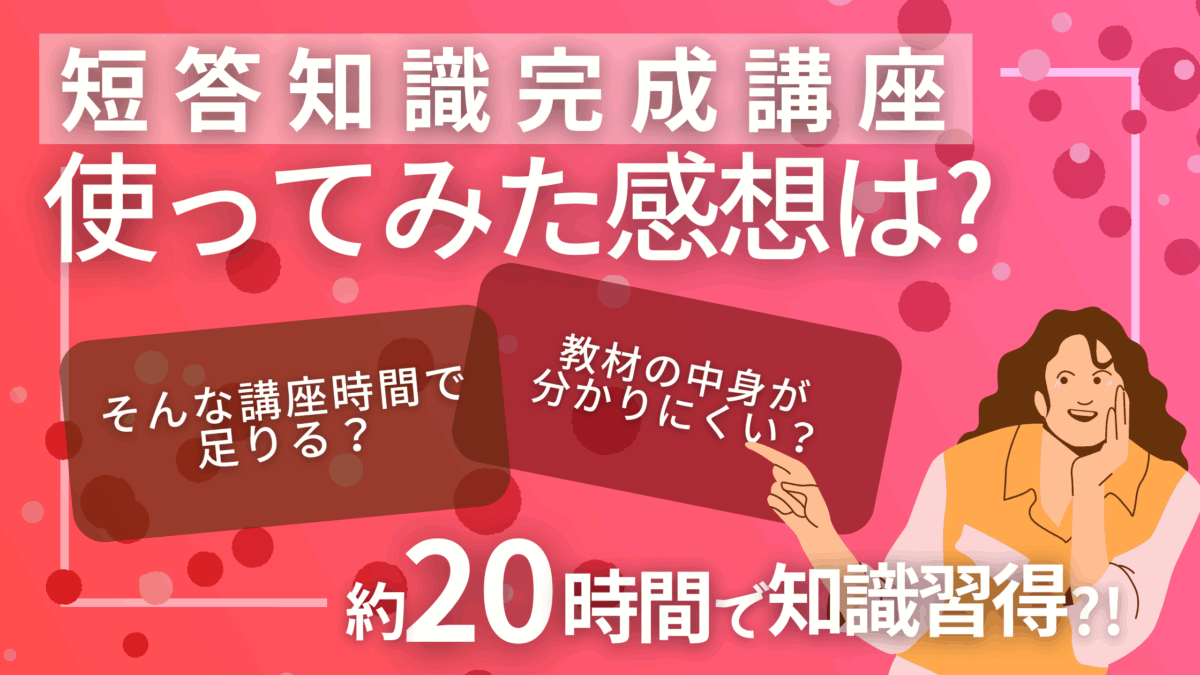









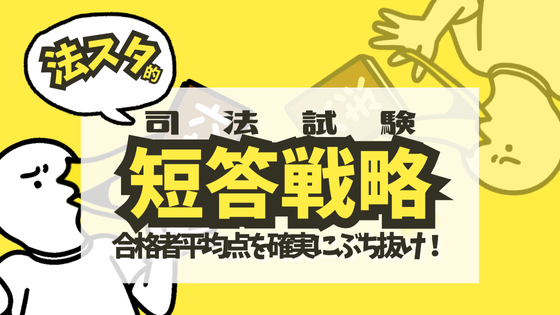
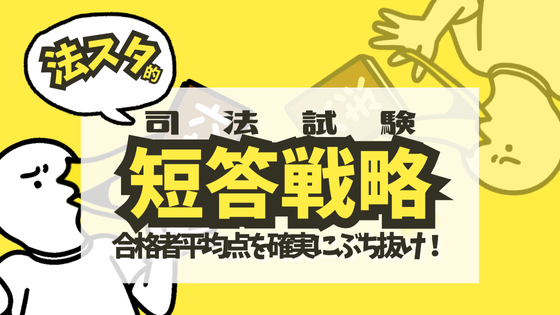
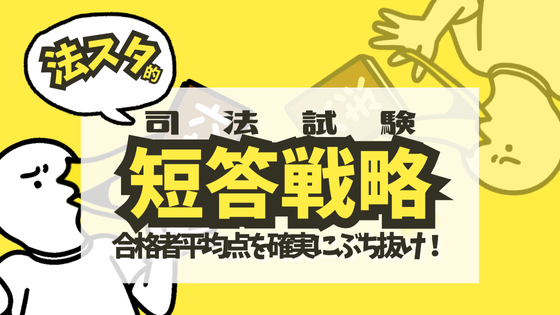
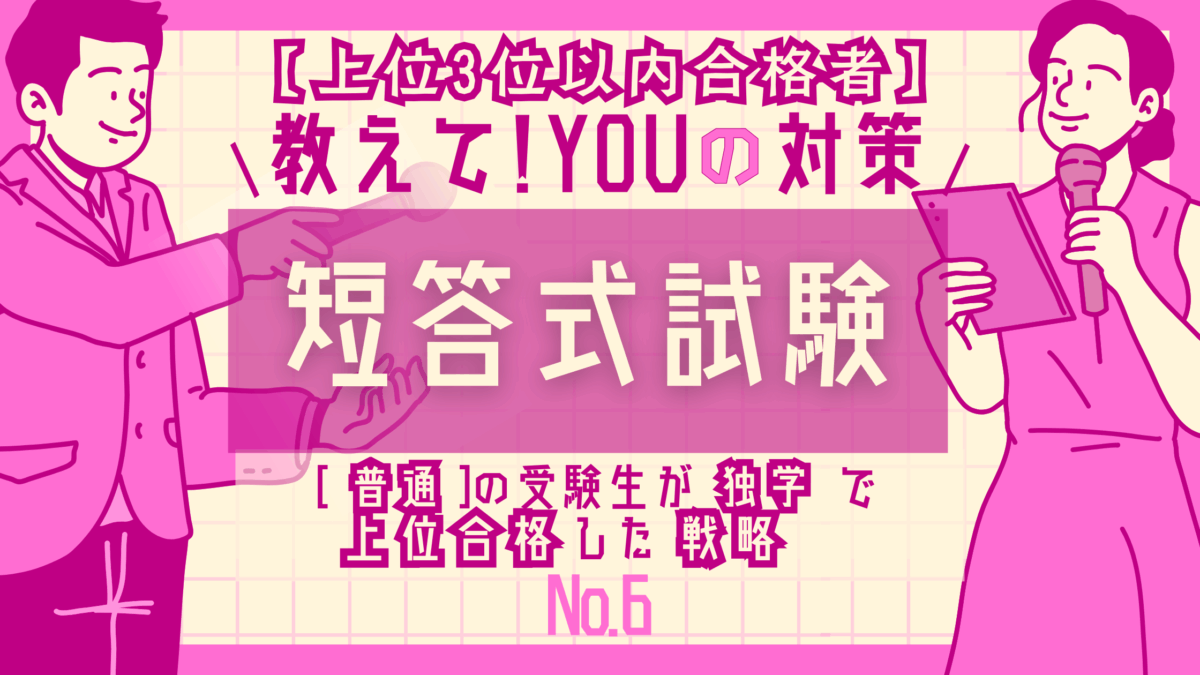
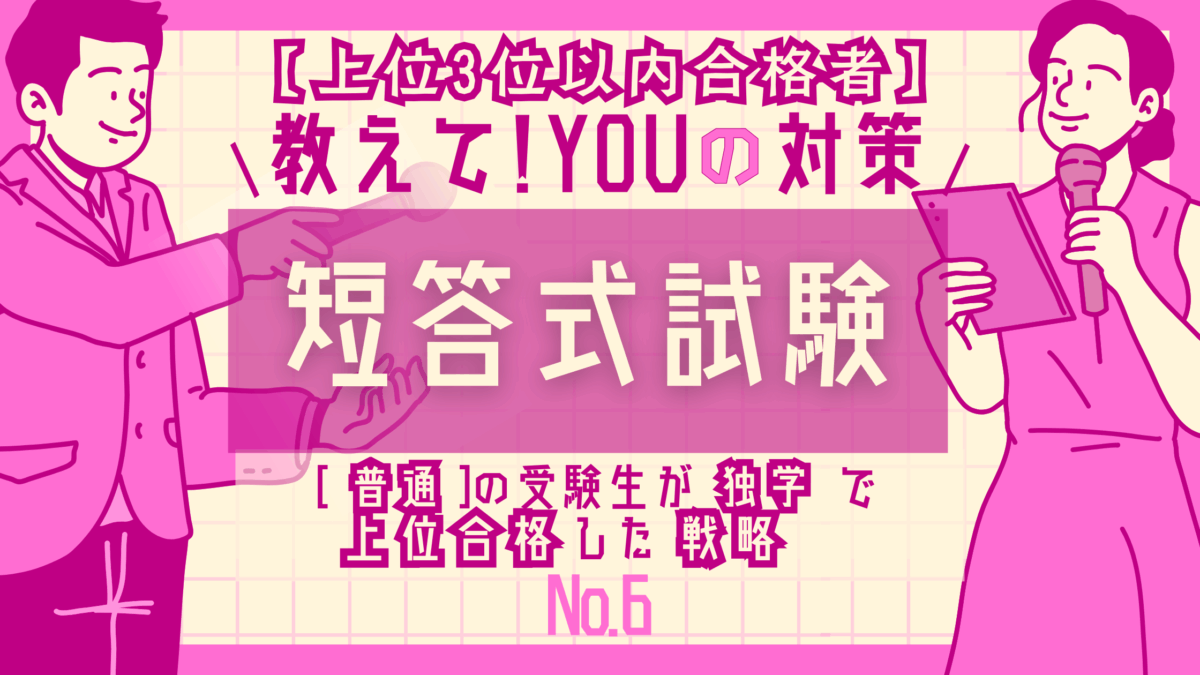
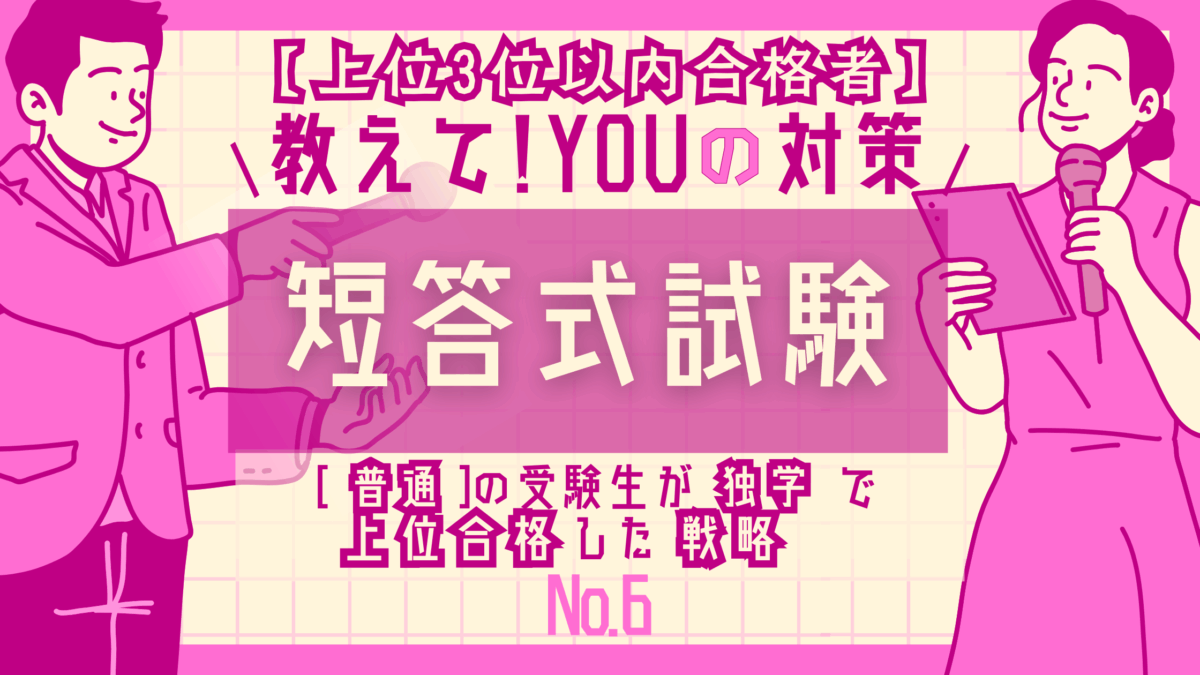
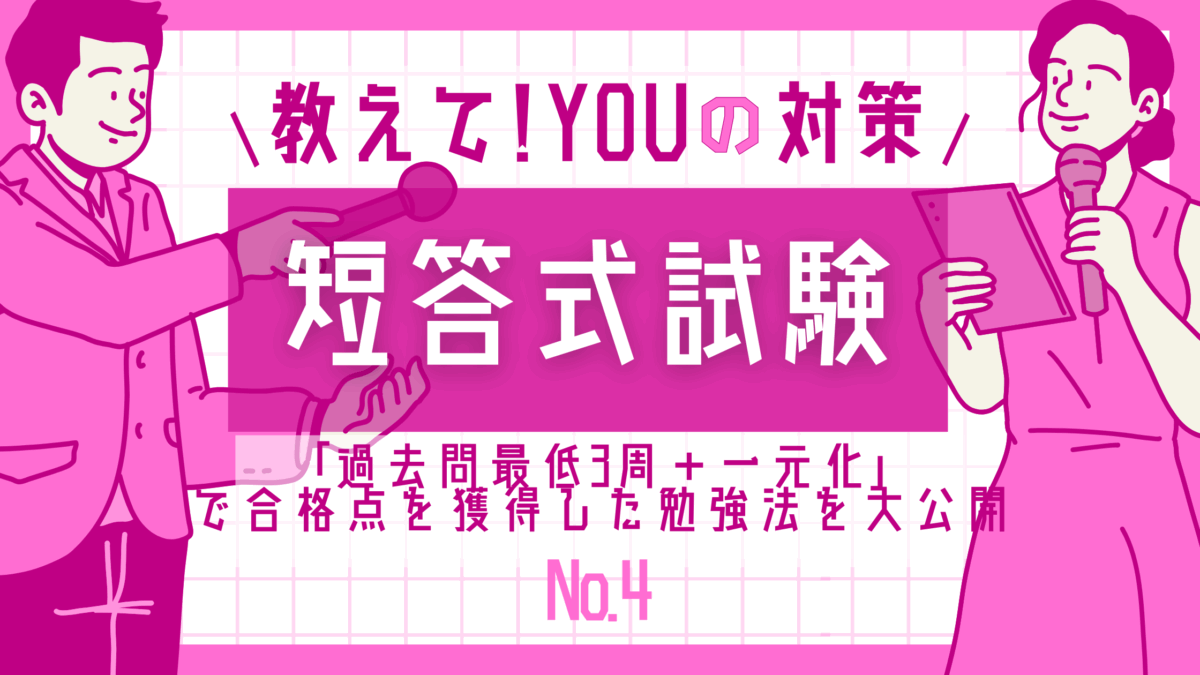
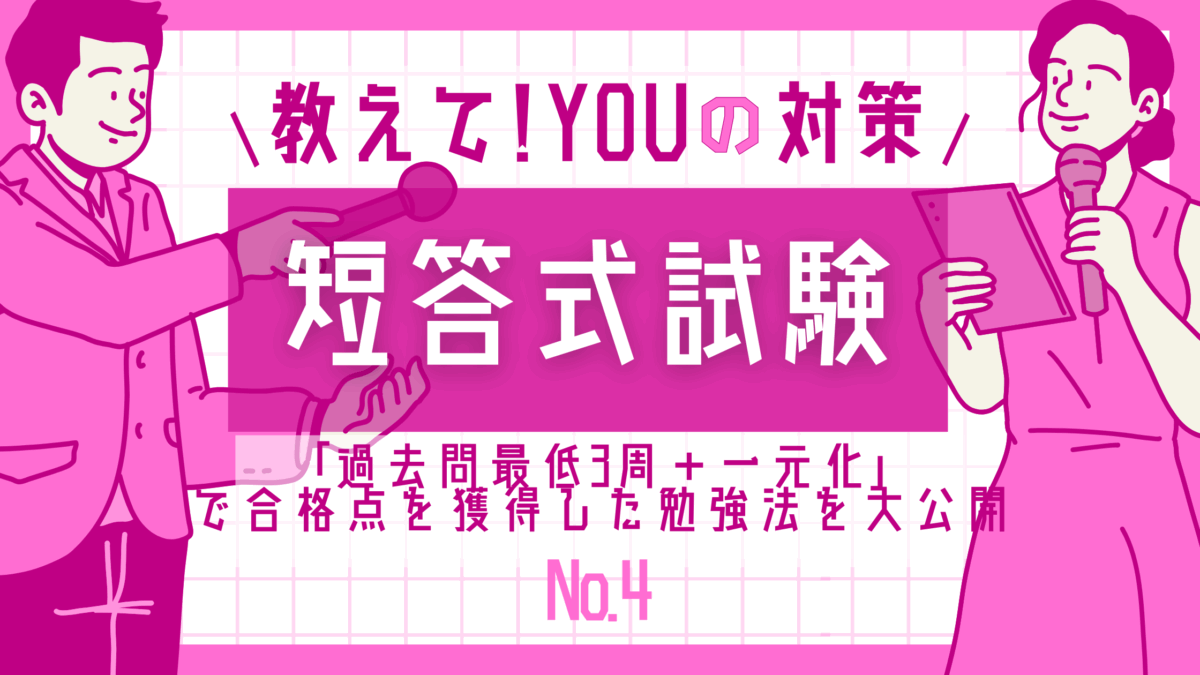
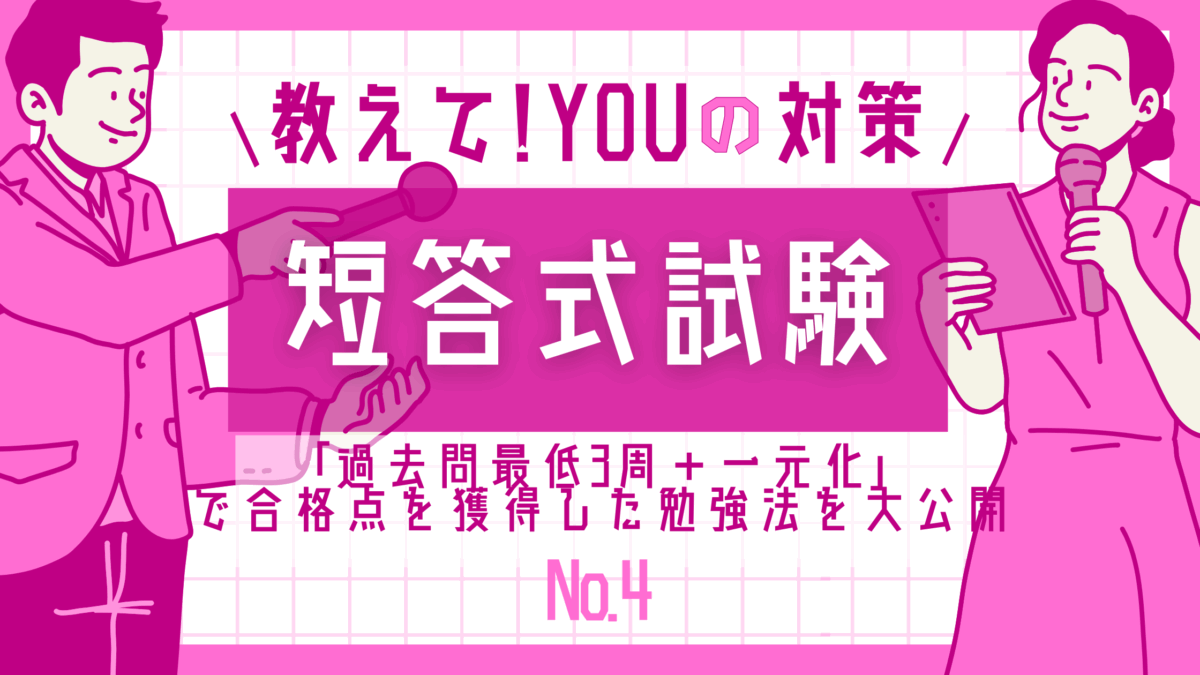
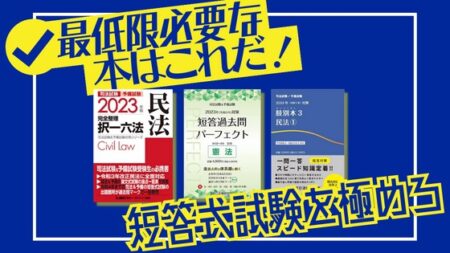
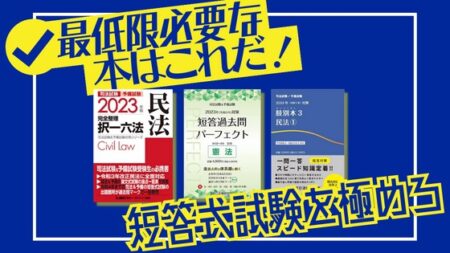
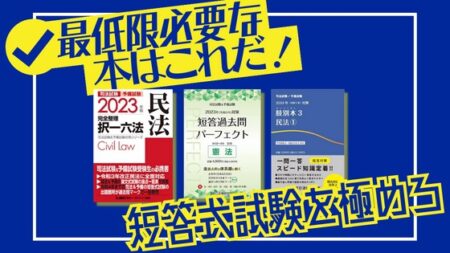
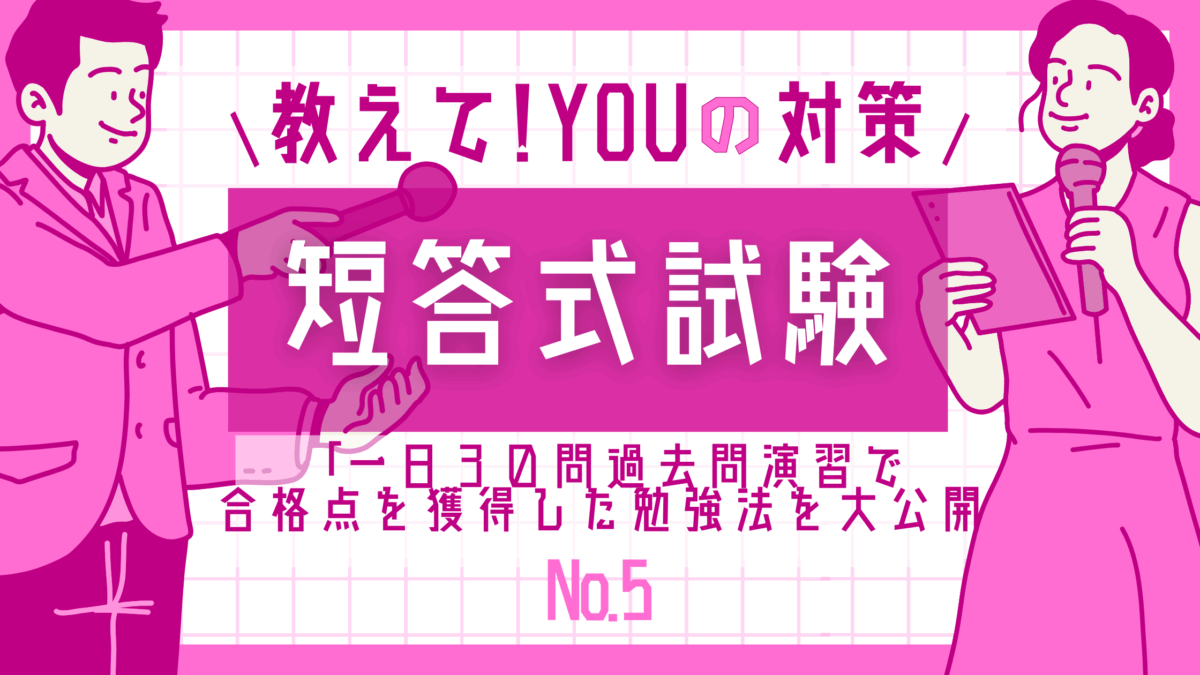
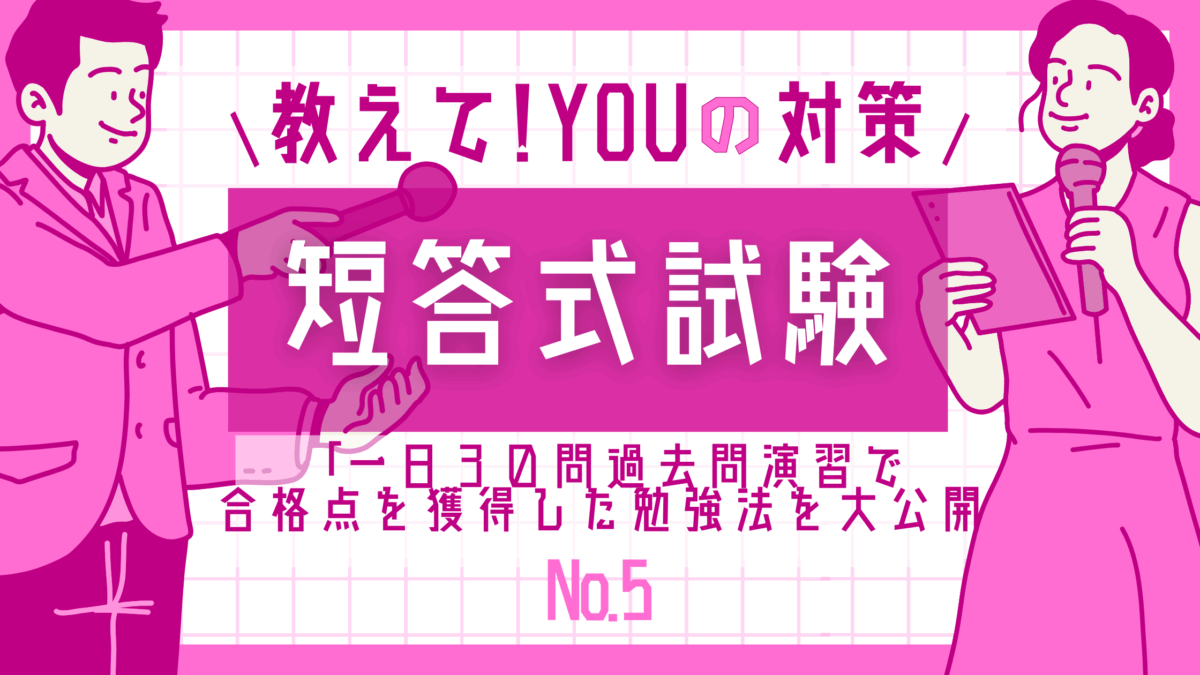
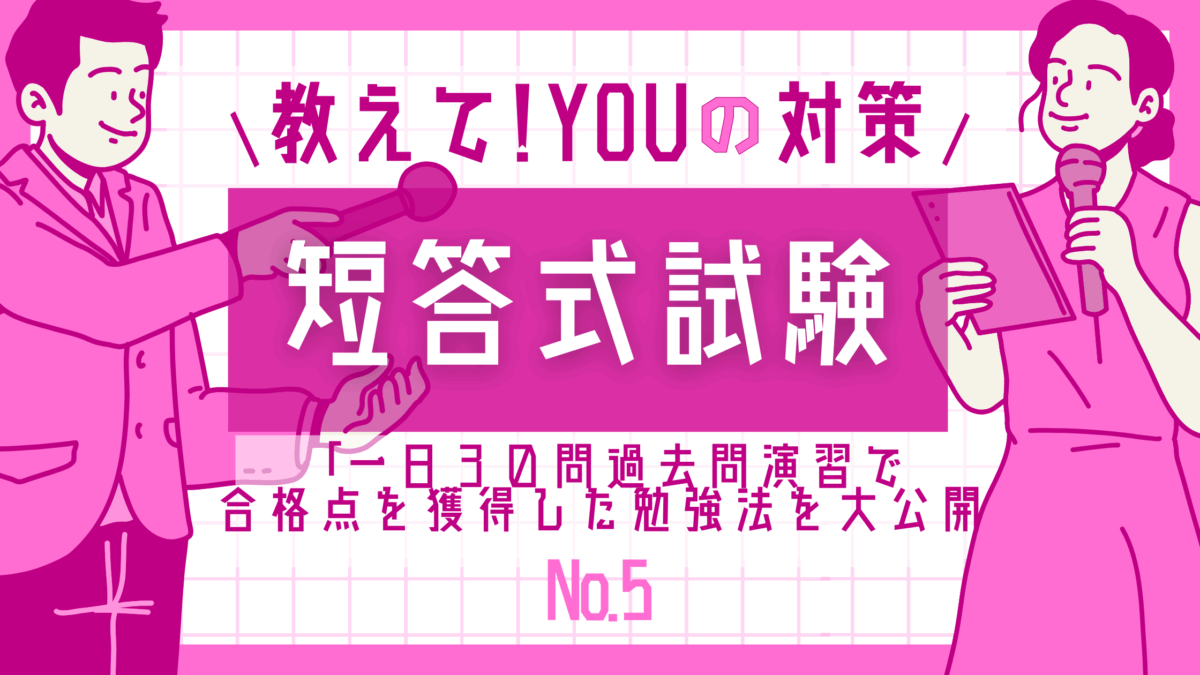
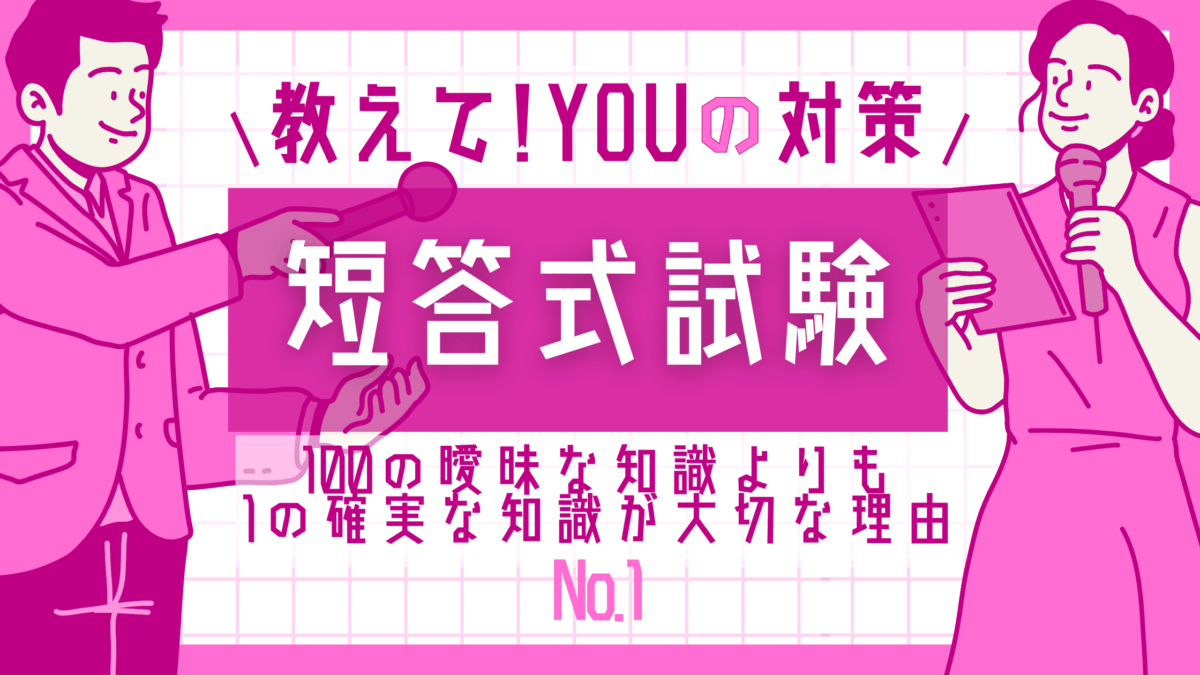
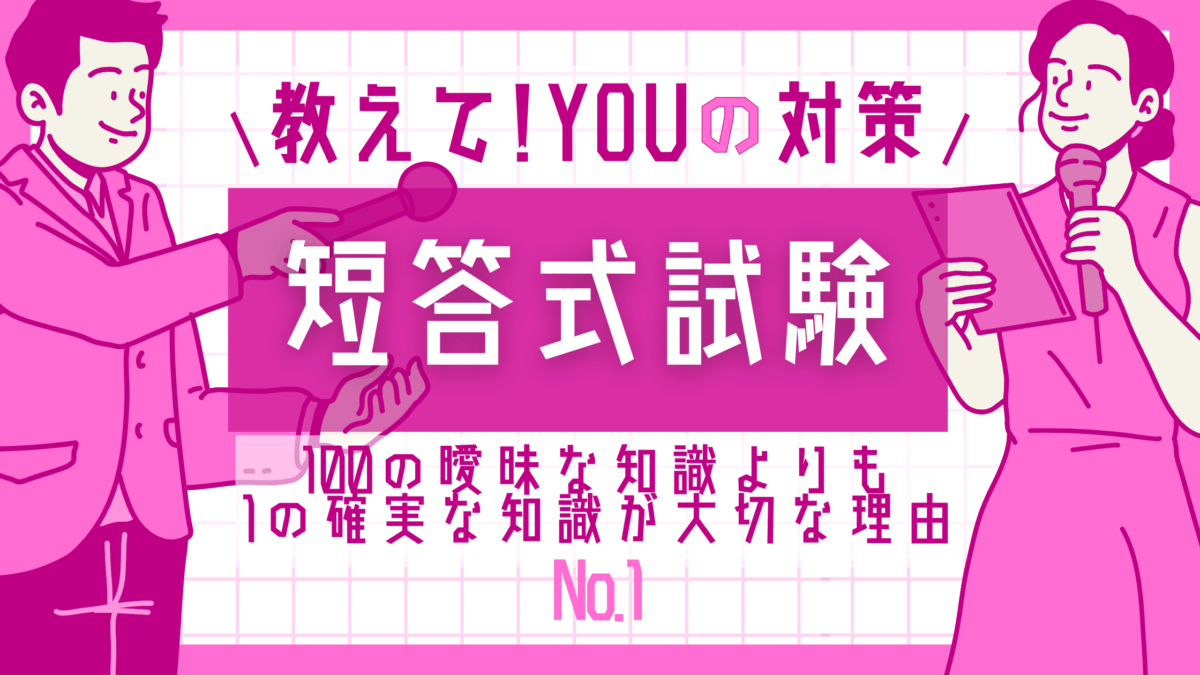
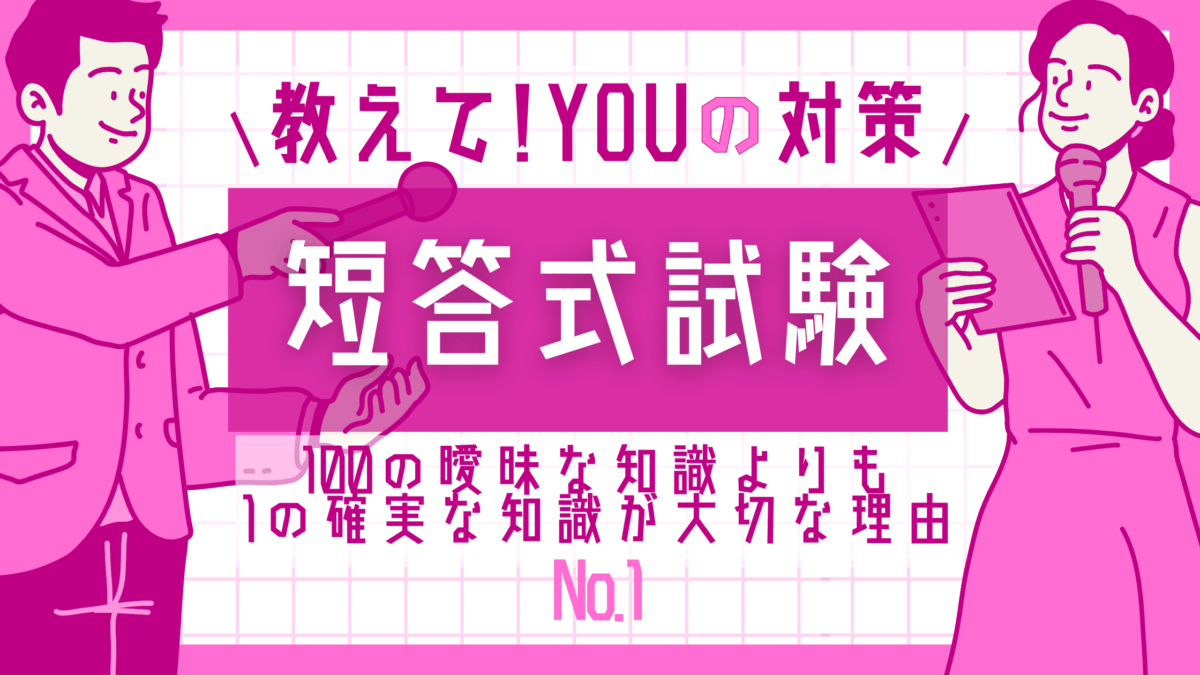
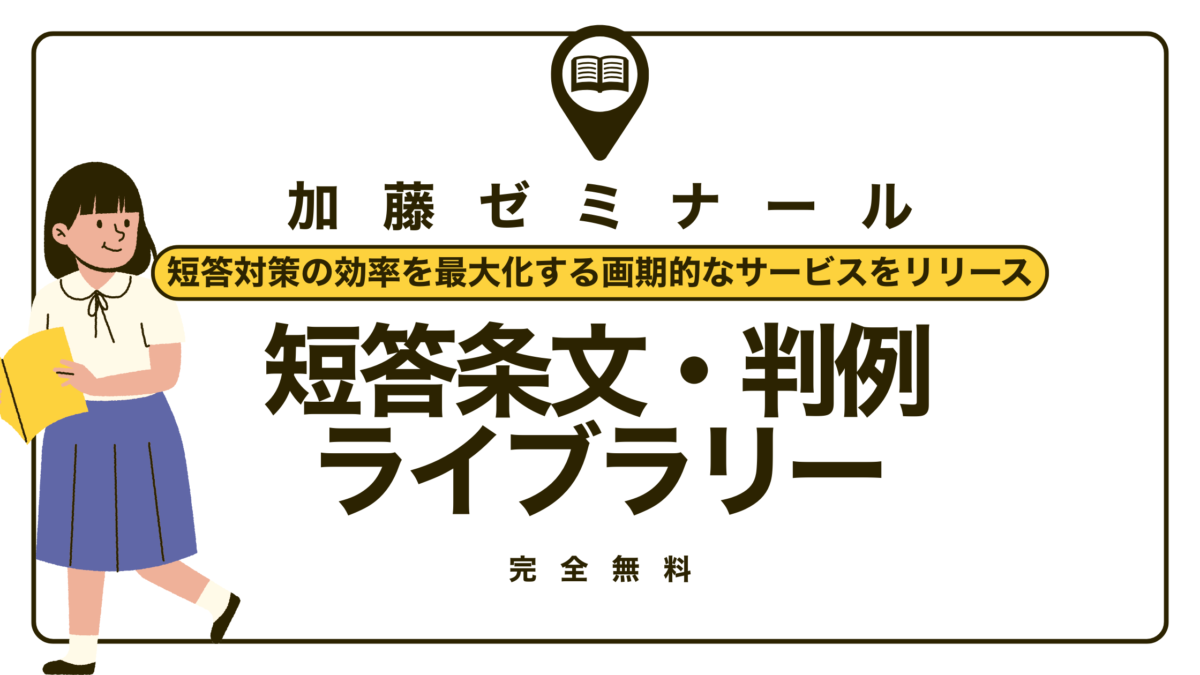
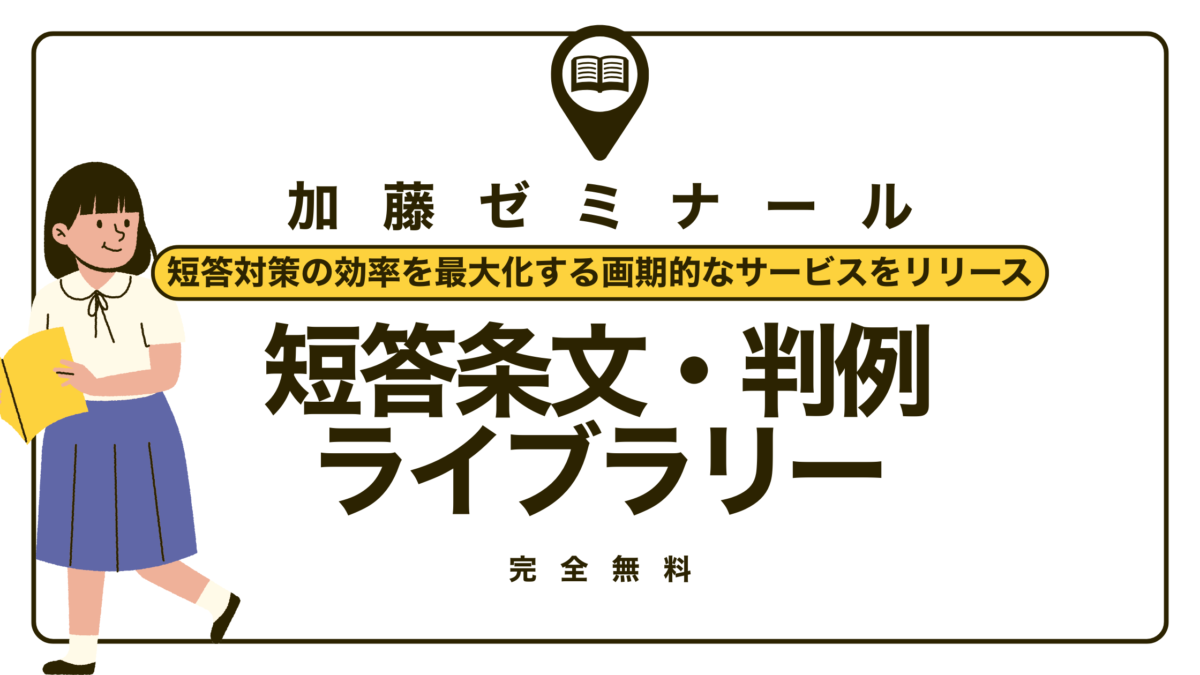
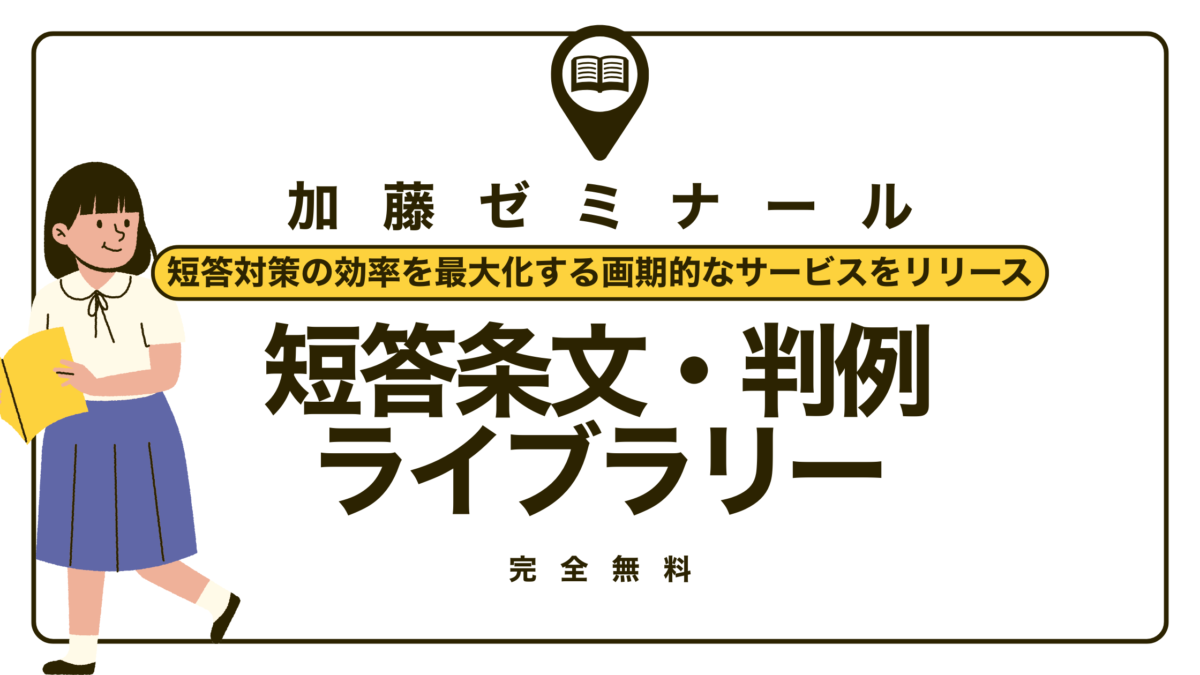
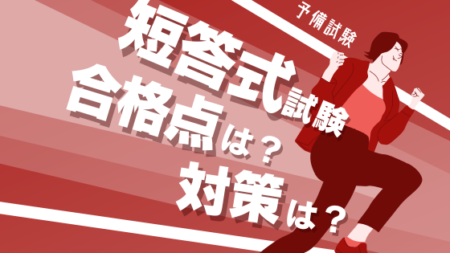
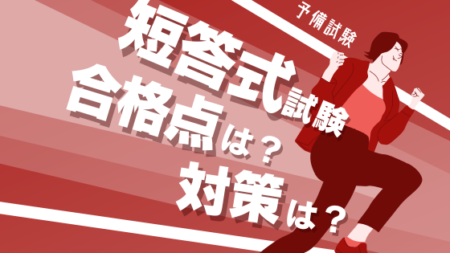
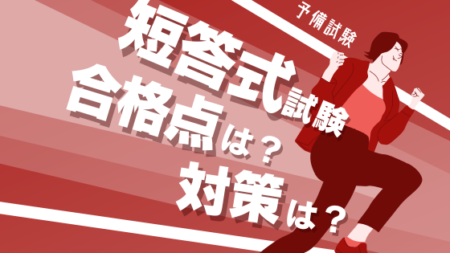
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
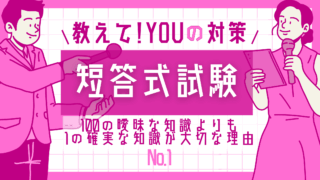
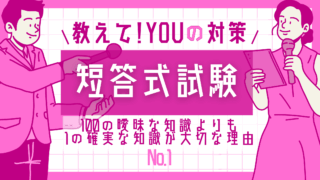
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

