
【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!
司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF
※閉じるとこの案内は7日間再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?


司法試験への挑戦は人生を大きく変える決断です。
「法曹への道」は決して平坦ではありませんが、「正しい勉強法と環境」を揃えれば、必ず道は開けます。



司法試験ってやっぱり人生かける覚悟がいるんだよねぇ…



そうだな。でも、その覚悟があるからこそ、合格したときの景色は格別だぞ。
本記事では、司法試験の基本情報から実践的な学習戦略まで、合格に必要な全てを網羅的に解説します。



やあ、法律を学ぶみんな!
今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!



そうなのそうなの〜!
受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨



特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!



あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱
お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!
📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】
司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!
現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。
\ このタイミングを逃す手はありません /
合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。
まずは、司法試験の基本的情報から整理します。
司法試験は「短答式試験」と「論文式試験」の2つの試験で構成されています。
短答式試験(満点175点)
ポイントは「短答式試験」は「憲法、民法、刑法」の3科目だけという点です。



えっ、「短答」って3科目だけなんだ!
もっとあると思ってた〜



そうだ。
でも範囲は広いし、正確さが求められるから侮れない。近年は、難易度が上がっていて、足切りを食らう受験生も少なくないんだ。
論文式試験(満点800点)
最終的な得点は「短答式試験の得点+論文式試験の得点×1400/800」で算出され、配点比重は短答1:論文8となります。この配点からも分かるように、司法試験は論文式試験が圧倒的に重要です。
「配点割合」は「短答1:論文8」つまり司法試験の山場は論文式試験です



「論文」の方が、比重めちゃくちゃ大きいんだねぇ…



そう。「短答」も大事だけど、山場はやっぱり「論文」だ。
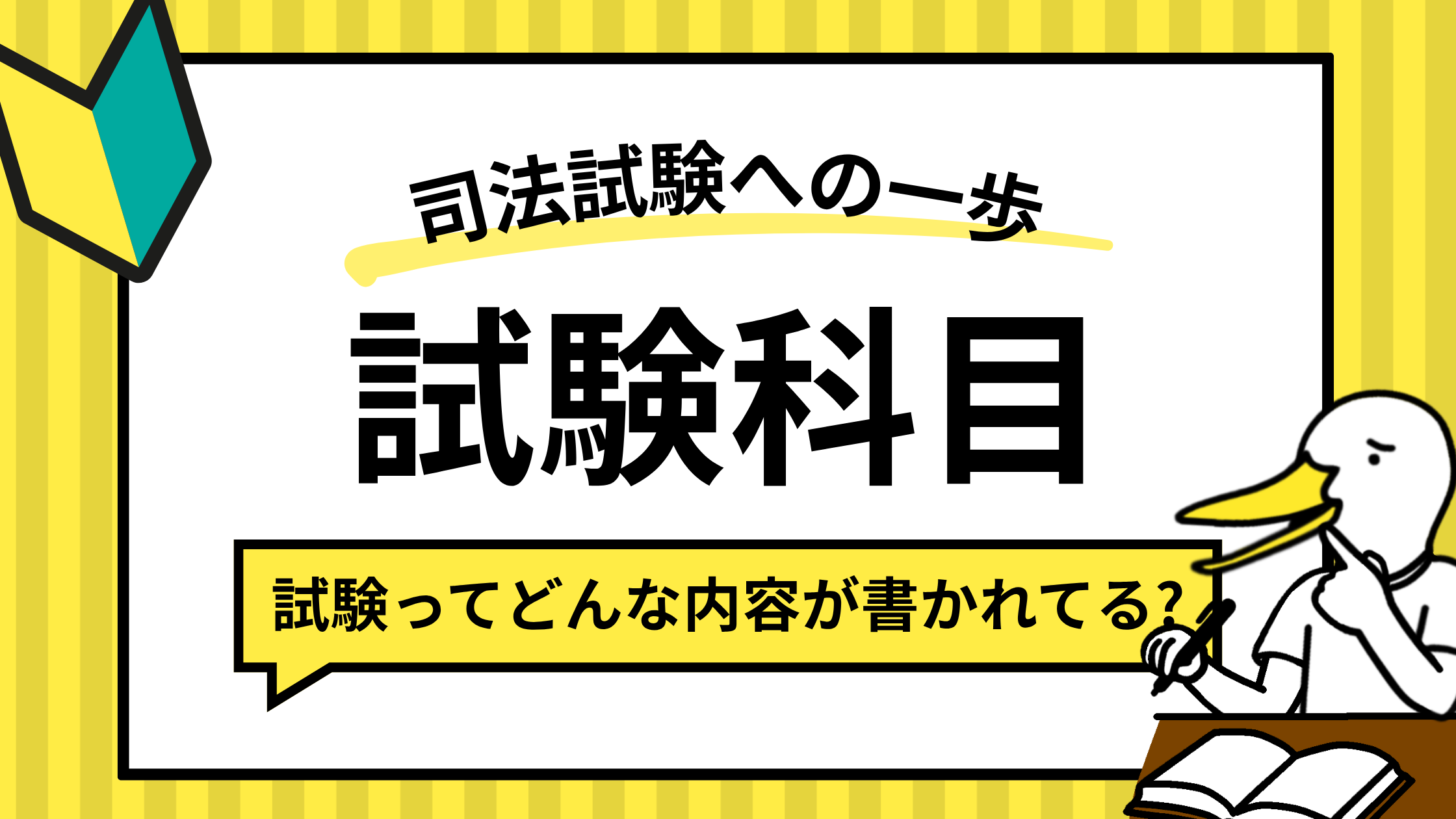
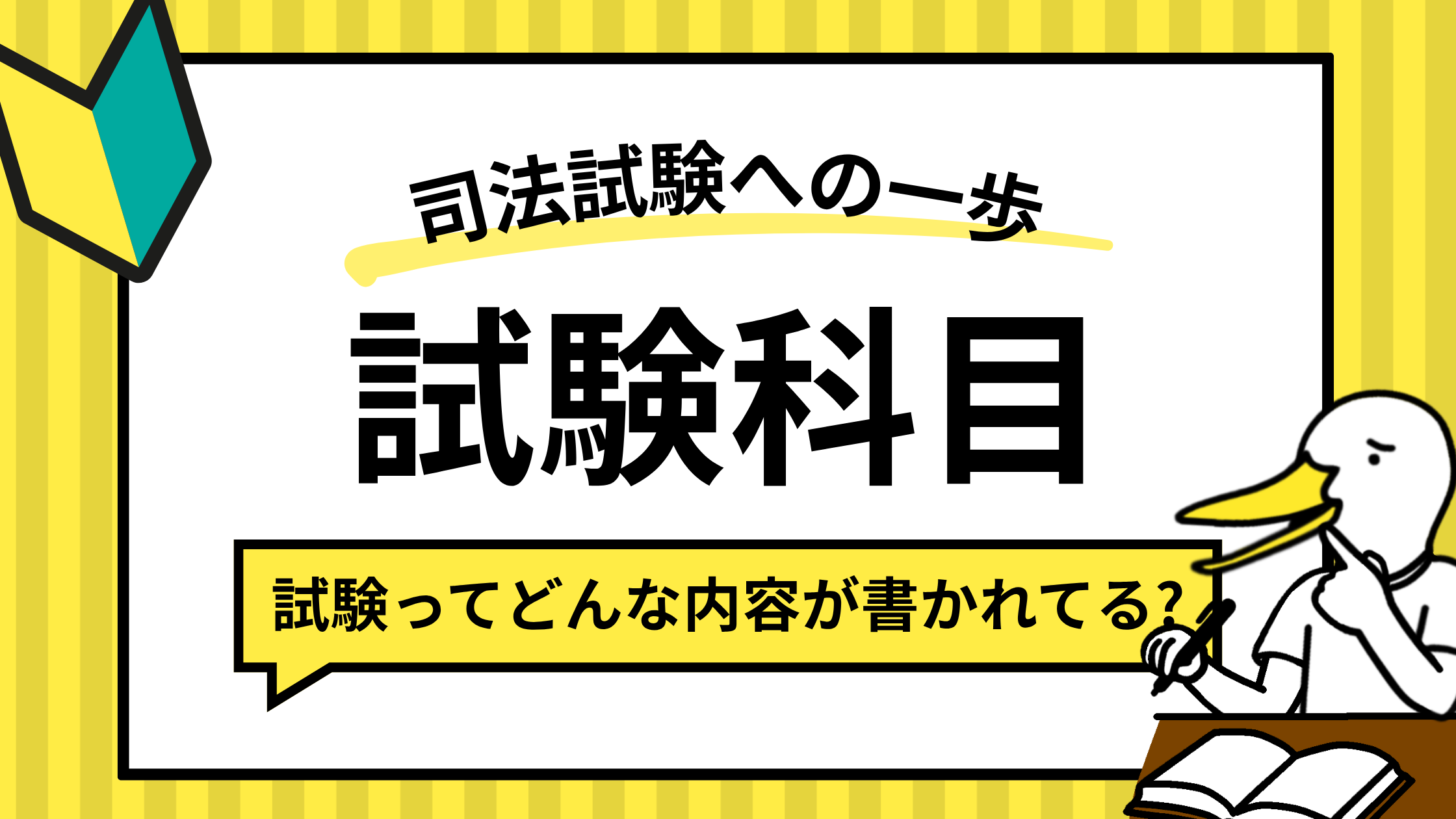
司法試験は毎年7月中旬に実施されます。
論文式試験が1日目・2日目・3日目、短答式試験が4日目、計4日間(中日をいれる5日間)にわたって行われ、合格発表は11月上旬に行われます。
出願は例年3月から4月上旬にかけて行われ、受験手数料は28,000円です。
合計5日間(中日の1日を含む)で司法試験が行われます。かなり体力的にもハードな試験となっています。



5日間も試験漬けなんて、体力もメンタルも削られそう…



だからこそ、普段から体力作りや生活リズムも大事なんだ。
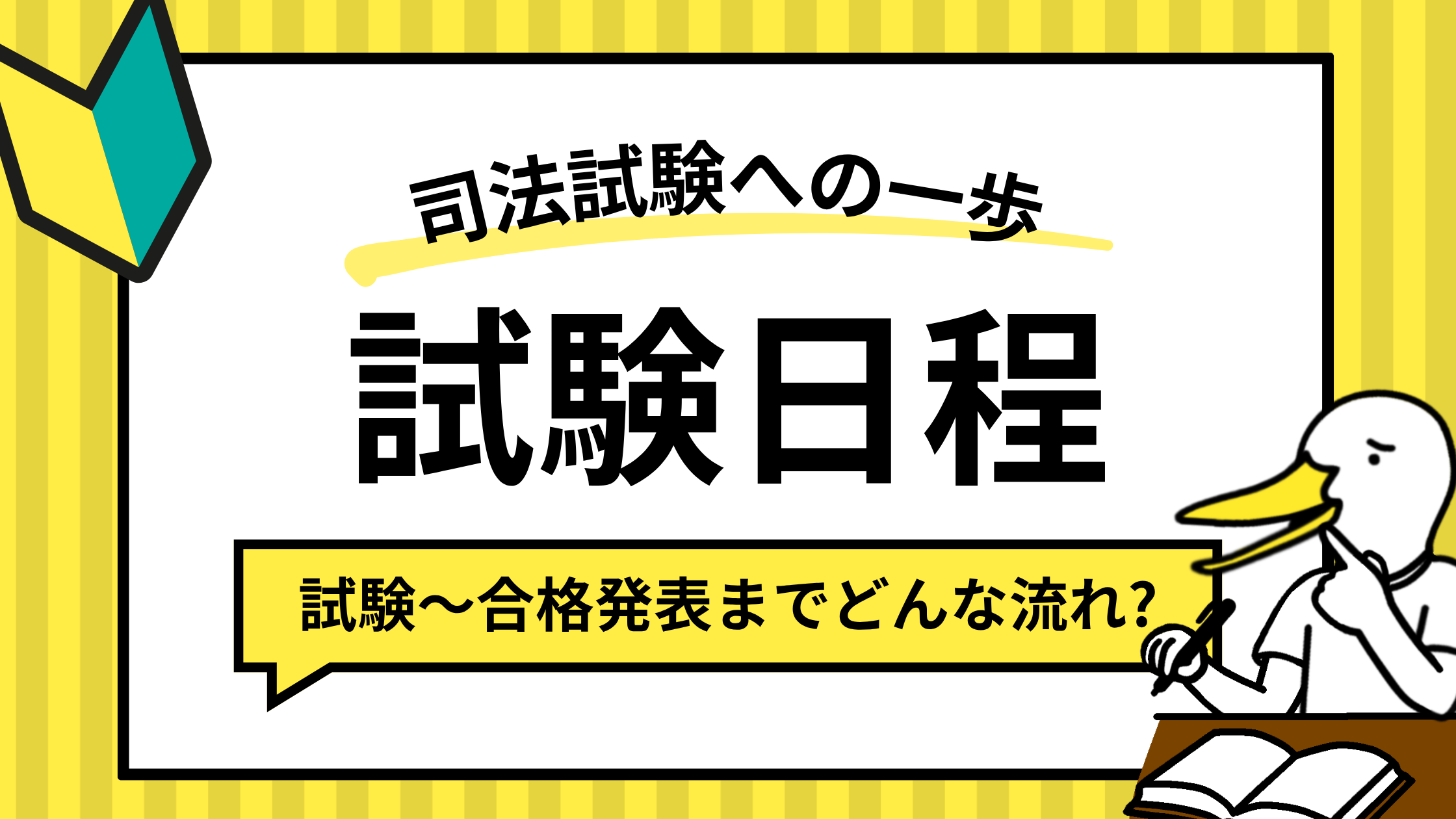
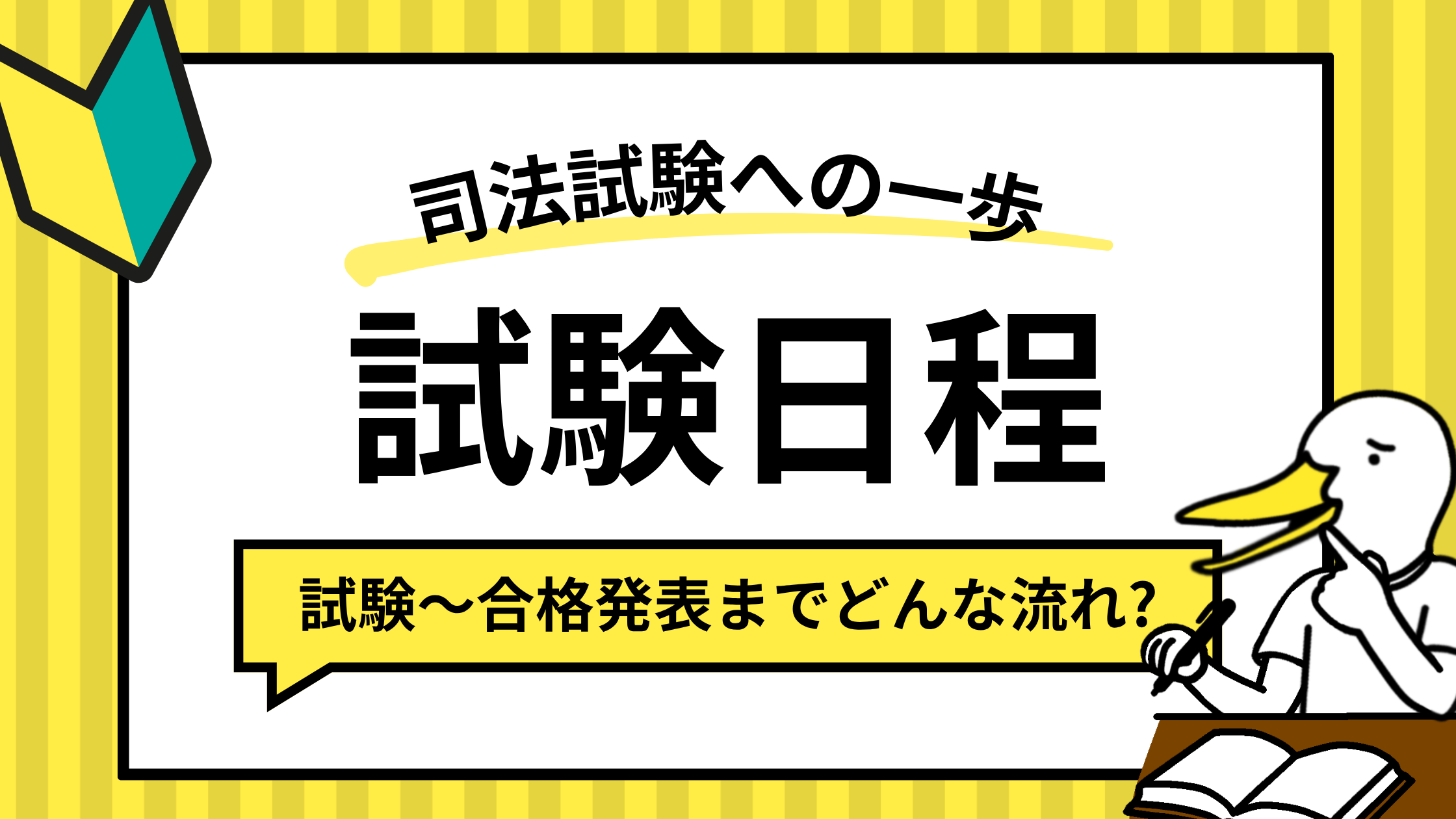
司法試験を受験するには、以下のいずれかの資格が必要です。
1. 予備試験合格ルート
2. 法科大学院修了ルート
司法試験の受験資格は、①予備試験に合格すること、②法科大学院を終了すること(在学中受験は可能)の2つだけです。受験資格が制限されており、誰でも受験できるわけではありません。
どちらのルートを選ぶかは個人の状況によりますが、予備試験合格の難易度を考えると、「法科大学院ルート」の方が合格可能性が高いと言えます。
そのため、基本的には、法科大学院ルートを検討し、経済的制約又は時間的制約がある方は予備試験ルートを検討するのが良いでしょう。



予備試験の合格率って4%!? これは…狭き門だ



だから多くの人はロー(法科大学院)ルートを選ぶんだ。




短答式試験は司法試験の第一関門ですが、配点比重が低いため「確実に合格点を取ることが重要」です。



えっ、短答って一番最初の関門なんだねぇ。でも、配点は低いんだ?



「そうだ。落ちない点数を確実に取ればいい。満点狙いよりも“安定”が大事だぞ。
ここでは、短答式試験の基本方針や勉強法を紹介していますが「初学者の段階では特段の対策は不要」です。後述のとおり、最初の1年間は、基本的な事項のインプット、事例演習に注力するべきです。短答式で問われる細かな知識のインプットは、2年目以降で良いかと思いいます。



じゃあ、最初から細かい暗記ばっかりしなくてもいいってことかも?



そうだ。まずは基礎を固める方が、後で短答の点も自然と伸びるんだ。
短答式試験の合格率は70-80%程度であり、基礎をしっかり固めれば十分に合格可能です。以下の点を意識して学習しましょう。
短答対策の重要なポイント



足切りって…1科目でもめちゃ低いとアウトってやつ?



そうだ。各科目の合計点が4割未満の場合、合計得点に限らず不合格になるんだ。だから苦手をなくして、確実に合格点を狙う対策が重要になる。
憲法(50点) 憲法は条文数が少ないものの、抽象的な概念が多く、判例の知識が重要です。



憲法って条文少ないのに、なんでこんなに難しいの〜?



少ないからこそ、判例の意味や背景を深く理解しないと点が取れないんだ。
民法(75点) 民法は出題範囲が最も広く、配点も高いため重点的な対策が必要です。



範囲広すぎて、どこからやればいいかわからないかも…



基本概念から押さえて、そこから枝分かれするように整理すると覚えやすいぞ。
刑法(50点) 刑法は論理的な体系性があり、比較的学習しやすい科目です。



刑法はストーリー仕立て理解しやすいかも!



そうだ。事案をイメージしながら要件を当てはめると理解が進むぞ。
短答式試験では過去問の重要性が極めて高く、過去10年分は少なくとも3回は解くことになるでしょう。
しかし、これも最終的には「過去10年分を少なくとも3回」は解いておきたいという目標です。初学者の段階では、将来、過去問10年分を最低3回は解く必要があることを理解しておけば十分です。
□第1回転(理解重視)
□第2回転(定着重視)
□第3回転以降(実戦重視)



うわ〜、第3回転で90%って、けっこうハードル高いねぇ



3周でここまで持ってこれたら上出来だよ!
短答式試験では条文の正確な理解が不可欠です。特に以下の点に注意しましょう。
効果的な条文学習法
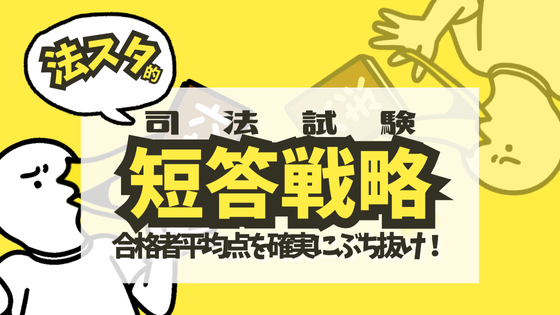
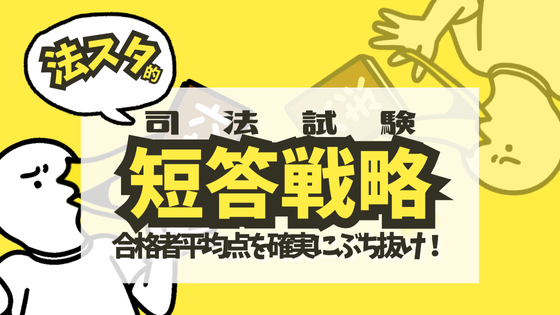
論文式試験は司法試験の核心部分であり、最も対策が困難な分野です。
しかし、体系的にアプローチすれば必ず上達します。
論文答案は以下の4つの要素から構成されています。
1. 問題提起
事案における法的争点を明確に提示する。「~が問題となる」という形で簡潔に述べる。
2. 規範定立
問題解決の基準となるルールを理由とともに示す。条文解釈や判例法理を基に論理的に導出する。
3. あてはめ
規範を具体的事実に適用して評価する。事実を単に列挙するのではなく、規範の要素に対応させて論理的に検討する。
4. 結論
問題提起に対する明確な回答を示す。「よって~」という形で簡潔に述べる。
これらの要素を意識して答案を構成することで、採点者に評価される論文を書くことができます。
詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
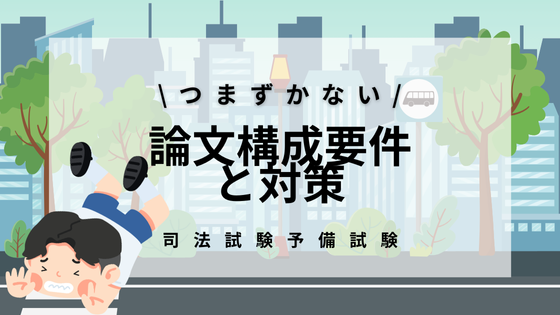
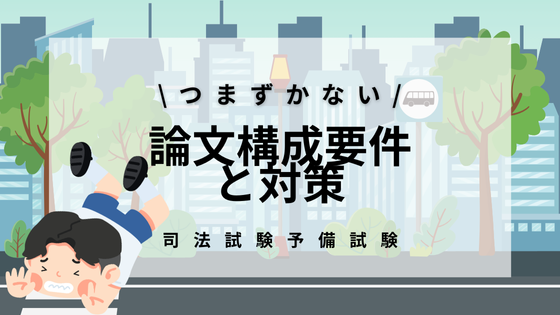
論文式試験では「半分ちょい」の得点を安定して取ることが合格への鍵となります。
科目別目標得点(800点満点)
公法系(200点):110-120点
民事系(300点):160-180点
刑事系(200点):110-120点
選択科目(100点):55-65点
合計目標:435-485点(約55-60%)
→総合順位上位30%
この戦略により、一部の科目で多少失敗しても全体として合格点を確保できます。



半分ちょいでいいの!?もっと取らなきゃって思ってたかも…



「全科目で安定してそのラインを取るほうが大事なんだ。1科目爆死しても挽回できるようにな。
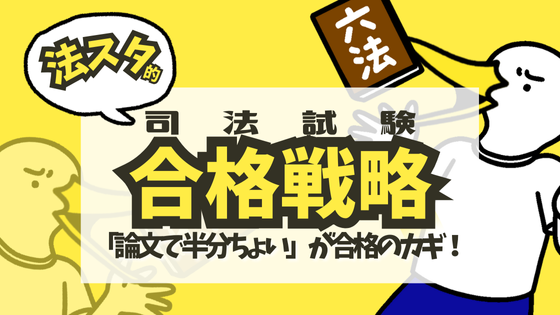
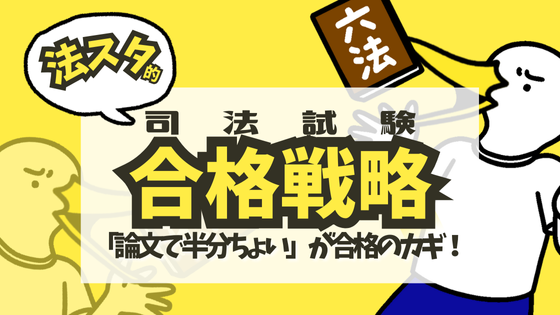
初期段階(基礎固め期:開始~6か月)



型を覚えるって、作文のテンプレみたいな感じ?



そうそう。“問題提起→規範→あてはめ→結論”っていう法律版テンプレだな。
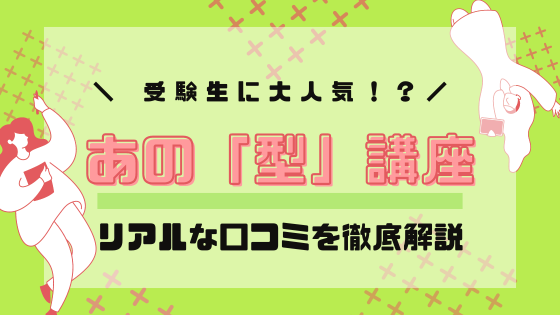
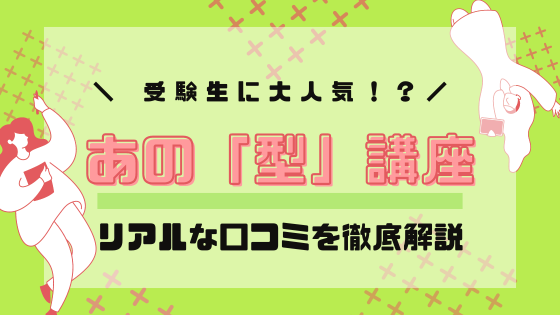
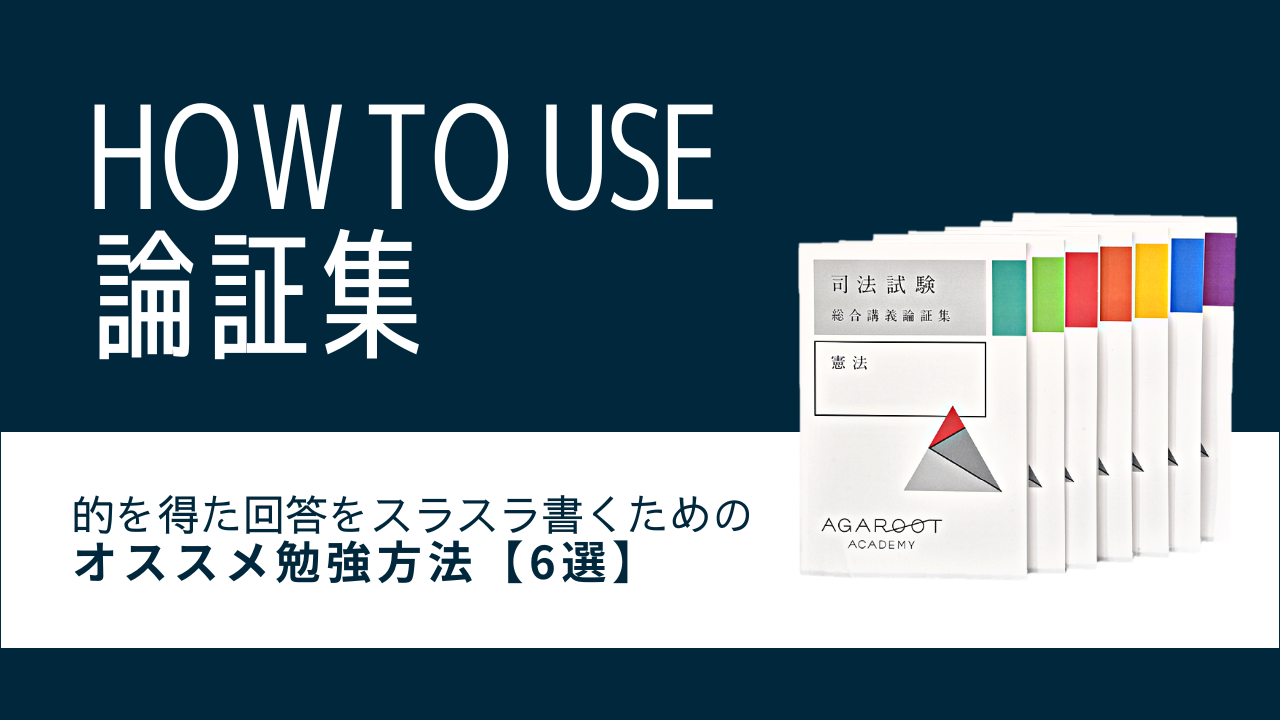
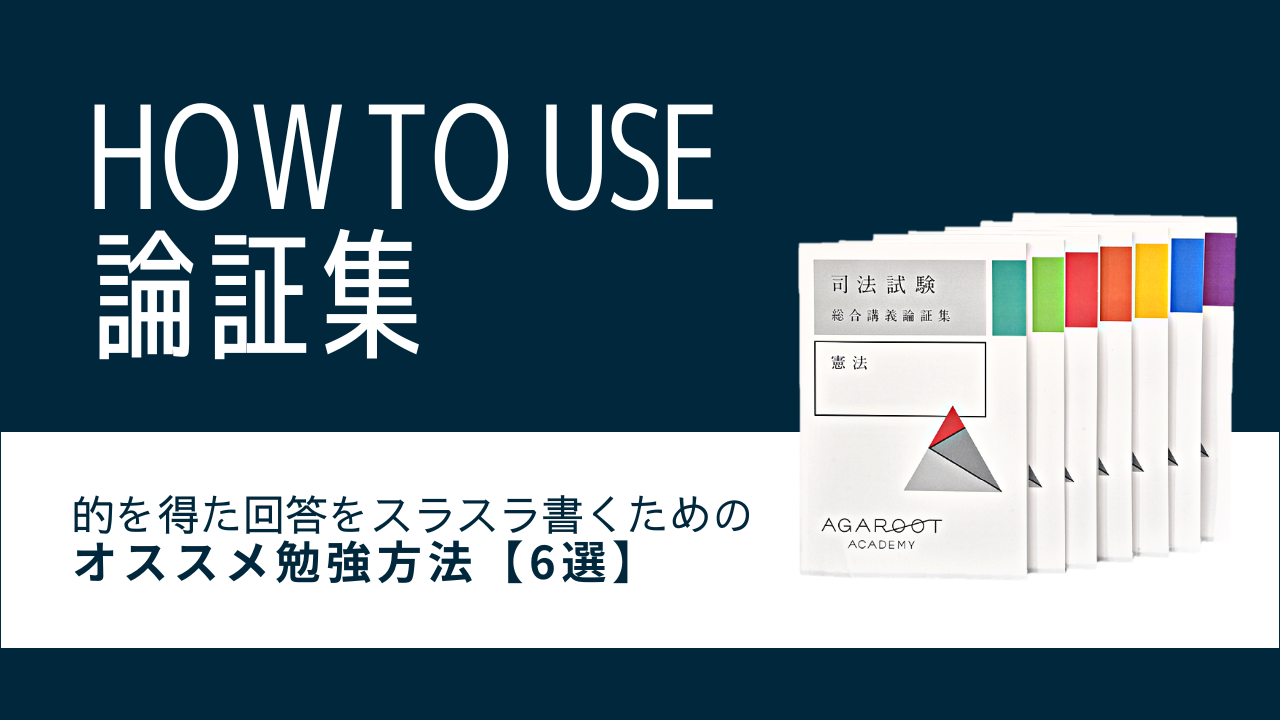
中期段階(応用力強化期:6か月~1年6か月)



「フィードバックって、ちょっと怖いけど大事なんだよねぇ…



痛い指摘ほど、伸びしろになるんだぞ。


実戦力完成期:1年6か月~



もうこの時期は“合格点を取る練習”って感じだねぇ



そうだ。本番を想定してやるかどうかで、当日の落ち着きが全然違うぞ。
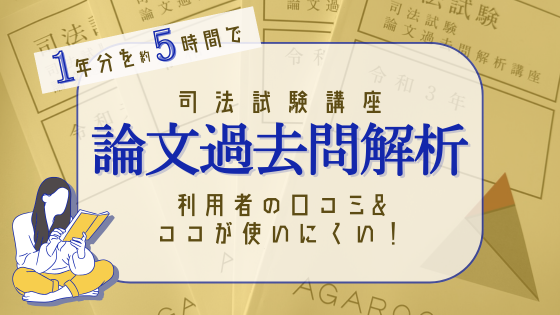
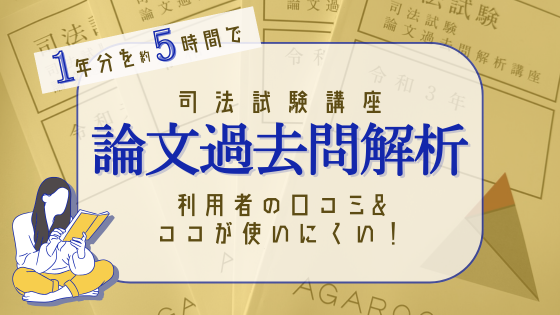
論文対策には良質な演習書が必須です。以下のように段階的に活用しましょう。
基本演習書の選定基準



いろんな演習書があって迷っちゃう…



まずは各科目1冊に絞った方がいいね。浮気するとどっちつかずになるぞ。
演習書活用の5段階
演習書は「読み物」ではなく「記憶の対象」として扱うことが重要です。



口頭で答案構成って、意外と難しそう…



「書かなくても頭の中で組み立てられるようになれば、実力は本物だぞ
おすすめは、アガルートの重要問題習得講座です。
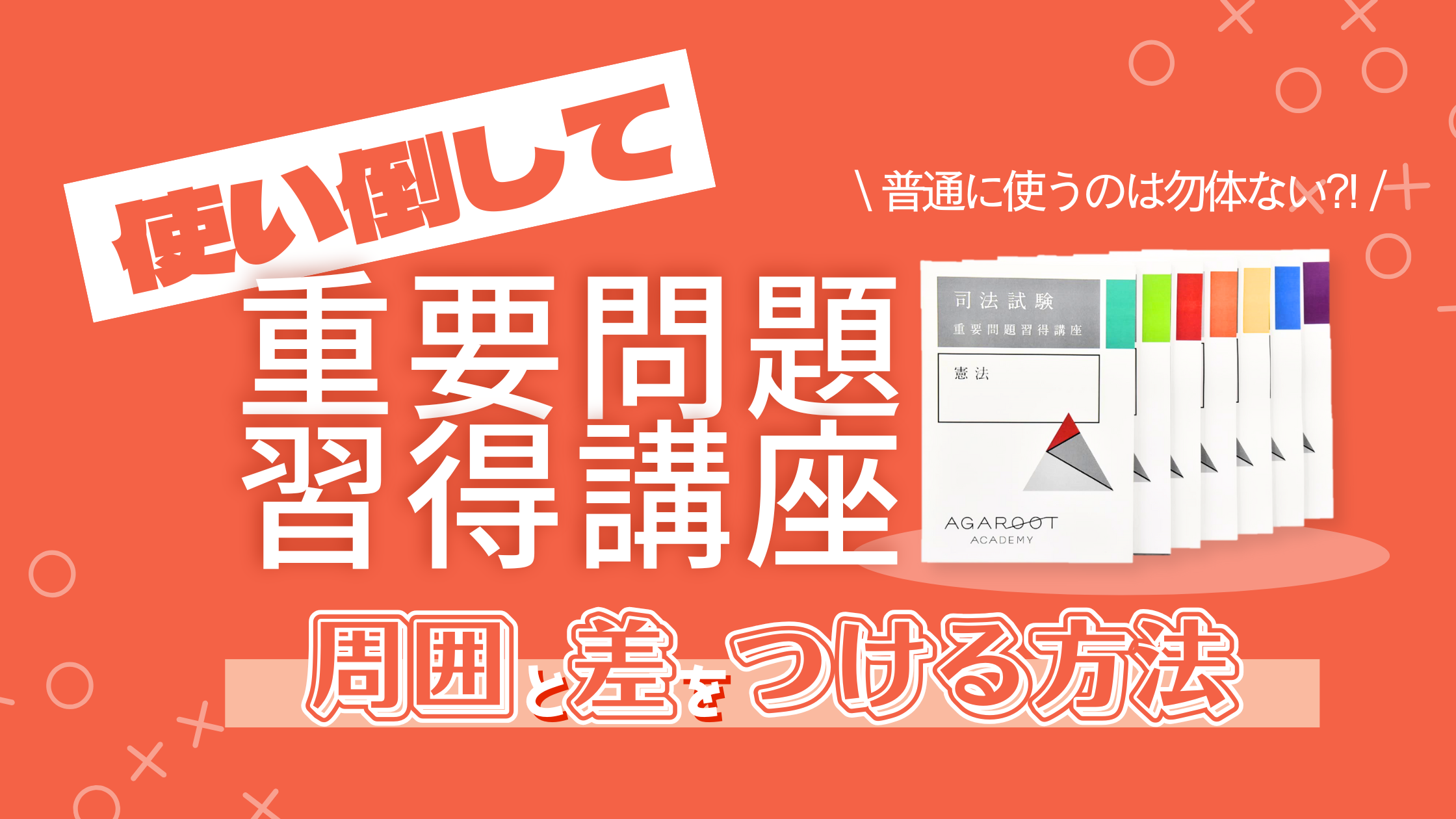
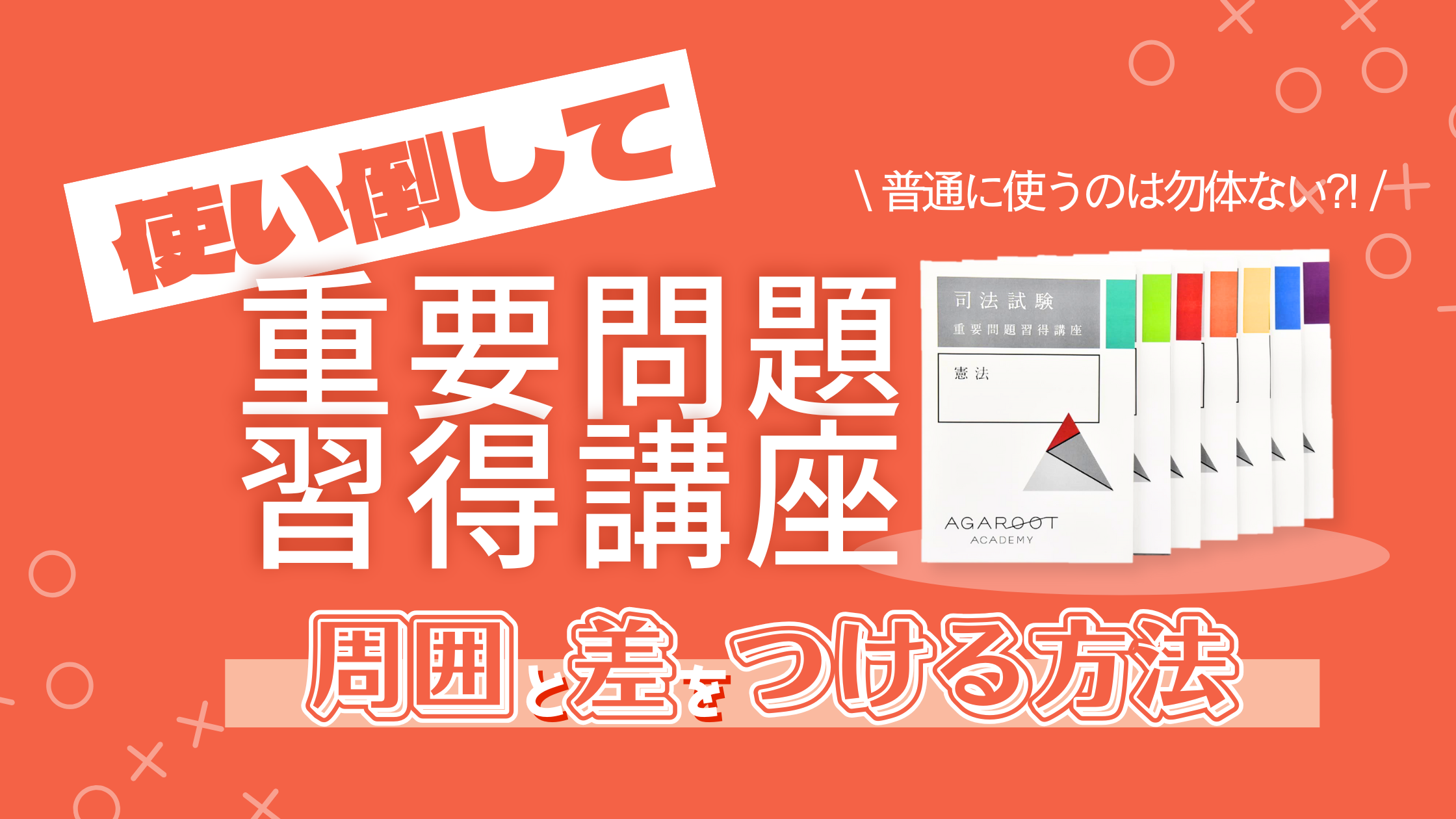
論文式試験では判例の理解が極めて重要です。効果的な判例学習法を身につけましょう。
判例学習の3段階


おすすめの判例教材
初学者:「スタートアップ判例集」
中級者:「判例百選」各科目
上級者:「精読憲法判例」「精読行政法判例」



判例百選ってカッコいい名前だねぇ





司法試験生の必須アイテムだな。読み込めば論文の武器になるぞ
ここからが本記事で最もお伝えしたいことです。
司法試験の学習において最も重要なのは、まず1年間は法律の勉強に完全に没頭することです。これは単なる精神論ではなく、極めて合理的な戦略なのです。



1年間、どっぷりって…けっこう長いよねぇ。途中で疲れちゃいそうかも…



長く感じるけど、その1年が土台になる。ここで本気を出せば、その後が一気に楽になるんだぞ。
1. 法律的思考の定着には時間が必要
法律の学習は積み上げ型であり、基礎概念の理解から応用まで段階的に進む必要があります。
法的三段論法、要件事実の考え方、利益衡量の手法など、法律家特有の思考パターンを身につけるには最低1年間の継続的な学習が必要になると思います。合格者の中には、1年間の学習期間に予備試験に合格する方がいますが、明らかに試験強者の方のエピソードです。通常は、少なくとも3年程度の学習期間は必要と考えておく必要があります。



「じゃあ、ボクはまず基礎の1年をちゃんと走り切ることが先決ってことだねぇ



そう。基礎を飛ばすと、後から全部やり直しになるからな。
2. 自分の適性と実力を正確に把握できる
1年間真剣に取り組むことで、以下のことが明確になります
この自己分析が今後の学習戦略を立てる上で極めて重要です。



1年間やれば、自分の“伸びるところ”と“つまずくところ”が見えてくるってこと?



その通り。それがわかれば、効率よく次のステップに進めるんだ。
3. 学習リズムと習慣の確立
司法試験の学習は長期戦です。最初の1年で以下の習慣を確立することが重要です



かもっち、朝型と夜型ってどっちがいいの?



自分が集中できる時間帯を知って、それを毎日続けるのが一番だぞ。
基本7科目の基礎レベル完成 まずは憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法について、以下のレベルまで到達しましょう。



これを1年間で達成できれば、きっとその後の司法試験対策もスムーズに進むでしょう。
学習順序の戦略
「刑法→民法→憲法」 刑法は条文構造が明確で法的思考の基礎を学ぶのに最適です。犯罪の成立要件(構成要件該当性→違法性→責任)という明快な体系により、法的三段論法を自然に身につけることができます。
民法は範囲が広いものの、契約、物権、不法行為など日常生活に関わる内容が多く、具体的事例を通じて法的思考を鍛えるのに適しています。「民法を制する者は司法試験を制す」と言われるほど重要な科目です。
憲法は人権や統治構造など抽象的な内容が多いため、他科目で法的思考の基礎ができてからの方が理解しやすくなります。



えーと、じゃあ最初は刑法からやればいいの?



あくまでも推奨だけどね。どうしても民法から勉強がしたいというのであれば、それでも良いと思うよ。刑法は、検討フローがはっきりしているから、法的な考え方をつかみやすいから、特に拘りがないならば、刑法からスタートしても良いだろうね!
インプットとアウトプットの時期別配分
あくまでもイメージですが、最初はどうしてもインプット中心の勉強になりますが、徐々にアウトプットの時間を増やしてください。
最初の3か月:インプット90%、アウトプット10%
4-6か月:インプット70%、アウトプット30%
7-9か月:インプット50%、アウトプット50%
10-12か月:インプット30%、アウトプット70%
この配分により、知識の定着と実践力の向上を両立できます。



アウトプットって、答案書くことだよねぇ?



そうだね。基本的には答案を構成、又は作成することと考えた方がいいかな。理解したことを思い出したり、友人に解説をしてみることもアウトプットだね。その中でも、「答案を書く」のが一番大切かな!
1年間の学習を終えた時点で、必ず以下の振り返りを行いましょう:
学習進度の評価
今後の戦略の再構築
この客観的な自己評価により、残り期間の学習戦略を最適化できます。
多くの予備校は「合格までの完全パッケージ」を推奨しますが、司法試験合格には通常3年程度かかることを考えると、最初から全てを決める必要はありません。



全部そろえたら安心かな〜って思ってたけど、そうでもないんだねぇ



「この予備校で必ず合格する」と覚悟を持てたなら、フルパッケージの講座でも良いと思うよ。
これから司法試験の勉強をゼロから始める段階だと、最初から全部買うと、合わない教材まで抱えることになるぞ。必要なものは段階的に選ぶのが良いと思うんだ。
あと、もうすでにある程度の勉強を進んできて、自分にあう予備校が分かっている人は、「フルパッケージの講座」もおすすめだ!
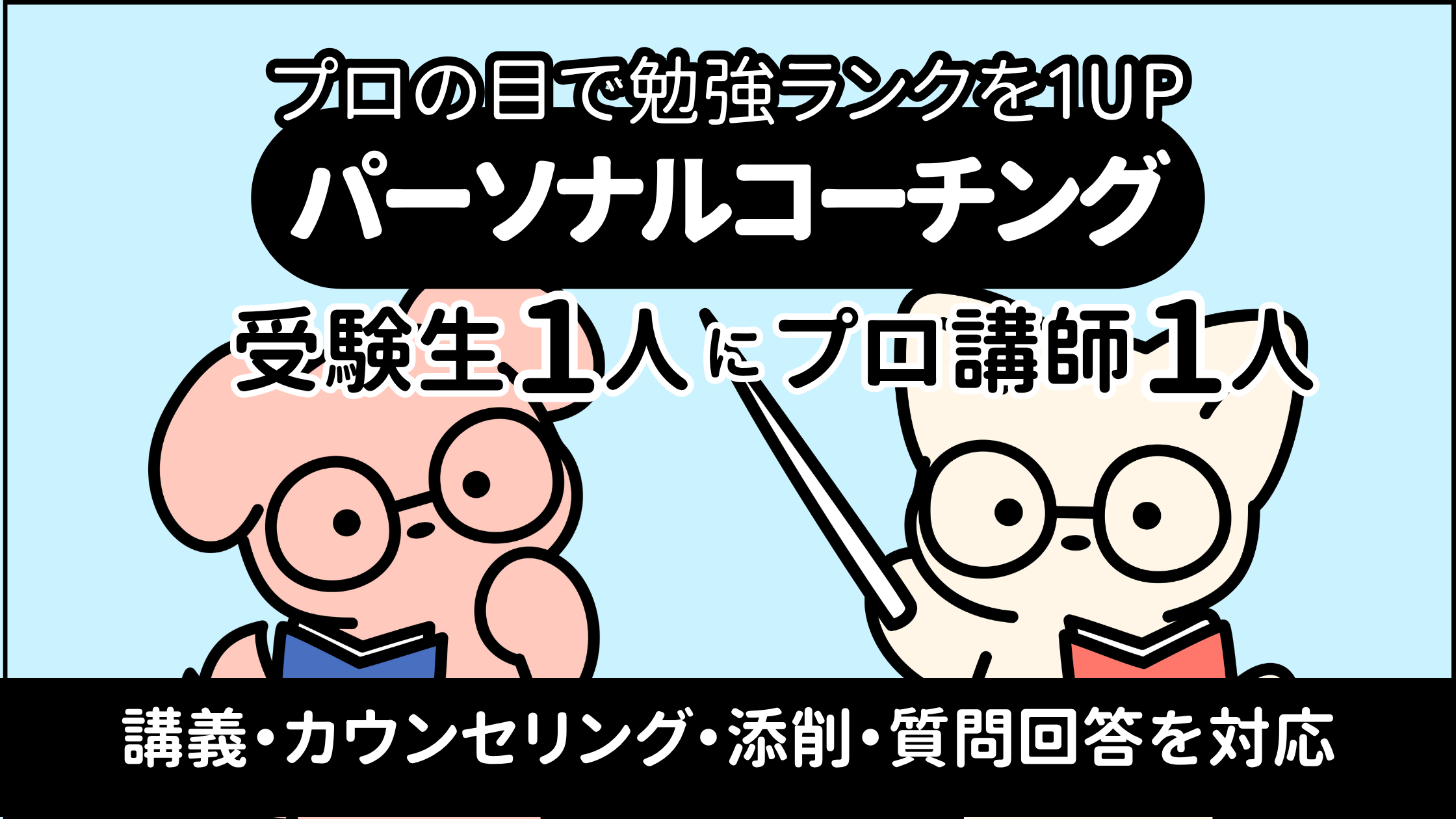
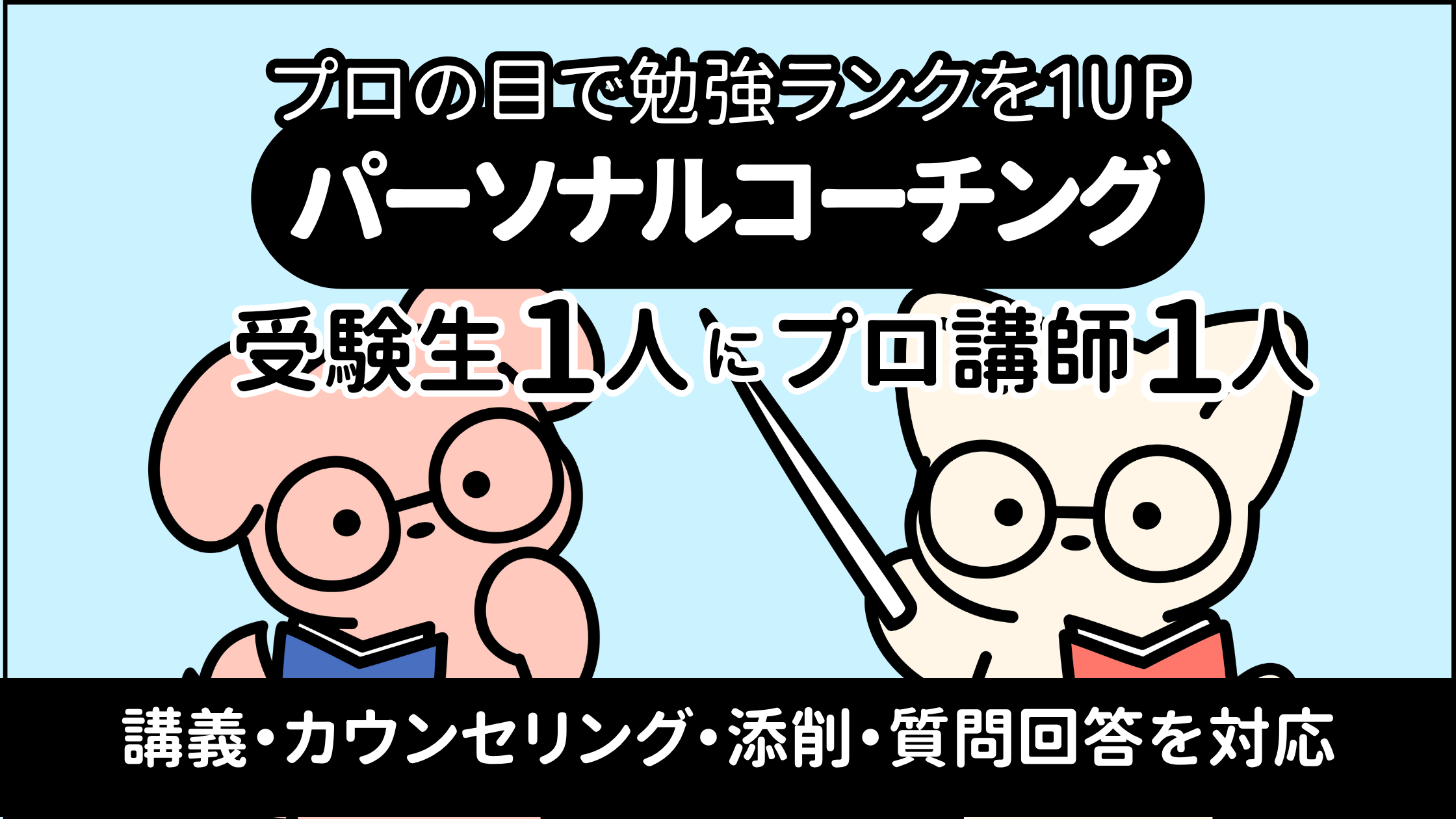
◆フルパッケージの問題点



たしかに…途中でやめたらお金もったいないかも〜



そう。だから最初は必要最低限から始めて、合うものを見極めていくんだ
段階的アプローチの推奨理由
司法試験の学習は長期間にわたるため、学習の進行に伴って以下の点が変化します。
これらの変化に柔軟に対応するため、段階的な講座選択が実はおすすめです。
第1段階:基礎固め期(最初の1年)
インプット講座:各科目の総合講義
基礎演習講座:基本的な論文演習(事例演習)
投資額の目安:30万円程度



1年目はとにかく基礎固めかぁ…



「そうだ。ここで基礎がグラつくと、あとでボロがでる。
基礎を徹底的に叩き込んだ人は、後から急速に実力を伸ばしていく
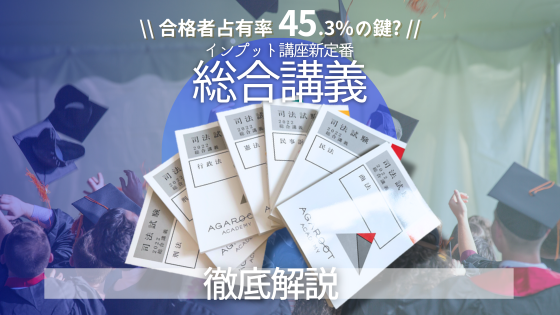
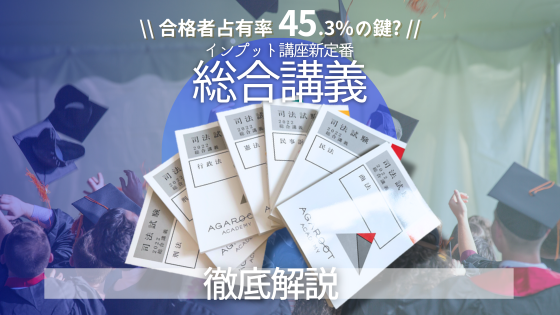
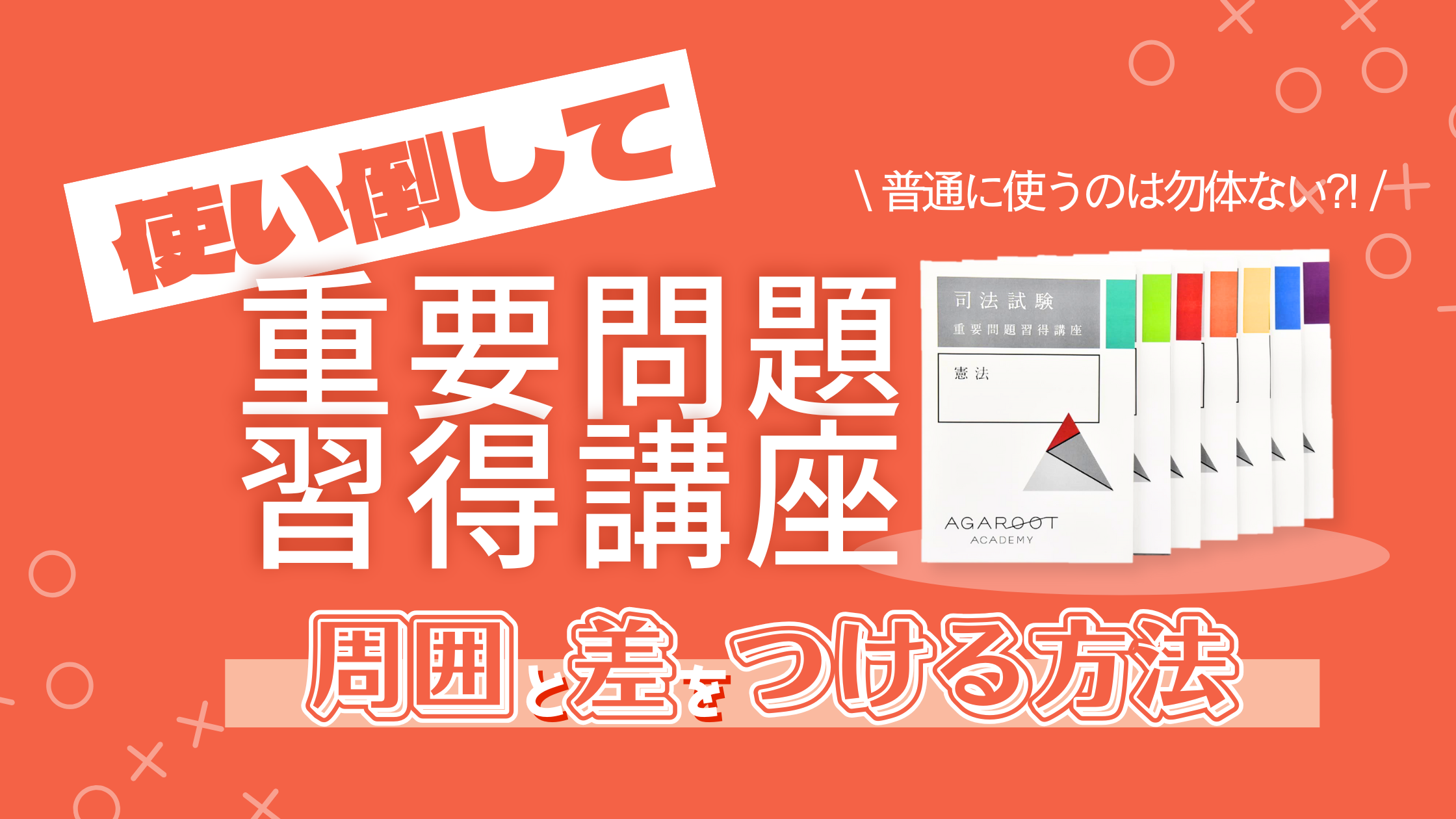
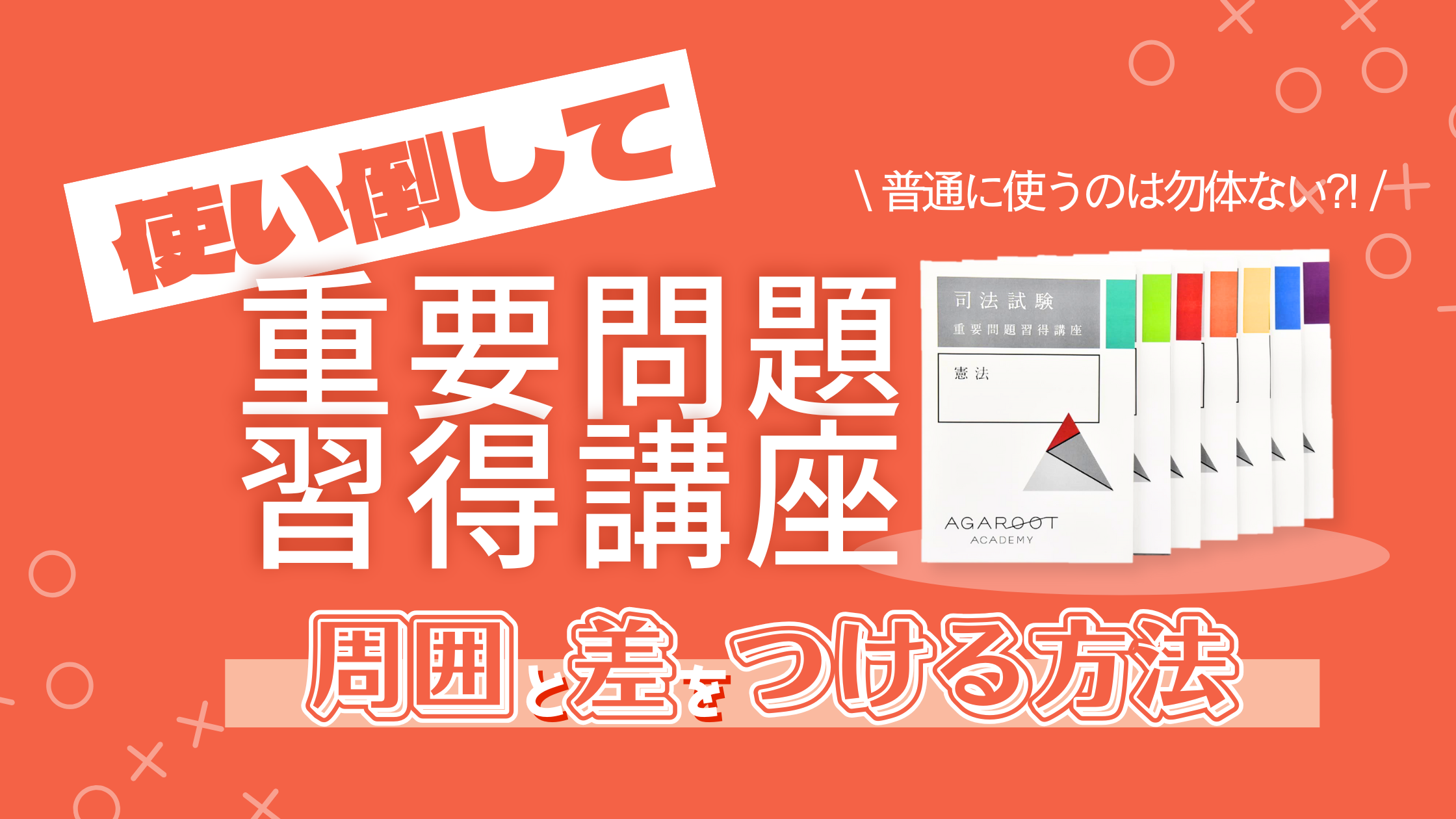
第2段階:実力向上期(1-2年目)
論文演習講座:本格的な論文対策
過去問分析講座:出題傾向の把握
弱点補強講座:苦手科目の集中対策
短答対策:短答知識の集中対策と過去問演習
投資額の目安:15-25万円程度



ここで一気に実戦力を伸ばすんだねぇ



そう。答案を書く練習量を増やして、時間内に仕上げる感覚を身につける時期だ。
第3段階:直前期(2年~)
直前対策講座:最新判例・法改正対応
模試パック:実戦力の確認
答練、個別指導:答案添削の強化
投資額の目安:10-20万円程度



直前期はやっぱり模試が大事?



模試や答練で実戦感覚をつけないと、本番で力が出し切れないぞ。
この方法により、総額60-70万円程度でフルパッケージと同等以上の効果を得られると思います。
主要予備校の特徴
アガルートアカデミー
合格実績:令和5年司法試験合格者占有率45.3%
特徴:オンライン完結、高品質テキスト、手厚いサポート
おすすめ講座:総合講義300、重要問題習得講座
料金:比較的高額だが充実した内容
資格スクエア
特徴:AI学習システム、効率重視のカリキュラム
おすすめ講座:基礎講座、論文対策講座
料金:中程度、コストパフォーマンス良好
スタディング
特徴:格安料金、スマホ学習対応
おすすめ講座:基礎講座(インプット用)
料金:最安値クラス、初学者におすすめ


独学の課題
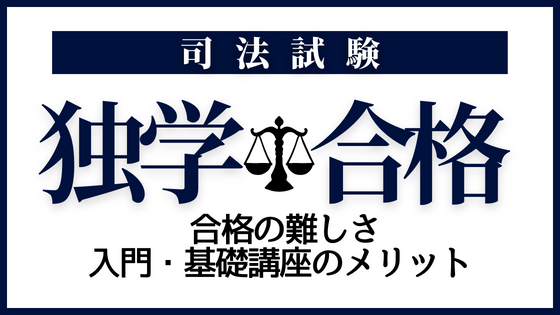
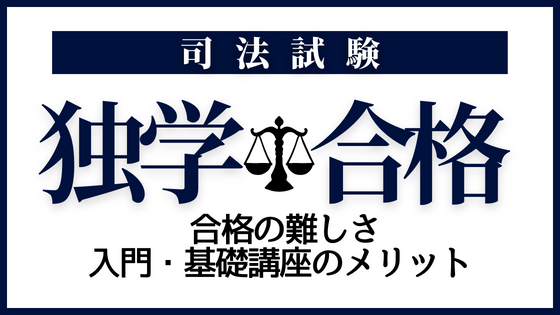
予備校活用のメリット
予備校が推奨するままに講座を受講する必要はありませんが、実際には、司法試験に合格するために予備校の利用は必須といえる状況です。そのため、「予備校を賢く利用する」という意識を持ちましょう。
自宅学習の場合



家だとついスマホ見ちゃうんだよねぇ…



じゃあ勉強中は別の部屋に置くとか、物理的に手元から離すんだ。自制だけに頼るのは危険だぞ。
図書館・自習室の活用



図書館って静かすぎて眠くなっちゃうかも〜



そういう時はイヤホンで自然音を聞くとか、人が座っているテーブルで勉強をするとか。環境も自分で工夫して調整できる!
学習時間の管理
1日の標準的な学習時間配分
効率的な時間配分例



朝って本当に集中できるの?夜型でも?



夜型だろうが、朝型であろうが、試験は朝からだから、慣れておくと本番に強いぞ。


司法試験は長期戦です。健康管理が非常に大切となります。
身体的健康の維持
精神的健康の維持



勉強だけしてると気分が落ちるかも…



だから趣味も必要だ。短い時間でも“脳の切り替え”ができる習慣を持って!
司法試験の学習計画では、最初から完璧な計画を立てようとせず、実際の学習進度に応じて軌道修正していく姿勢が重要です。
計画立案の基本原則



「計画って、一回決めたら変えちゃダメな気がしてたかも



逆だ。変えられない計画ほど危ない。現実に合わせて修正していくのが成功のコツだぞ。
具体的な計画立案手順
年間計画(大まかな方向性)
四半期計画(中期目標)
月間・週間計画(短期実行)
学習記録の重要性 毎日の学習を「見える化」することで、客観的な分析が可能になります。
記録すべき項目



記録するのって、時間かかって面倒そう…



「1日3分でいい。それで客観的に自分を見直せるなら安い投資だぞ。
定期的な分析・評価 週1回、月1回の頻度で以下を確認しましょう:
週次レビュー
月次レビュー
軌道修正の判断基準
以下の場合は計画の大幅な見直しを検討しましょう。



計画見直すのって負けっぽく感じるけど…



むしろ勝つための作戦変更だ。合格は柔軟なやつが手にするもんだぞ
司法試験の学習において、完璧主義は最大の敵です。「今日は60%できればOK」という気持ちで取り組むことで、長期的な継続が可能になります。
完璧主義の弊害



この前の模試で撃沈したから、もう全部嫌になっちゃったんだよねぇ…



その気持ちはわかるけど、失敗はむしろ宝だぞ。修正ポイントが見つかるんだから。
健全な学習マインドセット



昨日より少しわかった気がするかも〜



そそれが大事。今日の“少し”が積もれば、いつの間にか“すごい”になるからな。
小さな達成感の積み重ね 大きな目標だけでなく、日々の小さな達成感を大切にしましょう。
日常的な成功体験の例
中期的な達成感の例
長期的な達成感の例
一人で学習を続けることの困難さを軽視してはいけません。



かもっちと一緒に勉強してなかったら、途中で挫折してたかもしれないかも〜



お互い支え合える相手がいると、試験勉強はずっと楽になるんだ。
仲間づくりの方法
仲間との適切な関わり方



ライバルっていうより、一緒に走る仲間って感じだよねぇ



「そうそう。合格してからも付き合える人間関係を作れるのが理想だな。
短答式試験の傾向
論文式試験の傾向
もっとも、これから司法試験の勉強を始める方は、特に短答式試験の対策をする必要はありません。
まずは、基本的な事項のインプット、基本的な事例問題を処理する能力を養成することに注力してください。枝葉の知識ではなく、幹の知識です。
司法試験への道のりは決して平坦ではありませんが、以下のポイントを押さえて学習を進めれば、必ず合格に近づくことができます。
最重要ポイントをおさらい



こうやって見ると、合格までの道って“全部一気に”じゃなくて、順番にやっていけばいいんだねぇ



そうだ。焦らず、でも止まらず、が合格への鉄則だぞ。。



あと、やっぱり短答と論文って、力の入れ方が違うんだねぇ



そうだ。配点を見れば一目瞭然。論文重視だけど、短答の足切りは絶対に避けるんだ。
司法試験は「情報戦」でもあります。
効率的な学習方法、最新の出題傾向、有用な参考書、法改正情報などを常にアップデートしながら学習を進めることが重要です。また、合格者の体験談や予備校講師のアドバイスなど、様々な情報源から有益な情報を収集し、自分の学習に活かしていくことも大切です。



情報って多すぎて、何を信じればいいかわからなくなる時あるかも…



「だから“自分の合格戦略”に沿ったものだけを選んで活かせばいい。全部追いかける必要はないぞ。
法スタでは、効率的な勉強法、教材紹介、合格者の体験談など合計400件以上の豊富なコンテンツであらゆる学習スタイルをサポートしているから是非、活用してほしい!
最後に、司法試験は人生を変える素晴らしい挑戦です。困難な道のりですが、法曹として社会に貢献したいという強い意志があれば、必ず道は開けます。今日からまず1年間、法律の世界にどっぷりと浸かってみてください。その1年間の経験があなたの司法試験合格への確実な第一歩となり、将来の法曹としてのキャリアの土台を築くことになるでしょう。
途中で迷いや不安を感じることもあるでしょうが、それは成長の証拠です。一歩一歩着実に前進していけば、必ず目標に到達できます。



不安になるのは、成長してる証拠…ちょっと勇気出るかも〜



その通り。怖さを抱えたままでも前に進んでいけば、必ず希望が見える!
法スタは、皆様の司法試験合格と、その先の素晴らしい法曹人生を心から応援しています
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

