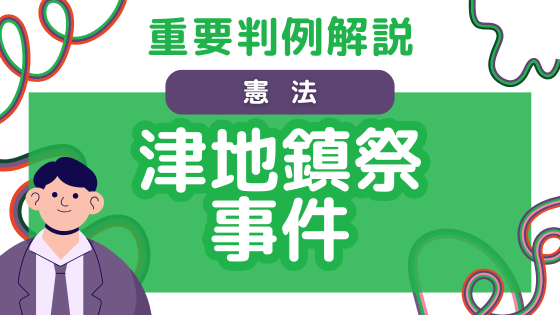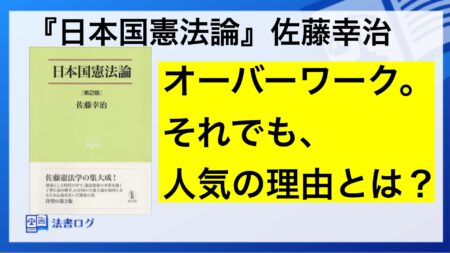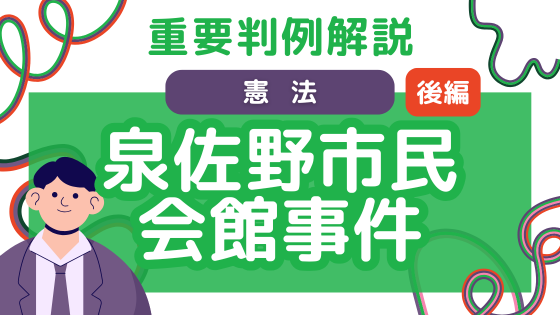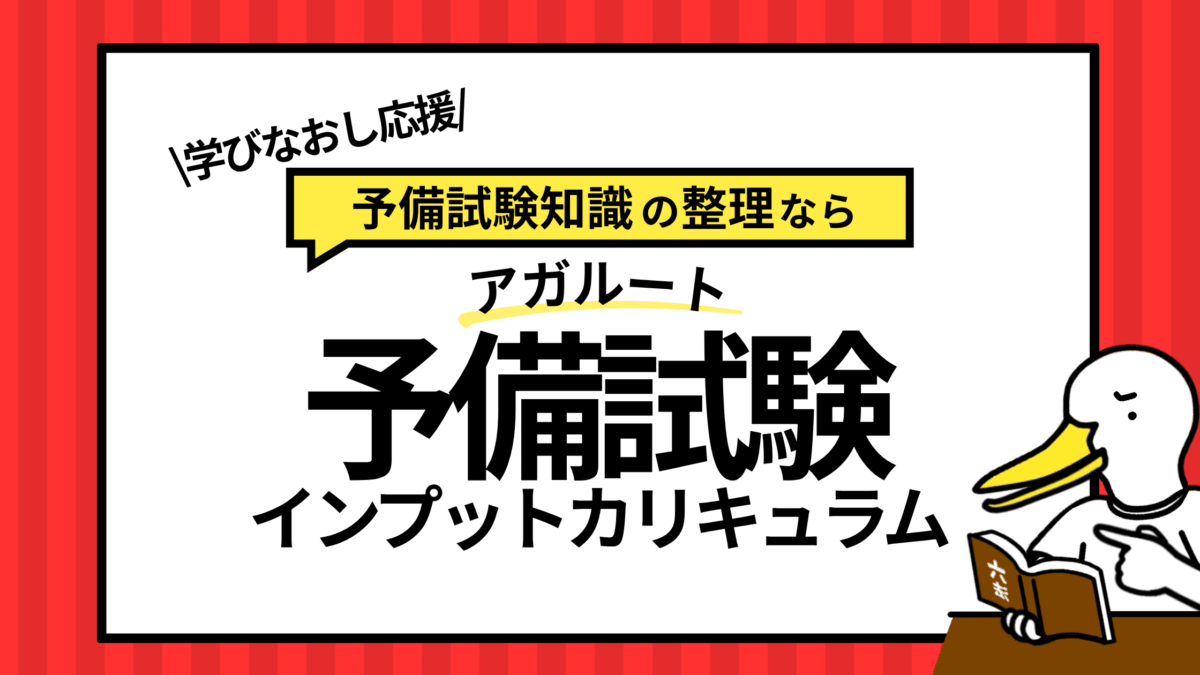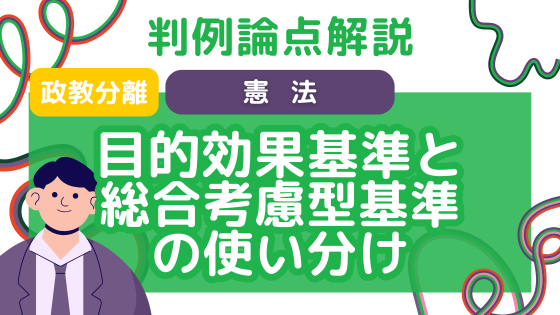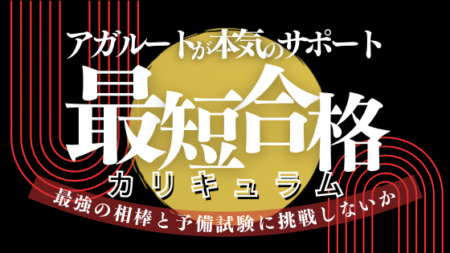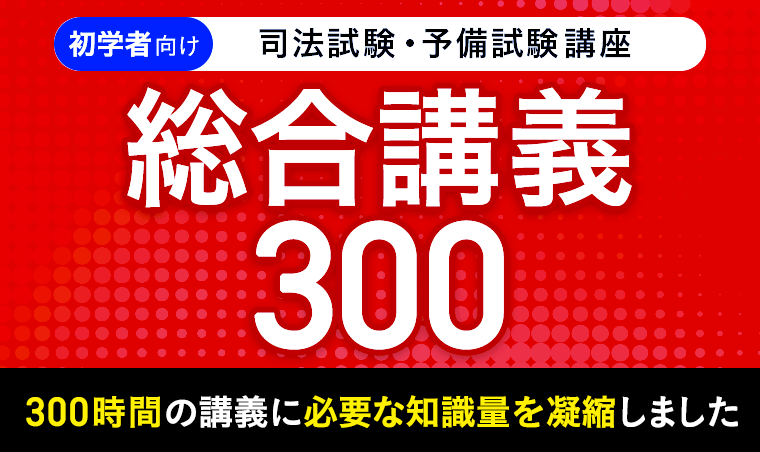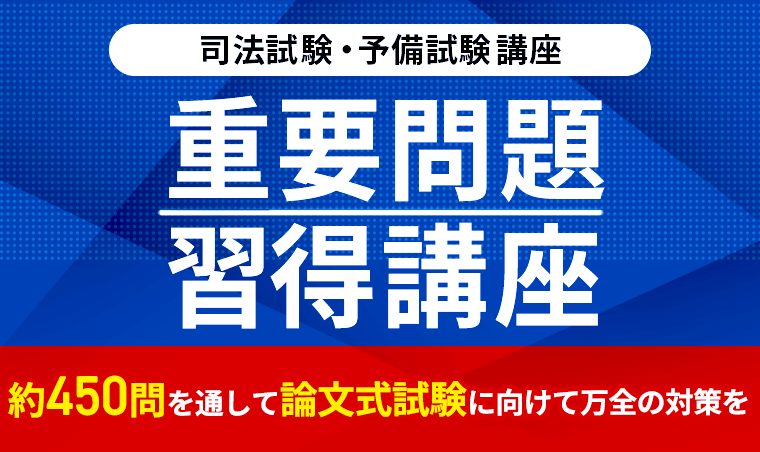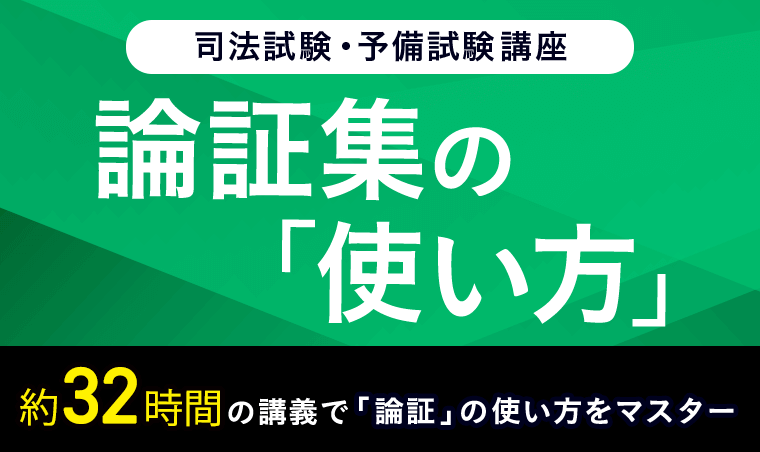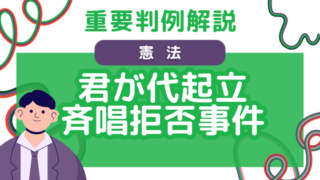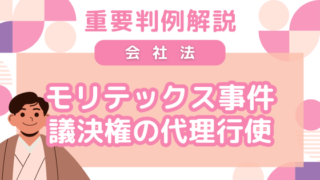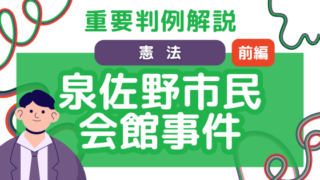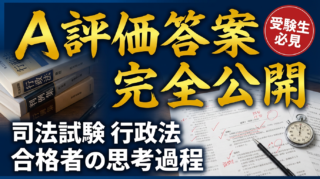君が代起立斉唱拒否事件をどこよりも分かりやすく解説
当ページのリンクにはPRが含まれています。
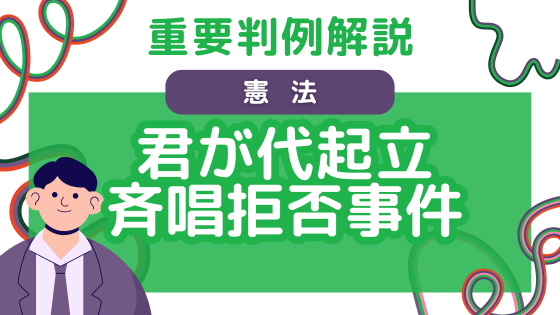
「君が代起立斉唱拒否事件(最二小判平成23.5.30)」は「『思想・良心の自由』についての間接的な制約は認められるのか?」が問題になった事案です。
「思想・良心の自由」は、憲法19条により絶対的に保障されており、何人も思想良心に反する言動を強制されませんが、思想良心に関係ない行動については職務命令を出すことができます。ただ、その職務命令が思想及び良心の自由についての「間接的な制約」に当たる場合は許容されるのかが問題となります。



では、解説を始めるぞ!
目次
「思想・良心の自由」とは?
憲法19条では「思想・良心の自由」を絶対的に保障しています。
簡単に言うと、「人が内心で、どのようなことを考えていたとしても外部から干渉を受けることはない」ということですが、実質的には、次の3つの意味があると解されています。
「思想・良心の自由」の意味 3つ
- 公権力が一定の思想や良心を持つことを禁止したり強制することはできない。
- 一定の思想や良心を持つことを理由に不利益を課することはできない。
- 人の思想や良心の告白を強制することはできない。
「君が代起立斉唱拒否事件」では、君が代を起立斉唱する行為が、原告である教諭の思想や良心に反する行為を求めるものだったために問題になりました。
まず、事件の概要を確認しましょう。
「君が代起立斉唱拒否事件」の概要
「君が代起立斉唱拒否事件」概要
Xは、都立高校の教諭でしたが、卒業式において、国家斉唱の際に校長から「起立斉唱行為の職務命令」を受けたにもかかわらず、拒否しました。
拒否の理由としてXは「日本の侵略戦争の歴史を学ぶ在日朝鮮人、在日中国人の生徒に対し、日の丸や君が代を卒業式に組み入れて強制することは教師としての良心が許さない」との考えを有していると主張しました。
これに対して都教育委員会は、不起立行為は職務命令に違反しており、全体の奉仕者である公務員としてふさわしくない行為であるとして、戒告処分としました。
また、Xは、定年を機に非常勤の嘱託職員としての採用選考を受けましたが、上記の処分を理由に不合格となりました。
これに対してXが「上記職務命令が憲法19条違反であること」また「非常勤の嘱託職員の採用選考を不合格としたことも違法である」として、国家賠償法第1条1項に基づく損害賠償を求めて訴えを提起しました。
第一審、控訴審はともに職務命令が憲法に違反しないと判断しました。「非常勤の嘱託職員の採用選考を不合格としたこと」については、第一審では裁量権の逸脱濫用を認めましたが、控訴審では認めませんでした。
そこで、Xが上告した事件です。
「君が代起立斉唱拒否事件」最高裁の判断
最高裁は、Xの上告を棄却しました。
まず、争点となったのは「『日の丸』の掲揚や、『君が代』起立斉唱行為が、特定の思想の表明になるのか?」という点です。
順番に確認していきましょう。
「日の丸」の掲揚や「君が代」起立斉唱行為について
最高裁は、以下のように言っています。
これらの行為は「一般的、客観的に見て、卒業式等の式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有する」ものに過ぎず、「特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難」だ
「Xが、起立斉唱行為をしたとしても、Xの歴史観ないし、世界観の否定にはならない」と判断しています。
校長が「起立斉唱行為の職務命令」を出したことについて
起立斉唱行為が「特定の思想又はこれに反する思想の表明」に該当しない以上、校長が起立斉唱行為の職務命令を出したことも、以下の類のものではなく「個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできない」と判断しました。
「起立斉唱行為の職務命令」は以下に該当しない
- 特定の思想を持つことを強制すること
- 特定の思想に反する思想を持つことを禁止すること
- 特定の思想の有無について告白することを強要すること
つまり、「直接的な制約」にはならないとしているわけです。
「思想・良心の自由」の間接的な制約
一方で、最高裁は「Xの思想及び良心の自由に対する『間接的な制約』に当たる可能性」を指摘しています。
まず「日の丸に向かって君が代を起立斉唱する行為」は「国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為」だと認定しました。
そのため、Xのように「国旗及び国歌に敬意を示すことには応じがたい」と考える人にとっては、本来の内心である「敬意の表明の拒否」と異なる外部的行為である「敬意の表明の要素を含む行為」を求められることになります。
その限りにおいて、Xの思想及び良心の自由についての「間接的な制約」に当たると判断しました。
このような「間接的な制約」を受けることは、憲法19条で保障する「思想・良心の自由」に反しないのかが問題になります。
「思想・良心の自由」の間接的な制約は許されるのか?
最高裁は、「内心に由来する外部的行動が社会一般の規範等と抵触する場面では、制限を受けることがある」としたうえで「その制限が必要かつ合理的なものである場合には、その制限を介して生ずる間接的な制約も許容され得る」と判断しました。
そして「間接的な制約が許容されるか否か?」については、以下としています。
「職務命令の目的及び内容並びに制限を介して生ずる間接的な制約の態様等を総合的に較量して、当該職務命令に間接的な制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断すべき」
本件へのあてはめ
まず、「日の丸に向かって君が代を起立斉唱行為する行為を校長が職務命令で命じること」は、「Xの思想及び良心の自由に対する『間接的な制約』に当たる」と認定しています。
一方で、「学校の卒業式等の儀式的行事では生徒等への配慮を含め教育上の行事にふさわしい秩序を確保して式典の円滑な進行を図ること」が必要とされています。
また、Xは「住民全体の奉仕者として法令等及び職務上の命令に従い、公共性の高い職務を遂行すべき地方公務員の立場」にあります。
よって、以下のように判断しました。
「校長の職務命令」は、Xの「思想及び良心の自由」についての「間接的な制約」となるものの、職務命令の目的及び内容並びに制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量すれば、許容し得る程度の必要性及び合理性が認められる
まとめ
最高裁の考え方を簡潔にまとめましょう。
まず、「日の丸」の掲揚や「君が代」起立斉唱行為は、以下としました。
「日の丸」の掲揚や「君が代」起立斉唱行為
- 特定の思想又はこれに反する思想の表明に当たらない
- 国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為に該当する
「思想の表明」に当たらない以上、職務命令で強制しても「思想及び良心の自由」を侵害したことになりません(「直接的な制約」に該当しない)。
ただ、「敬意の表明」であるため、「思想及び良心の自由」についての「間接的な制約」に当たると判断しました。
そして、「間接的な制約」でも「必要性及び合理性」が認められる場合は、許容されるとしています。
本件では、「卒業式の円滑な遂行の必要性」や「Xが公立高校の教師として公共性の高い職務に従事している点」を鑑みて、許容されると判断しました。
この裁判の最高裁の判断はややこしいですが、混乱しないように整理して押さえておきましょう。