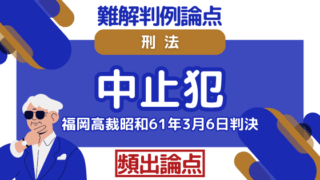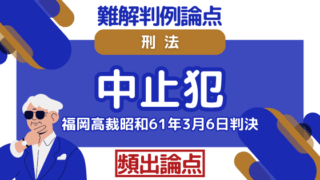【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
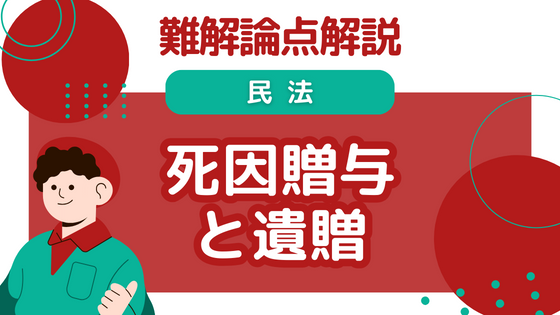
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。
動画解説の「法スタチャンネル」も大好評、運営中!
▽動画解説を順次公開中▽



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



皆さん、知ってましたか?
あのアガルートがアプリをリリースしています。



これにより講義視聴がより便利になり、学習の効率が大幅にアップしました!
是非、公式サイトで詳細を確認してください!
\講義動画のダウンロード可能/
データ通信料を気にせず受講しよう!!
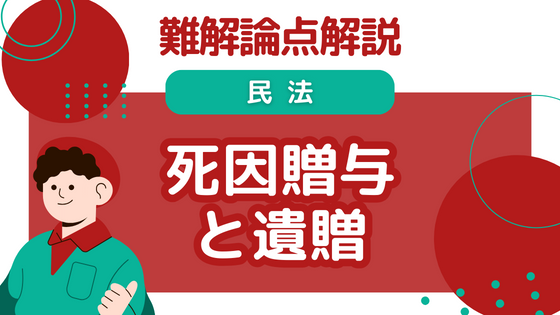
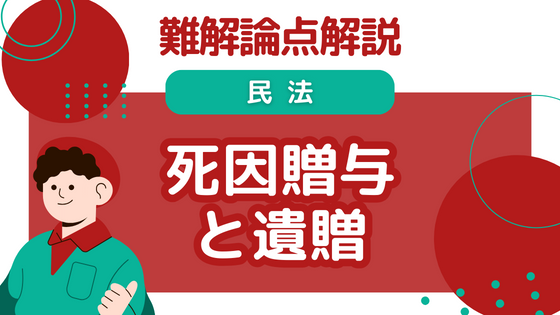
「死因贈与と遺贈の規定の準用の論点がよくわからない」
「昭和47年5月25日最高裁がよくわからない」
「昭和57年4月30日判決がよくわからない」


今回は、相続法の重要論点の一つである「死因贈与と遺贈の規定の準用」について解説をしたいと思います。
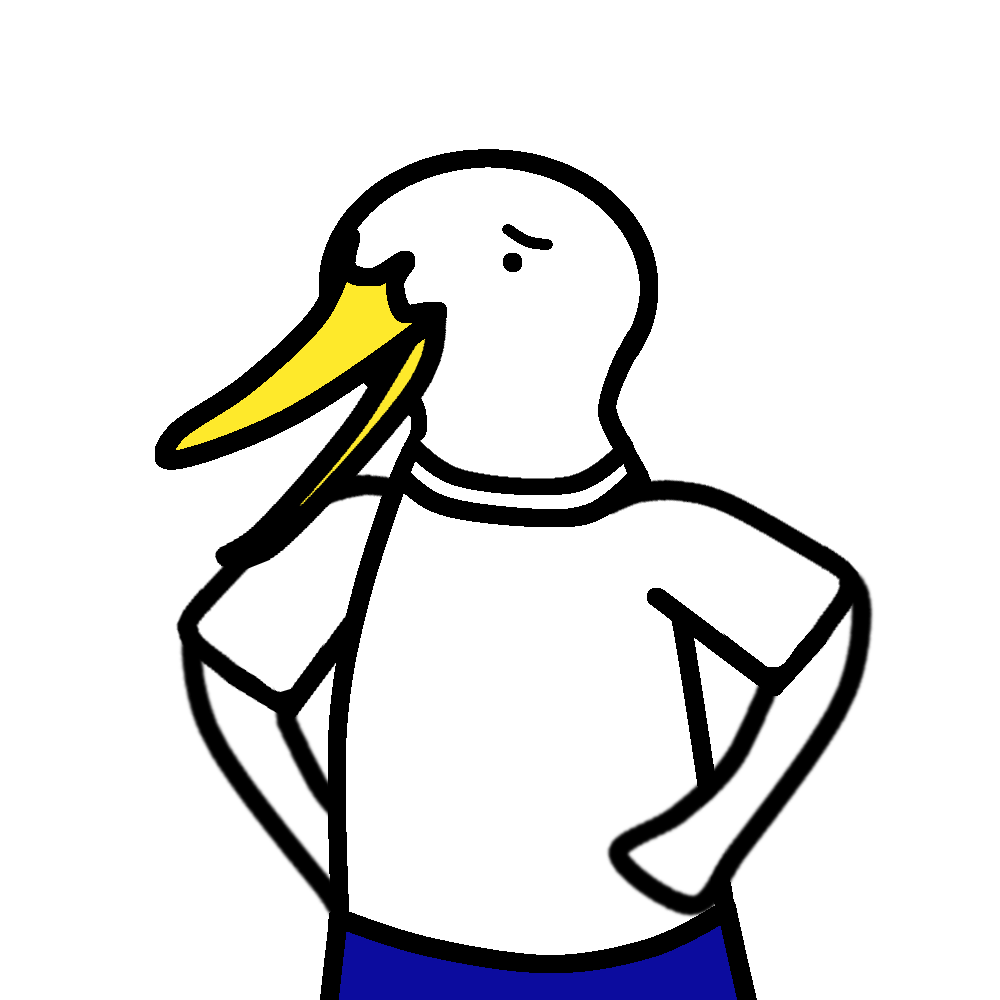
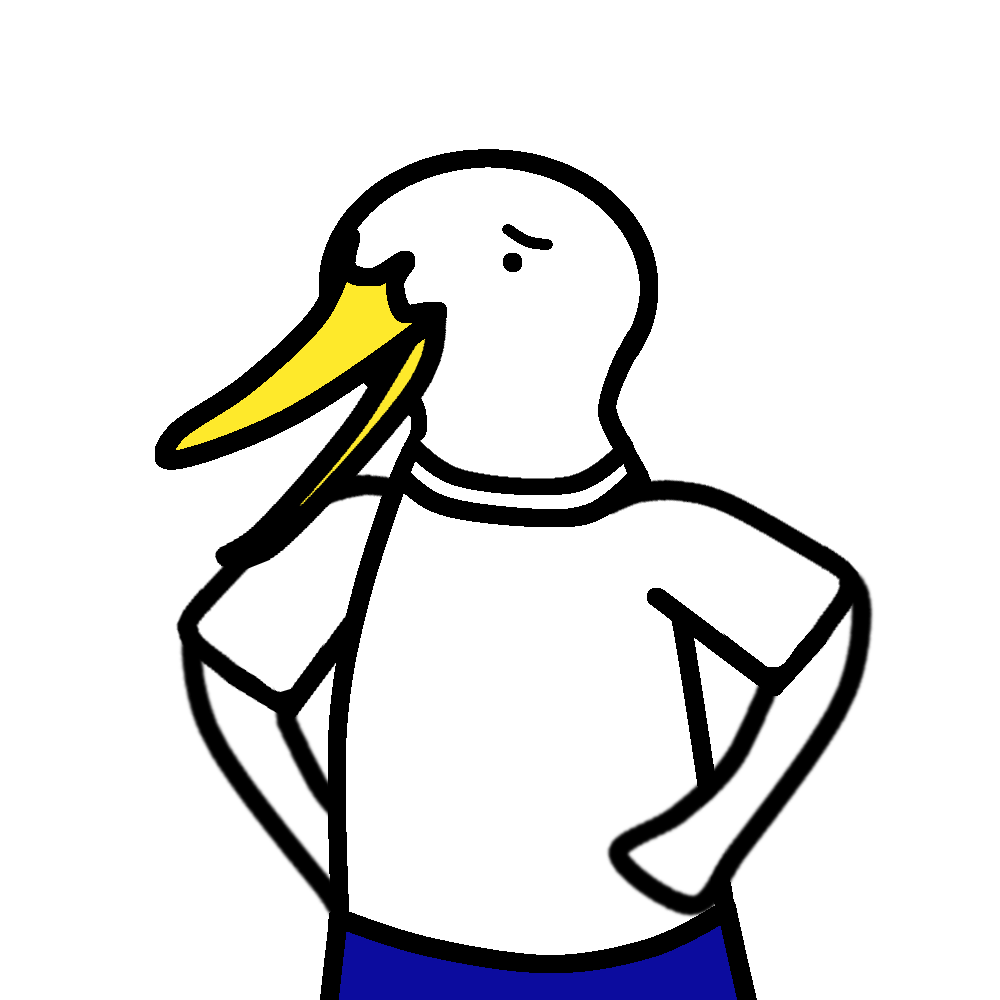
家族法は、司法試験では2年に1回くらいの頻度で出題される重要なテーマだね!
その中で、債権法を絡めた出題が可能な「死因贈与と遺贈の規定の準用」の論点は、出題可能性の高い論点と言えるかと思います。
本記事では、「死因贈与」と「遺贈」の違いという基本的な点から関連する最高裁判例まで解説をさせていただきます。
※本記事の解説は、当サイトが各文献を参考に整理した見解であり、内容の正確性を保証するものではございませんのでご留意ください。



みなさ~ん!
この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。



「これさえやりきれば、もう怖くない!」
そんな演習書や問題集が欲しいと思ったことはありませんか?
通称「重問」と呼ばれるアガルートの重要問題がおすすめ



その人気の秘密や効果的な活用方法について、アガルートの専任講師に直接インタビューを行いました。
受験生に支持される理由が詰まった記事、ぜひチェックしてみてくださいね!
今売れてます!!
\司法試験合格者占有率37.8%/
▼重要問題だけで合格する究極の勉強法【独占インタビュー】▼


まずは、基本的なことから確認していきましょう。
「死因贈与と遺贈の違いはなんでしょう?」
いずれも相続を契機とし、財産を移転する効果を有する点で共通していますが、法的には明確に区別されています。
まず「死因贈与」とは、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与」(民法554条)のことです。
ポイントは「贈与(契約)」の一種という点です。そのため、贈与をする者と贈与を受ける者との間で合意が必要となります。両者間の合意を必要となる点で、遺贈とは異なります。
次に、「遺贈」とは「遺言者が、(遺言により)包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分すること」(民法964条)です。遺贈は、単独行為です。
遺贈は、遺言書の中で、相続財産の全部または一部を処分する行為です。相続財産をあげる者ともらう者との間で合意は不要です。遺言者が一方的に、遺言書の中で書けば実現します。
・「死因贈与」は贈与者の死亡によって効果を生ずる贈与であって、当事者間の合意が必要。
・「遺贈」は遺言者が遺言の中で、財産を処分する行為であり、当事者間の合意は不要。
以上のとおり「死因贈与」と「遺贈」は法律上、明確に区別をされていますが、相続を契機に財産を移転させる効果を有するという点で、類似しています。
そのため、民法は、死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用すると規定しています。
(死因贈与)
第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。


さて、ここで死因贈与と遺贈の規定の準用に関する重要判例の一つである「昭和47年5月25日判決」について解説をしたいと思います。
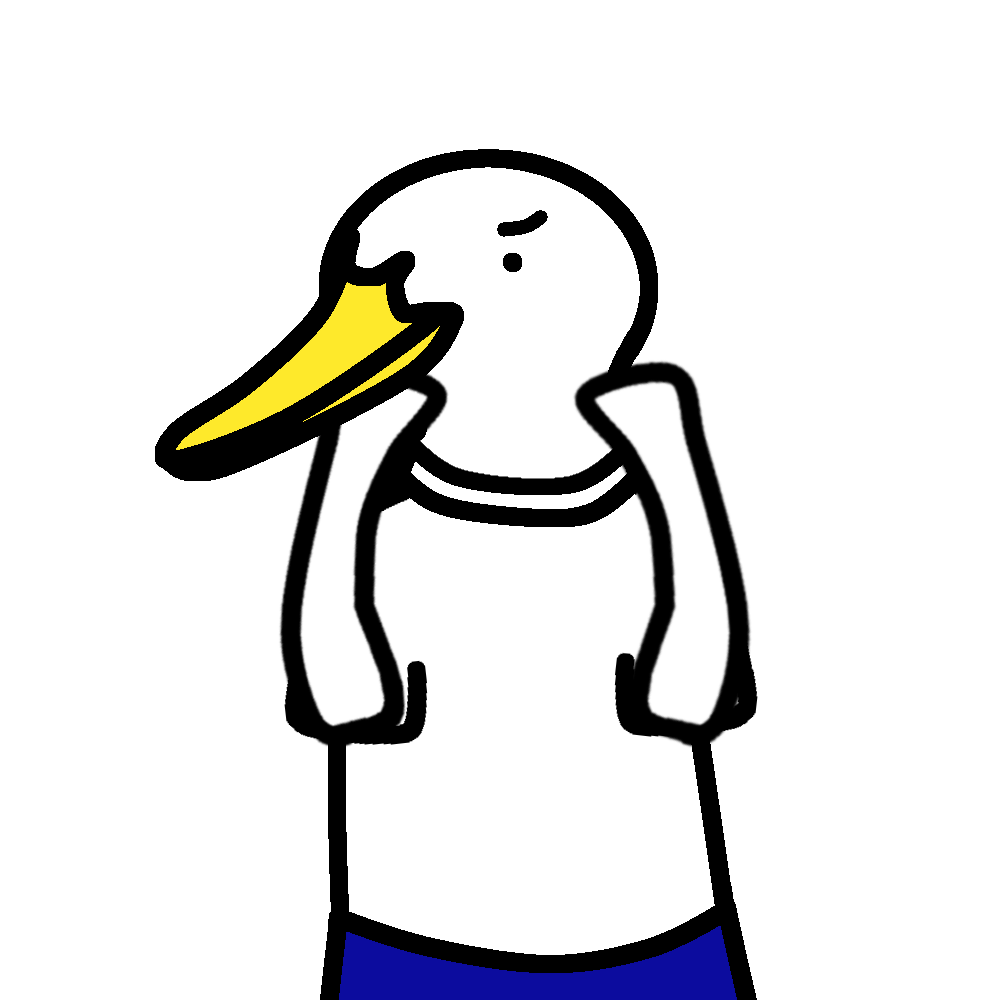
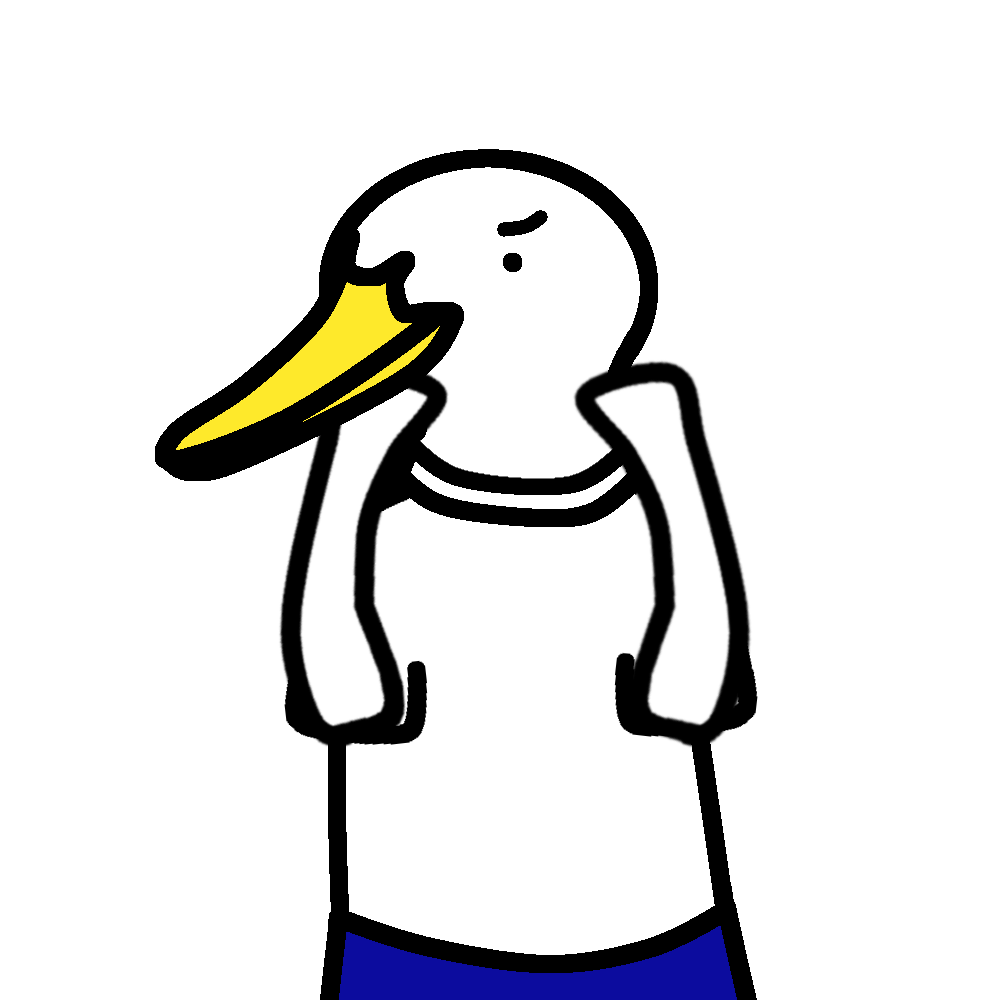
後で解説する「昭和57年4月30日判決」の理解の前提となる判例だね!
甲には、妻Yと、子Xらがいた。甲は、生前、Yに対し、書面によって自己所有不動産の死因贈与をしたが、Yとの関係が悪化したので、死因贈与を取り消した。他方、Yは、死因贈与に基づき、当該不動産について仮登記手続をしていた。その後、甲が死亡したため、Xらは、Yに対し、当該死因贈与契約の不存在の確認とYのなした仮登記の抹消登記手続を求めて裁判を起こした。
甲は、Yとの間の死因贈与を取り消しているところ、死因贈与に、遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部又は一部を撤回することができるとする民法1022条が準用されるかのが争点となった。
最高裁は、「死因贈与については遺言の取消に関する民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである」と判断しました。
まず、民法1022条の条文を確認しておきましょう。
(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
この規定が死因贈与に準用されるのであれば、贈与者は、死因贈与契約をした後に、一方的に死因贈与を取り消すことができることになります。死因贈与は、遺贈と異なり、当事者間の合意に基づくものです。契約の拘束力という観点から、準用が制限されるべきではないか、という問題意識があります。
結果として、最高裁は、1022条の準用を認めています。
その理由としては、贈与者の死後に関する財産の処分については、遺贈と同様に、贈与者の最終意思を尊重し、これによって決するのを相当、と述べています。
死因贈与は、贈与者の死亡によって効果を生ずるものであり、相続財産の処分行為といえます。この意味で、贈与者(被相続人)の最終意思が優先されるべきだという判断をしています。
契約の拘束力、契約の相手方の信頼よりも、贈与者の最終意思を尊重したと言えるかと思います。
①民法1022条の規定は、死因贈与に準用される。
②趣旨は、贈与者の死後に関する財産の処分については、遺贈と同様に、贈与者の最終意思を尊重し、これによって決するのが相当なため。
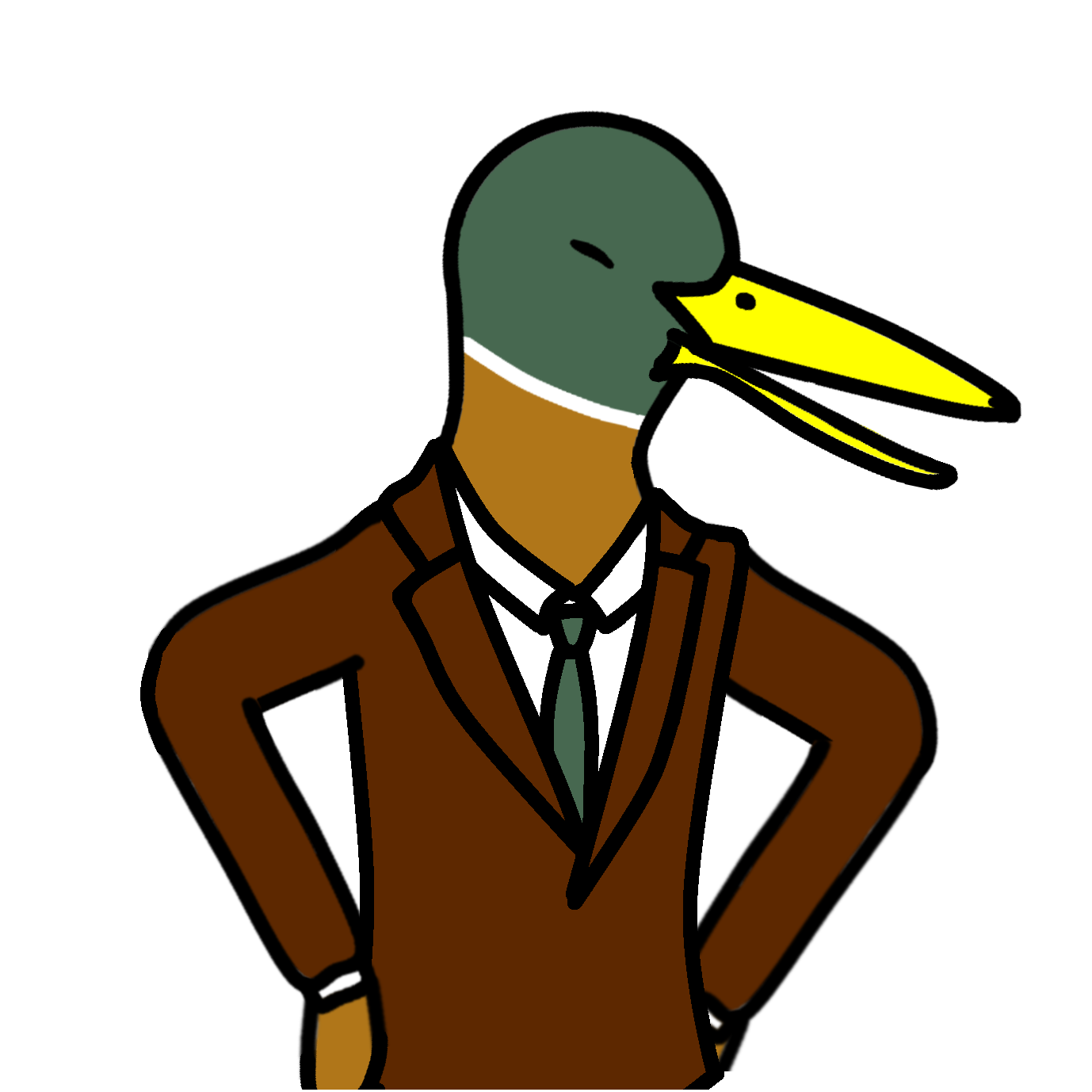
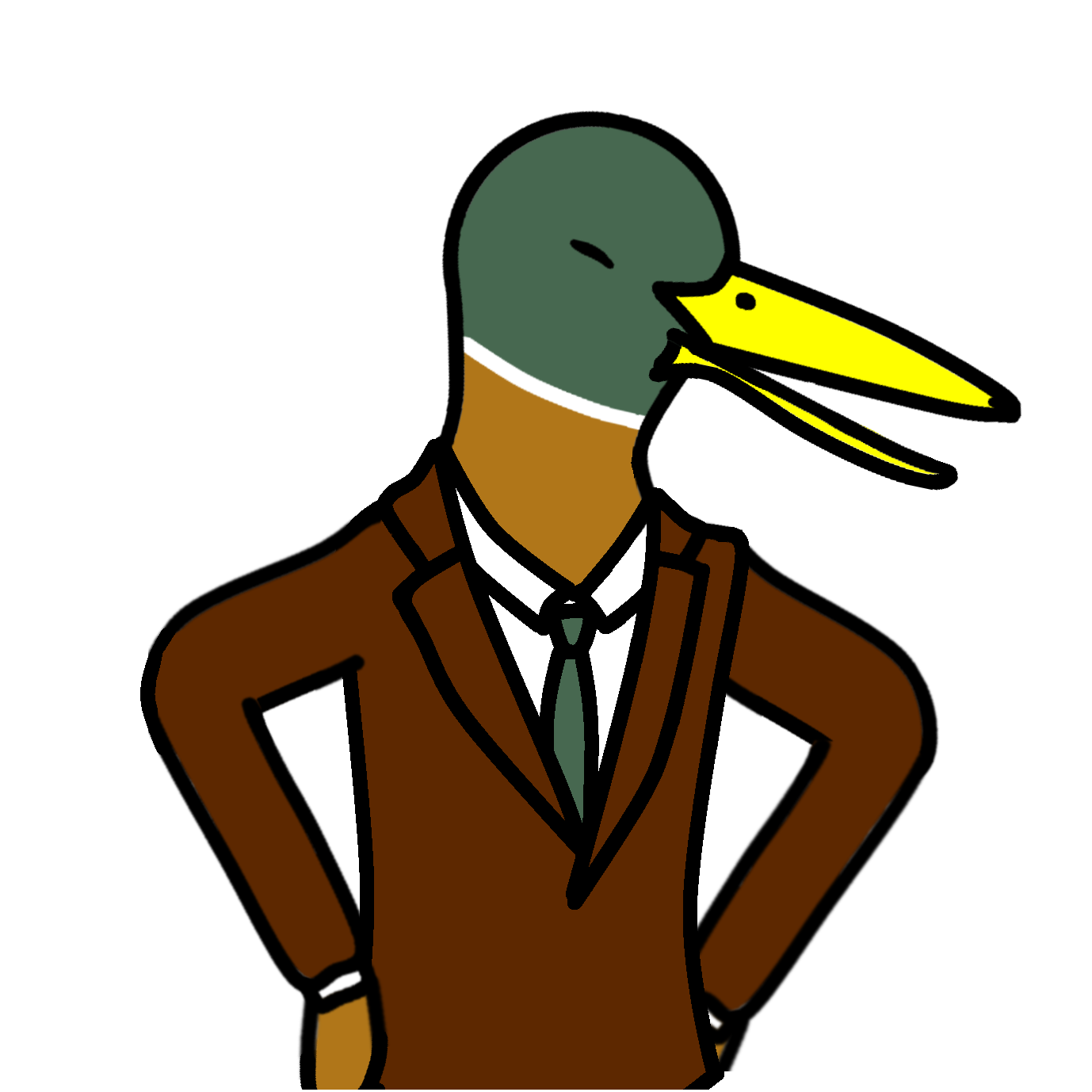
続いて、昭和57年4月30日判決について、その理解のポイントと論述のコツをご紹介したいと思います。


最高裁昭和57年4月30日判決は、判例百選にも掲載されている重要判例だね!
遺言者甲と、長男乙は、負担付き死因贈与契約を締結した。具体的には、乙の在職中、乙が甲に、定額贈与をし、これを履行した場合には、死因贈与として甲の財産の全てを乙に贈与するというものであった。
その後、甲は、乙の兄弟らに対して、所有する財産の一部を遺贈する内容の遺言(本件遺言)を作成した。
乙は、本件遺言が無効であるなどと主張した。
「負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法1022条、1023条の規定の準用の有無」(原文)
本件は、死因贈与の中でも、負担付き死因贈与契約において、負担がすでに履行されている場合に、遺言の取消の規定が準用されるのか、という点が争われました。
「負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法1022条、1023条の各規定は準用されない。」(原文)
「負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約に基づいて受贈者が約旨に従い負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては、贈与者の最終意思を尊重するの余り受贈者の利益を犠牲にすることは相当でないから」(原文)
まず、議論の前提として、死因贈与に関して、遺言の取消の規定が準用されることは認められています。
そのうえで、本判決は、負担付き遺贈のケースで、しかも、負担がすでに履行されている事例において、遺言の取消の準用が制限されるべきではないか、という点が争点となりました。
このような場合にまで、遺言取消の規定を準用すると、負担を履行した受贈者の理解を著しく害しないかという問題意識があります。
この点について、最高裁は、原則として、準用されない。特段の事情が認められる場合には、準用される、という判断枠組みを明らかにしました。
「特段の事情」の具体的な中身までは言及されていませんが、例えば、受贈者が贈与者に対して、忘恩行為をした場合、大きな事情変更などが学説上、指摘されているところです。
①負担付死因贈与の場合、原則として、民法1022条、1023条は準用されない。
②例外として、負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合、(右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし)右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がある場合には、民法1022条、1023条は準用される。
③例外の適用前提:「負担付死因贈与の受贈者が負担の全部またはこれに類する程度の履行をした」
④特段の事情の考慮事項:①契約締結の動機、②負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、③契約上の利害関係者間の身分関係、④その他生活関係等
⑤契約の全部または一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情が必要。
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。