
【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!
司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF
※閉じるとこの案内は7日間再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする


皆さん、かもっちです。数ある記事の中から本記事をお選び頂きありがとうございます。
本記事では、刑事訴訟法のおすすめの入門書、基本書、演習書、判例集、参考書をお探しですか。



刑事訴訟法のおすすめの書籍が知りたいです!



法書ログは、法律書籍専門の口コミサイトです。400件以上の口コミが投稿されています。
本記事では、当サイトに投稿された口コミを基に、おすすめの刑事訴訟法の書籍(基本書、演習書、判例集、参考書、入門書)を紹介しているから、きっと参考になると思うぞ。
法書ログは、法律書籍専門の口コミサイトです。各試験(司法試験、予備試験、行政書士試験など)の合格者や受験生の口コミを閲覧することができます。また、レビューをシェアしたい書籍があれば、登録不要で口コミを投稿することができます。
\本記事を読めば分かること/
・刑事訴訟法のおすすめの入門書
・刑事訴訟法のおすすめの基本書
・刑事訴訟法のおすすめの演習書
・刑事訴訟法のおすすめの判例集
・刑事訴訟法のおすすめの参考書
それでは、さっそく、おすすめの刑事訴訟法の書籍をご紹介していきたいと思います。ジャンル別にご紹介させて頂きます。まずは、入門書からご紹介させて頂きます。



やあ、法律を学ぶみんな!
今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!



そうなのそうなの〜!
受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨



特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!



あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱
お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!
📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】
司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!
現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。
\ このタイミングを逃す手はありません /
合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。


まずは、刑事訴訟法のおすすめの入門書から紹介していきます。これから刑事訴訟法を勉強をしていくという方は、入門書から読み進めるようにしましょう。いきなり基本書から読み始めると、挫折に繋がりかねません。
刑事訴訟法のポイントは、まずは、刑事手続きの流れを押さえることです。
論点は、飛ばして、全体の手続きの流れを押さえることを当分の目標にしましょう。



刑事訴訟法のおすすめの入門書はこの2冊だ!
・伊藤真の刑事訴訟法入門 講義再現版
・入門刑事手続法
憲法的刑事訴訟法の理念を基礎にいち早く平成28年刑訴法改正の解説を織り込んだ定番入門書の改訂版。新しい刑訴法の重要問題もコラムでわかりやすく解説。
わかりやすい入門書
刑事訴訟法は、正直おすすめできる入門書が少ない状況下にあります。伊藤塾出版のこの本は、講義形式で読みやすくかつわかりやすい記載となっており、刑事訴訟法の全体像を掴むための本として非常に有用であると思います。
したがってこの本を読まれることを強く推奨いたします。
https://lawbooks-reviews.com/archives/lawbooks/7521
ステップアップに
本書は刑事訴訟法の入門書で、手続きの流れに沿って説明するものとなります。似たような内容のもので基本刑事訴訟法Ⅰがありますが、そちらはとは違ってケースを用いず欄外に条文を示して淡々と説明していく形になります。また、逮捕状等、書面の具体例が示されているので模擬裁判にも有用です(著者のふたりは模擬裁判で使えるように配慮したとのこと)。
もっとも論点への深堀りはないため別の書籍で補充することが前提になってるでしょう。
https://lawbooks-reviews.com/archives/lawbooks/ks1
刑事訴訟法の基本書を選ぶ際には、以下の点を確認してみましょう。
・具体例が豊富か?
・検索性がしやすいか?
・刑事の手続の流れがビジュアル化されているか?
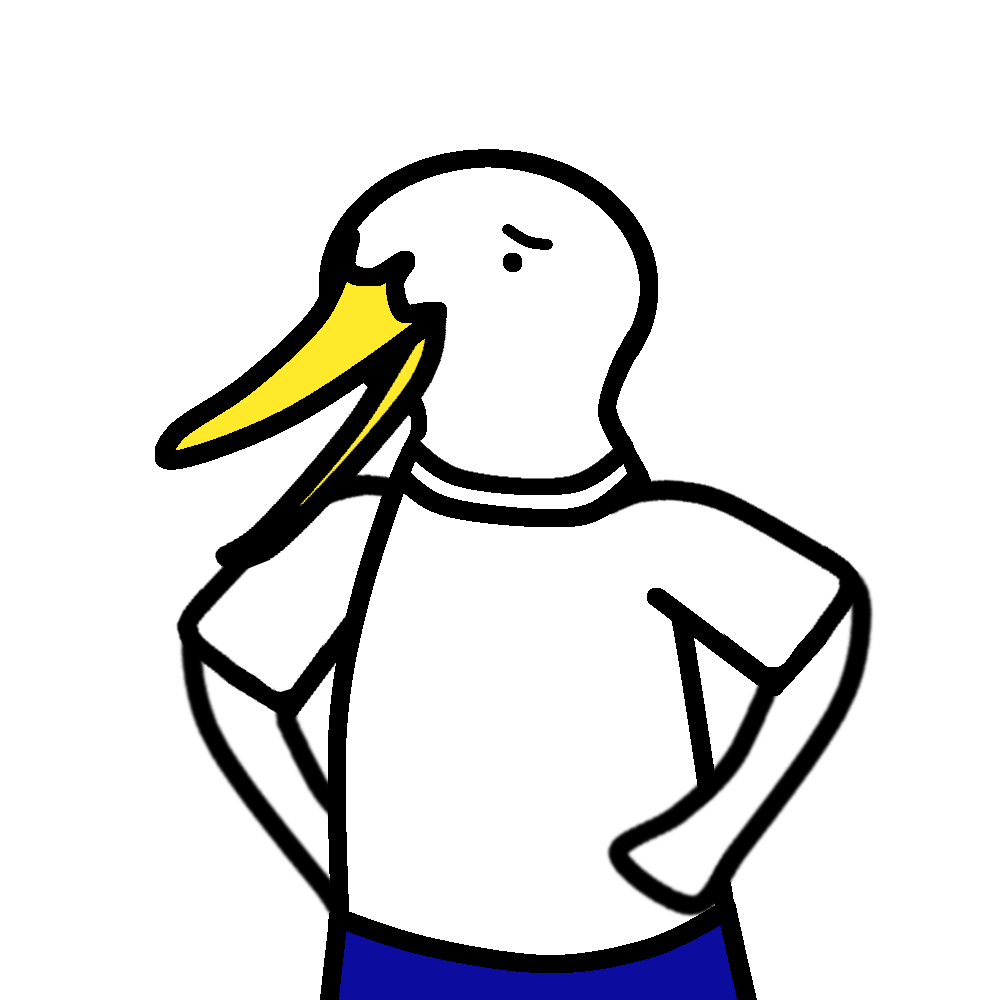
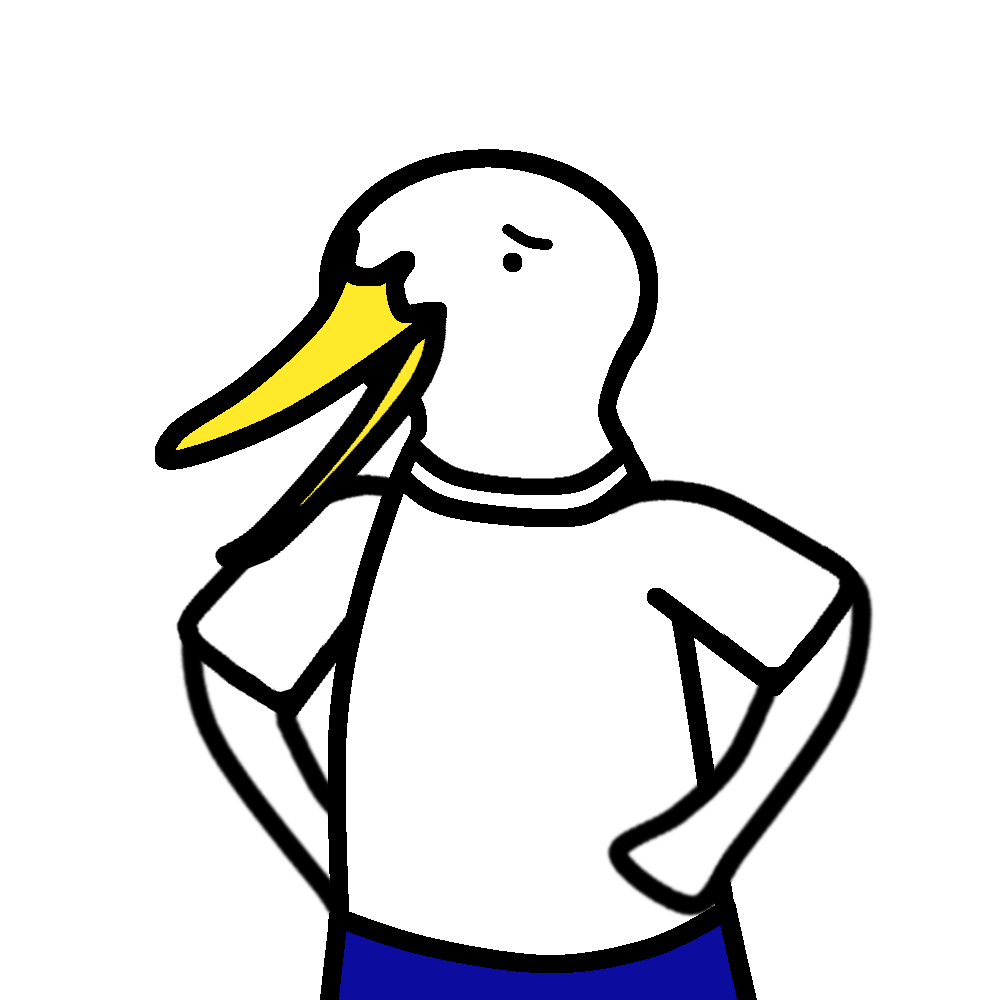
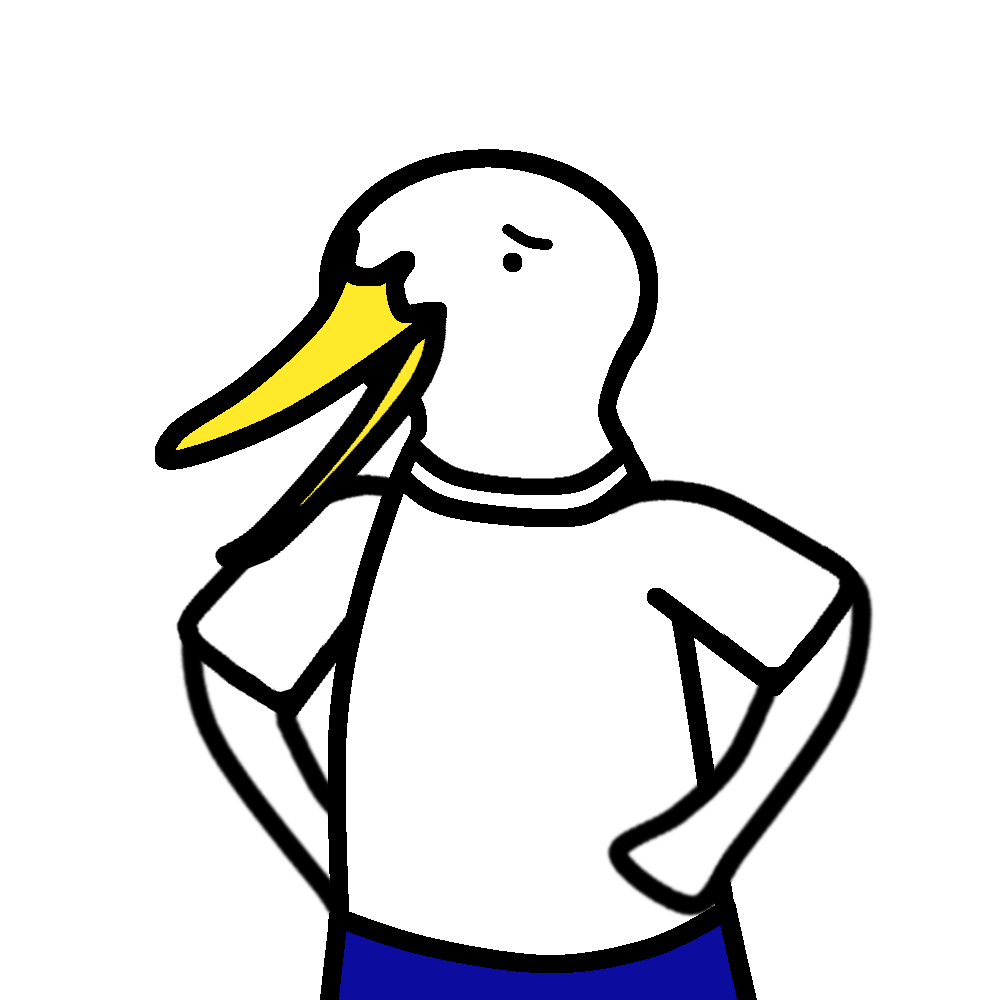
刑事訴訟法のおすすめの禁書はこの3冊だよ!
・基本刑事訴訟法I 手続理解編
・刑事訴訟法(酒巻)
・刑事訴訟法 (LEGAL QUEST)
手続の理解には最適か
本の題名にある通り,手続理解に即した内容です。
刑事裁判修習中に参照し活用することができました。刑事手続中に必要となる書類の例が記載されていたりとイメージを掴みがら読み進めることができます。
もっとも,論点に深入りしていないため,この一冊では司法試験対策の観点では不足するといえるでしょう。
その点に注意したいところです。
https://lawbooks-reviews.com/archives/lawbooks/7530
松尾門下の信頼出来る1冊
ハードカバー,頁数が多い,値段もそこそこ高いため,手を出す学生は少ないように思えるが,個人的には刑事訴訟法の本の中でいちばん信頼におけるものであると考える。
刑事訴訟法で人気の分野はリーガルクエストであるが,当該書籍は共著であり,他にも人気が出ている基本刑事訴訟法や前田先生等による刑事訴訟法(6版)も同様である。共著であれば必ずその弊害がどこかに隠れており,初学者は気づかない危険がある。そのリスクを避けるには単著が1番安全である。
本書は自説が多いものの,内容としては比較的穏当な見解に留まっており,渥美先生や白取先生などのように独自説に突っ走るような箇所も見受けられない。もっとも初版は参考文献の記載がほとんどなかったとの批判から2版について参考文献を充実させたとの事だが,そこまで変わっておらず,学説などを知りたい人には向かないように思える。
https://lawbooks-reviews.com/archives/lawbooks/ks2
刑事訴訟法はここから初めるべき
刑事訴訟法は、学者ごとにそもそもの体系が違ったり説も百家争鳴に近い状態にある学問ではあるが、その中でもリークエは判例、通説に沿った1番の教科書だと思う。これをベースに図書館等で酒巻教授や川出教授の体系書をめくりながら勉強をすれば受験において必要な知識は十分身につくと思う。
https://lawbooks-reviews.com/archives/lawbooks/ks3
・シャア率が高いか?
・解説が豊富か?
・問題のレベルが自分にあったか?
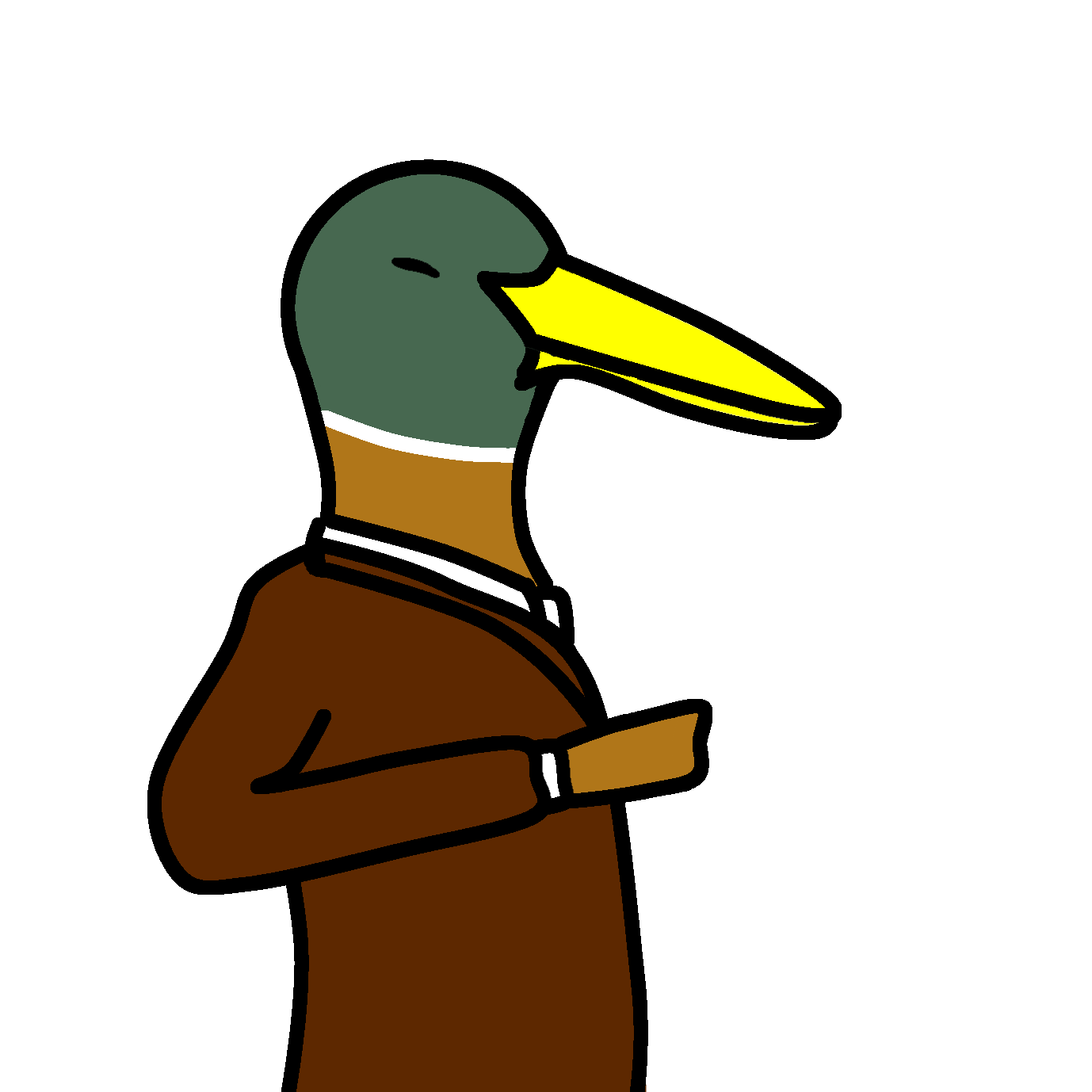
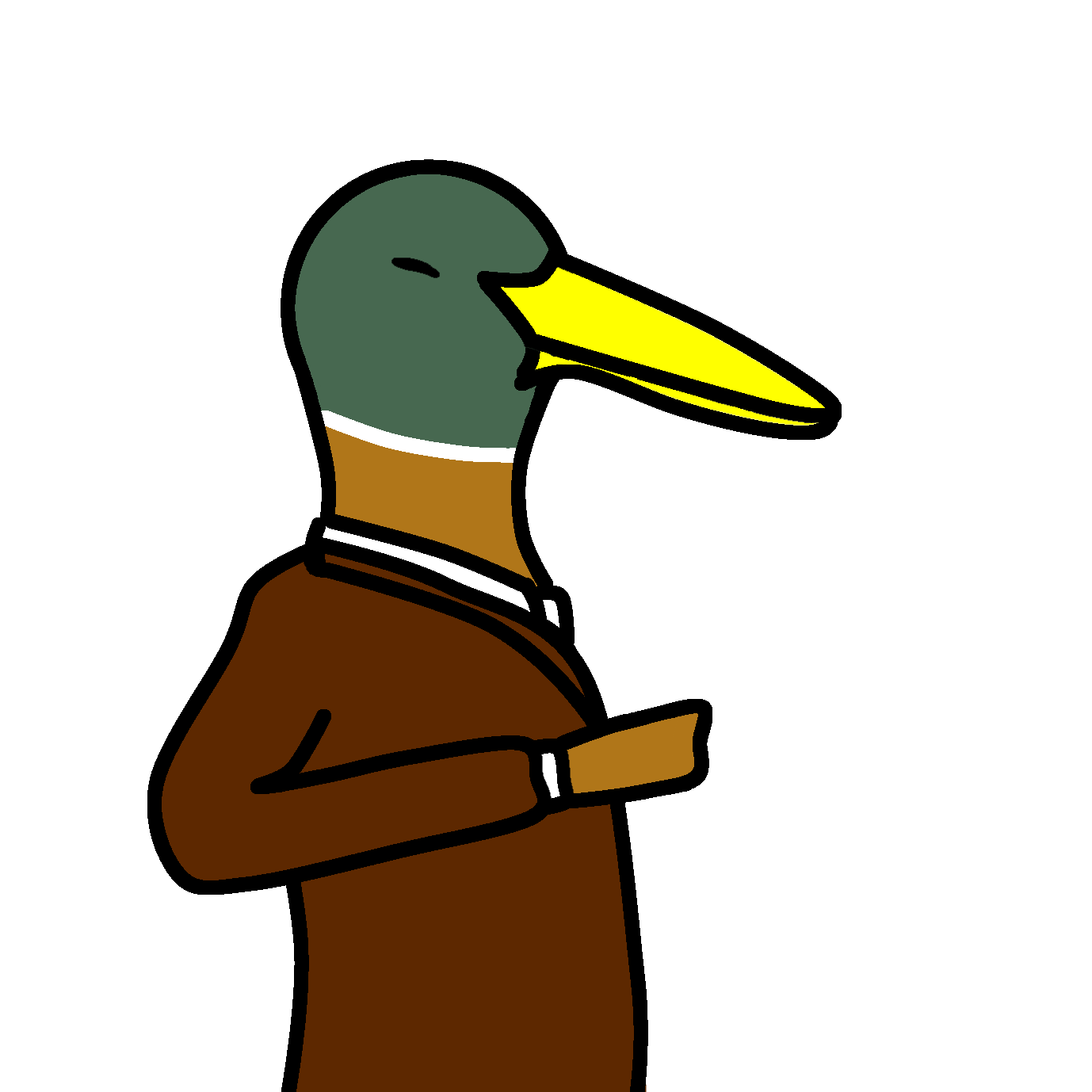
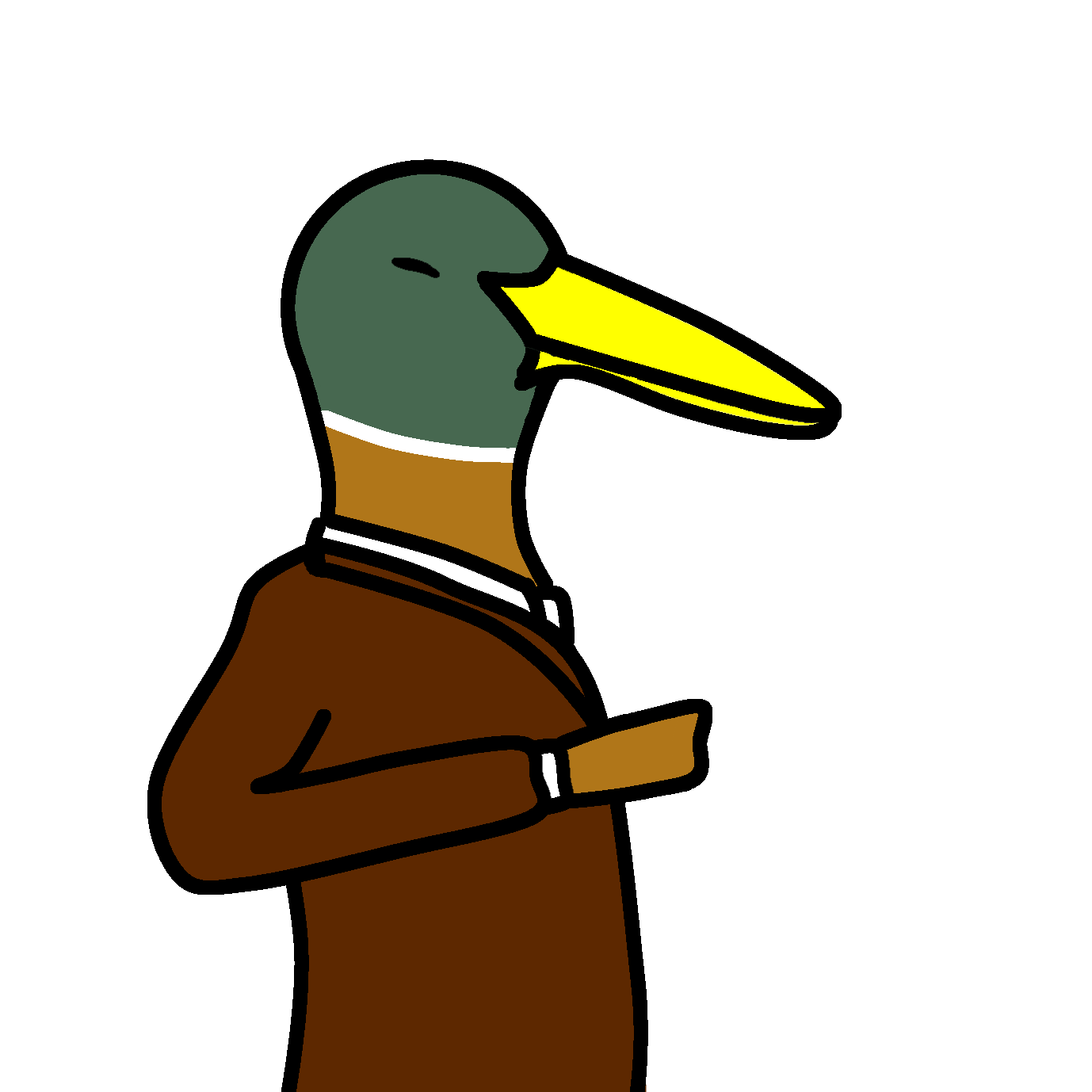
刑事訴訟法のおすすめの演習書はこれだ!
・事例演習教材刑事訴訟法
論点についてはこれ一冊でOK
比較的短文の事例問題をもとに、そこから問題となる論点を学生と教授の対話形式で解説している。学説なども反対説などを踏まえながら解説しているので、反対説まで知っていないと解けないような近年の司法試験にも対応している。
ちなみに、演習書というよりは論点理解の参考書といったイメージ。だから規範を立てるところまではめちゃくちゃ勉強になるが、当てはめまでは対応していないかな。
これで論点についてマスターし、あとはエクササイズ刑訴などで演習すれば完璧だと思います。
https://lawbooks-reviews.com/archives/lawbooks/7531
司法試験であれ、予備試験であれ判例学習は非常に大切です。試験の問題は、判例の事案を基に作られていることが多いです。判例の事案をベースに事情を追加したり、事情を変更したりして作られていることが多いです。試験委員は、重要判例の事案の概要と判旨を当然理解しているものとして、問題を作成しております。
基本書や演習書の学習を通して、判例を学習することができますが、判例は、判例集を使って一つずつ勉強をするべきです。
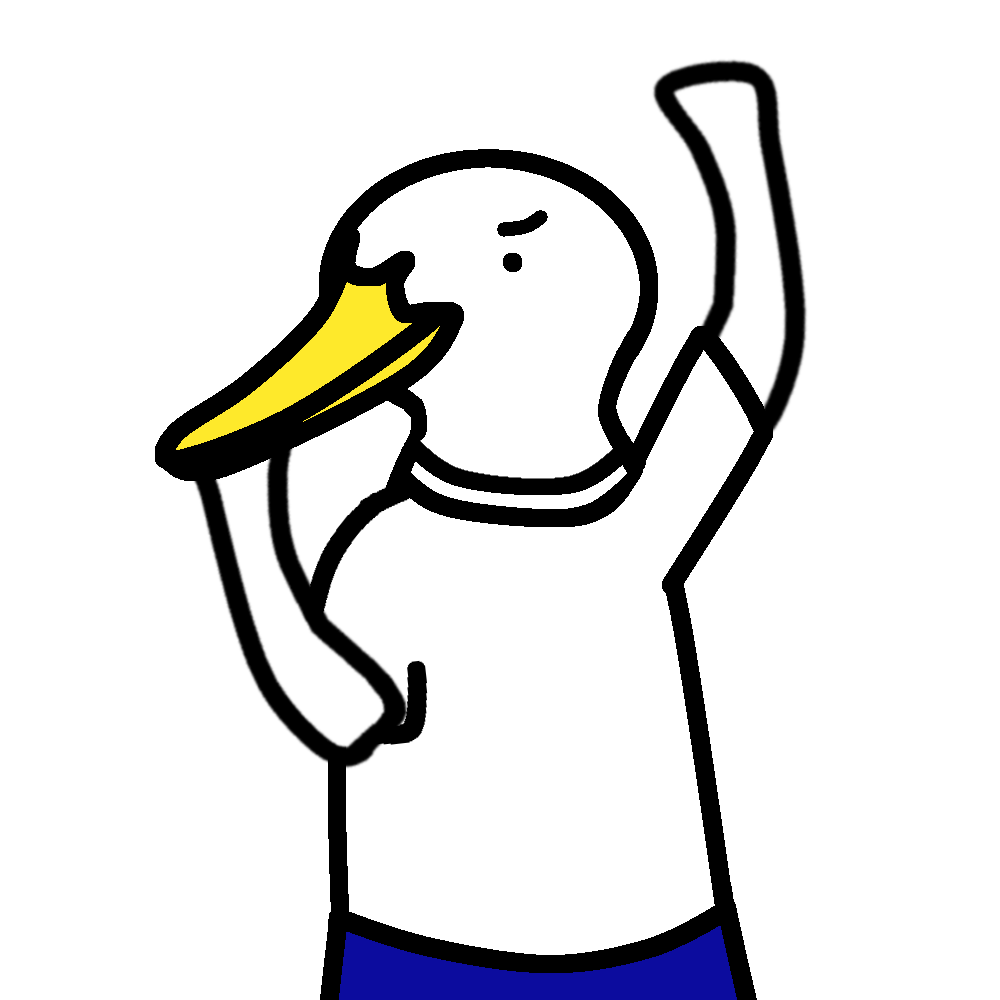
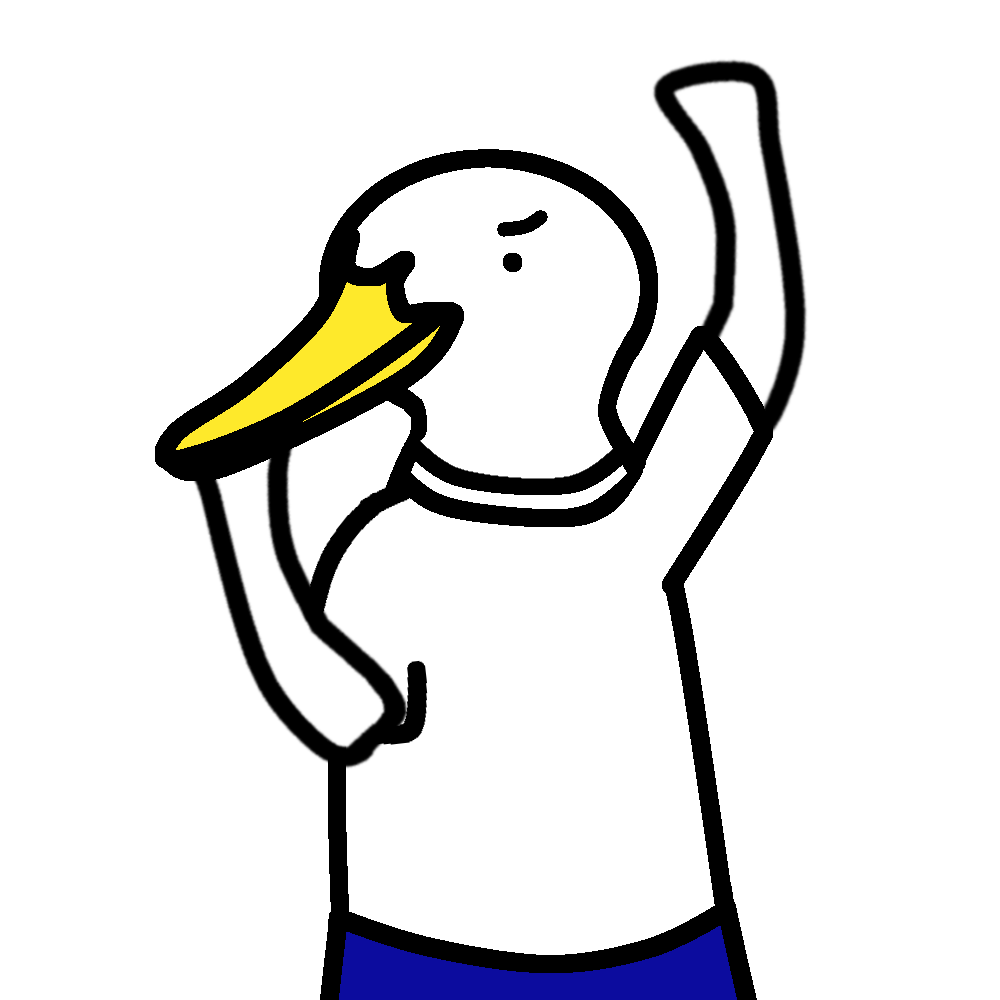
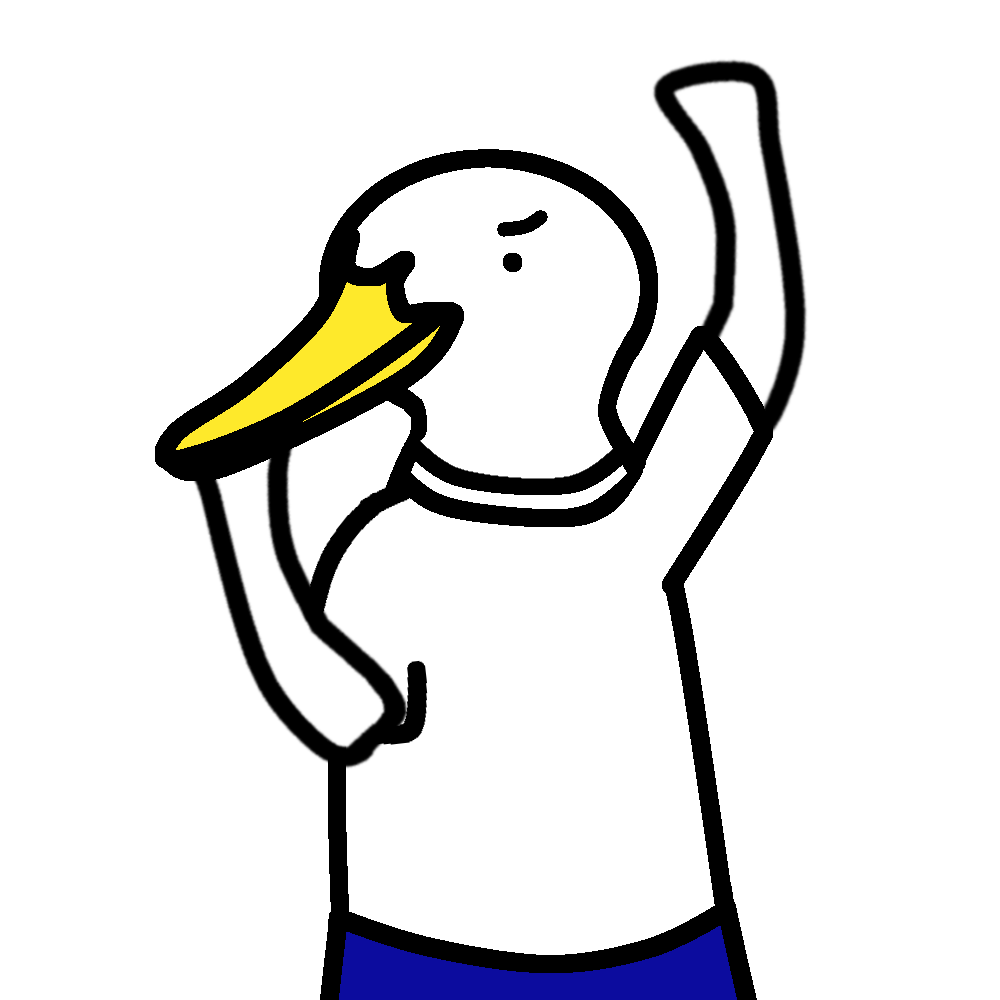
刑事訴訟法のおすすめの判例集はこれだよ!
・刑事訴訟法判例百選
判例教材の定番シリーズ,待望の第10版! 刑事訴訟法の理解に不可欠な最重要判例を精選,分類・整序し,簡潔・的確に解説する決定版。気鋭の研究者・実務家による信頼の判例解説(計100件ほかアペンディックス56件・統計資料)。
Ⅰ 捜 査
捜査の端緒と任意捜査
強制捜査
被疑者の権利
Ⅱ 公訴の提起
Ⅲ 訴因と公訴事実
Ⅳ 公 判
裁判所および訴訟関与者
公判準備および公判手続
Ⅴ 証 拠
証拠による証明
証 人
Ⅵ 自 白
Ⅶ 伝聞証拠
Ⅷ 違法収集証拠
Ⅸ 裁判・上訴
(計100件ほかアペンディックス56件・統計資料)
勉強は、基本書、演習書、判例集の3点を回して勉強するのが基本です。しかし、基本書、演習書、判例集だけでも理解が難しいこともあるでしょう。
そんな時に頼りになるのが、参考書です。参考書をうまく使って勉強を効率よく進めましょう。



刑事訴訟法のおすすめの参考書はこの2冊だよ!
・刑事訴訟法の思考プロセス (法セミLAWCLASSシリーズ)
・アガルートの司法試験・予備試験 合格論証集 刑法・刑事訴訟法
2016年刑訴法改正に対応。標準的な法学部生向けのテキスト。 刑事訴訟法の考え方を思考プロセスから学ぶ工夫にあふれた新機軸。
第1章 刑事訴訟法の目的とその基本思想
第2章 捜査法の基本的な思考プロセス
第3章 行政警察活動に対する法的規律とその思考プロセス
第4章 任意処分に対する法的規律とその諸問題
第5章 憲法35条から導かれる捜索・差押えの基本的な思考プロセス
第6章 令状主義の趣旨と要請から導かれる法的規律と適法性判断の
視点を活用する
第7章 令状主義から導かれる逮捕に伴う無令状捜索・
差押えに対する法的規律
第8章 強制処分を統制する規律としての強制処分法定主義、
そして令状主義
第9章 被疑者の身体拘束制度とその諸問題
第10章 憲法33条の令状主義と逮捕に対する法的規律
第11章 逮捕・勾留に関する諸原則を活用する思考プロセス
第12章 被疑者取調べに対する法的規律の現状とその問題点
第13章 被疑者の防御権の内容とその制限の適法性判断
――弁護人依頼権を題材として
第14章 公訴の提起・追行とその規制
第15章 協議・合意制度の構造と手続
第16章 訴因論の思考プロセスとその活用1――訴因の特定
第17章 訴因論の思考プロセスとその活用2――訴因変更の要否
第18章 公判前整理手続と証拠開示
第19章 証拠法の基本的思考プロセス1
第20章 証拠法の基本的思考プロセス2
――「関連性」と証拠能力の判断プロセス
第21章 証拠法の基本的思考プロセス3
――刑訴法320条1項の適否を判断する思考プロセス
第22章 証拠法の基本的思考プロセス4
――刑訴法321条以下の伝聞例外規定を活用する
第23章 証拠法の基本的思考プロセス5
――違法収集証拠排除法則の基本的思考プロセスとその活用
第24章 証拠法の基本的思考プロセス6
司法試験・予備試験受験 待望の論証集 続刊! 1.最新の判例に完全対応 2.アガルートアカデミー講師の書き下ろし 3.論証を精査しブラッシュアップ 発行:アガルート・パブリッシング
本書伝聞法則に特化した参考書で,法学セミナーの連載を加筆して単行本化したもの(はしがきⅰ頁)。
著者は研究者。
伝聞法則に特化した参考書としては本書の他に「事例でわかる伝聞法則」(弘文堂)もあるので,これと対比しつつレビューしたい。
本書が「事例でわかる伝聞法則」より優れている点は,私見では,第1章伝聞証拠とは何か,の記述にある。伝聞証拠の定義については他の基本書や「事例でわかる伝聞法則」にも当然,記述はあるが,本書は,供述概念(第1章2)から論じることで,伝聞証拠の規範を相対的にみて厳密に導出している。
>>>続きはこちら
伝聞法則に特化した参考書。
著者は弁護士であり,実はこれが本書の最大の特徴。
受験生が伝聞法則につまづく最大の理由は,私見では,立証構造が把握できていないために,供述の内容の真実性が問題となっているか否かの判別ができないことにある。
本書は弁護士,つまり法廷で検察官の立証構造を吟味する立場にある者による本であり,大げさにいえば,立証構造を把握できるようになるメソッドを知り尽くしている者といえる。
本書はまず,「基本書を見てみても,実際の裁判で具体的にどういう供述が伝聞になり,あるいは非伝聞になるのかといった具体的なことは今ひとつわからない」「学生にこの壁を越えてもらうには,とくかく擬似的にでも法廷における実務体験をしてもらうしかない」(はしがきⅱ頁)と問題提起する。そして,その解決のために,「いわゆる論点を含まない事例も多く検討し」「実務感覚を擬似的に体験できるよう,事例問題を中心に極力具体的な記述を心がけ」ている(同ⅲ頁)。
確かに,手続法の学習のポイントは論点を含まない,平常時の手続の把握にあり,論点という,いわば法廷における限界事例のみを学習すると,かえって全体像の理解が遅れることになる。
論証集は、司法試験受験生や予備試験受験生にとっては、非常に有益なツールです。おすすめの論証集を知りたい方は以下の記事をご確認ください。
>>【2024年】司法試験受験生におすすめの論証集4選と利用するメリット
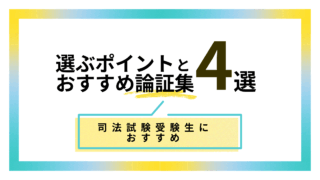
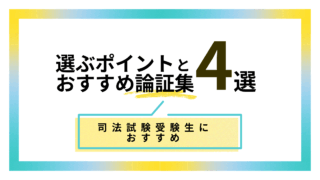
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。


司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
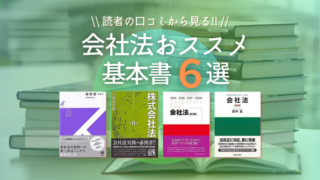
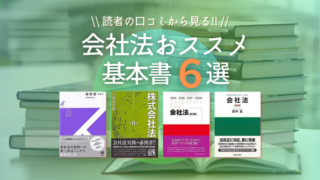






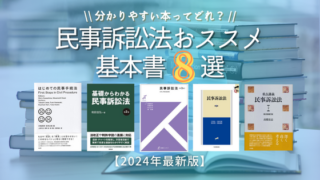
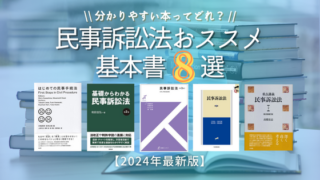






勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

