
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
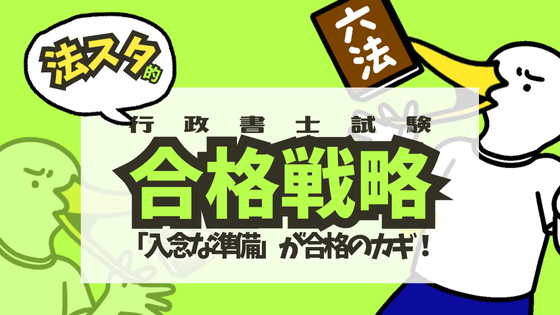
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする


ねぇねぇ、かもっち〜。最近さ、将来のこと真剣に考えてて…
「なんか、自分の力で働ける資格がほしいな〜」って思ってるんだけど…何がいいと思う?🤔



お、ついに“本気モード”だな。だったら…おすすめは「行政書士」だな。



ぎょ、ぎょうせいしょし??それってなんかカタイ名前だよぉ〜💦
ぼくみたいなポンコツでも目指せるの…?



もちろん。行政書士は、年齢も学歴も関係なく誰でも受験できるんだ。
そして、合格すれば「書類のプロ」として、相続・許認可・外国人支援とか…いろんな分野で活躍できる。
しかも、独立開業もできるし、会社勤めの人にも強い武器になるんだぞ。



な、なんかカッコいいかもぉ…✨
でも難しいんでしょ?合格率とかヤバそうなイメージある〜😰



確かに、合格率は毎年10%前後で簡単じゃない。でも逆に言えば、“正しい方向で勉強すればちゃんと受かる試験”なんだよ。
この記事では、そのための「地図とコンパス」を全部まとめてるから、あひるっぺでも大丈夫。



おぉ〜!それなら読んでみたいかも〜!!🔥
夢をカタチにするための一歩、いっしょに踏み出すんだ〜!!
「法律の専門家になって、人生を変えたい」「いつかは独立して、自分の力で働きたい」——
そんな思いを抱える多くの方に選ばれているのが、行政書士という国家資格です。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続き代理を通じて、人々の暮らしやビジネスを支える“街の法律家”。近年では、相続・在留資格・建設業許可・補助金申請など、社会の多様化に伴って活躍のフィールドも拡大しています。
しかも、受験資格に制限がなく、学歴・年齢・職歴を問わず誰でもチャレンジできる点も大きな魅力。正しい戦略と努力次第で、法学未経験者でも十分に合格を狙える資格です。
とはいえ、行政書士試験の合格率は例年10%前後と決して甘くはありません。多くの受験生が途中で挫折してしまうのも事実です。
この記事では、これから行政書士を目指す方に向けて、試験制度の全体像から科目別対策、勉強法、モチベーション管理に至るまでを、3万字の大ボリュームで徹底的に解説します。
法律学習が初めての方も、再チャレンジを考えている方も、この記事を読めば合格までの道筋がクリアに見えてくるはずです。
資格を、キャリアの転機に。
人生を、自分の手で動かす力を。
そんなあなたの挑戦を、この記事が全力でサポートします。
「街の法律家」として、私たちの暮らしやビジネスを法的な側面からサポートする行政書士。その資格は、法律系国家資格の中でも挑戦しやすく、かつ独立開業やキャリアアップに繋がる魅力的な選択肢として、近年ますます注目を集めています。しかし、合格のためには正しい知識と戦略に基づいた学習が不可欠です。
行政書士の主な業務は、官公署(役所など)に提出する書類の作成やその代理申請、そしてそれに伴う相談業務です。例えば、飲食店を開業するための営業許可申請、建設業を始めるための許可申請、外国人の在留資格に関する手続き、あるいは遺言書の作成支援や相続手続きなど、その業務範囲は非常に多岐にわたります。
この仕事の魅力は、何と言っても人々の夢の実現や困りごとの解決に直接貢献できる点にあります。「あなたの会社を設立したい」「新しいビジネスを始めたい」といった前向きなサポートから、「法的な手続きが分からず困っている」という切実な悩みに寄り添うことまで、行政書士は法的な知識を駆使して社会の潤滑油のような役割を果たします。
資格を取得することで、専門知識が身につくだけでなく、独立開業という道も現実的な選択肢となります。自身の裁量で仕事を進め、地域社会に貢献できることは大きなやりがいとなるでしょう。また、企業内で法務や総務を担当する際にも、行政書士の知識は大きな強みとなります。
行政書士試験は、法律系国家資格の中では比較的挑戦しやすいと言われることもありますが、決して簡単な試験ではありません。例年の合格率は10%前後で推移しており、しっかりと対策を練らなければ合格は難しいのが実情です。
直近の試験結果を見てみましょう。
例えば、令和5年度(2023年度)の試験では、申込者数59,460人に対し、受験者数は46,991人、合格者数は6,571人で、合格率は13.98%でした。令和4年度(2022年度)は合格率12.13%、令和3年度(2021年度)は11.18%となっており、概ね10~14%程度で推移しています。この数字からも、多くの受験者が涙をのんでいる厳しい試験であることが分かります。 (参考:一般財団法人行政書士試験研究センター 試験結果の概要)
しかし、見方を変えれば、毎年数千人の方が合格を手にしていることも事実です。
正しい方向性で、必要な量の努力を継続すれば、必ず合格は見えてきます。少子高齢化やグローバル化、デジタル化といった社会の変化に伴い、行政書士が活躍できるフィールドは今後ますます広がっていくと予想されます。
例えば、ドローン飛行許可申請や各種補助金申請支援など、新しいニーズも生まれています。
この記事は、行政書士試験合格を目指すすべての方に向けて、3万字という圧倒的な情報量で、合格に必要な知識とノウハウを網羅的にお伝えすることを目的としています。
具体的には、以下の内容を盛り込んでいます。
法律学習が初めての方から、再受験で今年こそ合格を掴みたい方まで、すべての受験生が安心して学習に取り組めるよう、具体的な情報と実践的なアドバイスをふんだんに盛り込みました。この記事が、あなたの行政書士試験合格への確かなロードマップとなり、夢の実現の一助となれば幸いです。さあ、一緒に合格への第一歩を踏み出しましょう。



かもっちー!ぼく、行政書士の勉強始めるって決めたんだけど〜…なにからやればいいか、もう全然わかんないかも〜🌀



お、いいじゃないか。…でも、いきなりテキストを読み始めるんじゃなくて、まずは“全体像”をつかむことが大事だぞ。



ぜんたいぞう…?なんか…でっかい?



そう。行政書士試験って、実は“何が出るか”“どうすれば合格できるか”が、最初にわかってないと勉強の方向がズレちゃうんだ。最短ルートを進むには、まず地図を見ることからなんだよ。



たしかに、地図なしで森に入ったら、ぐるぐる迷っちゃうもんねぇ〜🌲



よし、じゃあこの第1章で、試験の仕組みとルールをばっちり整理していくぞ。



おっけーかも!しっかり読んで、冒険の準備をととのえるんだ〜🔥
行政書士試験の学習を本格的に始める前に、まずは試験制度の全体像を正確に把握することが不可欠です。どのようなルールで試験が実施され、何が問われ、どうすれば合格できるのか。ここでは、行政書士試験の基本的な情報を網羅的に解説します。
行政書士試験の大きな特徴の一つは、受験資格に制限がないことです。年齢、学歴、国籍、実務経験などを問わず、どなたでも受験することができます。中学生や高校生が合格するケースもあれば、定年後に新たな挑戦として受験される方もいらっしゃいます。間口が広く開かれているため、多くの方に資格取得のチャンスがある試験と言えるでしょう。
行政書士試験は、「行政書士の業務に関し必要な法令等科目」と「行政書士の業務に関連する一般知識等科目」の2つに大別されます。



行政書士試験の問題は
⑴行政書士の業務に関し必要な法令等科目
と
⑵行政書士の業務に関連する一般知識等科目
から出題されるんだ!
行政書士試験は、総得点300点満点の試験です。合格するためには、以下の3つの基準をすべて満たす必要があります。
この3つの基準のうち、1つでも満たせない場合は不合格となります。特に注意が必要なのは、一般知識等科目の「足切り」です。たとえ法令等科目で高得点を取っても、一般知識等科目で24点未満(14問中5問以下しか正解できない場合など)だと、それだけで不合格になってしまいます。バランスの取れた学習が求められる試験と言えます。
行政書士試験の出題傾向は、毎年細かな変化はありますが、全体として基本的な知識を正確に理解し、それを事案に当てはめて考える能力が重視される傾向にあります。
詳細な科目別対策は後の章で詳述しますが、まずは試験全体の構造と合格基準をしっかりと頭に入れ、学習計画の土台としましょう。



かもっち〜、ぼくついにテキスト買っちゃったんだよ〜📚✨
もう今日からどんどん読みまくって、ばりばり勉強していくかも〜🔥!



…ちょっと待った、あひるっぺ。
気合いはすごくいい。でもな、いきなり走り出す前に「準備」が超大事なんだ。



えっ、準備って…えんぴつ削るとか?🖍️💦



いやいや、そういう物理的な準備も大事だけど、それより
「目標をどう設定するか」とか「どんな教材を使うか」とか、「どこで勉強するか」みたいな“戦略面の準備”がカギなんだ。



なるほどぉ〜…たしかに地図もコンパスも持たずに森に入ったら、すぐ迷子になるかも…🌲🌀



そのとおり。ここから先は、「学習スタート前に絶対押さえておきたいこと」をぜんぶ整理してある。
これを読めば、あひるっぺも安心して出発できるはずだぞ。



うんっ、ちゃんと準備してから、かっこよくスタート切るんだ〜!!💪✨
行政書士試験合格という目標を掲げたなら、やみくもに勉強を始めるのではなく、まずは入念な準備と心構えを整えることが成功への鍵となります。
この章では、学習をスタートする前に押さえておくべきポイントを具体的に解説します。
何事も、明確な目標がなければ進むべき方向を見失いがちです。行政書士試験の学習を始めるにあたり、まずは以下の点を具体的に設定しましょう。
これらの目標設定は、学習の羅針盤となります。定期的に見直し、必要に応じて修正していくことも大切です。
行政書士試験の学習方法は、大きく分けて「独学」「予備校(通学・オンライン)」「通信講座」の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況や性格に合わせて最適なスタイルを選びましょう。
自分に合った学習スタイルの選び方 上記のメリット・デメリットに加え、以下の点を考慮して総合的に判断しましょう。
複数の選択肢を比較検討し、無料説明会や体験講義があれば積極的に参加してみることをお勧めします。
どの学習スタイルを選ぶにしても、教材選びは合否を左右する非常に重要な要素です。ここでは、主な教材の種類と選び方のポイントを解説します。
教材選びの注意点
長期間にわたる試験勉強では、集中して学習に取り組める環境を整えることが非常に重要です。
最後に、学習を始めるにあたっての心構えです。
これらの準備と心構えを整え、いよいよ本格的な学習のスタートラインに立ちましょう。次の章からは、具体的な科目別対策について解説していきます。
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
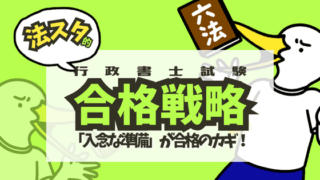
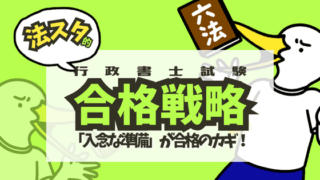
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

