
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
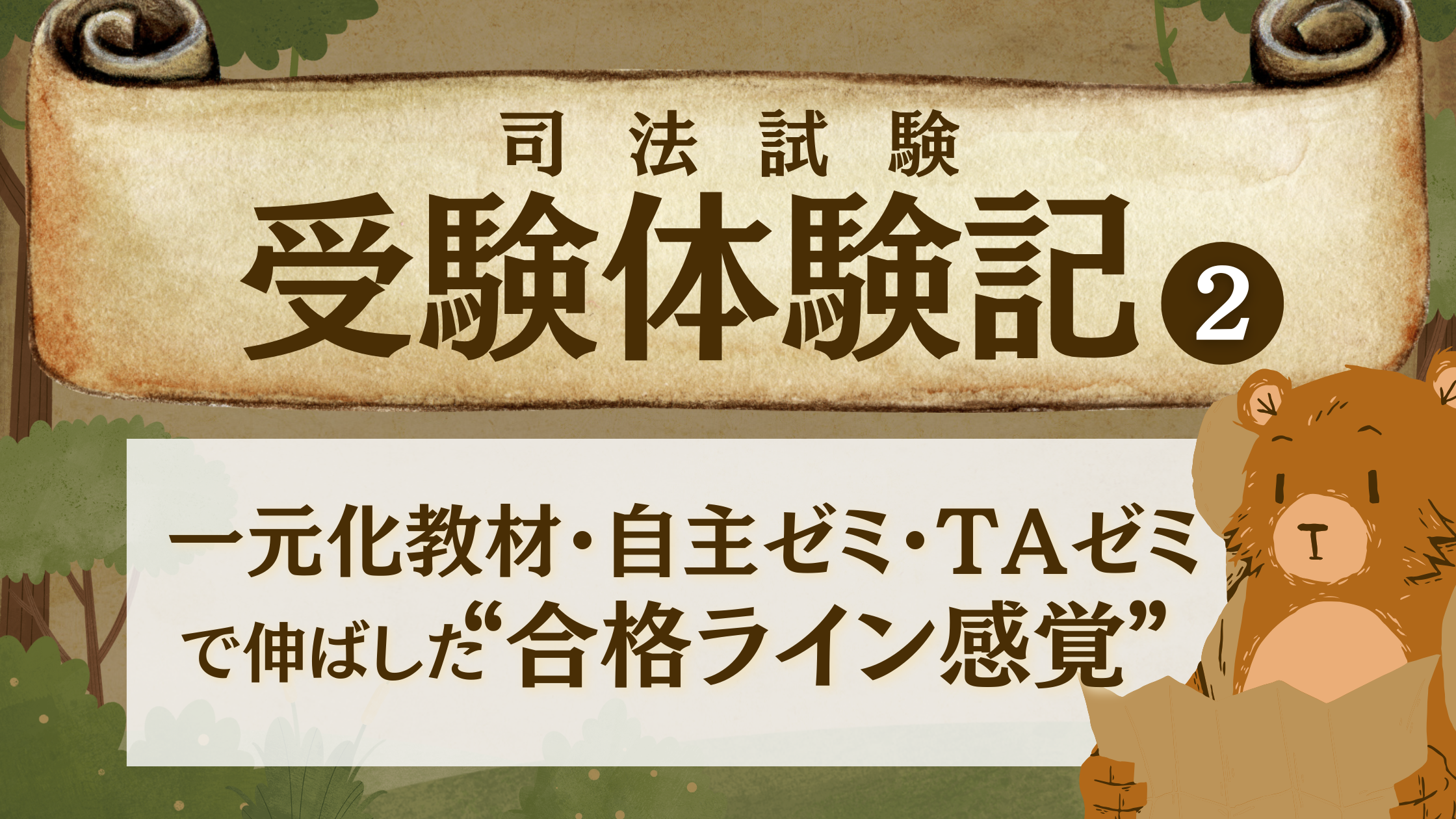
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする司法試験は「日本で最も過酷な試験の一つ」と言われます。
合格を目指すには、膨大な知識を積み上げ、数年間にわたり計画的に学習を続ける必要があります。しかし、机上の学習法や一般論だけでは、その厳しさやリアルな雰囲気を実感することはなかなか難しいのではないでしょうか。
そこで今回、「令和7年度司法試験」を実際に受験された3名の方にご協力いただき、それぞれの受験体験記を寄稿いただくことにしました。法科大学院での学習、就活や日常生活との両立、本番直前の過ごし方や試験当日の雰囲気など、合格を目指す皆さんにとって貴重なヒントとなる内容が詰まっています。
これから司法試験を受けようと考えている方、あるいは受験生活の真っ只中にいる方にとって、「自分はどう取り組むべきか」を考える手がかりになれば幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
こんにちは!先日、令和7年度司法試験を受験いたしました橋籠と申します。
今回は、私の司法試験受験体験記を書かせていただきます。皆様の参考になれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします!
自己紹介をしますと、私は国立大学法科大学院3年に在籍している者です。先日在学中受験で司法試験を受験し、短答式試験を無事通過いたしました。
これまで予備校の答練や模試を除き、ほぼ独学で司法試験の勉強をして参りました。予備試験の受験経験はありません。
そんな私が、在学中受験までの勉強の進捗や試験当日のこと、受け終えての感想等についてお話させていただきます!
私は法科大学院に既習2年として入学いたしました。
この時期は、司法試験対策といえるような勉強はほぼしておりません。私は企業法務弁護士志望だったので、入学後すぐに就活が開始しました。そして、ローの成績も就活で重要であるため、ローの予復習をしっかり行って良い成績を取ろうと奮闘しておりました。
そのため、授業時間以外は授業の予復習やESを書いたりしていました。
もっとも、司法試験対策とかろうじて呼べるようなことはしていました。
私は論証集として辰巳法律研究所の趣旨規範ハンドブックを使っていたのですが、授業で学んだ重要そうなことを都度そこに書き込み、「司法試験用の知識の一元化教材」として使えるようにしておりました。
また、授業を受けて生まれた疑問は先生に質問したり基本書で確認したりして、必ず疑問を残さないようにしていました。
上述したように、私は企業法務志望だったので、夏休みは就活をしておりました。
また、エクスターンシップや、裁判傍聴もしていました。それ以外の時間は帰省やバイト、遊びに時間を使っていました。正直、夏休みは勉強のやる気が全く出ませんでした(笑)。
この時期から、本格的に司法試験対策といえるような勉強を開始しました。
授業の予習の時間を前期に比べて大幅に削り、復習をする際も、司法試験に出そうな重要事項を一元化教材に書き込んだり、趣旨規範ハンドブックの論証を正確・詳細なものに訂正したりしていました。
そして、司法試験の過去問を、加藤ゼミナールの司法試験の重要問題ランキングというサイトを参考に、Aランク問題から全科目解き始めました。
2時間で起案し、3~5時間くらいかけて辰巳法律研究所のぶんせき本、基本書で復習、論証作成、及びC答案との比較をしていました。
このC答案との比較は、合格ラインに自分が達しているかを確認するために重要だと言われているため、毎回必ず行っていました。C答案が書けているのに自分が書けていなかった論証や当てはめは、特に復習するようにしていました。加えて、A答案やB答案の中でいいなと思った論証を論証集に加えたりしていました。
また、10月から短答の勉強を開始しました。
週1で友達と予定と短答を勉強する時間を作り、初めは刑法から取り組みました。もっとも、授業の予復習や期末の勉強、論文の勉強が大部分を占めていたため、短答の進捗は良くなかったです。
今年は短答が難化した年だったので、短答の勉強をもっと早くからやっておけばよかったと後悔しています。
さらに、後期からはローのTAゼミという現役弁護士が答案を添削・解説してくれるゼミに所属し、月1で民法や商法の過去問を添削してもらっていました。
司法試験に合格してからあまり年数が経っていない弁護士が指導してくれるため、自分の答案の違和感や誤り、どこで点が入りそうか、合格答案との比較、答案構成の方法や時間配分、今後の勉強計画等、ありとあらゆることを指導していただきました。
予備校に通っていなかった自分にとっては、合格ラインを確認できるのはC答案を見ることだけだったので、司法試験合格者の指導を受け、自分と合格ラインの距離を測ることができたのはとてもためになりました。
ローの期末試験が終わり、春休みを迎えると、司法試験対策の勉強中心の生活にシフトしました。予定がある日を除き、ほぼ毎日ローの自習室に通っていました。
勉強内容としては、主に論文の過去問の起案+復習、短答をしていました。
また、この時期から友人2人と一緒に自主ゼミを本格的に開始し、司法試験の過去問を起案して、ぶんせき本や採点実感を読みながら添削し、疑問点を議論していました。
1,2週間に1回の自主ゼミを司法試験本番の2週間前まで継続して行いました。自主ゼミのおかげで自分の答案の日本語の違和感や形式面での読みにくさ、論理の矛盾や誤りに気づくことができ、成長に大きく繋がったと感じています。
TAゼミとやっていることが被るのでは?と思われるかもしれませんが、自主ゼミはTAゼミよりも長い時間かつ詳細に添削・議論ができます。なので、自分の中では、TAゼミは自分の答案と合格答案の距離を測る+自分に足りないところの確認、自主ゼミでは自分の答案の具体的な内容面での誤りの修正+法律の議論をメインとして分けて考えていました。
個人的に、自主ゼミで法律の議論をしっかり行うことで、1人では気づかなかったような疑問に気づけたり、自分の法律知識のアウトプットができたりと、深い法律学習ができた実感があります。
TAゼミも月1で行っており、現場思考問題・未知の問題の解き方や当てはめの方法等、合格答案を作るために意識すべきことを中心に学びました。
そして、2月から短答の勉強を本格化させ、1日3時間くらいは短答の勉強に時間を割くようになりました。初めは知らない知識ばかりで苦戦しましたが、徐々に知識が定着してくるようになり、10月から3月までで市販の短答過去問集をなんとか2周することができました。
3月末には予備校の答練(3万円くらいで安かった)を司法試験と同じような日程で受けてみました。
これは、私がTKC模試を定員の関係で3月末に受けることができず、5月初めに受けることになってしまったため、自分もライバルたちと同様、3月末に自分の実力を確認しておこうと思ったからです。問題も採点も違うためあまり意味ないですが、これらの点数と令和6年の司法試験短答の自己採点を合わせて、令和6年の合格ラインを超えていたため、なぜかほっとしていました(笑)。
無事進学でき、司法試験が近づいてきたこの時期は、バイトや遊びをほぼせず、司法試験の勉強に取り組みました。
3月までに司法試験の過去問のAランク問題を半分以上は終わらせていたため、残りを解き、復習するというような勉強をしていました。また、短答も1日3時間は取り組むようにしていました。
ローの授業は、司法試験に出そうなところを主に復習していました。復習の仕方もこれまで同様、趣旨規範ハンドブックに一元化したり、論証を追加・変更したりしていました。
また、この時期から論証の暗記を本格的に始めました。寝る前に1時間くらい覚え、眠くなったら寝るみたいな生活をしていました。
しかし、結論としてもっと早く始めるべきでした。というのも、後述するように、作った論証が詳細かつ多量なため、そう簡単に覚えることができなかったからです。実際に試験本番でも論証忘れが2個ほどあったため、とても後悔しています。
そして、5月上旬に、TKC模試(会場)と辰巳模試(在宅)を受験しました。
結論として、模試を受けて本当によかったと思っています。なぜなら、今年の司法試験ではこの2つの模試の出題と同じような問題が出題されたからです。司法試験受験後、これら2つの予備校にとても感謝した記憶があります(笑)。
それに加えて、会場受験のおかげで試験耐性がついたと思います。
本番前に1日目7時間と2日目6時間という地獄の試験時間を経験していたおかげで、本番ではそれほど疲労もなく受験することができました。これら2つの模試では共に合格推定圏に入ることができたので、自分のこれまでの勉強方法は間違っていなかったと確信を持つことができました。
この時期から、短答1日2~3時間、論文はAランク問題の解き直し、残りの時間は論証をひらすら暗記する勉強をし始めました。
もっとも、論証は思っていたよりも暗記するのが大変で、全科目3周くらいしようと思っていたのに科目によって1、2周くらいしかできませんでした。
暗記が不十分なまま試験本番を迎えてしまったことは悔やみきれませんでした。少なくとも、論証を追加・変更するたびに暗記もしておくべきだったと思いました。
私の家は会場から遠かったため、会場近くに住んでいた父の家に寝泊まりし、会場まで通っていました。
試験本番は、思ったよりは緊張しませんでした。というのも、隣の席に友人がいたからです(笑)。まさかとは思いましたが、試験本番に緊張して頭が回らなくなりがちな自分にとってはありがたかったかもしれません。おかげで、自分の実力を発揮できたのではないかと思います。
会場の注意点としては、よく言われることですが、トイレが非常に混むことです。私は初日、着席時刻の30分前に着いたのですが、トイレが混みすぎて20分くらい待つこととなり、選択科目の最後の確認が不十分なまま試験に臨むことになってしまいました。そのため、2日目からは40~50分前に着くようにしました。
会場への持ち物としては、時計、受験票、受験番号シール、ボールペン4本、マーカー、短答用の鉛筆6本、鉛筆削り、論証集、短答集、昼ご飯、水、お茶かカフェオレでした。一応寒いとき用の長そでも持っていきましたが、使わなかったです。
≪会場への持ち物≫
・時計
・受験票
・受験番号シール
・ボールペン4本
・マーカー
・短答用の鉛筆6本
・鉛筆削り
・論証集
・短答集
・昼ご飯
・飲み物(水、お茶かカフェオレ)
・長そで(寒いとき用)
試験の合間はひたすら論証集を確認していました。
試験は、「自分はこれまでどんな問題が出ても解けるくらい広く深く勉強してきた。だから自分が分からない問題はみんな分からない。解けるところを厚く書き、分からないところは守りの答案を作ろう。」という気持ちで受けました。
試験本番のメンタルとしては良い状態で臨むことができたのではないかと思います。
司法試験の勉強・受験はとても楽しかったです!
分からなかった部分が理解できた時や友人と法律の議論をしている時間、自分の答案が正解筋だった時など、至る所に自分の楽しみがありました。そのため、司法試験が終わって今は少し物足りない感情です(笑)。
まだ受かっていないため大したことは言えませんが、司法試験の勉強は長期戦だと思うので、メンタルがやられそうな時は、勉強の中に楽しみを見つけてみるのも大事なんじゃないでしょうか。
最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました!
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
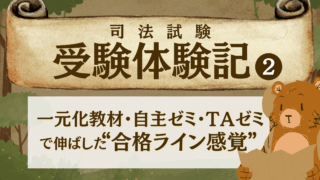
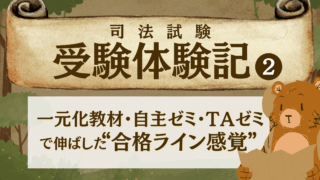
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法律記事を書いております、橋籠(ばしろう)です。現在は、国立大学法科大学院に在籍しながら、主に会社法の判例の解説記事を執筆しております。
自分が司法試験の勉強をしている上で必要だと思った知識を中心に執筆しております。初学者の方にも分かりやすいような解説記事を目指しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。令和7年司法試験合格者。
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

