
【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!
司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF
※閉じるとこの案内は7日間再表示されません
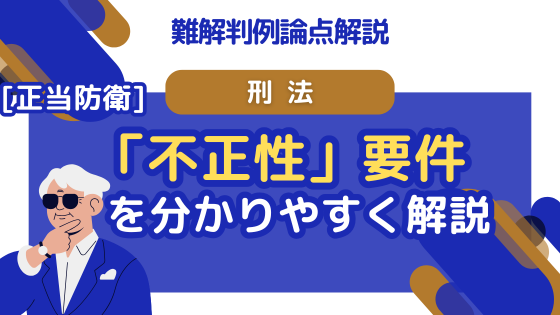
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする今回は「正当防衛」の要件としての「不正性」についての解説をしていきます。ただ、「不正性」についての論点はあまり多くありませんし、判例とかもあまりありません。今回はちょっと箸休め的な感じで、「正当防衛」そのものについて深堀をしながら解説していきます。
司法試験であまり使わない知識も含みます。ですが格好いいじゃないですか。「正当防衛の正当化根拠は法確証の利益にある」ってサラッと言えたら。
出身法科大学院の先生からは「君たちは法律の専門家なのだから、ちゃんと学説的な知識もちゃんと把握しておかないとなりません」と言われました。



まずは「正当防衛」のおさらいからです!



やあ、法律を学ぶみんな!
今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!



そうなのそうなの〜!
受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨



特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!



あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱
お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!
📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】
司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!
現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。
\ このタイミングを逃す手はありません /
合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。
「正当防衛」は何か?についてです。
「正当防衛」が成立する要件は「①急迫」「②不正」な侵害に対して、「③防衛するため」「④やむを得ずにした」行為であることです。
本来なら犯罪になることもありますが「正当防衛」が認められれば、罰せられません。
刑法(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。



今まさに危険が迫っている不正な攻撃から、自分や他の人を守るために、やむを得ず行った行為のことですね!
「正当防衛」は以下の4つの条件を満たす必要があります
①急迫:侵害が現在進行形であるか、今にも始まりそうな状態であること
②不正:侵害が法律に反していること(例:殴る、蹴る、物を盗むなど)
③防衛するため:自分の身を守るため、または他人の権利を守るために行った行為であること
④やむを得ずにした:他に侵害を防ぐ方法がなかった、またはそれに近い状況であったこと
今回は「侵害が『②不正』であるとはどういう場合か?」について解説していきます。「①急迫」については前回解説をしていますので、そちらの記事をご覧ください。
≪前回の記事≫
正当防衛の要件①急迫性をどこよりも分かりやすく解説【初学者から司法試験受験生まで】 | 法スタ
「侵害の不正性」とは、刑法上の「違法な侵害」をいいます。



まずは「自力救済」の禁止について見ていくぞ!
法律では「自力救済」が禁止されているが、その例外として、「正当防衛」があるんだ!
「自己救済の禁止」についても前回の記事でご紹介しましたが、念のため再度触れておきます。
そもそも法律には「自力救済」の原則というものがあります。
「自力救済」は原則禁止されています。
「自力救済(じきゅうこうい)」とは?
法的な手続きや公的機関の助けを借りずに、自分の権利や利益を自分の力で回復・実現しようとする行為を指します。
過去に受けた侵害や将来受ける侵害の回復は、法に任せなければなりません。
貸したお金が返ってこなかった経験は、読者であるみなさんにも、あるかもしれません。
「内臓売れや!!」
上のように恫喝してお金を返してもらったことはありますか?
ないでしょう。あったら違法ですから、自首してください。
正当な権利であっても、自らの実力で実現することはできません。これを「自力救済の禁止」と言います。権利の実現は、裁判所など法執行の機関にゆだねなければなりません。
ただ、例外があります。「正当防衛」と「緊急避難」です。
刑法(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
「自力救済の禁止」の例外である「正当防衛」と「緊急避難」はどちらも「自己又は他人の権利を保全するために行った行為の違法性」を阻却する制度です。
どちらも「法の保護を待っていては権利が守れない緊急事態に行われる行為」の「緊急行為」のため許容されています。
同じ「緊急行為」ですが、「正当防衛」と「緊急避難」の2つはどう違うのでしょうか。
・緊急避難
成立するには「避けようとした損害が生じさせた損害以上のものである必要」があります。
・正当防衛
「小さな利益のために大きな利益を犠牲にしてもよい場合がある」のです。「正当防衛」は不正な侵害に対する反撃であり、権利の防衛という目的が正当化の根拠となるため、侵害行為によって失われるであろう利益と、防衛行為によって侵害される利益を厳密に比較衡量する必要はありません。
「正当防衛」は「緊急避難」に比べ、厳密に要求されません。なぜでしょうか?
1つの説明は「正対不正」の対立であるから「不正側の要保護性が若干減少するから」というものです。司法試験の答案ではこの説明でも十分だと思います。
正対不正とは?
「正義」と「不正義」が対立する構図のことです。
・「正」 は「法秩序によって守られるべき権利や利益、または適法な行為、正当な行為」を指します。
・「不正」 は「法秩序に反する侵害行為、違法な行為」を指します。
「正当防衛」が認められる根拠の一つとして、「不正」に対して「正」が立ち向かう対立構造があるため、「やむを得ない行為として、社会的に許容される」という考え方です。



不正な侵害があるからこそ、それに立ち向かう正当な防衛行為が例外的に許される、という基本的な考え方を示しているんですね!
ただ、厳密なことを言うと「いくら侵害をしているからといって、生命や身体の要保護性が減少するというのは乱暴ではないか?」などの反論があり得るところです。
もっと掘り下げていくと、ほとんどの教科書では「法確証の利益」という考え方を説明してくれます。
法確証の利益とは?
違法な侵害行為に対して、侵害行為をやめさせ、法秩序を維持するという、法が本来持っている役割や価値を守る利益のことです。
「正当防衛」行為は「単に利益を侵害から守る」というだけでなく「法はいかなる状況でも妥当するという規範を表明する行為でもあり、それ自体に価値のあるものだと考えられる」というのです。
こういった理由で「正当防衛」では「侵害が不正なもの」である必要があるのです。
「不正な侵害」とは「違法な侵害」のことです。
教科書にそう書かれています。ただの言い換えでは?確かにそうかもしれません。もう少し詳しく見ていきましょう。
「違法」とは、概ね実質的違法性だと考えてください。つまり、刑法上の違法性です。
「不正な侵害」の理解するために、ポイントを2つご紹介します。
「不正な侵害」の理解のポイント 2つ
ポイント①「正当な行為」は「不正な侵害」にあたらない
ポイント②「有責性」を問わない
ポイント①正当な行為は「不正な侵害」にあたらない
「正当防衛」や「緊急避難」に対しては「正当防衛」をすることはできません。「正当防衛」や「緊急避難」など「違法性阻却事由」がある場合には、それは「不正な侵害」に該当しないのです。
例えば、適法な逮捕や捜索、正当防衛行為自体は「不正な侵害」にはあたりません。したがって、これらの行為に対して正当防衛は成立しません。
ただ、違法であればよいので、侵害者に有責性が伴う必要はありません。
ポイント②有責性を問わない
侵害行為者に責任能力がない場合(例えば、精神障害者や幼児の行為)でも、その侵害行為が客観的に違法であれば「不正な侵害」となり、正当防衛が認められることがあります。
したがって、14歳未満の者の行為や心神喪失者の行為は犯罪にはなりませんが「不正な侵害」になります。
このように、必ずしも「侵害」が犯罪である必要はありません。
刑法に規定はありませんが、違法性がある侵害が生じたとしたら、それも「不正な侵害」といえます。学説上の争いはありますが、例えば、過失による器物損壊に対して「正当防衛」をすることができる可能性があります。
故意行為も、過失行為も「不正な侵害」と言えます。また、作為のみならず、不作為であっても「不正な侵害」となりえます。
刑法学な深遠な議論により、故意も過失もない場合に「不正な侵害」であるといえるかが問題となります。
「対物防衛」についても正当防衛の成立を肯定されるのでしょうか?
「対物防衛」とは「物からの不正な侵害」に対する防衛行為を指します。
人の行為とはいえない事態から、権利の侵害が生じたため、物を破壊することで侵害を回避することを指します。
例えば、犬に噛みつかれそうになったときに反撃し、犬にけがを負わせた場合、器物損壊罪(動物傷害罪)の構成要件に該当します。
飼い主が特に犬をけしかけたわけでもなく、鎖で縛っておくのを怠った等の過失すらない場合、行為から侵害が発生したとはいえません。
上記のようなときに、「対物防衛」が問題となります。正当防衛の成立は肯定されるのでしょうか?
刑法(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
民法(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
正当防衛の成立は肯定されるかについては、「結果無価値論」と「行為無価値論」のどちらの立場に立つかによって、結論が左右されることがあります。
・結果無価値論:犯罪の違法性は、法益侵害という結果そのものにあると考えます。
・行為無価値論:犯罪の違法性は、法規範に違反する行為そのものにあると考えます。
「結果無価値論」において違法性は「法益侵害」のことですので、物からも違法性が生じます。よって「対物防衛」は肯定されます。
一方の「行為無価値論」においては、違法性は行為からしか発生しないので、「不正な侵害」が存在せず、「正当防衛」は成立しないように思えます。したがって、このような場合に物を破壊したなら、それは「緊急避難」の問題となります。
先ほど挙げた例でいうと「飼い主が特に犬をけしかけたわけでもなく、鎖で縛っておくのを怠った等の過失すらない場合、行為から侵害が発生したとはいえません」という部分は、行為無価値論の立場からはその通りです。
しかし、結果無価値論の立場からは、犬という「物」から法益侵害という結果が生じていると捉えるため、「侵害が発生した」と考えることになります。
とはいえ、猛犬の事例で考えれば、反撃する際に背後の飼い主の過失があるかどうかで判断が変わるのは、行為者にとって酷です。飼い主に、管理上の過失があるかどうか?は行為者には判断できないからです。
また、民法720条2項が不法行為責任を免除していることとの均衡がとれていません。
「行為無価値論」をとる場合にも「対物防衛」を肯定することを考えたいところです。
「不正性」の要件は犯罪の成立要件とは異なり、「正当防衛」として許容しうるかという観点から判断し、「正当防衛」と認めるという考え方があります。
別の考え方もあります。「正当防衛」それ自体は認めがたいが、「緊急避難」の問題とするのも均衡を失する。そこで、「防衛的緊急避難説」という考え方が主張されます。
防衛的緊急避難説
正当防衛の要件を満たさない急迫した危険に対し、通常の緊急避難よりも緩い要件で自己救済を認める考え方です。
特に、法益均衡や補充性の要件を緩和し、正当防衛に近い状況での被害者保護を図ります。
この説は、民法720条2項によって責任が免除される場合には、法益均衡と補充性を要件とせずに「緊急避難」も認めるというものです。
| 結果無価値論 | 肯定説 | 正当防衛 | |
| 行為無価値論 | 否定説 | 緊急避難 | |
| 肯定説 | 正当防衛 | 不正性要件を規範的に解釈する | |
| 防衛的緊急避難説 | 緊急避難 | 法益均衡と補充性を要件としない |
「対物防衛」に近い事例として、他人の物を用いた攻撃があります。この場合「正当防衛」が成立するでしょうか?
侵害者が、他人の物を用いて攻撃してきたのに対して、行為者がその他人の物を破壊することで自分の身を守る場合「対物防衛」と同様に、他人の所有権を侵害しています。
「対物防衛」で、どの説を採る論者でも、他人の物を用いた侵害の際には、物はその侵害行為と一体となっているため、問題なく「正当防衛」ができるというのが共通した見解です。
一方で、侵害に対して他人の物を用い、物の破壊を伴って防衛する場合も問題となります。この場合には、その者の所有者との関係では「正当防衛」は成立せず、「緊急避難」の問題となります。
本稿の内容は、「結果無価値論・行為無価値論」といった違法性の本質についての対立とリンクしています。
司法試験の刑法では、どちらの立場を採っても構わないのですが、どちらにしても一貫した立場を採ることが求められる(らしい)ので、この対立についての知識が曖昧な場合は、参考文献欄の井田良教授の講義刑法学をお勧めします。わかりやすい定番の教科書でありつつ、各論点において、これでもかと言わんばかりに結果無価値論・行為無価値論を絡めてきます。
それでは、次回に続きます。ここまで読んでいただきありがとうございました。
・大塚裕史『応用刑法I 総論』(日本評論社、2023)
・大塚裕史ほか『基本刑法I 総論[第3版]』(日本評論社、2019)
・佐伯仁志・橋爪隆編『刑法判例百選I[第8版]総論』(有斐閣、2020)
・井田良『講義刑法学・総論[第2版]』(有斐閣、2018)
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
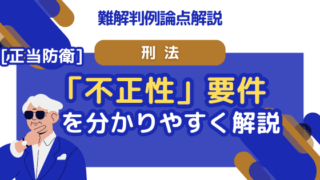
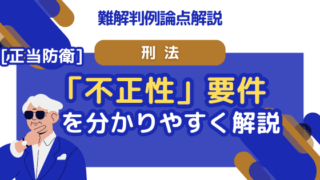
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

