
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
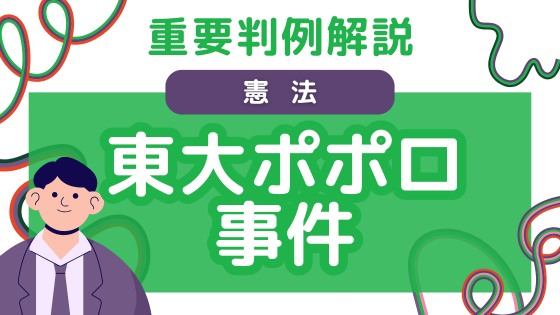
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする「東大ポポロ事件」は、「学問の自由」と「大学の自治」が「どのように憲法上で保障され、またどの範囲で制限されるのか?」を示した重要な判例です。
この事件を通じて、憲法23条に基づく「学問の自由」の具体的内容や、「大学の自治」が持つ意味、さらには「警察権力との関係性」についての議論が深まりました。



本記事では、「事件の概要」から「最高裁判決の詳細」までを整理し、その「法的意義」を解説するぞ!
東大ポポロ事件は、「学問の自由(研究・発表・教授の自由、大学自治)」の具体的内容と限界を示した判例です。1952年、東京大学で学生が行った演劇に警察が介入し「大学の自治」や「学問の自由」が争点となりました。
最高裁は、大学自治は大学当局に認められるもので、学生は利用者に過ぎないと判断。また「学問の自由」も「公共の福祉」による制約を受けるとし、政治的活動に該当する場合は警察介入を認める見解を示しました。
憲法23条では「学問の自由」を保障しています。
憲法〔学問の自由〕
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
「学問の自由」は、次の4つを意味すると解されています。「東大ポポロ事件」の最高裁判決では、「学問の自由」の内容としてこれらの4つが含まれることが示されました。詳細な意味は、記事の後半で解説していきます。
≪学問の自由の意味≫
ただ、すべての自由が認められたわけではなく、「教授の自由」については一般的に認められているわけではなく、大学に限定して認められるとの解釈を示しています。
「東大ポポロ事件」の概要
1952年(昭和27年)に東京大学構内の教室において、大学の公認の学内団体である「劇団ポポロ」が松川事件を題材にした演劇発表を行いました。
松川事件とは、当時の国鉄東北本線の松川駅付近を走行していた機関車が脱線した事故に関して、何者かが線路に工作を仕掛けたことが原因とされ、国鉄の労働組合員らが容疑者として逮捕された事件です。のちの裁判で容疑者は全員無罪となっており、戦後最大の冤罪事件とされました。
当時、日本は、GHQ・連合国軍総司令部の統治下にあり、共産党を貶めるためにアメリカ軍が仕組んだ謀略だったとの説も唱えられています。こうした事件を学生が演劇で扱うことに関しては、当時の治安当局は神経をとがらせていました。警視庁の警察官は、警備情報収集のために、この演劇発表会に私服で入場していましたが、学生らに見つかり、暴行を受けました。
そのため、当時の暴力行為等処罰法違反の容疑で学生らが逮捕された事件です。
「学問の自由」・「大学自治」と「警察権の限界」が争点となり、国会でも議論が行われるなど大きな注目を集めました。
「第一審」と「控訴審」は学生らを「無罪」としましたが、その理由は次のとおりです。
≪「第一審」と「控訴審」で学生らが「無罪」となった理由≫
これに対して、検察側が上告しました。
最高裁は「原判決」と「第一審判決」を破棄し、東京地裁に差し戻しました。
つまり、検察側の主張を認めたわけです。「最高裁がどのように判断したのか?」を確認していきましょう。
「東大ポポロ事件」の最高裁判決では「『学問の自由』についてどのように解釈しているのか?」を確認します。
≪学問の自由の意味≫
まず「①学問研究の自由」「②学問研究発表の自由」「③教授の自由」の3つについて見ていきます。
最高裁は「学問の自由」は「学問的研究の自由」とその「研究結果の発表の自由」とを含むとはっきりと述べています。
その上で、この2つの自由は、広くすべての国民に保障されているとしています。
そして、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としているということです。
最高裁は「教授の自由」又は「教育の自由」は、「学問の自由」と密接な関係を有すると認めつつも、一般的には、「学問の自由」に含まれないとの解釈を示しています。
そのため、例えば、小学校や中学校などの義務教育の現場において、教諭には「教授の自由」又は「教育の自由」が認められていないことになります。
一方、大学については「教授その他の研究者」が、「その専門の研究の結果を教授する自由」が保障されるとの解釈を示しました。
次の2つが根拠です。
≪大学で「教授その他の研究者」の「その専門の研究の結果を教授する自由」が保証される根拠≫
「学問の自由」に、限界はあるのでしょうか?
憲法23条には、公共の福祉と言った文言はなく、制約がないように見えますが、最高裁は「学問の自由」についても、「公共の福祉による制限を免れるものではない」と述べています。
ただ「大学における自由」は、大学の本質に基づいて、「一般の場合よりもある程度で広く認められる」との立場を示しています。
司法試験の論文式試験対策で「論証集をどう使えば良いのか?」と悩んでいる方におすすめなのが、「【2025年】アガルートの論証集の使い方の評判|アプリで更に使いやすくなった」です。
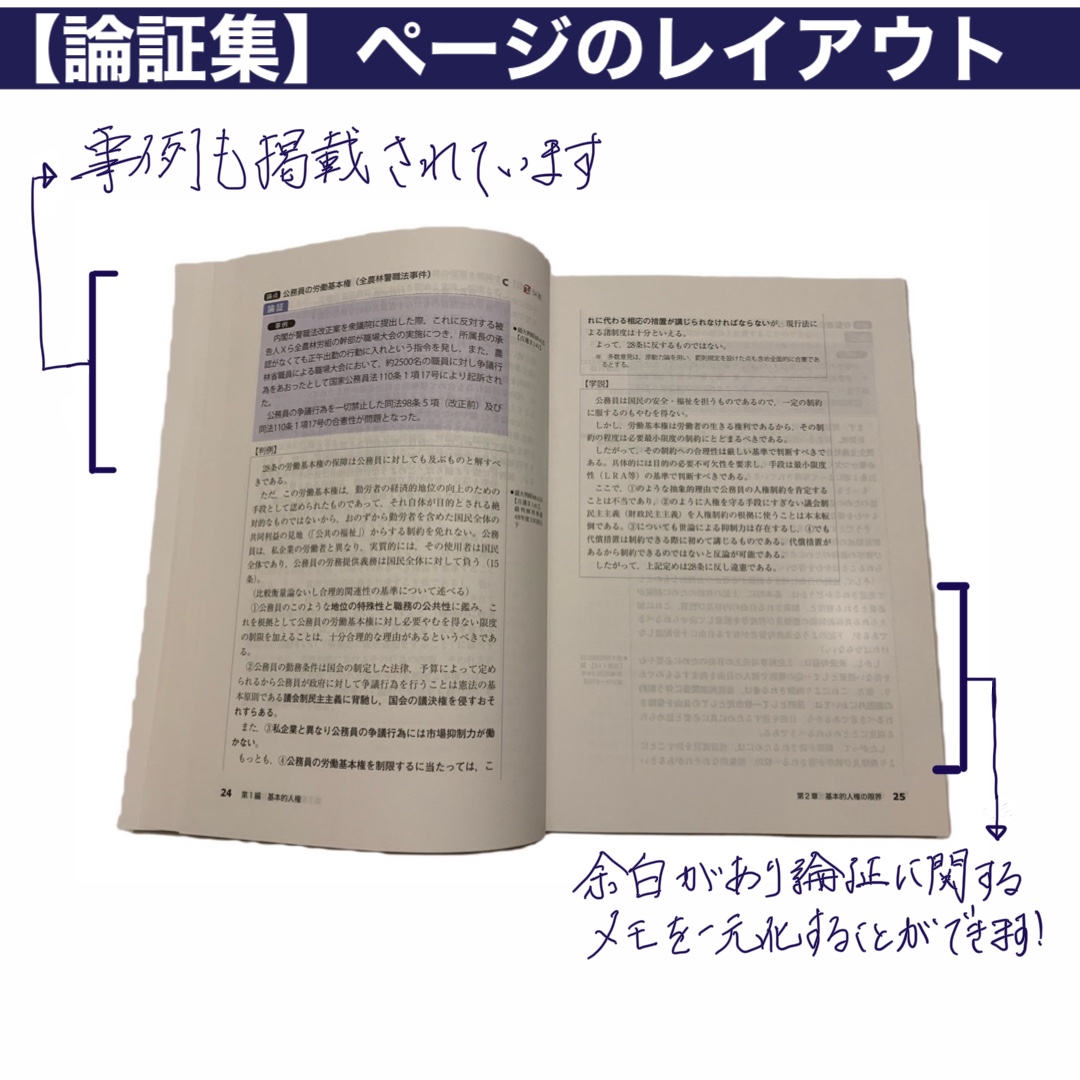
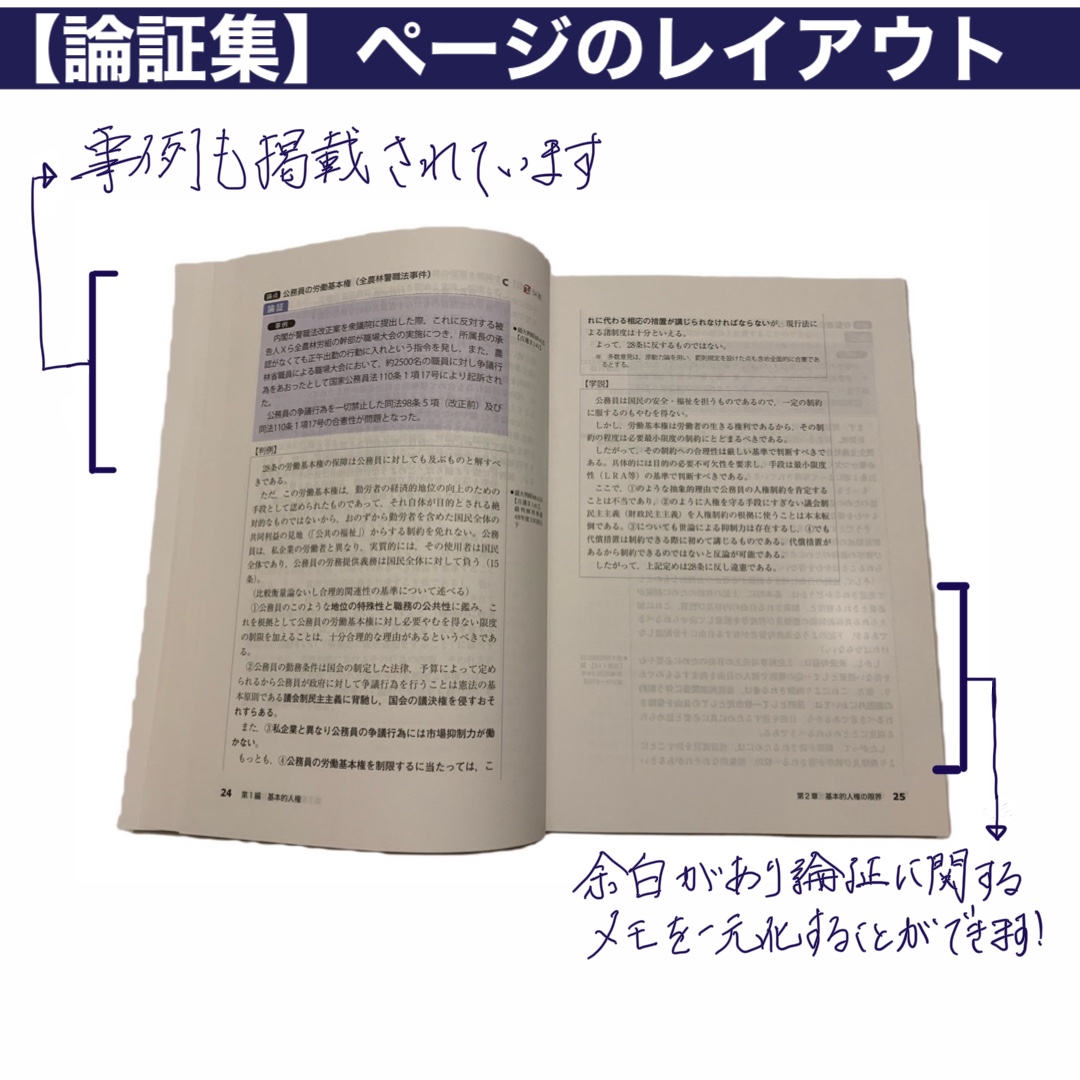
この記事では、アガルートの「論証集の使い方講座」の魅力や具体的な活用法について詳しく解説しています。論証集の効率的な使い方や、アプリを使った隙間時間での学習方法など、司法試験合格に向けた実践的なアドバイスが満載です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
こんな勉強法も紹介!
アガルートの論証集講座を使いこなせば、司法試験の論文式試験でも「芯を外さない」論証ができるようになります。詳しくは以下の記事で確認して、効率的な学習法を手に入れましょう!
▽詳しくはこちら▽
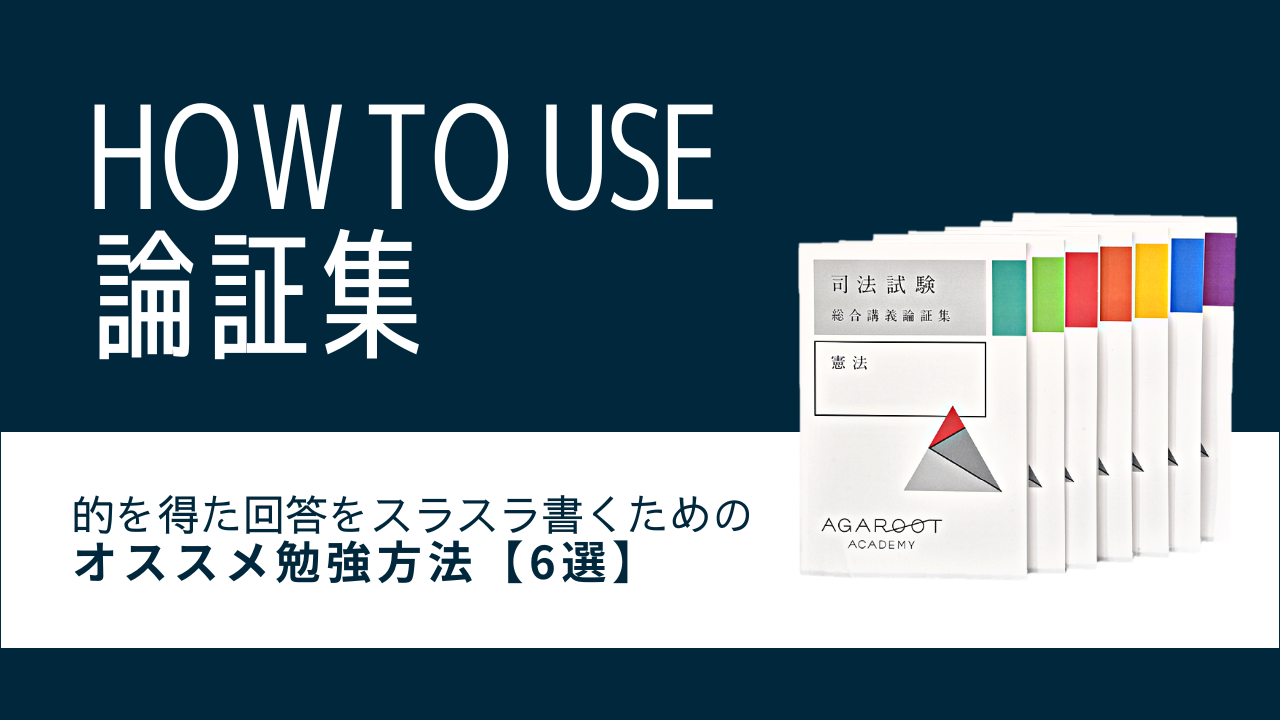
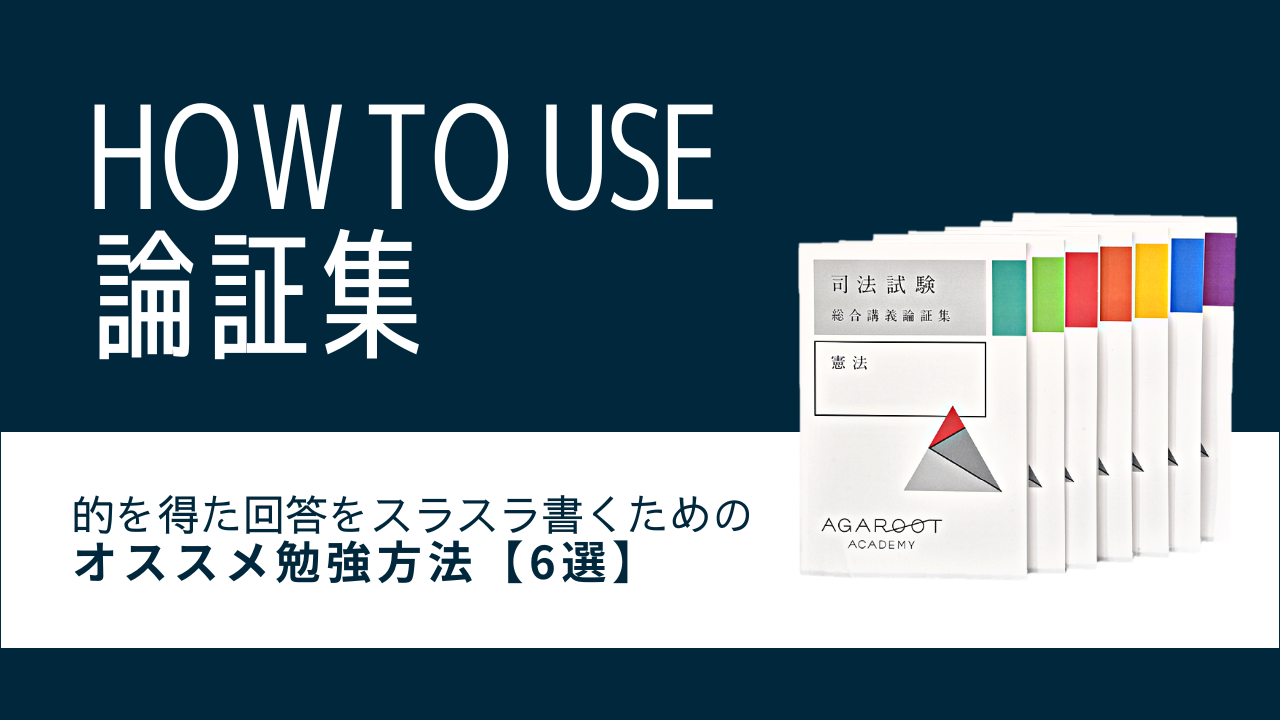
最高裁は「大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質」としていることからこうした意味での学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められているとの解釈を示しました。
「大学の自治」の具体的な内容としては、以下の3つが認められるとしています。
このうち、「1.大学の教授その他の研究者の人事」が最も重要で本質的なものであるとしています。
一方で「2.大学の施設の管理」と「3.学生の管理」は、「ある程度」で認められるとしており、限定的な権利と解しています。
「大学の自治」の性質からして、「大学の教授その他の研究者」が「大学の自治」の担い手であることは、言うまでもありません。
問題は「『学生』は『大学の自治』の担い手なのか?」ということです。
この点については、2つの学説が提唱されています。
≪『学生』は『大学の自治』の担い手なのか?に関する学説≫
「営造物利用者説」は「学生は大学の施設の利用者であって、大学の自治の主体ではない」とする考え方です。
「大学の自治」は、大学当局のみが担っていて、学生は反射的効果として「学問の自由」と「施設の利用」が認められているにすぎないとします。
「不可欠の構成員説」は「学生は大学の不可欠の構成員であり、重大な利害関係を有していることから、大学自治に関して大学当局に要望したり反対したり批判する権利がある」とする考え方です。
ただ「大学の自治」に関して「学生」と「教授」では地位も役割も異なることから、「大学の自治」の担い手であるとまでは認めていません。
最高裁は、この点について次のように判示しました。
「施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。」
つまり、上記学説のうち「営造物利用者説」を採っているということです。
学問研究活動では、時の権力に対する批判も行われることがあります。
これに対して、権力者が警察力を以って取り締まった場合は、「学問の自由」が保障されているとは言えません。
そのため、警察権力との関係でも「学問の自由」が保障されるべきことになります。
「東大ポポロ事件」で、最高裁は「大学構内における警察による取り締まりを認めた」わけですが、次のような考え方によるものでした。
その上で、劇団ポポロの演劇は、反植民地闘争デーの一環として行なわれたもので「実社会の政治的社会的活動」に該当すると認定しました。また、一般の人が自由に入場できたことから、「公開の集会」と見なされるべきであるとしています。
よって、本件の「集会に警察官が立ち入ったことは、大学の『学問の自由と自治』を犯すものではない」と判断しました。
東大ポポロ事件は、「学問の自由」の内容として、次の4つを示した判例として重要な意味があります。
≪学問の自由の意味≫
このうち「③教授の自由」は、一般的には認められておらず、大学には認められるとしています。
また「④大学の自治」は、大学当局に求められるのであって、「学生は『大学の施設の利用者』に過ぎない」との見解を示しました。
そして、警察権力からの「大学の自主性の確保」に関しては、「『実社会の政治的社会的活動』に該当する場合は、学問の自由と自治は認められず、警察による介入が認められる」との判断を示しました。
論点の多い判例ですが、整理して押さえておきましょう。
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
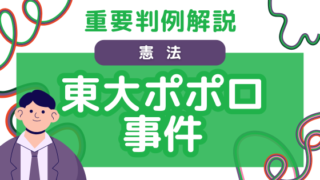
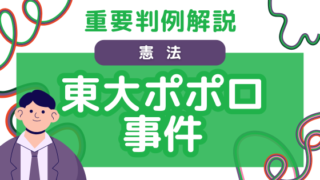
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
















勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

