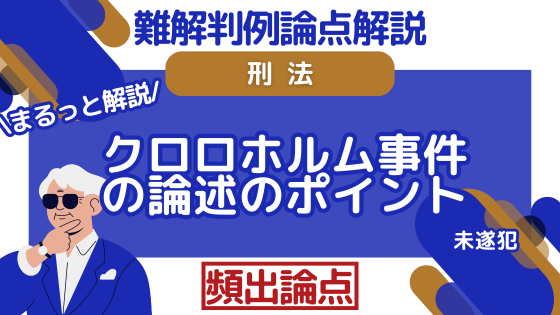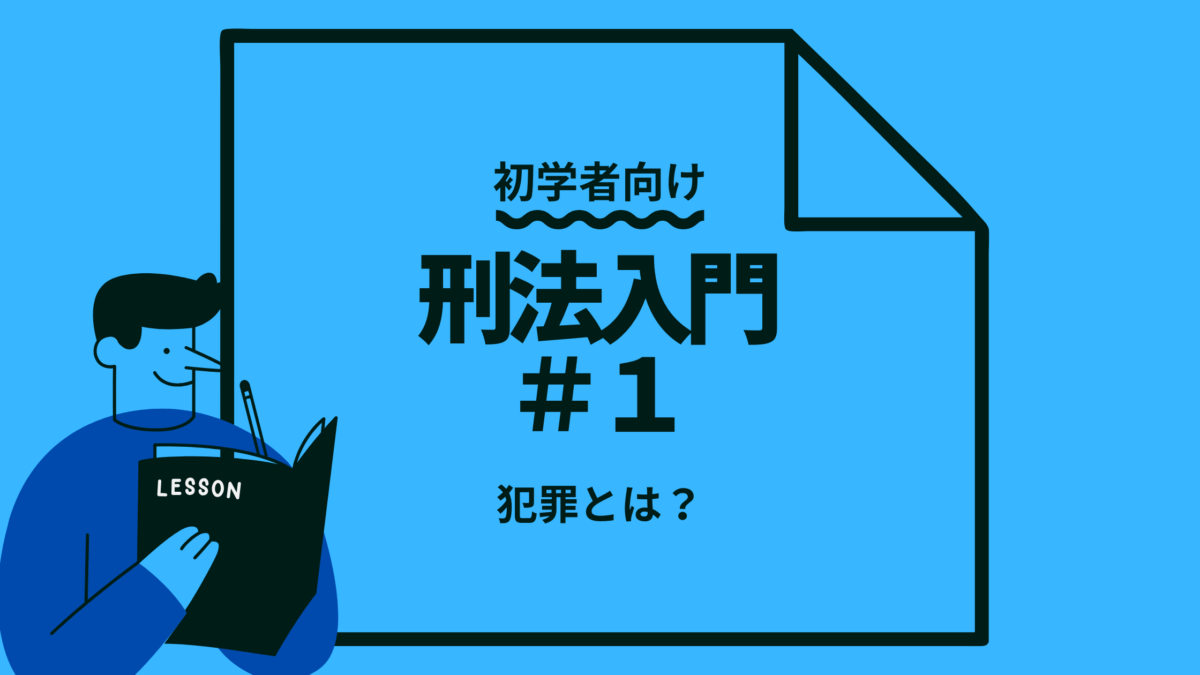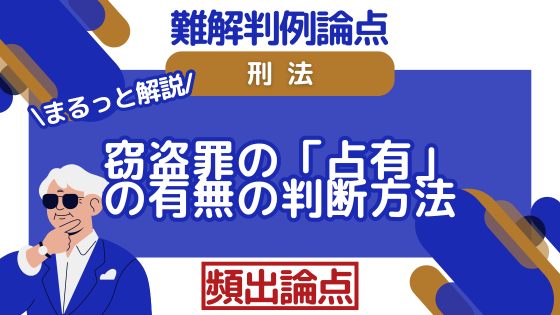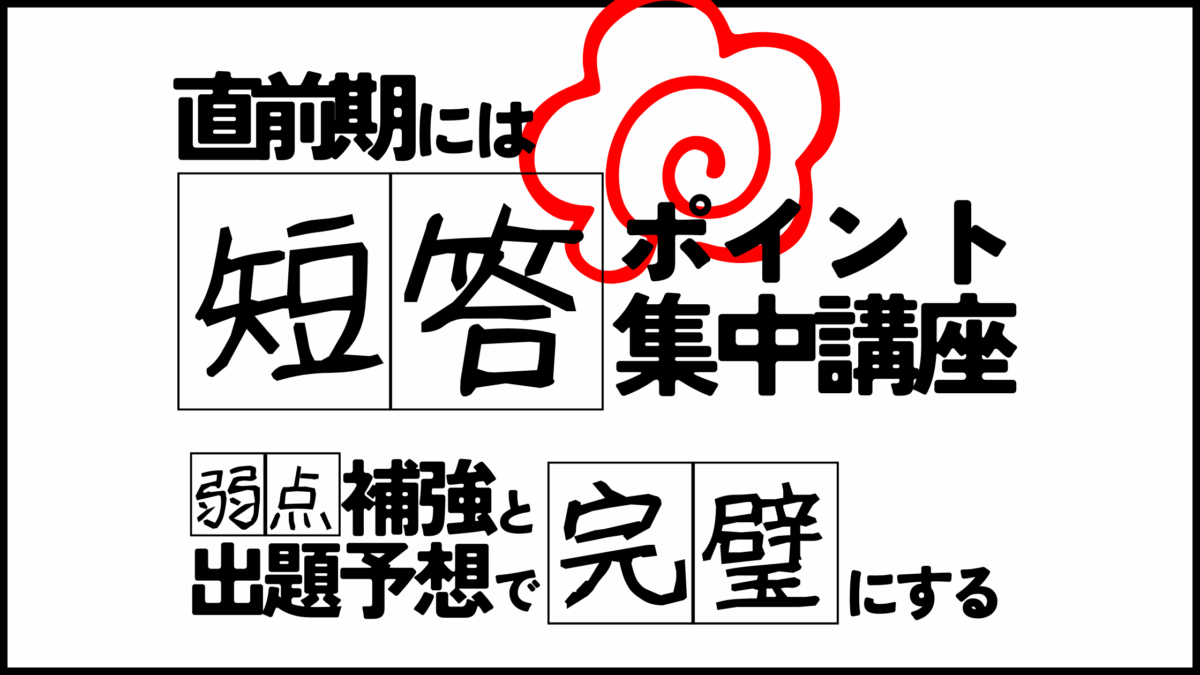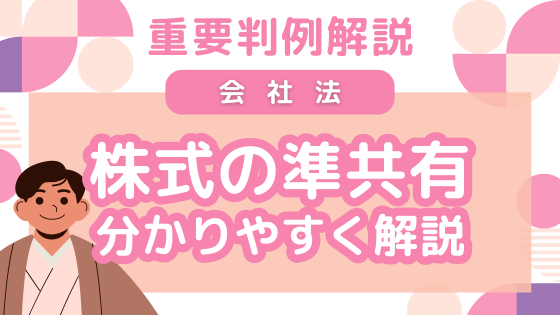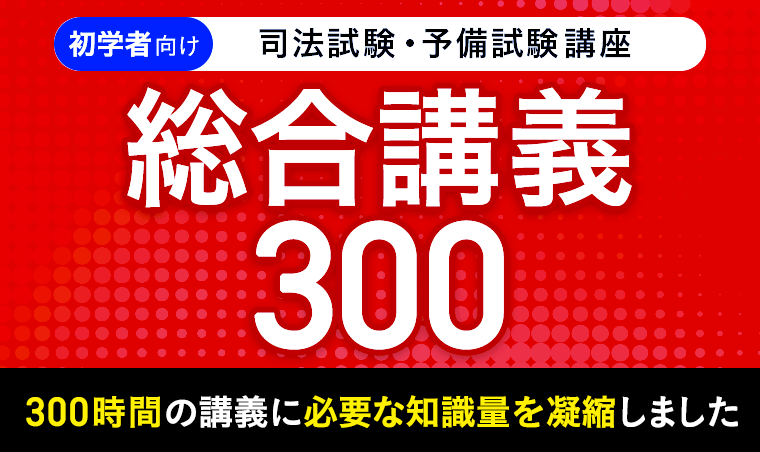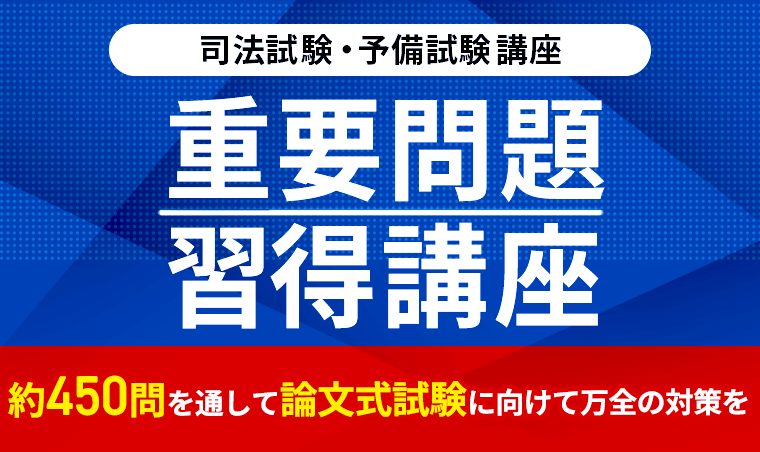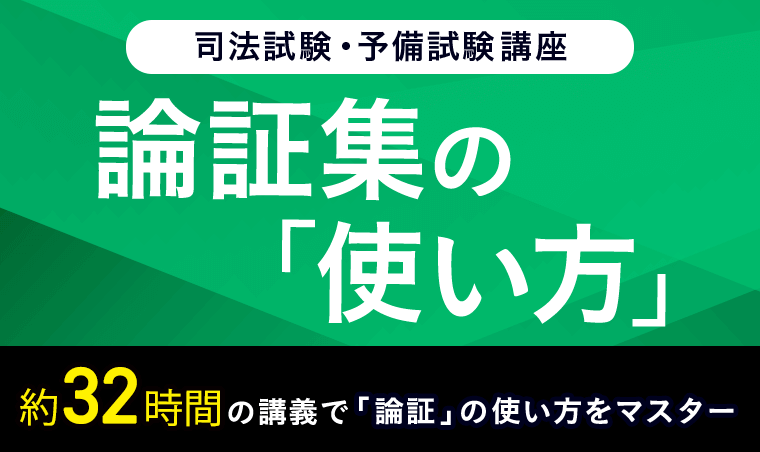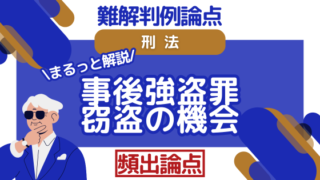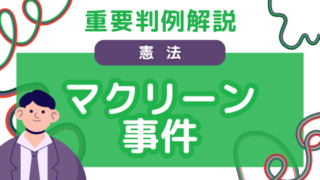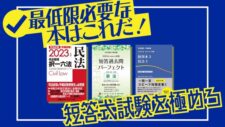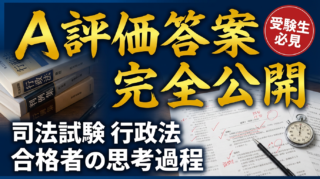【初学者向け】事後強盗罪の窃盗の機会の理解と論述のポイント
当ページのリンクにはPRが含まれています。
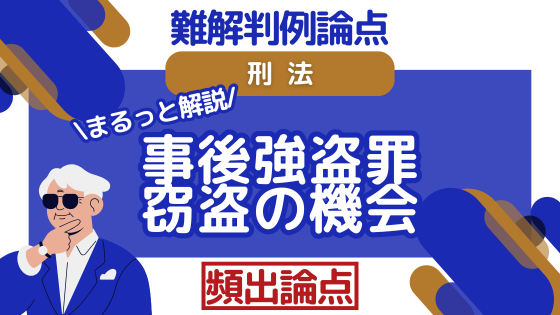
「“窃盗の機会”って何だ?なんとなく聞いたことはあるけど、しっかり説明できる気がしない…」
「事後強盗罪って強盗罪とどう違うんだろう?名前が似てるからごっちゃになりそう…」
「平成14年と平成16年の判例、違いは分かるけど、論述でどう活かすかがイマイチ分からない…」
本稿では、まず、初学者向けに、事後強盗罪の他の要件について、ざっくりと確認した上で、「窃盗の機会」の意味について解説していきます。
本題から逸れるので、あまり深く掘り下げませんが、他の要件も、学説の対立や重要論点を含みます。初学者の方は他の記事や教科書も併せてお読みください。
さて、「窃盗の機会」はいわゆる書かれざる要件であり、判例や学説からその内容を確認するほかありません。



重要判例の枠組みと『基本刑法II』と『応用刑法II』をかみ砕いて解説していきます!
目次
「事後強盗罪」とは?
(事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
「事後強盗罪」の趣旨は?
刑法238条が制定された理由は、以下の二つです。
刑法238条が制定された理由
①窃盗を行った者が、その物に対する支配を維持するために暴行・脅迫を行うのが、実際に多いこと
②窃盗を行った後の暴行・脅迫でも、財物奪取の目的で暴行・脅迫を行う強盗と規範的に同視できる場合があること
この条文の解釈で重要なのは、②の方です。つまり、窃盗(財物の奪取)の後の暴行・脅迫が、強盗(財物の奪取)のための暴行・脅迫と規範的に同視できるときにのみ、事後強盗罪の成立が認められるのです。
「事後強盗罪」の要件は?
この視点でみれば、条文の要件は以下のように整理できます。
◆「窃盗が」
通説・判例は、事後強盗罪を、窃盗犯のみが行える真正身分犯としています。
◆目的の要件
暴行・脅迫の目的が、次の3つのいずれかである必要があります。
① 財物奪還阻止目的
② 逮捕免脱目的
③ 罪跡隠滅目的
◆暴行又は脅迫
最狭義の暴行・脅迫です。
強盗と同視するためには、相手方の反抗を抑圧するに足るものである必要があります。
◆窃盗の機会
強盗罪では、暴行・脅迫は財物奪取の手段であって、両者の間には強固なつながりがあります。事後強盗罪は、強盗と同視できるような状況ですので、暴行・脅迫と窃盗行為の間に同じくらい強固なつながりが必要になります。
「暴行・脅迫が窃盗の機会に行われた」とは、このような関連性があることを指します。



ここから、その「窃盗の機会」について解説していきます!
盗の機会の典型
典型的には、窃盗を犯したその時・その場で暴行・脅迫を行った場合に、「窃盗の機会」が認められます。
つまり、「窃盗の現場」が、「窃盗の機会」の中心となります。
言い換えれば、「窃盗の機会」とは「窃盗の現場」及び「その延長と見られる場所」です。



どんな場合に「窃盗の機会」って認められるの?



具体的にどういった場合に、窃盗の機会と認められるか判例を紹介するぞ!
重要判例①平成14年2月14日
事案の概要
Xは、家主不在のV宅に侵入し、指輪1つを窃取し、その後、天井裏に潜んでいた。
1時間後に帰宅したVは、窃盗に遭ったこと、天井に犯人が潜んでいることに気づいたため、警察に通報した。
窃盗から3時間後、通報により駆け付けた警察官に発見されたXは、逮捕を免れるためにナイフで警察官の顔面を切りつけて傷害を負わせた。
判旨
Xの暴行は窃盗から、3時間は経過していたが、「上記窃盗の犯行後も,犯行現場の直近の場所にとどまり,V等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況が継続していたのであるから,上記暴行は,窃盗の機会の継続中に行われたものというべきである。」として、「強盗致傷罪」を肯定した。
重要判例②平成16年12月10日
事案の概要
午後0時50分ごろに、窓からV宅に侵入したXは、居間に置いてあった現金入りの封筒を窃取し、そのまま玄関から逃走した。
誰からも追跡、発見されることなく1km離れた公園に到着し、そこで盗んだ現金を確認したところ、3万円しか入っていなかった。そのため、Xは再度V宅に侵入して窃盗しようと考えた。
午後1時20分ごろ、Xは再びV宅に到着し、玄関の扉を開けた。しかし、Vがすでに帰宅していることに気づいたため、扉を閉めて門の外の駐車場に出たが、VがXを発見したため、Xは逮捕を免れるためにナイフを取り出して威嚇し、怯んだ隙に逃走した。
原審はXに事後強盗罪を適用した。X上告。
判旨
破棄差し戻し。
被告人は,財布等を窃取した後、だれからも発見,追跡されることなく,いったん犯行現場を離れ,ある程度の時間を過ごしており,この間に,被告人が被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況はなくなったものというべきである。そうすると,被告人が,その後に,再度窃盗をする目的で犯行現場に戻ったとしても,その際に行われた上記脅迫が,窃盗の機会の継続中に行われたものということはできない。
「窃盗の機会」の判断基準と類型


「窃盗の機会」については、「被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況が継続」しているかどうか?を基準に考えます。
学説では、判例や実務で問題となる類型を3つに分けています。ここでも、それに倣って整理していきます。
継続追跡型
窃盗の現場から場所的に離れたとしても、被害者や警察官から継続して追跡を受けている状態であれば、なおも窃盗の機会が継続していると言えます。
現場滞留型
窃盗から時間が経過していたとしても、犯人が現場に留まっていたような場合です。
平成14年判決では、被告人は窃盗から3時間ほど経過した後に暴行を行いました。3時間あれば普通は逃走も終わってしまっていて、窃盗の機会が続いているというには遅すぎることでしょう。しかし、被告人がその時間まで移動せず、V宅に留まっていたという事情から、窃盗の機会が続いていたと認定されました。
この時、重要となるのは、被告人が滞留していた場所の特性でしょう。屋根裏は、被害者が生活する環境に非常に近く、物音の一つでも立てれば潜伏していることはすぐに発覚してしまうでしょう。その意味で、この事件では、未だに「被害者に容易に発見・奪還・逮捕され得る」状況にあったといえます。
仮に、平成14年判決で被告人が滞留していた場所が、屋根裏でなく、もっと離れた、物置や離れであったとすれば、窃盗の機会の継続を認めるのは難しかったでしょう。
この場合には、被害者がすぐに窃盗に気づいたり、警察に通報したりして、その場所でも発見・奪還・逮捕されるおそれがなければなりません。
このように、場所の特性や被害者の動向を相関させて、判断します。
現場回帰型
このパターンでは、窃盗の現場から時間的・場所的に近接した状況で暴行・脅迫を行っています。しかし、一度、距離的に離れ、被害者等から発見・奪還・逮捕をされ得る状況から脱してから、再び現場に戻り、暴行を行いました。
このパターンにおいては、平成16年判決では、「被告人が被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況はなくなった」ことを理由として、窃盗の機会に行った脅迫でないと認定しました。
つまり、窃盗の機会が一度終了した場合には、すぐに再び窃盗の現場に戻っても、窃盗の機会性が復活することはないということです。
「事後強盗罪」の論述のポイント


「事後強盗罪」の規範定立
事後強盗の要件は、強盗罪との同視性を根拠として規定されます。したがって、論述の際には、強盗と同視できるかが基準となり、そのための要件として窃盗の機会が要求されることを明示します。
「事後強盗罪」のあてはめ
平成16年判決では、以下の2点でもって「窃盗の機会」が終了したとしています。
・誰からも発見・追跡をされることなく
・いったん犯行現場を離れて、ある程度の時間を過ごした
とはいえ、離れた距離は最大1kmほど、時間は30分ほどです。
この事案において重要な事実は、発見も追跡をされていない状態で、「被害者側の支配領域から完全に離脱して安全圏に入った」(大塚祐史など『基本刑法II―各論(第2版)』、2021年、193頁)ことです。
言い換えれば、被害者の追及を受けることのない安全圏に入った場合には、「被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況」を脱したといえます。
したがってあてはめで重要なのは、
・発見・追跡の状況がどうなっているか
・被害者等が探索して容易に発見される状況か
を連関して考えることです。
▽参考文献▽
・大塚裕史ほか『基本刑法II 総論[第3版]』(日本評論社、2019)
・大塚裕史『応用刑法II 総論』(日本評論社、2023)
・『アガルートの司法試験・予備試験合格論証集 刑法・刑事訴訟法』アガルートアカデミー編著(サンクチュアリ出版、2020)
・佐伯仁志・橋爪隆編『刑法判例百選II[第8版]総論』(有斐閣、2020)