
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
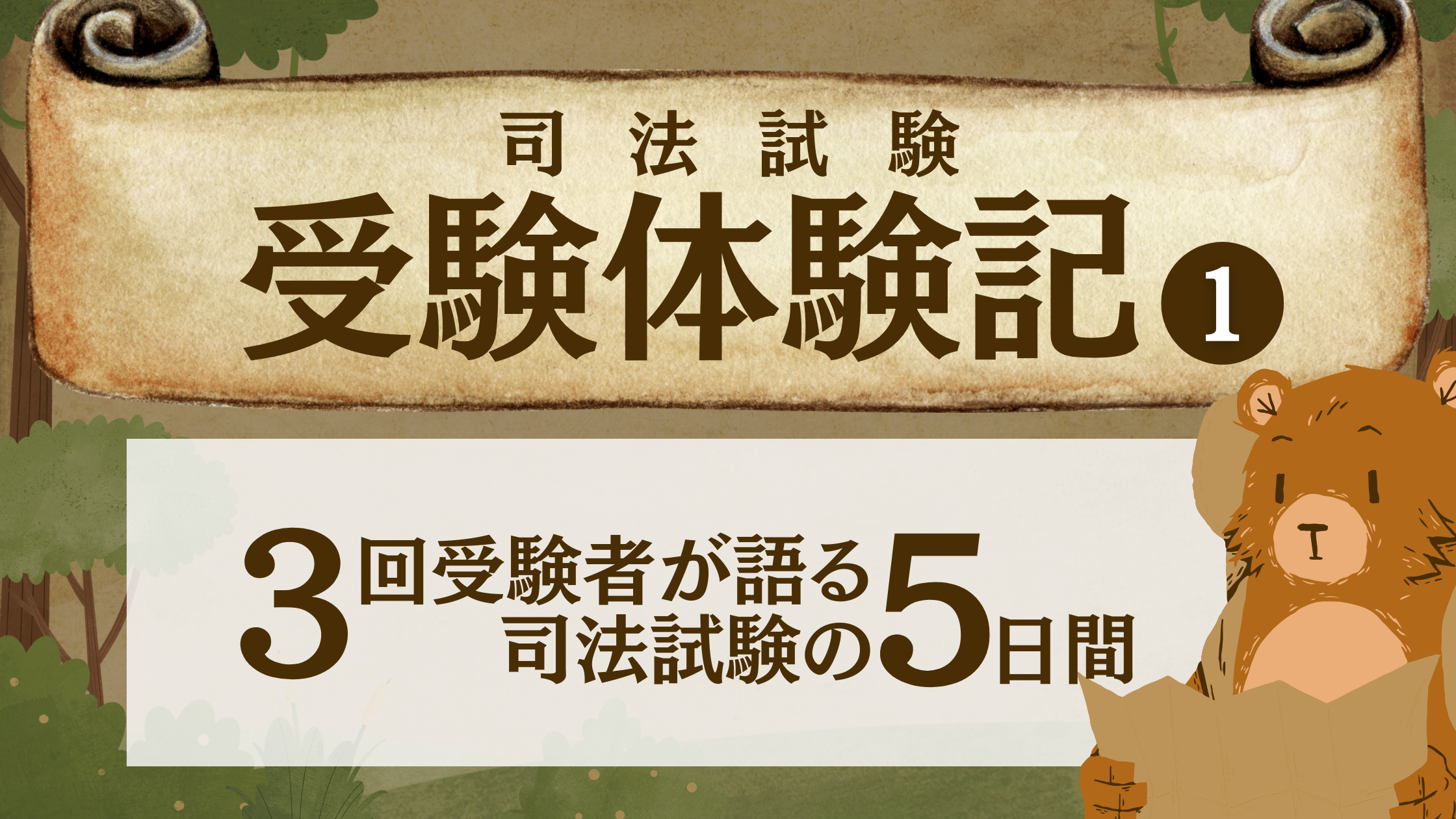
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする司法試験は「日本で最も過酷な試験の一つ」と言われます。
合格を目指すには、膨大な知識を積み上げ、数年間にわたり計画的に学習を続ける必要があります。しかし、机上の学習法や一般論だけでは、その厳しさやリアルな雰囲気を実感することはなかなか難しいのではないでしょうか。
そこで今回、「令和7年度司法試験」を実際に受験された3名の方にご協力いただき、それぞれの受験体験記を寄稿いただくことにしました。法科大学院での学習、就活や日常生活との両立、本番直前の過ごし方や試験当日の雰囲気など、合格を目指す皆さんにとって貴重なヒントとなる内容が詰まっています。
これから司法試験を受けようと考えている方、あるいは受験生活の真っ只中にいる方にとって、「自分はどう取り組むべきか」を考える手がかりになれば幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
この記事では、筆者の令和7年度の司法試験の受験の様子を、来年度以降に司法試験を受験される方へ向けて、試験の前日から試験最終日までの間の私の実際の過ごし方と、それに対する気付きや反省等を紹介します。
5日間に亘る試験期間の過ごし方の具体的なイメージの一例として、お役に立てられると幸いです。



すごく知りたいです!



では、早速聞いてみよう!
令和7年度司法試験は、私にとって3回目受験でした。
既修で国立ロースクールに入学し、在学中受験で令和5年度を受験して論文で振るわずに不合格、ロースクール修了後1年目に令和6年度を受験して短答の合計点が足らずに足切りになりました。令和5年度の受験では、様々な事情が作用して緊張感に支配された結果、初日から試験中に頭が真っ白になってしまい、4日目の刑事系第2問になりようやく落ち着いたものの手遅れでした。
現在の司法試験は、7月中旬の暑い時期に中日含めて5日間かけて実施される精神的にも体力的にも過酷な試験です。上記の私のように、当日に調子を崩す方も多くいると思います。私自身がそうとは言いませんが、優秀な方であっても調子を崩した結果、涙を飲むことになる、ということも十分あり得ると思います。
そのような非常に残念な事態を防ぐため、試験期間の過ごし方を考えておくことも、大切な試験対策と思います。
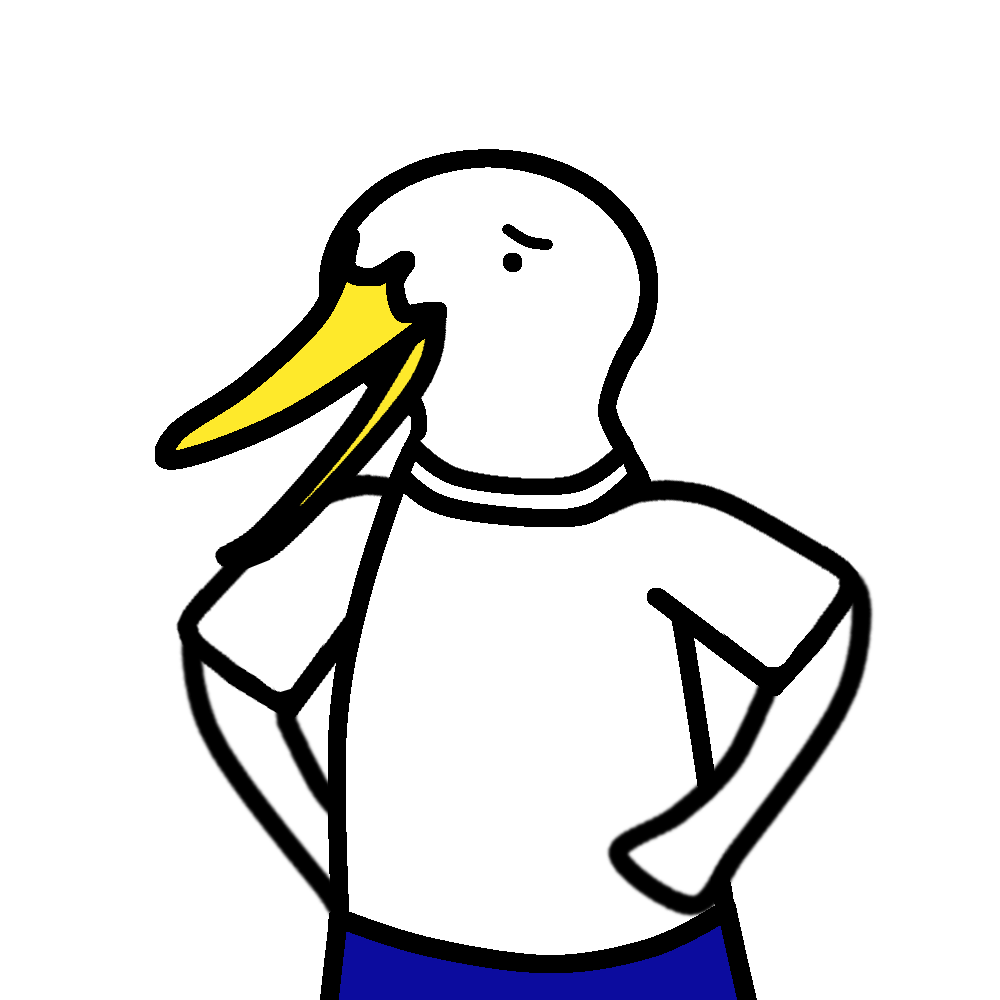
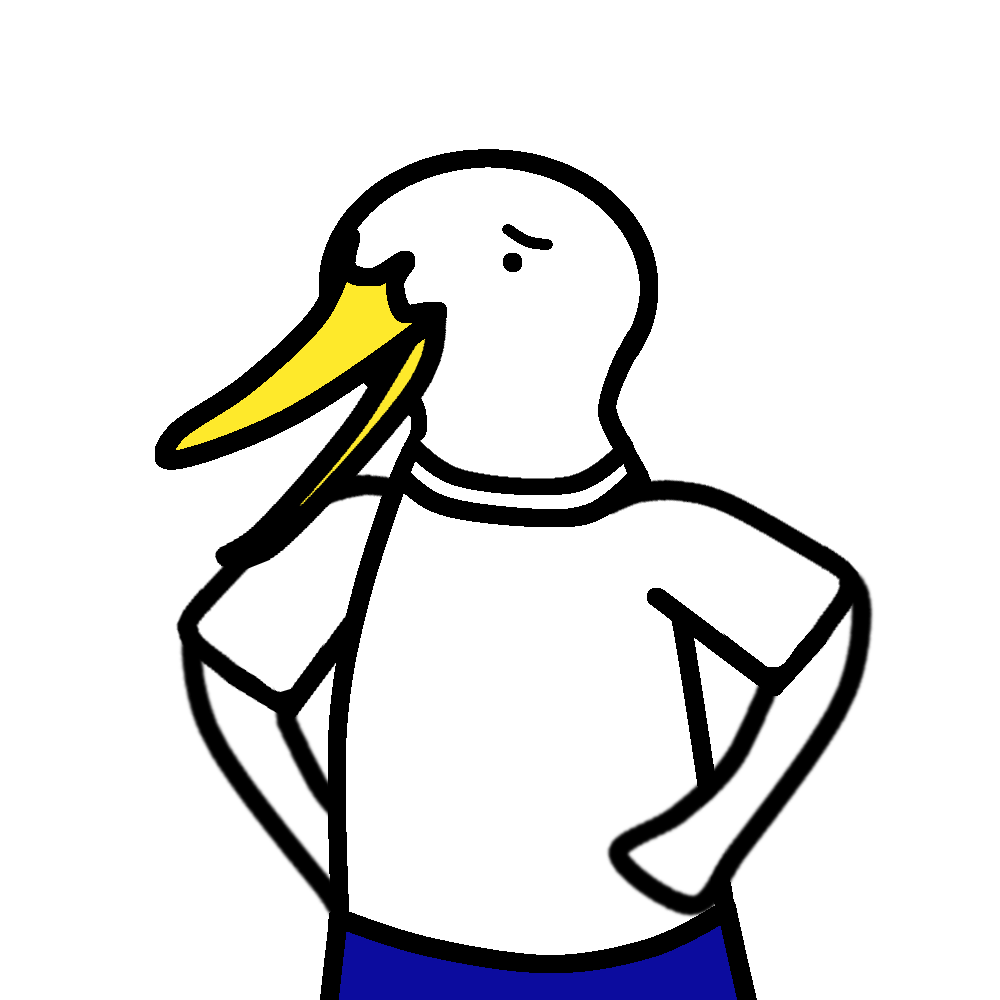
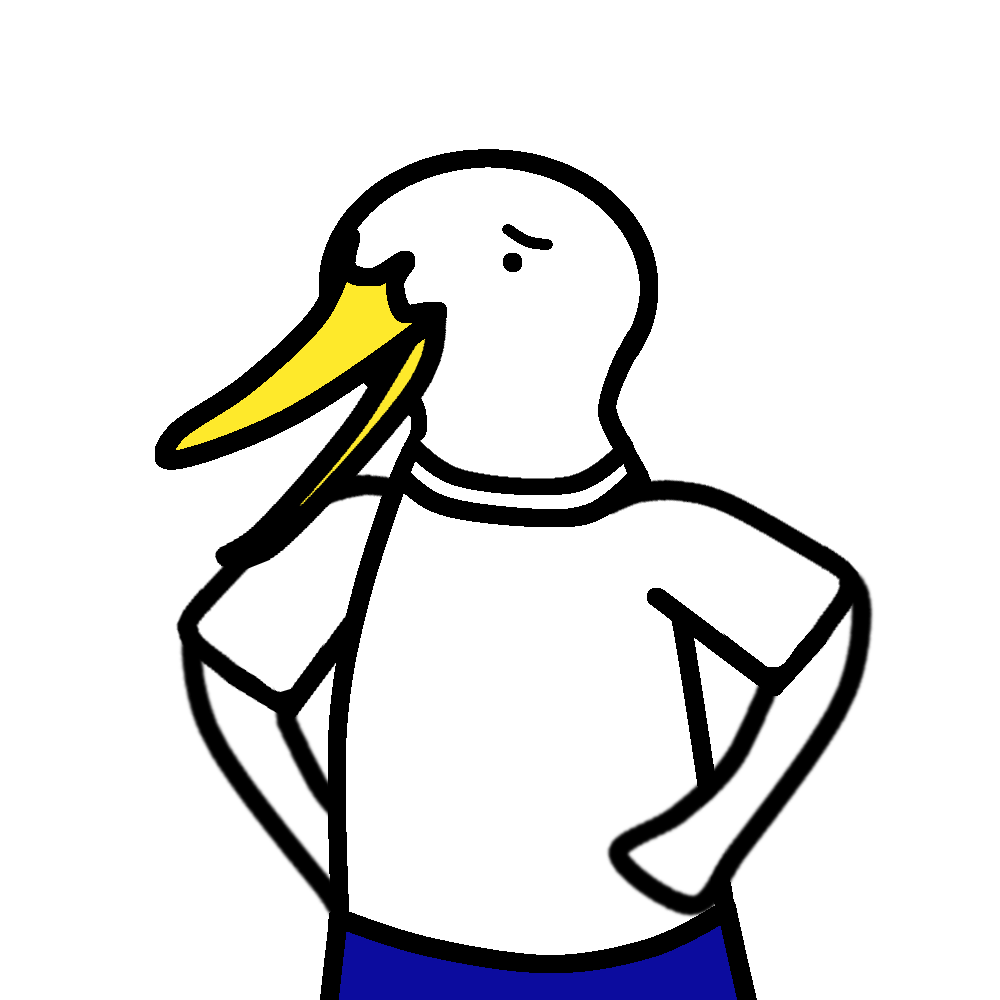
試験日当日に体調を崩すのは、とても怖いです…



確かに、体調で結果が変わることもあるかもしれない。
試験日当日に、最高のパフォーマンスを出せるように出来ると、後悔の少ない試験にできるね!
私は、試験前の2ヶ月ほど前から、試験の前日から最終日までの5日間のホテルを予約し、移動手段を調べ、必要となる持ち物をリストアップし、各日にどのように過ごすかの計画を立て始めました。
また、試験期間中は体力と精神の安定を最優先するという方針を立てていたため、試験期間中の勉強は最小限にとどめ、むしろリラックスすることに時間を割くように考え、実際にそのように過ごしました。
ホテルを予約したのは、試験場が公表された5月の頭でした。
実は過去2回と同じ試験場(マイドーム大阪)の近くのホテルを3月ごろに予約していたのですが、5月頭に公表された試験場(大阪アカデミア)を見ると、例年と異なる場所になっていた上、周辺にホテルが少なかったので、受験する知り合いに試験場の変更を周知しつつ慌てて別のホテルを予約した、という経緯があります。
急な試験場の変更もありますし、令和8年度以降はCBT試験となる予定なので、試験場がどこになるのか法務省のサイトでこまめに確認しておくと良いと思います。
前日チェックイン、最終日の朝チェックアウトという、5泊6日で予約しました。これは、試験期間中の移動による疲労やタイムロスを極力防ぐためでした。
令和5年度の試験では費用の節約のため下宿先から通っていました。しかし、朝早く起きて会場へ向かうことの身体的・精神的な辛さと、交通機関が止まってしまうリスクがあるため、通える距離であってもホテルを取ることお勧めします。
また、令和6年度の試験では、2日目の朝に一度チェックアウトして民事系科目の受験後に下宿先に帰って一泊し、荷物整理をしてから中日にもう一度チェックインする、ということをしましたが、身体的な疲労の面からあまりお勧めできません。
ホテルを選ぶ際にも、試験場との近さ以外にも、ホテルのサービスや設備、周辺の飲食店やスーパーマーケットの所在等を考慮して、自分が試験期間中快適に過ごすために何が必要か、という観点から判断しました。
私の場合は、健康的な食事を食べて体調を維持するためにビュッフェスタイルの朝食が付いていること、湯船に浸かり疲労を取るために大浴場があること、着替えを極力減らすためにランドリーが使えること、を重視していました。
飲食店やスーパーマーケットは、試験の間の休憩時間に食べる昼食の準備や、試験後の夕食を食べるために必要でしたが、試験場から20分以上歩かなければ見当たらないという、お世辞にも良いとは言えない立地でした。
そこで、前日のチェックインを済ませた後、気分を落ち着かせるための散歩を兼ねて、中日まで必要な量の水や1日目と2日目の昼食にするパンを買いに行きました。
このとき、ホテルによっては冷凍庫と電子レンジが備え付けられているものもあると思いますので、朝食や夕食にするために冷凍食品の弁当などを買っても良いかもしれません。このような意味でも、ホテルの設備は重要だと考えます。
≪ホテルを選んだ際に考慮したポイント≫
・試験場との近さ
・ホテルのサービスや設備
・周辺の飲食店やスーパーマーケットの所在等
・[重要]ビュッフェスタイルの朝食付き
・[重要]大浴場がある
・[重要]ランドリーが使える
一駅先で万博が開催されていることもあり、電車内では大量の乗客がいて大荷物を運べないだろうと予想していたため、荷物を極力少なくしてリュックサックとショルダーバッグに収まる程度にしようと、5月ごろから持ち物を考えました。
具体的な持ち物は、各科目と短答用の教材一つずつ、ランドリーの使用を想定した3日分の着替え、スマートフォンと充電器、常備薬でした。
≪持ち物≫
・各科目と短答用の教材一つずつ
・ランドリーの使用を想定した3日分の着替え
・スマートフォン
・充電器
・常備薬
教材については、その科目の試験の前日において重度に疲労した状態でも短時間で見返せるもの、という観点から準備することになります。普段の勉強の際にもこのことを意識しておくと良いと思います。
服装も、試験中の体調に直接関わるので重要です。
過去2回の受験で、エアコンの効き具合によりとても寒く感じることがあったため、調整できるように薄手の長袖のシャツとパンツを用意していました。もっとも、私の席はエアコンの風を直接受ける席で具合が悪くなりそうでした、膝掛けを準備しても良かったと思います。また、足元は、素足にサンダルを履いていましたが、初日が想像以上の寒さで足の指先から冷えていき、とても体力を消耗したので、2日目以降は靴下も履くようにしました。
その他の持ち物として、休憩時間や就寝時にリラックスするためのホットアイマスク、朝に気分を高揚させる用と夜に落ち着かせる用のお気に入りの楽曲で作成したプレイリストを準備していました。
試験期間中は、朝食をホテルのビュッフェ、昼食を食べやすい軽めのパンとブドウ糖入りのゼリー飲料、ブドウ糖タブレット、夕食を周辺の飲食店での外食としていました。
朝食では、試験期間中の不摂生な食生活に少しでも抗おうとサラダやフルーツ類、スクランブルエッグや卵焼きなどのタンパク質豊富な卵料理を多めに食べていました。糖質は、眠くなることを防ぐため少なめにしていましたが、必ず食べるようにしました。
昼食では、教材を眺めながら片手で素早く食べられる、手を汚さない、軽い、という要素を考慮して、卵蒸しパンが中心でした。次の科目の最終確認を少しでも長くしたいこと、食欲がなくても軽くて食べやすいこと、手を汚してトイレに行って長蛇の列で時間が取られる心配も無い点から、卵蒸しパンは優秀な食品でした。
また、ペットボトル飲料として,コーヒー1本とブドウ糖タブレットを飽和するまで溶かした水2本を用意して、昼食や休憩時間だけでなく、試験中も飲んでいました。さらに、試験開始の40分前ほどになると荷物をしまうように案内されるので、そのタイミングでブドウ糖入りのゼリー飲料を飲んでいました。
夕食では、基本的にその時食べたいものを食べるようにしようと考えていました。しかし、実際には、エアコンの風を長時間体に受けていたこともあって体調があまり良くなく、5日中3日はうどん屋に行き、他の1日はお好み焼き屋に行き、残りの1日はスーパーで買った弁当を食べました。他の飲食店として、マクドナルド、餃子の王将、焼肉屋がありましたが、とても選べる状態ではありませんでした。定食屋などあれば良かったのですが、こればかりは試験場を決定した司法試験委員会を恨みます。
| 午前中 | 民法の論文の確認,荷造り |
| 14時 | 移動中に民法短答の動画を聴く,ホテル到着後は民法短答の問題集を確認し,友達と談笑 |
| 15時 | チェックイン後,買い物と周辺の散策をして店の所在を確認,夕食まで選択科目と行政法の確認 |
| 18時 | 夕食を食べに行く,入浴 |
| 20時 | 選択科目の確認をするが,疲労で捗らず就寝することを決める |
| 2時ごろ | ようやく眠りにつく |
午前中は家で民法の確認と荷造りをして、午後15時のチェックインに向けて出発しました。
移動中は、普段使わない路線であり乗り間違えて余計なストレスを与えないことや、手が塞がっていることから、教材を手に持つことはやめ、アガルートがYouTubeに上げている短答の一問一答の動画を聴くことだけをしていました。
ホテルにチェックインした後は、中日までの3日間分の水と昼食用のパン、ゼリー飲料、ブドウ糖タブレットの買い出しをして、選択科目と行政法を簡単に復習し、夕食としてうどんを食べに行きました。
移動の疲れがあり、早めに就寝して備えようとしましたが、緊張していたのかなかなか眠れず、眠りについたのは体感で午前2時ごろになりました。リラックスのために音楽を聴いたりホットアイマスクをつけたりしましたが、もっと自分に合ったリラックスできる方法を用意しておくと良かったと思います。
| 6時 | 起床,散歩をして気分を落ち着かせる,身支度を済ませる |
| 8時 | ホテルの朝食時間の8時に朝食を食べ,8時半の集合時刻に合わせて試験室へ移動 |
| 9時 | 選択科目の最終確認 |
| 12時45分ごろ | 休憩時間に入る 昼食を食べながら憲法の最終確認 着席時刻の10分前ごろ,トイレ待ちの列が減ったの見計らい手洗いを済ます |
| 16時ごろ | 休憩時間に入る ブドウ糖を摂取しつつ行政法の最終確認 |
| 18時45分ごろ | 案内を受け試験室から退室し,夕食を食べに行く 移動中に民法短答の動画を聴く |
| 20時ごろ | ホテルへ戻り入浴,会社法の復習,就寝 |
朝6時ごろに起きて目を覚ますために散歩に行きました。朝の散歩は、雨が降った2日目以外全て行いました。結果として、散歩だけで目が覚めることはありませんでしたが、2日目以外は朝の時間は晴天が広がる気持ちの良い天気であり、散歩に行くたびにまるで天が自分のこれからの人生を祝福していると思えるほど清々しい気分になりました。このように、ちょっとした良いことに着目してポジティブに捉え、自分で自分の気分を上げていく行動を意識的に取ることで、精神の安定を図りました。
試験後は、会場がとても寒くて体が冷え切ってしまったことや前日にあまり眠れなかったことも影響して、すでに疲労困憊でした。試験監督の方にエアコンの風量の調整をお願いし,試験室を出た足で夕食にうどんを食べに行き、ホテルに帰った後はすぐに入浴して寝ることにしました。勉強をしない不安もあったので、移動中や就寝前に絞って、民法短答と会社法の復習を少しだけしました。強烈な気怠さと熱っぽさがあり,風邪を引いてしまったと思い,20時ごろには眠りについたと思います。
試験の雑感として,選択科目である知的財産法は可もなく不可もなく,という感覚でしたが,憲法では選挙権が出題され,行政法では過去2年連続して処分性が出題されていたことから流石に処分性を避けて原告適格が出題されるだろうと考えていたところ,処分性が出題されたため,「試験委員会め…やってくれたな…。」という気持ちになりました。また,行政法に取り組んでいる時点で,例年よりも小問数や検討事項が多いことに気付き,「おや…?傾向が変化している…?」と感じました。
| 6時 | 起床,身支度を済ませる |
| 8時 | 朝食を食べ会社法の確認,9時の集合時刻に合わせて試験室へ移動 |
| 9時半 | 民法論文の最終確認 |
| 12時15分ごろ | 休憩時間に入る 昼食を食べながら会社法の最終確認 着席時刻の10分前ごろ,手洗いを済ます |
| 15時半ごろ | 休憩時間に入る ブドウ糖を摂取しつつ民事訴訟法の最終確認 |
| 18時45分ごろ | 案内を受け試験室から退室し,夕食と買い物に行く |
| 20時ごろ | ホテルへ戻り入浴,気分転換に徹する |
| 21時ごろ | 就寝 |
朝6時ごろに起きましたが、あいにくの天気だったため散歩の代わりにシャワーを浴びて目を覚そうとしました。全然疲労が取れておらず、シャワーをしても結局眠いままでしたが、シャワー後は身支度をして朝食を食べ、試験室に移動しました。
試験の雑感として,民事系はどの科目も小問が多くて時間が足らず,いまひとつの手応えでした。私は,難しい問題を見たときに,パニックになることを防止するため,事実関係に現れた捻りや試験委員会が聞きたいと考える問題意識を見つけて,「面白い問題を作ったな。」と笑顔を浮かべ,楽しんで解くことを心がけています。そのように考える私でも,問題数の多さに辟易しました。また,多くの受験生が見たことのない,いわゆる現場思考系の問題による思考力を試す令和以降の出題傾向に加えて,問題数をさらに増加させて事務処理能力をも試す出題傾向に変えてきた,と確信しました。
もっとも,このような出題傾向の変化に対応できる受験生は少数にとどまると思い,時間が足らなかったことは合否にそこまで影響しないと考えて,気持ちを切り替えるようにしました。
試験後は、雨が上がっていたので外に出て、夕食と最終日までの水とパンの買い物を済ませました。その後は、頭をフル回転させた疲労でぼーっとしていたため、中日に集中して復習した方が効率が良いと考え、入浴を済ませ、YouTubeで好きな動画を観て気分転換をして、21時ごろに寝ました。
| 8時〜10時半ごろ | 起床,散歩,朝食,洗濯など |
| 11時ごろ | 昼食を食べに行き,店内で刑法の論文と短答の確認 |
| 16時〜18時ごろ | ホテルに帰り,憲法短答と民法短答と刑事訴訟法の確認,夕食 |
| 21時ごろ | 入浴,就寝 |
ある程度ぐっすり寝て、8時ごろに目が覚めたと思います。軽く散歩をして朝食を食べ、ランドリーで洗濯を済ませた後は、1,2駅先にあるガストで昼食を食べるついでに刑法の論文と短答の復習をしました。
夕方以降は,ホテルに帰り,憲法と民法の短答と刑事訴訟法の復習をして,帰り道に買った弁当を食べて21時ごろに寝ました。
| 6時 | 起床,散歩,身支度を済ませる |
| 8時 | 朝食を食べ,9時の集合時刻に合わせて試験室へ移動 |
| 9時半 | 刑法論文の最終確認 |
| 11時45分ごろ | 休憩時間に入る 昼食を食べながら刑事訴訟法の最終確認 着席時刻の10分前ごろ,手洗いを済ます |
| 15時半ごろ | 案内を受けて試験室から退室しホテルへ戻り,1時間半ほど仮眠 |
| 16時半ごろ | 憲法短答の確認 |
| 18時半ごろ | 夕食を食べに行く 移動中は民法短答の動画を聴き,ホテルに戻ってからは民法短答の問題集を確認 |
| 22時ごろ | 入浴,就寝 |
1日目と同様,朝6時ごろに起きて散歩に行き,朝食を済ませ,試験室で刑法の確認をしました。疲労もそれなりに取れていたので,かなり落ち着いていました。落ち着きの程度として,自分がそのとき羽織っていたシャツの色と机上の試験用法文の色が完全に一致していることに初めて気付き,なぜ今まで気付かなかったのか,おかしくて笑いそうになったほどでした。
試験の雑感として,刑事系,特に刑法も事務処理能力を試す出題になったと感じ,やや時間不足になりました。刑事訴訟法は,設問2でたまたま前日の夜に見ていた条文が問われたため,それなりの手応えを感じました。試験中は面白いと感じつつも,試験後は「やってくれたな…。」と感じたのは刑事系も同様でしたが…。
試験後は,ホテルの部屋に戻り刑法の短答の復習をして,18時ごろに夕食としてお好み焼きを食べに行き,入浴と民法の短答の復習をして,22時ごろに寝ました。
| 6時 | 起床,散歩,身支度を済ませる |
| 8時 | 朝食を食べチェクアウトし,9時の集合時刻に合わせて試験室へ移動 |
| 9時半 | 民法短答の最終確認 |
| 11時45分ごろ | 休憩時間に入る ブドウ糖を摂取しつつ憲法短答の最終確認 |
| 13時5分ごろ | 休憩時間に入る ブドウ糖を摂取しつつ刑法短答の最終確認 |
| 15時45分ごろ | 案内を受け試験室から退室,友達と談笑 |
| 18時ごろ | 帰宅 |
連日と同じく朝6時ごろに起きて散歩に行き,朝食を済ませました。この日は,あまり眠れなかったこと,問題文の読み間違う傾向があり睡眠不足の日は特に顕著なこと,前年度に短答で不合格となっており今年も同じ結果になるのではという恐怖があったことから,とても緊張していました。
荷造りをしてチェックアウトをし,試験室に行き,民法短答の確認をして開始を待ちました。
試験後は,短答のどの科目も手応えを感じなかったこと,とりわけ刑法は会話文の穴埋め形式の問題が半分近くあり急いで解いたため疲労困憊だったことから,無意識に回答用紙が回収される間は手を組み祈りの姿勢を続け,その後は試験室からの退出の案内があるまで放心状態でした。後日,短答の自己採点をして無事に通過していたため,祈りが通じたのかもしれません。
その後は友達と少し会話をして,お互い労いあってから,帰路につきました。
司法試験は,本当に過酷な試験です。私は,今年度で3回目の受験となってしまいましたが,毎回,試験期間中は想定を上回るほどの精神的,身体的疲労に見舞われ,体調を崩してしまいます。
そこで,少しでも体調を維持し,普段通りの実力を発揮できるよう,必ず準備することをお勧めいたします。このような準備や試験期間中の過ごし方を考えることも,重要な試験対策であり,必ず合格に寄与する要素となります。
本記事が,読者の皆様の司法試験合格の一助となるよう,お役に立つと幸いです。
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
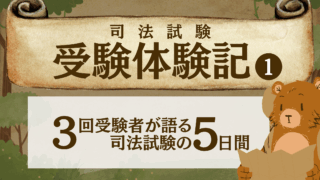
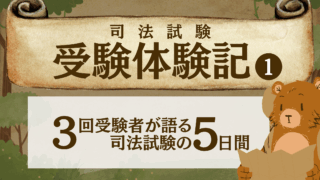
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

