
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
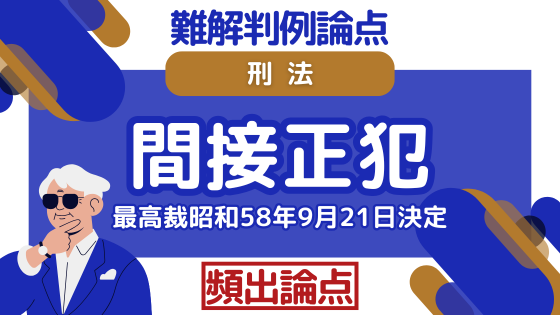
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする司法試験刑法で頻出のテーマのひとつに「間接正犯の成否」があります。
特に、「刑事未成年者」や第三者を「道具」のように利用した犯罪において、「正犯」としての処罰が可能かどうかは、刑法総論の核心的論点です。
本記事で取り上げる最高裁昭和58年9月21日決定は、12歳の養女に対して日常的な暴力や威圧的態度を繰り返していた被告人が、養女を利用して窃盗を実行させたという事案です。
この判例では、たとえ「実行行為者(養女)」が「是非弁別能力」を有していたとしても、加害者による強制と意思の抑圧があった場合には、「実行行為者」を「道具」として利用したものと評価でき、「間接正犯」が成立すると判示されました。
この記事では、「間接正犯」の理論的枠組みを整理しつつ、本判例がどのような基準で「道具としての利用」を認定したのか、また司法試験においてどのように答案に盛り込むべきかについて解説していきます。
「間接正犯の成否」が問題となった事案として、最高裁判所第一小法廷昭和58年9月21日決定(以下「本判例」と言います。)があります。
本件被告人には、当時12歳の養女がいました。
被告人は、日頃から、この養女が被告人の言動に逆らう素振りを見せると、タバコの火を顔に押し付けたり、ドライバーで顔をこすったりするなどして、自己の意のままに従わせていたました。
このような状況下において、被告人は、養女と旅行中、宿泊費などに窮したため、日頃の被告人の言動に畏怖している養女に命じて現金などを窃取させました。
この事案について、原審は、被告人に「間接正犯」として窃盗罪の成立を認めました。この原審に対して、弁護側・被告人が上告したのが、本判例です。
本判例で問題となった争点は、実際に実行行為を行っていない被告人を「正犯」として処罰できるのかという点です。
つまり、「間接正犯の成否」が争点となっています。
「正犯」とは、犯罪の実行行為を行う者のことを言います。
この実行行為を自らの手で行った者のことを「直接正犯」と言います。
実行行為を自らの手で行うことを「自手実行」と言うことがあります。
これに対し、「間接正犯」とは、「自らは直接手を下さずに、他人を利用して犯罪を実現し、共犯としてではなく正犯として処罰される者」のことを言います。
他人を利用して実行行為を行わせることを「他手実行」と言うことがあります。
「正犯」とは、本来、自ら実行行為(自手実行)をした者です。
しかし、「間接正犯」の場合は、自らは実行行為を行っていません。
したがって、自ら実行行為を行っていない者を正犯として扱うには、他人を利用する行為が、自手実行の場合と同様に、結果発生の現実的な危険性を生じさせるものである場合でなければなりません。
では、どのような場合に、他人を利用する行為が結果発生の現実的な危険性を生じさせるものであるのかと言うと、それは、他人の行為を「自己の犯罪実現のための道具として利用した」場合です。
例えば、ナイフを使って人を殺傷する場合のように、道具を使って犯罪を実現することがあります。「間接正犯」もそれと同じです。人間を一方的に道具のように利用して犯罪を実現するのが、「間接正犯」です。
したがって、「間接正犯」が認められるかどうかは、他人の行為を「自己の犯罪実現のための道具として利用した」と言えるかどうかが判断基準となります。
本判例以外の判例でも、他人の行為を「自己の犯罪実現のための道具として利用した」場合に、「間接正犯」の成立を認めたものがあります(最高裁判所第一小法廷平成9年10月30日決定)。
14歳未満の者は、「刑事未成年者」となり、刑罰を科されません(刑法41条)。
刑法 第四十一条(責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
この「刑事未成年者」の行為を自己の犯罪実現のための道具として利用した場合も、「間接正犯」は成立します。
もっとも、「刑事未成年者」の行為を道具として利用した場合、常に「間接正犯」となるわけではありません。「刑事未成年者」が「是非弁別能力」を備えている場合には、その行為を利用したとしても、「間接正犯」は成立しないことがあります。
「是非弁別能力」とは、物事の善し悪しを判別する能力のことです。
利用された者が「是非弁別能力」を備えていない場合、犯罪を悪いことであると判別できないため、これを思いとどまることができません。
そのため、「是非弁別能力」を備えていないものの行為を利用することは、「道具」として利用したものと評価できます。
他方、「是非弁別能力」を備えている場合には、自ら犯罪を思いとどまることが可能です。それにもかかわらず「実行行為」を行っているということは、その者が自らの意思で犯罪の「実行行為」を行っているということです。
したがって、「刑事未成年者」であっても、「是非弁別能力」を備えている者の行為を利用する場合は、「道具」として利用しているとは言えず、「間接正犯」は成立しないのです。
ただし、利用者に「間接正犯」は成立しませんが、「共犯(教唆犯、幇助犯または共同正犯)」が成立することはあります。
例えば…
本判例以外の判例には、被告人が犯行当時12歳の長男に命じて強盗を実行させた事案において、長男が是非弁別能力を有しており、意思を抑圧されておらず、
自分の意思で犯行を決意し、臨機応変に対処して犯行を行ったことから、長男は被告人の道具とは言えないので、「間接正犯」は成立せず、「共同正犯」が成立するとしたものがあります(最高裁判所第一小法廷平成13年10月25日)。
かつては、「共犯」が成立するには、「正犯」に「構成要件該当性、違法性、責任」のすべてが備わっていなければならないとする説(極端従属性説)がありました。
「直接の行為者に故意や責任能力がない場合、共犯が成立せず、背後者を処罰できないことから、その間隙を埋めるために、間接正犯の概念が取り入れられた」と言われています。
「極端従属性説」によると、「刑事責任能力のない刑事未成年者の行為を利用する場合」は、その「刑事未成年者」に「是非弁別能力」があるときでも、処罰の間隙を埋めるために、「間接正犯」が成立することになります。
しかし、現在では「極端従属性説」はとられておらず、「制限従属性説」が通説的見解となっています。
「制限従属性説」とは?
「共犯成立」には「構成要件該当性と違法性」があればよく、責任まで具備していることは必要とされないという説です。
「制限従属性説」によると、「刑事未成年者」に「是非弁別能力」がある場合には、「共犯」が成立するので、処罰の間隙を埋める必要性はありません。
現在では、「間接正犯」の理論は処罰の間隙を埋めるためのものではなく、それが「正犯」として処罰するに値するものであるからこそ必要な理論であると意義づけられるようになっています。
また、そもそも「間接正犯」は、「正犯」です。したがって、「共犯」の成立を検討する前に、まず「間接正犯の成否」を検討し、その成立が否定される場合に「共犯の成否」を検討する必要があります。
「刑事未成年者」を利用する行為が問題となる場合も、まずは「間接正犯の成否」を検討し、それが否定される場合に、「共犯の成否」を検討することになります。
前記のとおり、「刑事未成年者」に「是非弁別能力」がある場合には、「道具」として利用しているとは言えず、「間接正犯」は成立しないのが原則です。
もっとも、「刑事未成年者」が行為を強制されている場合には、「間接正犯」が成立することがあります。
ただし、行為を強制されているからと言って、必ずしも、「刑事未成年者」が自己の「是非弁別能力」に従って犯罪を思いとどまることができなくなるとは限りません。
したがって、「是非弁別能力」のある「刑事未成年者」の行為を強制したことにより、他の行為を選択できない程度に意思を抑圧されていたと言える場合に、被害者の行為を「道具」として利用したものとして、「間接正犯」が成立すると考えるべきでしょう。
本判例は、被告人に窃盗罪の「間接正犯」の成立を認めた原審の判断を支持し、弁護側・被告人の上告を棄却する決定をしています。
前記のとおり、本件被告人は、12歳の養女の行為を利用しています。しかも、日頃から暴行等を加えて養女を畏怖させ、自己の意のままに従わせていました。
したがって、本件では、「間接正犯の成否」に関して、「刑事未成年者」の行為を利用する場合、実行行為を強制する場合の両者が問題となってきます。
これらの点について本判例は、「刑事未成年者」の行為であることについては正面から触れず、「実行行為」を強制している場合に該当することを強調して、「間接正犯」の成立を認めています。
具体的には、以下のとおり判示しています。
「被告人は、当時12歳の養女Aを連れて四国甲等を巡礼中、日頃被告人の言動に逆らう素振りを見せる都度顔面にタバコの火を押しつけたりドライバーで顔をこすったりするなどの暴行を加えて自己の意のままに従わせていた同女に対し、本件各窃盗を命じてこれを行わせたというのであり、これによれば、被告人が、自己の日頃の言動に畏怖し意思を抑圧されている同女を利用して右各窃盗を行つたと認められるのであるから、たとえ所論のように同女が是非善悪の判断能力を有する者であつたとしても、被告人については本件各窃盗の間接正犯が成立すると認めるべきである。」
本判例は、まず、被告人が、日頃から養女が被告人の言動に逆らう素振りを見せる都度、養女の顔にタバコの火を押し付けたりドライバーで顔をこすったりするなどの暴行を加えて「自己の意のままに従わせていた」と認定しています。
そして、そのような被告人の「日頃の言動に畏怖し意思を抑圧されている」養女に窃盗を命じてこれを行わせたと判示しています。
養女は被告人に逆らうことができない状態であり、そのような養女の「実行行為」は、被告人に強制されたものに等しいと言えます。
したがって、被告人は、自己の犯罪(窃盗)実現のために養女の行為を「道具」として利用したと評価できます。
そして、養女が「是非善悪の判断能力を有する者であったとしても、間接正犯が成立する」と判示しました。
「間接正犯の成否」は、司法試験刑法で頻出のテーマです。特に、「刑事未成年者」や第三者を「道具」のように利用した犯罪において、「正犯」としての処罰が可能かどうかは、刑法総論の核心的論点です。
「間接正犯」の理論的枠組みを整理しつつ、本判例がどのような基準で「道具としての利用」を認定したのか、また司法試験においてどのように答案に盛り込むべきかについて整理しました。
本判例は、「刑事未成年者」に「是非弁別能力」が認められる場合でも、「実行行為」を強制されている場合には、「間接正犯」が成立することを認めたのです。
以下の記事でも「間接正犯」について解説しているので、是非ご覧ください。


刑法判例50!(著:十河太朗ほか、出版:有斐閣)118ページ
刑法判例百選Ⅰ(第7版)150ページ
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

