
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
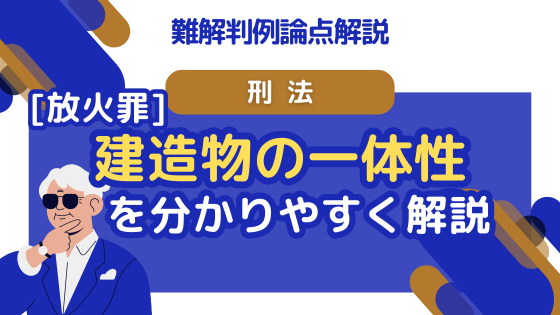
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする放火罪における「建造物の一体性」とは「元々複数の建造物を一個の建造物と評価できるか?」という論点です。
つまり「非現住建造物」と「現住建造物」が繋がっていて、「『非現住建造物』に放火した場合に、『現住建造物放火罪』に問えるのか?」ということです。
「放火罪」の条文にそのような状況は明示されていません。ですが、建造物2つがセットになっている状況は、ごくありふれたものです。つまりこれは、法律を現実に当てはめる際に生じるギャップであって、これを埋めるのが法律実務家の仕事です。



はりきって、いきましょう!
▼動画で学びたい方はこちら▼
まずは、「放火罪」の条文を確認しておきます。
刑法108条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法109条(非現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。



「平安神宮」って、観光で有名な、京都にある赤い大きな鳥居があるところだね!



そうだよ!そこの拝殿で昔、放火があったんだ!
「建造物の一体性」が関係してくるので、この事案をもとに進めていくぞ!
事案の概要 (最高裁平成元年7月14日)
1976年1月6日午前3時頃に、平安神宮内拝殿で放火があった。
平安神宮の構造としては、本殿や社務所などが歩廊で接続されていた。本殿などは現住していないが、社務所等は宿直員などが現住していた。
≪詳細≫
(1)平安神宮社殿は、様々な建物とこれらを接続する歩廊等から成り、中央の広場を囲むように方形に配置されており、歩廊などを伝って各建物を一周できる構造になっていた
(2)右の各建物は、すべて木造であり、歩廊なども、その屋根の下地、透壁、柱等に多量の木材が使用されていた
(3)祭具庫、西翼舎等に放火された場合には、社務所、守衛詰所にも延焼する可能性を否定することができなかつた
(4)外拝殿では一般参拝客の礼拝が行われ、内拝殿では特別参拝客を招じ入れて神職により祭事等が行われていた
(5)夜間には、神職各2名と守衛、ガードマンの各1名の計4名が宿直に当たり、社務所又は守衛詰所で、執務をするほか、以下巡回などが行われた
・出仕と守衛が、午後8時ころから約1時間にわたり社殿の建物等を巡回
・ガードマンも、閉門時刻から午後12時までの間に3回と、午前5時ころに同様の場所を巡回
・神職とガードマンは、社務所で就寝
・守衛は、守衛詰所で就寝
判旨 (最高裁平成元年7月14日)
右社殿は、
①その一部に放火されることにより、全体に危険が及ぶと考えられる一体の構造であり
②全体が一体として、日夜、人の起居に利用されていたものと認められる
そうすると、右社殿は「①物理的」に見ても「②機能的」に見ても、その全体が1個の「現住建造物」であつたと認めるのが相当である
「現住建造物等放火罪」と「非現住建造物等放火罪」では、「法定刑」が違います。
「現住建造物等放火罪」は「殺人罪」と同等で死刑または無期もしくは5年以上の懲役です。「非現住建造物等放火罪」は2年以上の有期懲役です。2年以上の有期懲役といえば他に該当するのは「往来妨害罪(刑法125条)」です。「殺人罪」と「往来危険罪」、その差はまさに天と地の差です。
「現住建造物等放火罪」と「非現住建造物等放火罪」の法定刑
現住建造物等放火罪:死刑または無期、もしくは5年以上の懲役(「殺人罪」と同等)
非現住建造物等放火罪:2年以上の有期懲役(「往来危険罪」と同等)



「現住建造物等放火罪」の法定刑は「殺人罪」と同じか!
ちなみに「現住建造物等放火罪」の名前に入っている「建造物」とは、「家屋その他これに類する建築物であって、屋根があり壁または柱で支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りできるもの(大判大正3年6月20日)」です。「現住」とは「人が起臥寝食の場として日常的に使用すること」を言います。典型的には住宅がそれに当てはまるでしょう。
「現住建造物等放火罪」への理解
建造物:家屋その他これに類する建築物であって、屋根があり壁または柱で支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りできるもの
現住:人が起臥寝食の場として日常的に使用すること(典型的には住宅など)
「現住」と「非現住」のどちらになるかで、「現住建造物等放火罪」と「非現住建造物等放火罪」のどちらになるかが変わってきそうです。
例えば、会社の入っているビルに放火した場合であって、従業員の居住スペースがビルの近くにあった場合は「現住建造物等放火」と言えるのでしょうか?「現住性」のない部分に放火したにも関わらず、施設全体を一つの「現住建造物」と評価できるのはどのような場合でしょうか?



次の章で、どのような場合に「現住建造物等放火罪」となるのかを詳しく見ていくぞ!
平成元年判決では、判旨で出てきたように「『①物理的』に見ても『②機能的』に見ても、その全体が1個の現住建造物」とし「現住建造物放火罪」を肯定しました。
「建造物の一体性」の判断基準は、「①物理的一体性」と「②機能的一体性」に分かれることとなります。
「①物理的一体性」とは、「構造上の一体性」を有し、火災時に延焼や有毒ガスの流入など「全体への危険が生じうる状態」を言います。
「建造物として一体」と言えるためには、少なくとも「構造上接続されている」必要があります。
「2つの建造物がそれぞれ独立している場合」で、その片方に放火をした場合は、その建造物に放火をしただけで、その両方を一体として、罰するわけにはいきません
まず前提として、2つの建造物が渡り廊下などで接続されている場合に、一体性を検討することとなります。
とはいえ、平安神宮のように「渡り廊下で接続されている」だけで、2つの建造物を1つのものとみなすのは、無理があります。
そこで「『現住建造物放火罪』として処罰されるのは、どのような場合であるのか?」考えると、それは「現住建造物放火罪」の保護法益である「生命への危険が生じた場合」であると言えます。
平成元年判決でも「その一部に放火されることにより全体に危険が及ぶと考えられる」ことを根拠としています。
全体に危険が及ぶ経路は、主に次の2つになります。
全体に危険が及ぶ経路
・延焼
・有毒ガスの流入
「非現住部分」に放火をすることで、「現住部分」を含む全体に延焼する可能性が「一体性の判断」の中心となります。そして、火災により発生した有毒ガスが「現住部分」に流入するような場合にも、「物理的一体性」が認められることになります。
平安神宮は、歩廊などが「木材」で出来ており、燃え広がりやすい構造でした。それでも、各建物はそれなりに離れており、それほど「延焼可能性」等が高いとは言えませんでした。
「物理的な接続があまり強くない場合」には、その「建造物の利用形態」を考えます。「人が日常的に、複数の建造物を一体のものとして利用しているという場合」には、「『非現住建造物』の部分にも人がいる可能性が高まるため、危険が及んでいる」と言えます。
平成元年判決では、守衛やガードマンが1時間ごとに建物を巡回することから「全体が一体として、日夜、人の起居に利用されていた」として、「機能的にも一体」であるとしました。
平成元年判決で「『建造物の一体性』があるのか?」を見るために、「①物理的一体性」「②機能的一体性」に当てはまるかを見ていきましょう。
「①物理的一体性」があるかを見ていきます。
構造上の一体性、つまり「複数の建造物が接続されているかどうか?」です。もしも「渡り廊下などで繋がっていない場合」には、それは単なる「独立した建造物」として扱います。
次に「生命の危険が全体に及ぶか?」を検討します。延焼可能性や有毒ガスの流入などによって、「『非現住部分』への放火が『現住部分』へと及ぶかどうか?」です。
これを考える際に重要なのが、「現住」と「非現住」部分との距離・建材・窓や通気口による繋がりです。一方で、風向きや実際の放火行為の態様などは考慮しません。あくまで当該建造物の性質として、一体性があるかを考えるからです。
こうして延焼可能性等が高いと認められる場合には、一体性が認められ、現住建造物等放火罪が成立するでしょう。
一方で、延焼可能性等が高いわけではない場合もあります。「延焼可能性等が否定できない」というレベルであっても直ちに一体性は否定されません。
次に「②機能的一体性」を検討します。人が日常的に複数の建造物を一体のものとして利用しているか。具体的には、非現住建造物部分に人が移動する可能性があるかどうかを検討します。
「機能的一体性」の位置づけについては、次の2つの有力な説があります。
①構造的一体性を前提に、延焼可能性等か機能的一体性のどちらかが認められれば一体性があるとする見解
②構造的一体性と延焼可能性等を前提に、延焼可能性等が弱い場合に一体性を補強するものであるという見解
今回参考にした文献では、後者の説を採っています。前者の見解は「延焼可能性と機能的一体性が同じくらいの生命の危険を拡大すること」を前提にしていますが、実際には機能的一体性だけでは延焼ほど確実に生命の危険は及ばないからです。
また、答案戦略としても、普通に論述をする際には、後者の見解を採るほうがいいでしょう。後者の見解なら「延焼可能性等と機能的一体性に関する事実を拾って評価することができる」からです。
「建造物の一体性」があるかどうかは以下のステップで見ていきましょう。
・複数の建造物が接続されているかどうか?
→物理的つながりがないのであれば「独立した建造物」
・現住と非現住部分との距離、建材、窓や通気口による繋がりを考慮した場合、生命の危険が全体に及ぶか?
・人が日常的に、複数の建造物を一体のものとして利用しているか?
・非現住建造物部分で、人が移動する可能性があるか?
この論点に関する判例には変遷があります。
たとえば大審院時代の判例には、構造的一体性なしに一体性を肯定していた事例もあります。これは特に判例変更もなく、古くなって先例としての価値を失いました。明治や大正時代には、現代よりも多くの建造物が木造であり、それゆえに生命の危険が生じやすかったことも背景にあります。このような時代背景の変遷などがあるため、裁判例を見る際には注意が必要となります。
裁判例の位置づけを調べるのに際しては、この論点に関する長めの論文を読むのが役に立ちました。参考文献欄にてその論文を示しているので、参考にしてください。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
▽参考文献▽
・大塚裕史ほか『基本刑法II 総論[第3版]』(日本評論社、2019)
・大塚裕史『応用刑法II 総論』(日本評論社、2023)
・『アガルートの司法試験・予備試験合格論証集 刑法・刑事訴訟法』アガルートアカデミー編著(サンクチュアリ出版、2020)
・佐伯仁志・橋爪隆編『刑法判例百選II[第8版]総論』(有斐閣、2020)
・秋元洋祐「放火罪における建造物の一体性」『法と政治』 62 巻 2 号 (關西學院大學法政學會、2011) 69頁から
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
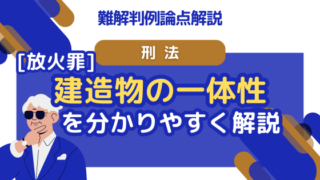
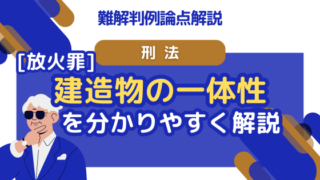
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
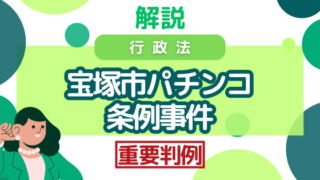
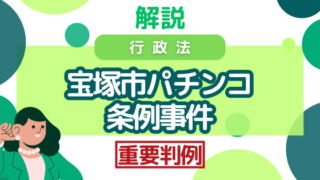














勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

