
【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!
※閉じるとこの案内は再表示されません
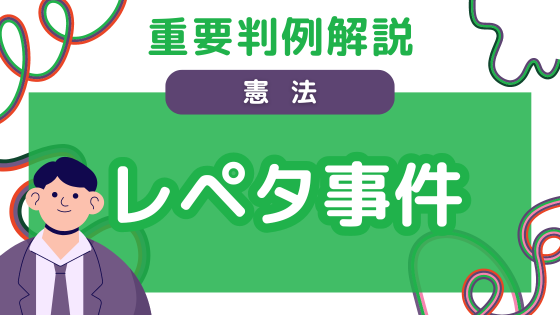
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?




その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?
>>>詳細をチェックする
レペタ事件(法廷メモ訴訟)最大判平成元年3月8日は、法廷において傍聴人がメモを取ることの自由が認められているのかどうかが問題となった判例です。
事件当時、法廷において、一般の傍聴人がメモを取ることは一般的に禁止されていましたが、この判決を機に、一般の傍聴人のメモ採取が認められるようになりました。
レペタ事件の意義とその内容について確認していきましょう。
法廷でメモを取る自由に関して事件当時は次のような状況でした。
・一般の傍聴人:メモを取ることは一般的に禁止されていた。
・司法記者クラブ所属の報道機関の記者:メモを取ることは許可されていた。


昭和40年代以降、法廷で一般の傍聴人がメモを取ることは禁止されていました。一般人とは、訴訟関係者以外の人のことで、弁護士であっても訴訟と関係なければ、メモ採取は認められていませんでした。
アメリカ人弁護士のレペタ氏は日本における証券市場の法的規制について研究しており、その一環として東京地裁で行われた所得税法違反被告事件の公判を傍聴しました。
その際、レペタ氏が裁判長に対して、法廷でメモを取る許可を求めましたが、裁判長は、一般人がメモを取ることは許可されていないとして、許可しませんでした。
そのため、レペタ氏がこの措置が憲法のほか、国際人権規約B規約19条、刑事訴訟規則に反するとして、国に対して国家賠償請求訴訟を提起した事件です。第一審、控訴審共に請求棄却の判決が出されたために、上告しました。


レペタ事件を理解する前提として、法廷における取材の自由についての最高裁の考え方を整理しておきましょう。


そもそも、取材の自由は憲法により保障されているのでしょうか?
憲法の条文中に、取材の自由についての直接の規定はありません。
しかし、最高裁は、博多駅テレビフィルム事件において、報道の自由が表現の自由を規定した憲法21条により保障されている旨を述べた上で、「報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いする」との見解を示しています(最大判昭和44年11月26日)。
なお、「取材の自由とは何か?」については、「報道機関の取材行為に国家が介入することからの自由」を意味していて、国家に対して一定の行為を請求する積極的な権利が導かれるものではないとの見解が示されています(東京地判平成12年10月5日)。


法廷においても、取材の自由が認められるのが原則です。
ただ無制限ではないことが北海タイムズ事件の判例により示されています。
この事件は、報道機関のカメラマンが公判中に被告人が証言台に立つ様子を裁判官席の壇上から撮影したものでした。しかし最高裁は、「公判廷の状況を一般に報道するための取材活動であっても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するがごときものは、もとより許されない」との見解を示しています(最大判昭和33年2月17日)。
法廷における取材の自由は、原則として認められています。
しかし、法廷の秩序維持に反するような形での取材は認められていませんし、法廷の秩序維持に関する法律により裁判官が処分を行うことも可能とされています。(法廷警察権)
では、法廷でメモを取ることは、法廷の秩序維持を困難にするような行為と言えるのでしょうか?
事件当時、司法記者クラブ所属の報道機関の記者がメモを取ることは許可していたことからして、一般人が法廷でメモを取ることが直ちに、法廷の秩序維持を困難にするような行為になるとは言えないのではないかと考えられていました。
現に、事件当時において、一般人がメモを取る行為が黙認されている事例もありました。
そんな折に、レペタ事件が起きたわけです。
※参考 日弁連 法廷における傍聴人のメモ問題について
レペタ事件では、憲法82条1項、憲法21条1項、憲法14条1項が論点となりました。
それぞれを見ていきましょう。


憲法には、裁判を傍聴する権利についての規定がありません。
ただ、憲法82条1項に、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」と定められており、この規定から裁判を傍聴する権利が認められると共に、傍聴人がメモを取る行為も認められるのではないかとの見解が成り立ちます。
(参考)憲法
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
最高裁は、憲法82条1項の趣旨について、「裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保する」ことが狙いであるとしています。
そのうえで、裁判を傍聴する権利を認めた規定でもないし、「傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものでない」との見解を示しました。
つまり、最高裁は、裁判の公開を制度的保障としてとらえた上で、傍聴できることは、その反射的利益に過ぎないとの立場を採ったわけです。


憲法21条1項は、表現の自由を規定していますが、派生原理として情報摂取の自由も認められるというのが当時の有力な学説でした。
(参考)憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。
そして、メモを取る行為も摂取した情報を記憶するために必要な行為ですから当然に認められると解されていたわけです。
それならば、一般の傍聴人が法廷でメモを取ることも、情報摂取の自由の一環として認められるべきではないかとの見解が成り立つわけです。
最高裁は、まず、憲法21条1項が、表現の自由を保障しており、同時に情報摂取の自由も、「民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要」として、表現の自由の派生原理として認められるとの見解を示しました。
そのうえで、法廷で傍聴人がメモを取る行為は、「その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならない」との見解を示しました。
もっとも、最高裁は、法廷で傍聴人がメモを取ることを権利として認めると明示したわけではありません。
まず、法廷は、「適正かつ迅速な裁判を実現する」場であり、裁判官及び訴訟関係人が全神経を集中すべき場です。傍聴人は、その活動を見聞する者に過ぎず、裁判に関与して積極的に活動するものではありません。
傍聴人のメモを取る行為よりも公正かつ円滑な訴訟の運営を図ることの方が、はるかに優越する法益になります。
そのため、傍聴人のメモを取る行為により、「いささかでも法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には、それが制限又は禁止されるべき」としています。
ただ、通常は、傍聴人のメモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるに至ることはないため、特段の事情のない限り、傍聴人の自由に任せるべきとの見解を示したわけです。


事件当時は、司法記者クラブ所属の報道機関の記者がメモを取ることを許可する一方で、一般の傍聴人がメモを取ることを一般的に禁止していました。
この扱いは、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するのではないかとの疑問が生じます。
(参考)憲法
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
まず、最高裁は、憲法14条1項は、「絶対的な平等を保障したものではなく、合理的理由なくして差別することを禁止する趣旨」であると述べました。
そのため、それぞれの事実上の差異に相応して法的取扱いを区別することは、その区別が合理性を有する限り、違憲ではないとしています。
そのうえで、「報道の公共性、報道のための取材の自由に対する配慮に基づき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置ということはできない」として、一般の傍聴人がメモを取ることを禁止する措置を取っていたことは、憲法14条1項に違反しないと述べました。
レペタ事件では、東京地裁の裁判長が法廷警察権に基づいて、レペタ氏が法廷でメモを取ることを禁止しました。この措置が、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に当たるのではないかが、問題になりました。
最高裁は、法廷警察権の行使における裁判長の判断は、「最大限に尊重されなければならない」したうえで、法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に当たらないと述べました。
そのうえで、当時は、法廷警察権に基づき傍聴人がメモを取ることを一般的に禁止する措置が広く一般的に行われていたものと認定し、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に当たるとまでは、断ずることはできない。との結論を下しました。
判決としては、レペタ氏の上告が棄却され、レペタ氏が敗訴したことになりました。
ただ、判決後、最高裁事務総局が、法廷における傍聴人のメモ採取を認めるように各裁判所に通知し、法廷における傍聴人のメモ採取が原則として自由に認められることになりました。
その意味で、実質的には、レペタ氏の勝訴に近い判決として評価されています。


レペタ事件(法廷メモ訴訟)をきっかけに、一般の傍聴人が法廷でメモを取ることが原則として認められるようになりました。
ただ、最高裁は、一般の傍聴人が法廷でメモを取る「権利」を認めたわけではなく、「尊重に値し、故なく妨げられてはならない」と述べているだけです。
試験で、「一般の傍聴人には法廷でメモを取る権利がある」という選択肢が出たら、間違いなので注意してください。
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
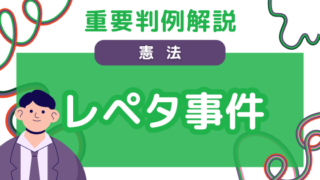
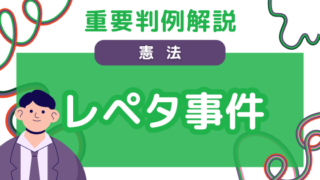
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。
法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。
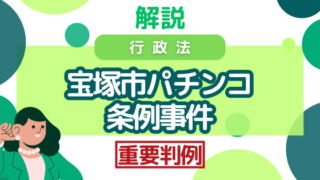
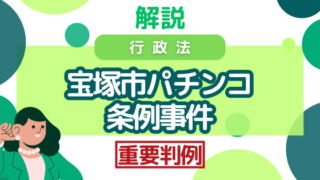














勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

