
【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!
司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF
※閉じるとこの案内は7日間再表示されません
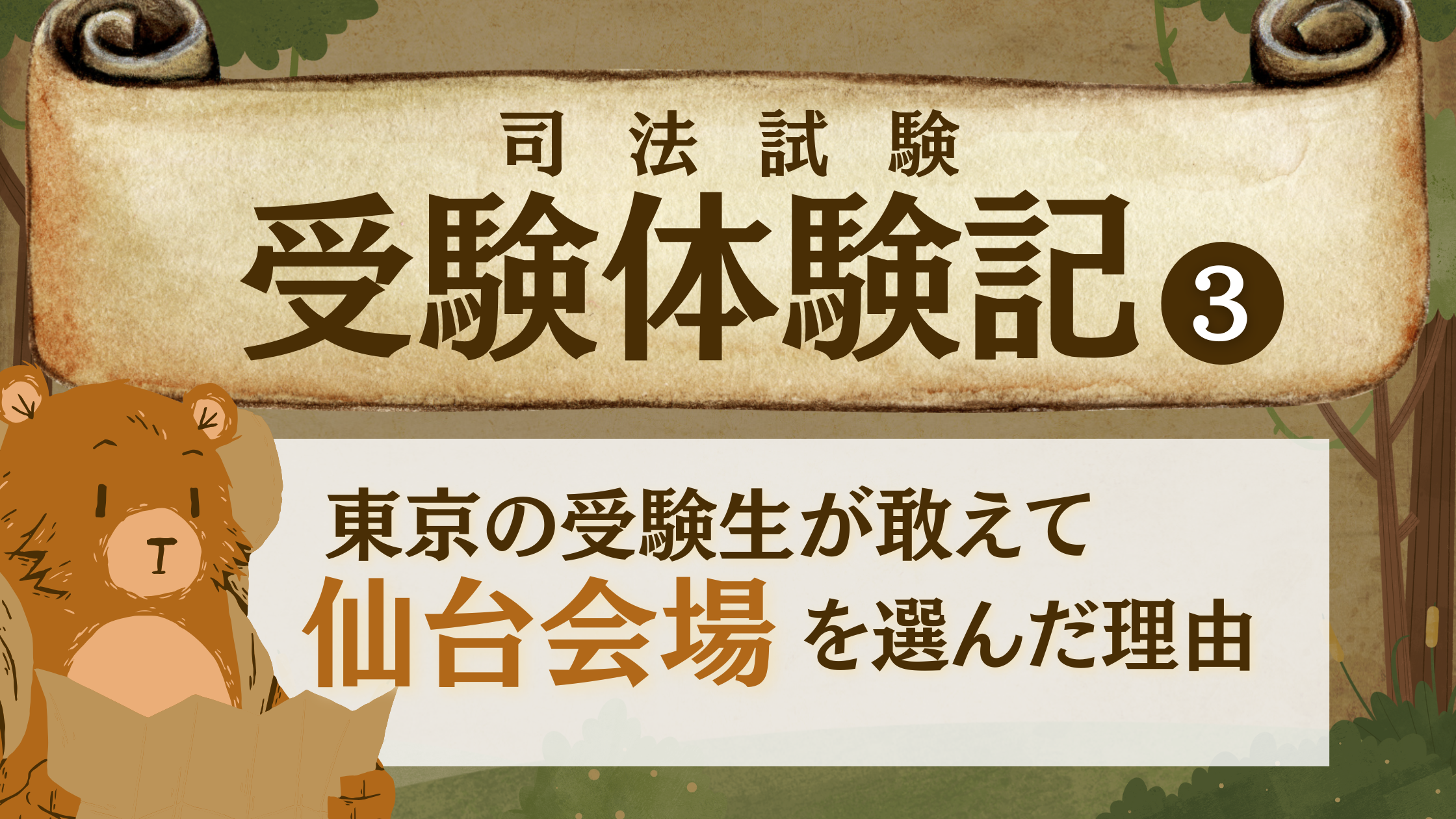
かもっち・あひるっぺからの挨拶
 かもっち
かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。
皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!
法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。



私は、司法試験受験生のあひるっぺ!
司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。
必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。



姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。



私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。
知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!
(挨拶おわり)



ねえ、もっち…。
記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。
私さ、
「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。
何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。



──それ、正直しんどいよね。
でもね、結論から言うと。
それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。
「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。



「落ちる勉強法?」
そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。



でも、ここは誤魔化しちゃいけない。
司法試験は、
努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。
実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、
・自分がなぜ落ちたのか
・どこでズレていたのか
・何を捨て、何に集中すべきか
──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。
その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』



何それ?気になる



ただの精神論じゃない。
✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”
✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」
✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い
を解説している。
もし今、
「こんなにやってるのに、なぜ…」
と感じているなら。
それはあなたがダメなんじゃない。
やり方を変えるタイミングが来ているだけ。
先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、
もう遠回りは終わりにしよう。
努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?


司法試験は「日本で最も過酷な試験の一つ」と言われます。
合格を目指すには、膨大な知識を積み上げ、数年間にわたり計画的に学習を続ける必要があります。しかし、机上の学習法や一般論だけでは、その厳しさやリアルな雰囲気を実感することはなかなか難しいのではないでしょうか。
そこで今回、「令和7年度司法試験」を実際に受験された3名の方にご協力いただき、それぞれの受験体験記を寄稿いただくことにしました。法科大学院での学習、就活や日常生活との両立、本番直前の過ごし方や試験当日の雰囲気など、合格を目指す皆さんにとって貴重なヒントとなる内容が詰まっています。



「これから司法試験を受けようと考えている方」あるいは「受験生活の真っ只中にいる方」にとって、「自分はどう取り組むべきか?」を考える手がかりになれば幸いです。
ぜひ最後までお読みください。



それでは、お話を聞いてみましょう!
読者の皆さんこんにちは。いつも司法試験の勉強お疲れ様です。
この記事では令和7年司法試験を受けた私の会場選び、ホテル選び、直前期の勉強法、司法試験を終えての教訓などについて書いています。
試験勉強の息抜きに読んでいってください。



やあ、法律を学ぶみんな!
今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!



そうなのそうなの〜!
受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨



特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!



あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱
お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!
📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】
司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!
現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。
\ このタイミングを逃す手はありません /
合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。


仙台会場のイメージ。会場のHPから。本番ではテーブルクロスはかかっていなかったが、それ以外はだいたいこんな感じ。
(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-sendai-nishiguchi/)
私は東京に家があり、ロースクールも東京都内ですが試験会場は仙台にしました。
理由は、東京会場は人が多くて混んでいそうだったこと、試験中知り合いと会いたくなかったこと、どうせホテルに宿泊するなら遠出してみようと思ったことです。
これらは私の性格に由来しています。すなわち私は人がたくさんいる場所があまり好きではないし、試験中知り合いに話しかけられたくなかったし、何かの間違いで答え合わせでもされようものなら心の平穏が乱されて後の教科に影響が及ぶだろうと考えたからです。(ホテルについては後述)
さて、仙台受験は最高でした。
会場もきれいだし、人は多すぎず、もちろん知り合いもいませんでした。あと牛タンがおいしいです笑。
これは半分冗談、半分本気です。司法試験中たまったストレスをいかに発散するかというのは結構大事で、おいしいものを食べる(夕食)というのは極めて有用な方法です(時間も使いません)。
ちなみに、東京受験の友達は「毎日コンビニ弁当だった」と言っていました。かわいそうに。
予想外のメリットとしては東京よりは涼しくて過ごしやすいなと感じました。しかし気温については日本全国どこに行ってもある程度暑いですし、北海道でも40度に迫る勢いですのであまり期待はしない方がいいかもしれません。
以下仙台最高だよということを長々書いてもいいのですが、来年からはCBTの導入で47都道府県に試験場が設置される可能性があるようですね。(https://www.moj.go.jp/content/001437905.pdf)(Q5参照)
すると、会場の様子についても8会場しかなかった私たちの頃と比べてずいぶん変わってくるでしょうから我々の経験は読者の皆さんにはあまり参考にならないのでしょう…。
というわけで、ここでは「心の平穏を望む受験生には地方受験がおすすめですよ」と言う程度にとどめたいと思います。


泊まったホテルのHPから。まさにこのまんまの部屋だった。
(https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/sendai_ax/rooms/)
私にとって司法試験受験の際にホテルに宿泊するということはもう確定していました。私は朝があまり強くないうえ、睡眠時間をしっかり確保(8時間半)したいタイプでした。また、朝の満員電車が大嫌いでとてもストレスでしたし、電車が遅れるリスクもとりたくありませんでした。そこで会場から徒歩圏内のホテルをとることで睡眠時間を確保し、移動のリスクを減らそうと思ったのです。
さて、ホテルには試験期間中の拠点になるのでホテル選びは試験の点数に影響を及ぼし得ます。そこで私はかなり時間をかけてホテルを探しました。
ホテルの条件は以下の通りです。
≪ホテル選びの条件≫
①壁が薄くない(隣の部屋の音が聞こえない)
②試験会場から徒歩圏内
③朝食付き
④大浴場付き
試験期間中、隣の部屋の音で眠れないというのはあまりにも最悪です。私はホテルの口コミサイトから「隣の部屋の音がうるさかった」という意見がないか確認してそういうホテルは候補から外していました。
近い方がいいよねという単純な考えです。1つ注意すべきは、東京会場だと人が多いので会場近くのホテルの争奪戦が繰り広げられていたようです。早めにとることをお勧めします。
朝ご飯の調達を考える時間が無駄なため。
疲れをとって、できるだけリラックスするため。
結果、ドーミーイン仙台ANNEXさんに決定しました。私の望む条件を全て満たした完璧なホテルでした。ちなみに会場までは特に急がず徒歩約5分という距離でした。
皆さんがホテルを選ぶときの参考になれば幸いです。
試験直前期の勉強をするにあたって私は以下の点を重視していました。
それは、民事系(論文)を中心に勉強することです。私は皆さんに「民事系だけ前日の勉強時間がないよ」ということを伝えたいです。
これは令和7年度司法試験の時間割です。


(https://www.moj.go.jp/content/001434166.pdf)
選択科目+公法系は試験前日に丸一日勉強できます。刑事系も中日が丸一日あります。
短答は丸一日はありませんが、刑事系のテストが3時前に終わりますし、中日でも勉強可能です。
さて、民事系はどうでしょう。
初日が終わった後の数時間しかありません。
それに、その数時間だって勉強できるかは怪しいものです。7時間も試験がある初日です。長時間頭をフル回転させ続け、終わったころにはもうへとへとです。勉強できないことを想定しておいた方がいいでしょう。
つまり「一番覚えなきゃいけないことが多い民事系だけ前日の勉強時間が(ほぼ)ない」のです。
そこで私は試験1週間前、民事系の論文にかなり傾斜をかけて勉強していました。(勉強時間の6割くらい民事系の論文の勉強をしていた印象です)
ちなみに、具体的には何をやっていたかと言うと①予備校などの出題予想分野の知識の復習、②過去問で頻出の知識の復習、③出たら即死しそうな論点・判例をつぶす、ということを中心にやっていました。
この章ではとにかく「一番覚えなきゃいけないことが多い民事系だけ前日の勉強時間が(ほぼ)ない」ということをお伝えしたいのです。
このことを考慮せずに勉強計画を組んで前日に「時間ないじゃん」と気が付くのが最悪です。ぜひそうならないように、自分なりに直前期における時間の使い方を考えてみてください。
試験期間中の論文は規範集(憲法:合格思考、選択科目:ロースクールのレジュメ、その他:趣旨規範ハンドブック)をグルグル回して復習する勉強がメインでした。9割はこの作業(とにかく規範を思い出す作業)をしていました。
グルグルと言っても実際には時間は1日しかないので一周くらいしかできませんでした。
民事系に関しては前述のように時間がなかったので一周もできていません。
ただ、時間がないのはわかっていたので民事系は事前に、直前に復習する規範にマークをつけておいてその範囲だけはやっていました。
短答は短期記憶で解けるので直前期の勉強の成果が出やすいと思います。
そして直前期に得点アップを図るにはなるべく大量の短答知識に触れることが大切です。
理由は単純で、直前にたくさんの知識に触れれば触れるほど、勉強した知識が出題される可能性が高まるからです。
そのために、知識を純粋に知識として摂取できる状況を作っておくことが大事です。
どういうことかと言うと、短答の勉強をする際、多くの方は合セレや短パフェなどの過去問集を使用すると思います。
短答は過去問がとにかく大事なのでその方法はおそらく正しいのでしょう。
しかし、試験の前日のような超直前期に膨大な短答知識に触れるには問題を解いている時間がもったいないです。
そこで自分が覚えていない知識だけをまとめた媒体をあらかじめ作成しておいて、試験一日前にはそれをひたすらグルグル見るという形で勉強するとよいのではないでしょうか。
形式はノートでもWordでも何でもよいですが、できれば紙媒体がいいと思います。
なぜなら試験が行われる教室では休憩時間も含めて電子機器の使用が禁止されているからです。
ちなみに、私はこのことに試験1日前に気が付いたので民法だけ知識をまとめた媒体を急いで作って、それをグルグル回していました(刑法憲法についてはそんなことをやっている時間はありませんでした)。
それはそれで勉強になったのですが、事前にやっておけばもう少し効率よく短答前日を使えたかなと思います。
これは本当に個人的、主観的な教訓です。これらの教訓が参考になるかどうかは読者の皆さんのパーソナリティーによります。しかし、自分の司法試験受験体験を語る上では欠かせない教訓なので書いておきます。
それは、司法試験を受けない親友の大切さです。
親友と書きましたが、心を許せる他人のことです。友人でも恋人でも家族でも誰でも構いません。司法試験を受けない人とのつながりというのは大事だなと思います。
私は2日目の民事系ができませんでした。
そのとき、私は司法試験を受けていない知人に「できなかった」というラインを送って慰めてもらいました。夜もほぼ毎日電話していました。
司法試験仲間もいたのですが、向こうも試験中なので気を使わないといけないし、向こうから「なんか今年簡単だよね」みたいな雰囲気を感じてしまったらもう最悪です。
その点、自分が司法試験を受けていることを知っている非受験生の親友への連絡はいいものです。
向こうは試験中ではないので気を使ったり見栄を張ったりする必要がありません。思う存分弱音を吐いたり、逆にできた時には喜びを分かち合えます。
特に孤独になりがちな(それがいいところでもあるのですが)遠征受験の場合、そういう存在は大きいのかなと思います。
私は現在合格発表待ちで受かっているか落ちているかわかりませんが、確実に言えることは、その親友との連絡という心の支えがなければ確実にメンタルが崩れて試験に落ちていただろうということです。
ちなみに、電話は一回15分から20分くらいでした。
短時間でできる気分転換としてかなり効果が高いと思うのでお勧めです。
多くの読者の皆さんにとって今はとても不安な時期かと思います。
そういうときにはしばしば当たり前の事すらわからなくなってしまうものです。
なので、この記事の最後では当たり前のことを確認していただこうと思います。
まず、体調が悪いときは休んでください。
なによりもまず体調第一です。体調が悪いときに勉強したってそんなに成果は上がりません。
そして、自信を持ってください。
合格するためには練習で不合格答案をたくさん書く必要があります。誰でもそうです。
論点は漏れまくり、論証はあやふや、当てはめはボロボロ。さらに時間が足りない。そういう答案をたくさん書くのです。
その過程で心が折れたり自信を無くしてしまうこともあると思います。
しかし、それでも勉強を続けている人は、それだけで既に自信を持つに値します。
自分のことが信じられず落ちてしまう人はいますが、自分のことを信じすぎて落ちることはありません。
(なお、自信過剰でするべき勉強を怠れば落ちますが、それは勉強していないから落ちるのであって自信があるから落ちるのではないでしょう)。
自分を信じて、一歩一歩、進んでいってください。
司法試験は情報戦だ!!
司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。
この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。
この記事の内容はこんな方におすすめ!
この記事で分かること
論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?


詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。
▼司法試験受験生なら必読▼
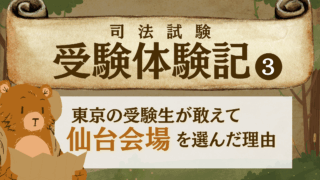
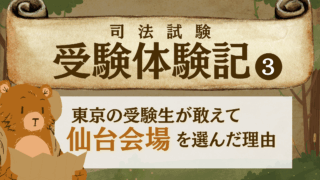
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
判例学習を“見える化”しよう!
事案図解で理解と記憶に革命を。
複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。
「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。


これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。
もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。
とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。
「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。
▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼
法律記事を書いております犬橋です。現在は国立大学法科大学院に在籍しながら、行政法の判例の解説記事を主に執筆しています。
初学者の方にもわかりやすく、興味を持ってもらえるような記事を書くことを目指しています。
勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。
法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!
実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。
迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。

