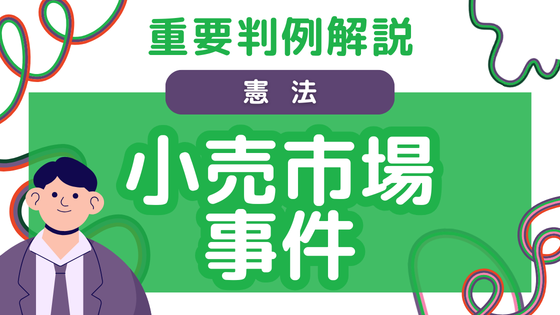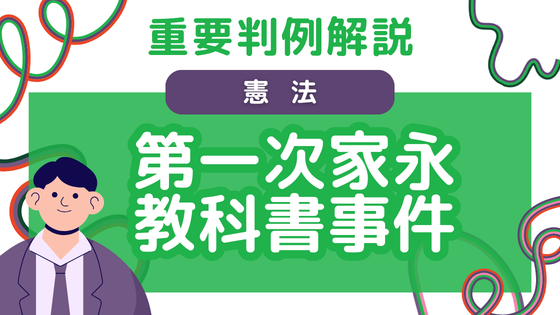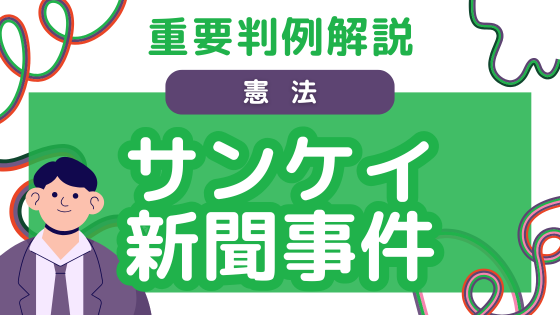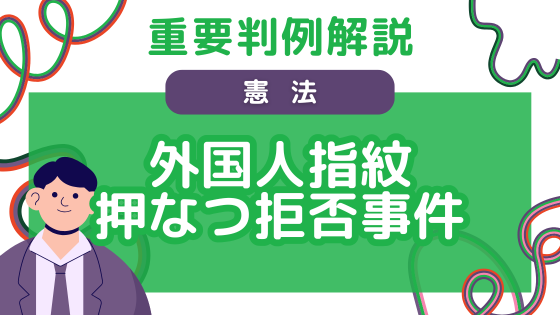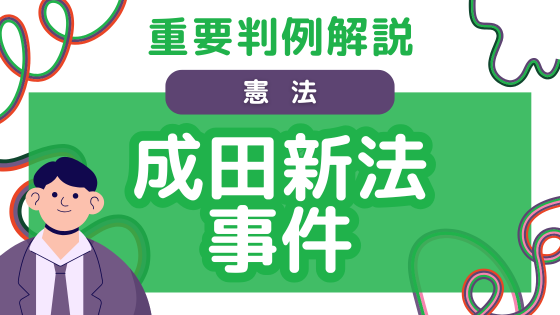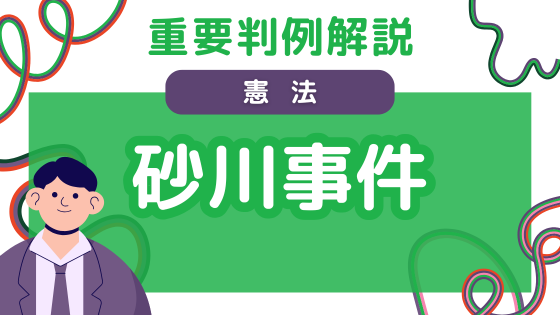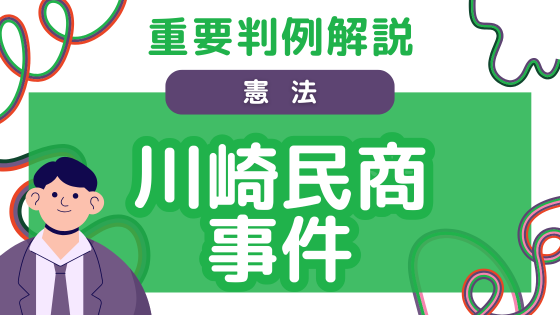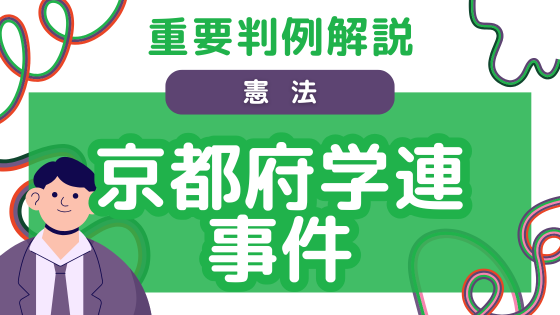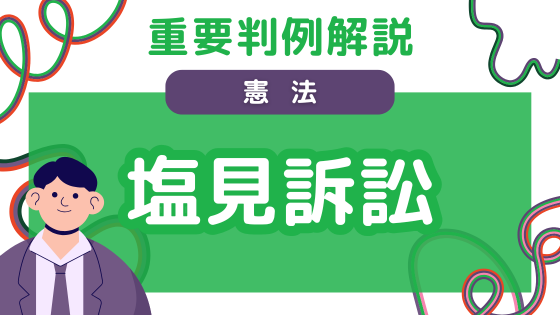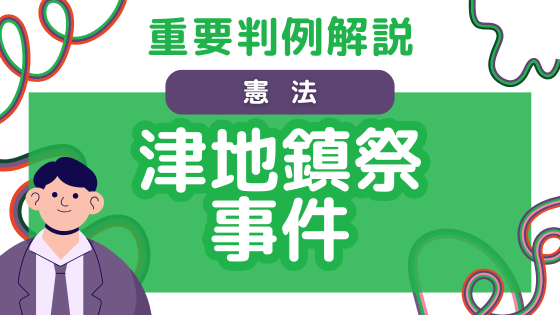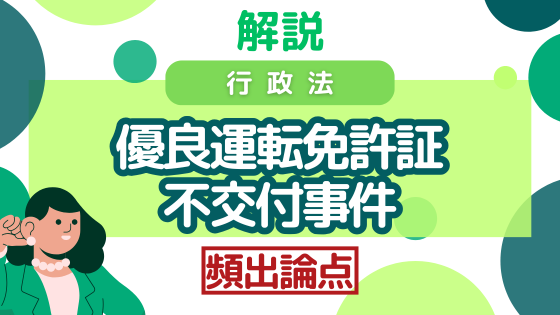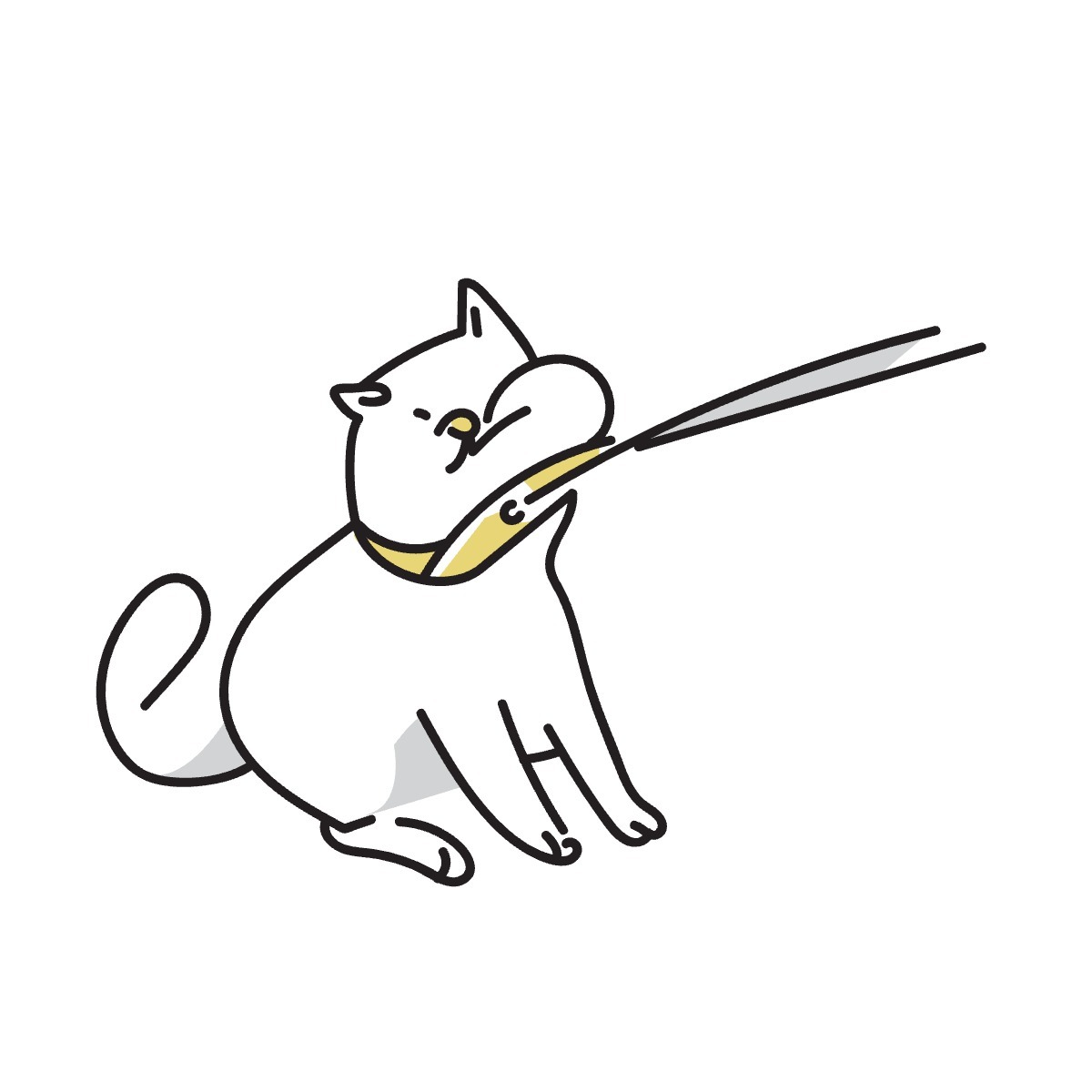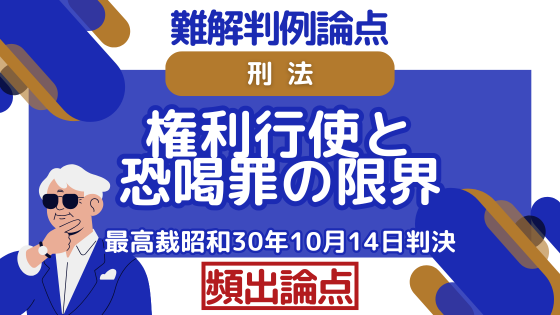判例論点解説– tag –
-

小売市場事件(最大判昭47.11.22)をどこよりも分かりやすく解説
小売市場事件(最大判昭47.11.22)は、公共の福祉を理由とする営業活動の制限が憲法22条に違反しないのかが問題となった事件です。 最高裁は、小売市場の開設制限を設けている小売商業調整特別措置法について、合憲とする判決を下しました。 営業... -

第一次家永教科書事件(最判平5.3.16)をどこよりも分かりやすく解説
第一次家永教科書事件は、教科書検定が検閲に該当しないか、表現の自由の制限に当たるのではないか、学問研究発表の自由を侵害しないか、教師の教育の自由に対する侵害にならないのかの4点が争われた事件です。最高裁はいずれの点からも合憲であるとの判断... -

サンケイ新聞事件(最判昭62.4.24)をどこよりも分かりやすい解説
サンケイ新聞事件は、憲法21条の表現の自由から派生するアクセス権の一つとして提唱されている反論記事の掲載を求める権利が認められるのかどうかが問題となった事件です。 最高裁は、反論記事の掲載を求める権利は個人の名誉やプライバシーを保護するため... -

外国人指紋押なつ拒否事件(最判平7.12.15)をどこよりも分かりやすく解説
外国人指紋押なつ拒否事件は、指紋の採取はプライバシーの侵害に当たるのか、外国人に基本的人権がどこまで保障されるのか、という点が問題になった事件です。 プライバシー権とはどのような権利か? プライバシー権という権利は、憲法上規定がありません... -

成田新法事件(最大判平成4.7.1)をどこよりも分かりやすく解説
「成田新法事件」は、刑事手続を対象とした「憲法31条の法定手続の保障」と「憲法35条の令状主義の保障」が、「行政手続」にも及ぶのか?が問題となった事件です。 最高裁は、「行政手続」にもこれらの保障が及ぶ可能性があることを示唆しました。 また、... -

砂川事件(最大判昭和34.12.16)をどこよりも分かりやすく解説
「砂川事件」は、憲法9条2項の「戦力の解釈と条約」が、憲法81条に基づく「違憲審査」の対象になるのか?が問題となった判例です。 結論から言うと、最高裁は、「合衆国軍隊は戦力に当たらない」旨と、「日米安保条約の合憲性は裁判所の司法審査権の範囲外... -

川崎民商事件(最大判昭47.11.22)をどこよりも分かりやすく解説
憲法35条1項の「令状主義」と、憲法38条1項の「黙秘権」は、「刑事手続き」において保障されている権利ですが、税務調査などの「行政手続き」では保障されないのでしょうか? 「川崎民商事件」は、これらの「令状主義」と「黙秘権」が「行政手続き」でも保... -

京都府学連事件(最大判昭和44.12.24)をどこよりも分かりやすく解説
京都府学連事件は、プライバシー権の一つである「肖像権」に相当する権利を認めた最高裁判決として知られています。根拠規定は「憲法13条の幸福追求権」です。 そして、警察官の捜査の一環としての写真撮影についても、正当な理由がなければ原則として認め... -

塩見訴訟(最一小判平成1.3.2)をどこよりも分かりやすく解説
外国人に認められる人権の範囲については、最高裁が「マクリーン事件」で性質説の立場を採りました。 では、憲法25条の「生存権」に基づく年金の支給を受ける権利などの「社会権」は、外国人に保障されるのでしょうか? 「塩見訴訟」はその点についての... -

津地鎮祭事件(最大判昭和52.7.13)をどこよりも分かりやすく解説
津地鎮祭事件は、「政教分離原則」について、最高裁が初めて本格的な判決を下した事件です。 「政教分離原則」の法的性格として、制度的保障説を採用し、憲法20条3項が禁止している宗教的活動に当たるかどうかの判断基準として「目的効果基準」を打ち出し... -

初学者でも分かる!優良運転免許証不交付事件(最判平成21年2月27日)のていねいな解説
この記事では、優良運転免許証不交付事件(最判平成21年2月27日)について、初学者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説していきます。 まず初めに本判決を理解するための「3つのポイント」と「簡単な結論」を以下に示しておきます。 1. 本判決はどの... -

最高裁昭和30年10月14日判決で学ぶ権利行使と恐喝罪の限界
恐喝罪(刑法249条)は、暴行・脅迫を用いて相手に財産的損失を与えた場合に成立しますが、債権者が正当な権利を回収するために恐喝的手段を用いた場合にも、果たして恐喝罪は成立するのでしょうか? 最高裁昭和30年10月14日判決は、この問題に正面から向...